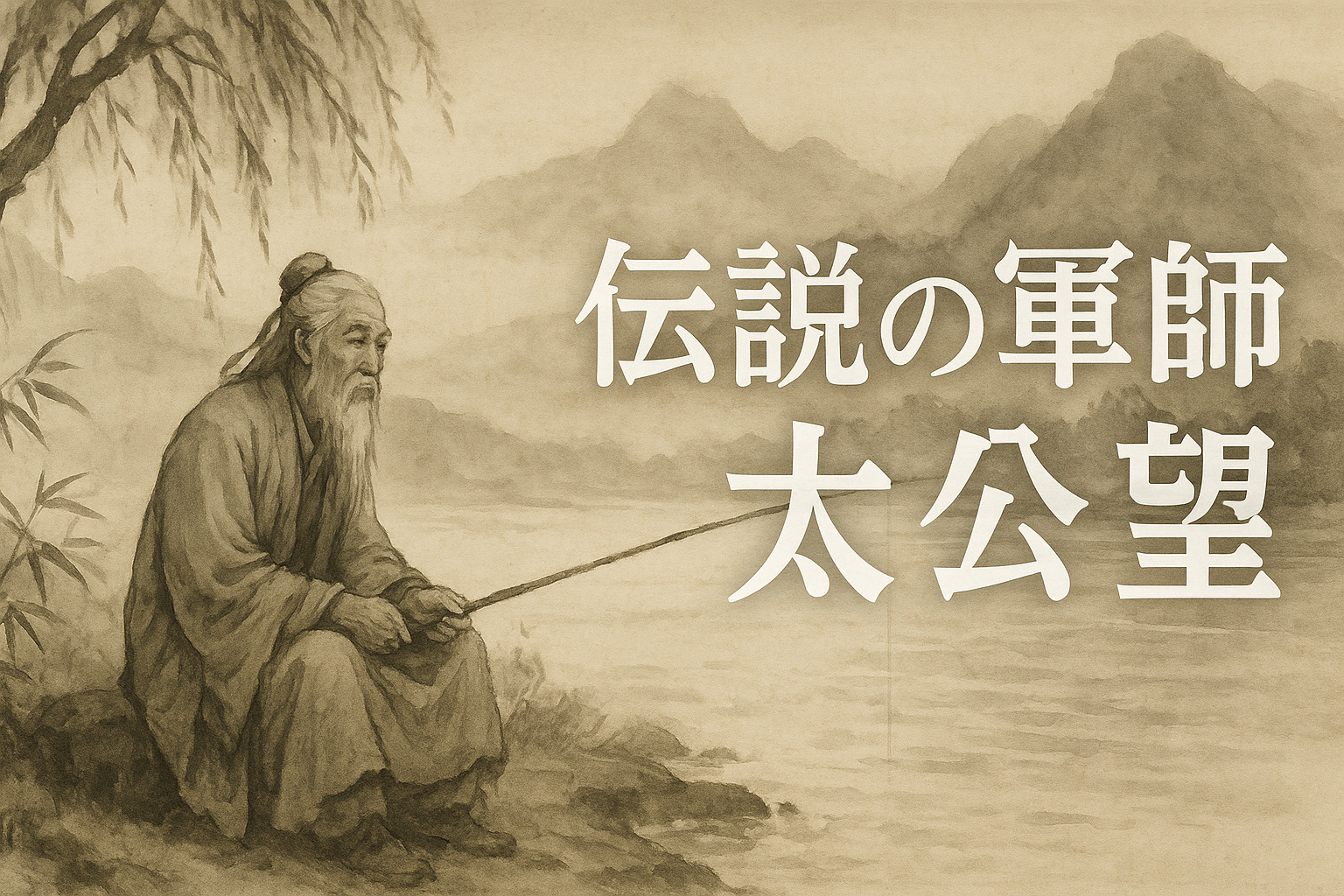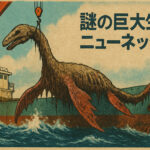川のほとりで釣りをしている老人を見かけたら、あなたはどう思うでしょうか?
平凡な趣味人だと思うかもしれません。しかし紀元前11世紀の中国では、その「釣りをする老人」が王朝交代という歴史的大事業を成功させる天才軍師だったのです。
70代で見出され、周王朝の建国に貢献した伝説の軍師・太公望。その名は今でも「釣り好きの人」を指す言葉として使われています。
この記事では、中国史上最も有名な軍師の一人である太公望の生涯と伝説について、分かりやすくご紹介します。
概要
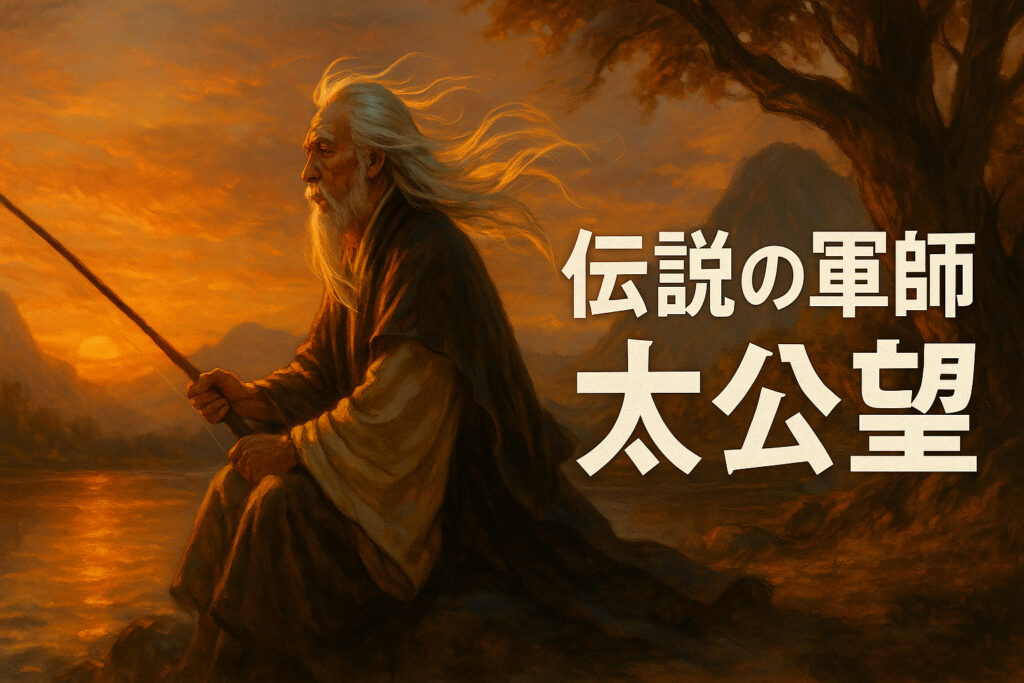
太公望(たいこうぼう)は、紀元前11世紀頃の古代中国で活躍した伝説的な軍師です。
周の文王と武王という二代の王に仕え、当時の支配王朝だった殷(いん)を滅ぼして周王朝を建国する大事業を成功させました。
太公望という名前は通称で、本名は呂尚(りょしょう)または姜尚(きょうしょう)、字(あざな)は子牙(しが)といいます。他にも姜子牙、斉太公、師尚父など、たくさんの呼び名があるんです。
周王朝が成立した後は、斉(せい)という国に封じられ、その地を治めました。春秋時代の強国・斉国の始祖として、子孫が長く国を栄えさせることになります。
中国最古の兵法書とされる『六韜(りくとう)』の著者と伝えられ、後世では兵法の神様として崇められました。唐の時代には「武成王」という称号を贈られ、孔子と並ぶ「武の聖人」として国家的に祀られたほどです。
偉業・功績
太公望の最大の功績は、何といっても周王朝の建国を軍事面で支えたことにあります。
殷王朝打倒への道
当時の中国を支配していた殷王朝の最後の王・紂王(ちゅうおう)は、恐怖政治を敷いて民を苦しめていました。
周の文王(姫昌)は、苦しむ人々を救うため殷を倒すことを決意しますが、そのためには優秀な軍師が必要でした。そこで現れたのが太公望だったんですね。
太公望は文王に軍事戦略を授け、周の国力を高めることに貢献しました。文王の死後も、その息子である武王に仕え続けます。
牧野の戦いでの勝利
紀元前1046年頃、ついに周と殷の決戦の時が訪れました。牧野の戦いと呼ばれるこの戦いで、太公望は周軍を指揮しました。
『詩経』という古典には、太公望が「鷹のように勇ましく戦った」と記されています。この戦いで殷の軍勢を破り、紂王は自らの宮殿に火を放って死にました。
こうして約600年続いた殷王朝は滅び、新しい周王朝が誕生したのです。
斉国の開祖として
戦功により、太公望は営丘(えいきゅう)(現在の山東省)を中心とする斉の地に封じられました。
斉の地は農業に不向きな土地でしたが、太公望は漁業と製塩業に注目し、これらの産業を発展させることで国を豊かにしました。また、複雑な儀礼を簡素化するなど、実用的な政治を行ったとされています。
こうして築かれた斉国は、後の春秋時代に強国の一つとなり、太公望の子孫が代々治めることになりました。
系譜

太公望の出自には、いくつかの説があります。
姜氏と呂氏
太公望の本姓は姜(きょう)で、古くは四嶽(しがく)という官職に就いて、伝説の英雄・禹(う)の治水事業を助けた一族の末裔とされています。
一族の支族が呂(りょ)という土地(現在の河南省南陽市)に移住したため、土地名にちなんで呂氏を名乗るようになったんですね。だから「呂尚」とも「姜尚」とも呼ばれるわけです。
斉国の始祖
周王朝建国後、太公望は斉に封じられ、その子・丁公(ていこう)が後を継ぎました。
太公望は100歳を超える長寿だったと伝えられており、斉国の基礎をしっかりと固めました。その子孫は春秋時代まで斉を支配し、後に有名な斉の桓公(かんこう)などの名君を輩出します。
周王室との縁
太公望の娘邑姜(ゆうきょう)は、周の武王の妃となりました。
彼女は後の成王や唐叔虞(とうしゅくぐ)を産んだとされ、太公望は周王室と深い縁で結ばれていたことが分かります。
姿・見た目
太公望の外見について、史書には詳しい記述がありませんが、いくつかの特徴が伝えられています。
高齢の老人
文王と出会った時、太公望はすでに70歳を超えていたという伝承があります。
白髪で長い髭を生やした老人の姿が一般的なイメージです。『史記』には「東海のほとりの出身」と記されており、海辺の地域で育った人物だったようです。
大柄な体格
興味深いことに、太公望は軍師にしては大柄な体格だったと伝えられています。
多くの軍師が小柄で文弱なイメージで描かれる中、太公望は体格に恵まれた人物だった可能性があるんですね。
釣り姿
太公望の最も有名なイメージは、やはり渭水(いすい)で釣りをする姿でしょう。
後世の絵画では、川のほとりで釣り竿を垂れる白髪の老人として描かれることが多いです。不思議なことに、その釣り針は曲がっていない真っ直ぐな針だったという伝説もあります。
特徴

太公望には、他の軍師とは違う独特の特徴があります。
遅咲きの天才
太公望の最大の特徴は、何といっても70代になってから頭角を現した「遅咲き」だということです。
若い頃は屠殺業や飲食業で生計を立てていたという伝承があり、決して順風満帆な人生ではありませんでした。一説によると、殷の紂王にも仕えたことがあるそうですが、その悪政に嫌気がさして立ち去ったといいます。
その後、諸侯を説いて遊説したものの認められず、最後に西方の周に身を寄せたのです。
知恵と戦略の達人
太公望は、長年かけて蓄えた知識と知恵を武器にしていました。
『六韜』という兵法書の著者とされ(実際は後代の著作とされていますが)、戦略や戦術に優れていたことが分かります。ただし、具体的にどのような戦術を使ったかは謎に包まれているんですね。
現実主義者
太公望の政治思想で特徴的なのは、民を愛し、民を豊かにすることが国を強くするという考え方でした。
「官僚が自分だけ豊かになって民が貧しければ、国は長く続かない」という現実的な視点を持っていたとされています。斉国で漁業と製塩業を重視したのも、この実用主義の表れといえるでしょう。
伝承
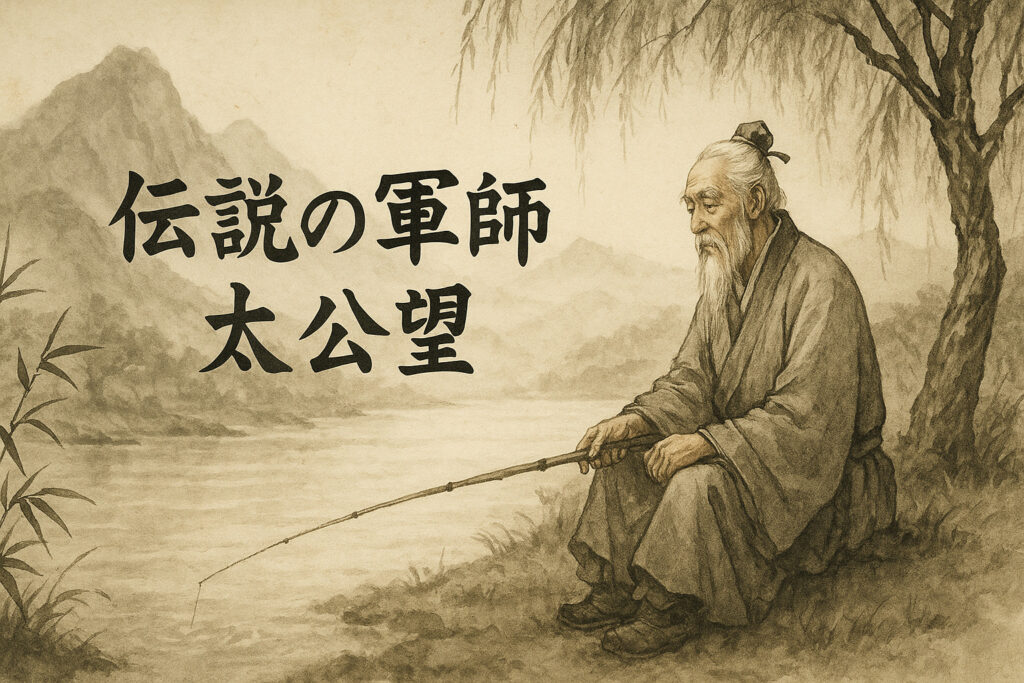
太公望にまつわる伝説は数多くありますが、特に有名なものをいくつか紹介します。
渭水での出会い
太公望伝説の中で最も有名なのが、文王との運命的な出会いです。
ある日、文王は狩猟に出る前に占いをしました。すると「獣ではなく人材を得る」というお告げが出たのです。
文王が渭水のほとりに行くと、一人の老人が釣りをしていました。それが太公望でした。
二人は語り合い、文王はその知恵の深さに感銘を受けます。そして「あなたこそ、我が祖父(太公)が代々待ち望んでいた賢人だ」と喜び、軍師として迎え入れました。
これが「太公望」(太公が望んでいた人)という名前の由来です。
不思議な釣り針
この出会いにまつわる民間伝承では、太公望の釣り針は曲がっていない真っ直ぐな針だったといいます。
文王が「魚は釣れるのですか?」と尋ねると、太公望は答えました。
「私が釣りたいのは、自ら進んで釣られる魚です。無理に釣る必要はありません」
これは実は、自分を見出してくれる明君を待っているという暗示の言葉だったんですね。中国には「姜太公釣魚——願者上鉤(太公望の釣り、願う者が針にかかる)」という言葉があり、自ら進んで関わることの例えとなっています。
覆水盆に返らず
もう一つ有名な故事が「覆水盆に返らず」です。
太公望が周に仕える前、妻の馬氏がいました。しかし、太公望が貧しく出世の見込みがないと見た馬氏は、彼のもとを去ってしまいます。
ところが太公望が周の軍師として大出世すると、馬氏は復縁を望んで戻ってきました。
そこで太公望は、盆(お皿)の水を床にこぼして見せ、こう言ったのです。
「この水を元通り盆に戻すことができますか? できないでしょう。夫婦も同じです。一度別れたらもう元には戻れないのです」
この故事から、一度してしまったことは取り返しがつかないという意味の「覆水盆に返らず」という言葉が生まれました。
牧野の戦いでの活躍
紀元前1046年頃、太公望は武王を補佐して殷との決戦に臨みました。
『詩経』には「師尚父(太公望のこと)は鷹のように勇ましかった」と記されています。この戦いで太公望は方(ほう)という殷の諸侯の軍勢を攻撃し、見事に勝利を収めました。
殷の軍は奴隷や捕虜を兵士にしていたため士気が低く、多くが投降したり反乱を起こしたりしたといいます。こうして周軍は殷の都を陥落させ、紂王は宮殿に火を放って自害しました。
出典・起源
太公望についての記録は、複数の古典文献に残されています。
『史記』での記述
太公望の伝記として最も重要なのが、司馬遷(しばせん)が書いた『史記』の「斉太公世家」です。
ここには太公望の出自、文王との出会い、周王朝建国への貢献、斉国の開祖となったことなどが記されています。ただし、文王との出会いについては3つの異なる説が紹介されており、どれが本当かは分かりません。
その他の古典
『詩経』『孟子』『戦国策』『呂氏春秋』などにも、太公望に関する記述が散見されます。
特に『詩経』の「大雅・大明」には、牧野の戦いでの活躍が称賛されています。
兵法書『六韜』
太公望は『六韜』と『三略』という兵法書の著者とされてきました。
『六韜』は、文王と武王が太公望に軍事や政治について質問し、太公望が答えるという問答形式の書物です。「文韜」「武韜」「龍韜」「虎韜」「豹韜」「犬韜」の6編からなり、「武経七書」という中国の代表的な兵法書の一つに数えられています。
ただし、現代の研究では、『六韜』は戦国時代末期以降に書かれた後世の作品で、太公望の名前を借りた著作だと考えられています。
神格化と武成王廟
春秋時代になると、強国となった斉は自国の権威を高めるため、始祖である太公望を神格化していきました。
唐の時代には、玄宗皇帝が前漢の張良とともに太公望を祀る太公廟を各地に建立します。さらに粛宗皇帝は太公望に「武成王」という称号を贈り、廟を「武成王廟」に改称しました。
これは、孔子を祀る「文宣王廟」に対応するもので、文の孔子、武の太公望という位置づけです。武成王廟には「武廟十哲」と呼ばれる10人の名将が合祀され、後には「武廟六十四将」まで増やされました。
ただし明の時代になると、洪武帝(朱元璋)が「周の臣下を王として祀るのは不適当」として武成王の称号を剥奪し、祭祀を中止させてしまいます。
『封神演義』での変容
明代に書かれた神怪小説『封神演義』は、太公望のイメージを大きく変えました。
この小説では、太公望(姜子牙)は崑崙山で修行した道士として描かれ、師匠の元始天尊から「殷の暴君を倒し、戦死者を神々に封じよ」という使命を受けて下山します。
72歳で下山した太公望は、打神鞭(だしんべん)という神秘的な武器と、四不象(しふぞう)という霊獣に乗って活躍します。仙人としての能力は高くありませんが、知恵と戦略で数々の困難を乗り越え、最終的に365柱の神々を封じるという大業を成し遂げるのです。
この小説は中国だけでなく日本でも広く読まれ、太公望の神秘的なイメージを決定づけました。
まとめ
太公望は、中国史上最も有名な軍師の一人であり、周王朝建国という大事業を成功させた立役者です。
重要なポイント
- 70代で見出された「遅咲きの天才」軍師
- 周の文王・武王を支え、殷を滅ぼして周王朝を建国
- 斉国の始祖となり、子孫が長く国を治めた
- 渭水で釣りをしていた時に文王に見出されたという伝説
- 「覆水盆に返らず」の故事の主人公
- 『六韜』という兵法書の著者と伝えられる
- 唐代には「武成王」として兵法の神様に
- 明代の『封神演義』で神秘的な道士として描かれる
日本では「釣り好きの人」の代名詞として「太公望」という言葉が使われていますが、それは彼が渭水で釣りをしていた時に人生が変わったという伝説に由来します。
何歳になっても遅すぎることはない——太公望の生涯は、そんなメッセージを私たちに伝えてくれているのかもしれませんね。