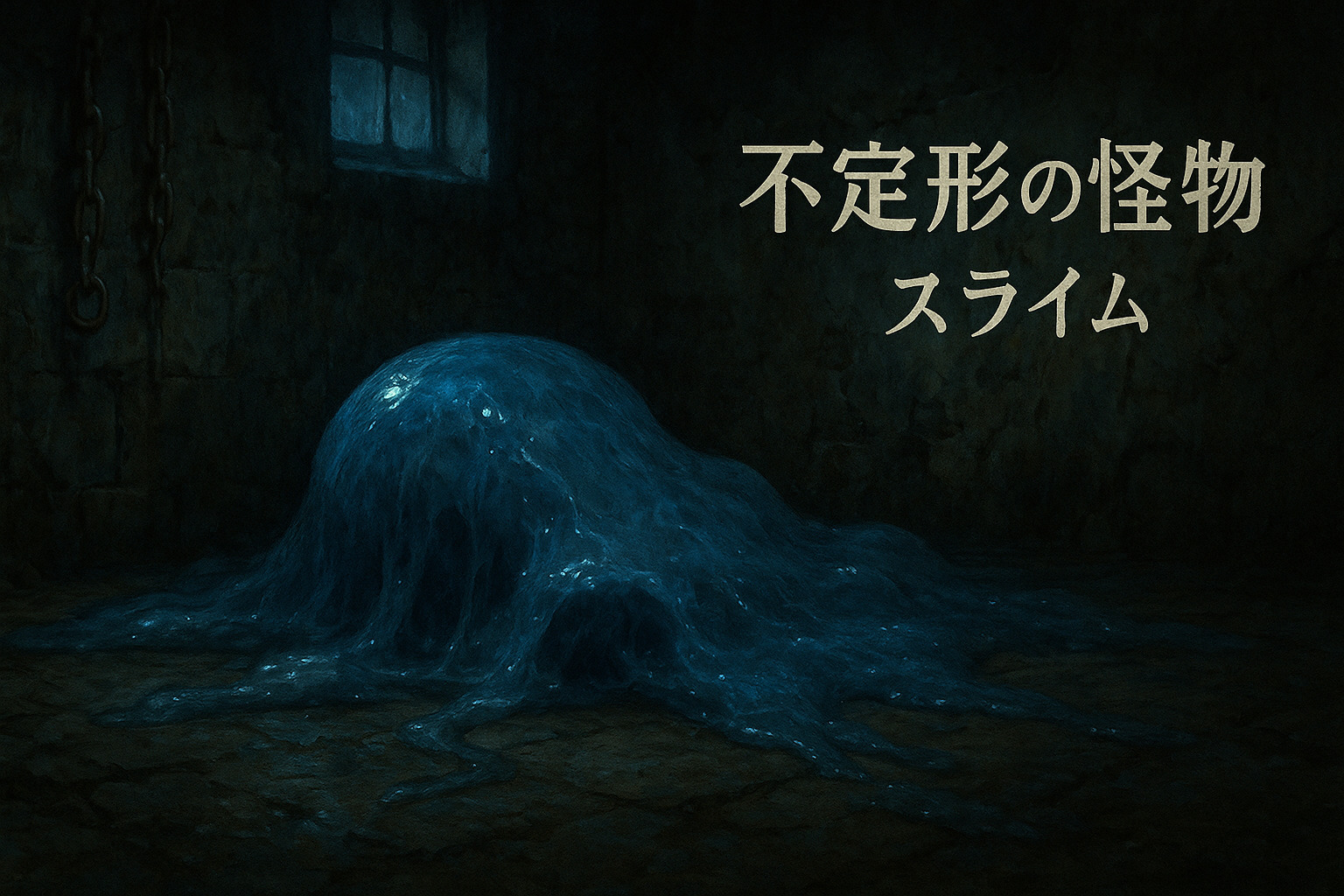地下室の暗がりで、ドロドロと音を立てながら動く何かを見たことはありますか?
それは武器も通さず、切っても増えてしまう、恐ろしい怪物「スライム」かもしれません。
現代ではゲームの雑魚キャラとして親しまれていますが、もともとはホラー小説に登場する恐怖の存在だったんです。
この記事では、不定形の怪物「スライム」について、その不気味な姿や特徴、興味深い文学的起源を分かりやすくご紹介します。
概要

スライムは、ゼリー状やドロドロした粘液状の体を持つ架空の怪物です。
決まった形を持たず、自由に体を変形させることができる不定形生物なんですね。英語では「ウーズ(ooze)」や「ブロブ(blob)」とも呼ばれ、これらは「ねばねばしたもの」「不定形な塊」という意味があります。
もともとは1950年代のアメリカのホラー小説に登場した恐怖の怪物でした。触れたものを溶かしたり、取り込んだりする貪欲な食欲を持つ危険な存在として描かれていたんです。
現代では、特に日本のゲーム文化の影響で、かわいらしい雑魚モンスターとしてのイメージが定着していますが、本来は人間を襲う恐ろしい存在だったというわけです。
姿・見た目
スライムの見た目は、作品によってさまざまです。
基本的な外見
- 粘液状タイプ:ドロドロした液体のような姿
- ゼリー状タイプ:プルプルした半固体の姿
- 両方を行き来するタイプ:状況に応じて形態を変える
色は半透明のものが多いですが、灰黒色、緑色、青色など様々。有機質でできているように見えるものもあれば、液体金属や溶岩でできているという設定もあるんです。
形状の変化
スライムの最大の特徴は、決まった形がないこと。触手を伸ばしたり、平たく広がったり、岩のような塊になったりと、自由自在に形を変えられます。
アメーバのような単純な構造から、巨大なヒトデやイカのような複雑な形まで、様々な姿を取ることができるんですね。
特徴
スライムには、普通の生物とは違う恐ろしい特徴があります。
主な能力と性質
- 貪欲な食欲:触れたものを何でも溶かして吸収する
- 物理攻撃無効:刃物や銃弾が効かない
- 分裂増殖:切っても切断面がくっついたり、新しい個体になる
- 隙間侵入:どんな小さな隙間にも入り込める
- 高速移動:見た目に反して素早く動ける
弱点
多くの作品で共通する弱点は火です。炎で焼き払うことが唯一の対処法とされることが多いんです。また、冷凍すれば動けなくなるけれど、解凍するとまた動き出すという設定もあります。
電気や魔法などのエネルギー攻撃も効果的とされることがありますが、物理攻撃はほとんど意味がないというのが定番です。
伝承
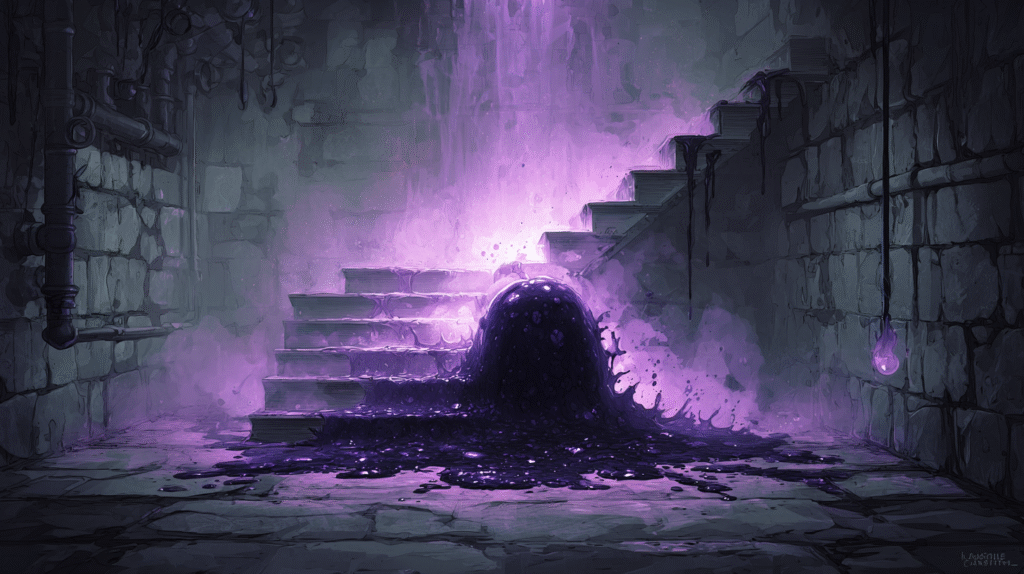
スライムの歴史は、意外と新しいんです。
文学での誕生(1920年代~)
最初期の例として、1923年の『Weird Tales』誌に掲載されたアンソニー・M・ラッドの『OOZE』があります。実験で巨大化したアメーバが人間を襲うという内容でした。
H.P.ラヴクラフトの影響
1936年、ホラー作家ラヴクラフトが『狂気の山脈にて』で描いた「ショゴス」は、黒い粘液状の不定形生物でした。この作品が後のスライム像に大きな影響を与えたんです。
『Slime』の登場(1953年)
ジョセフ・ペイン・ブレナンの『Slime』(邦題:『沼の怪』)が、現代のスライムの原型となりました。太古の海底から地上に現れた灰黒色の怪物が、恐るべきスピードで動き、人や動物を次々と飲み込んでいくという恐怖の物語です。
映画『The Blob』(1958年)
宇宙から来た不定形生物が人間を襲うパニック映画で、スライム系怪物の知名度を一気に高めました。この映画は「スター・ジェリー」という、流星の後に現れるゼリー状の物質の伝説にインスピレーションを得たといわれています。
起源
スライムという怪物のアイデアは、どこから生まれたのでしょうか。
科学の発展が生んだ恐怖
19世紀後半から20世紀初頭、顕微鏡の発達によりアメーバや粘菌が発見されました。これらの不定形生物の存在が、作家たちの想像力を刺激したんです。
古代や中世の神話には、不定形の怪物はほとんど登場しません。スライムは、科学の時代が生んだ新しいタイプの怪物といえるでしょう。
ゲームでの変化
1974年、テーブルトークRPG『ダンジョンズ&ドラゴンズ』に「ウーズ」として登場。ダンジョンの清掃動物という設定で、触れるものを溶かす危険な罠として扱われました。
1981年の『Wizardry』では、武器で倒せる低レベルの敵として登場。これが日本に影響を与え、1986年の『ドラゴンクエスト』で鳥山明がデザインした涙滴型のかわいいスライムが誕生したんです。
日本での独自進化
日本では「最弱モンスター」「かわいいキャラクター」としてのイメージが定着。
現代では、人型の「スライム娘」や、知性を持つ主人公スライムなど、独自の発展を遂げています。
まとめ
スライムは、科学の時代が生んだ新しい恐怖から、親しみやすいキャラクターへと変化した興味深い怪物です。
重要なポイント
- ゼリー状・粘液状の不定形な体を持つ架空の怪物
- 1920年代のホラー小説が起源
- 物理攻撃が効かない恐ろしい特性
- 触れたものを溶かして吸収する貪欲な食欲
- 火や魔法でしか倒せない
- H.P.ラヴクラフトの「ショゴス」が影響
- D&Dで「ウーズ」として体系化
- 日本のゲームで「最弱モンスター」として再定義
- 現代では恐怖から親しみやすさへ変化
もし地下室でドロドロした何かを見つけたら、それはスライムかもしれません。
でも安心してください。現実世界にスライムはいませんから。
それは作家たちの想像力が生み出した、永遠に形を変え続ける創造物なのです。