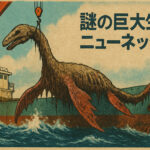広大な海の向こうから、巨大な影が近づいてくる様子を想像してみてください。
古代から現代まで、世界中の船乗りたちが恐怖に震えながら目撃してきた海の怪物――それがシーサーペント(大海蛇)です。何千年もの間、数え切れないほどの目撃談が語り継がれ、中世の航海図にまで描かれてきました。
この記事では、海洋史上もっとも多く目撃された未確認生物「シーサーペント」について、その姿や特徴、有名な伝承を詳しくご紹介します。
概要

シーサーペントは、世界中の海で目撃されてきた巨大な海の怪物の総称なんです。
英語で「Sea Serpent(海のヘビ)」という名前の通り、細長いヘビのような姿をしていると言われています。日本語では「大海蛇(おおうみへび、だいかいじゃ)」とも呼ばれます。
最古の記録は紀元前4世紀にまでさかのぼります。西暦77年には、古代ローマの学者プリニウスが著した『博物誌』にも登場しているんですね。
中世ヨーロッパでは、航海に使う海図にシーサーペントの姿が描き込まれていました。これは船乗りたちへの警告の意味があったとされています。つまり、当時の人々にとって、シーサーペントは実在する危険な生物だったわけです。
歴史上もっとも多くの人間に目撃された怪物が、このシーサーペントだと言われています。
姿・見た目
シーサーペントの外見は、膨大な数の目撃談から以下のような特徴がまとめられています。
基本的な身体構造
サイズ
- 体長:20〜60メートル(目撃談によって異なる)
- 体の太さ:船と同じくらい、または船の幅の数倍
体の形状
- ヘビのような細長い体
- 1対または複数対のヒレを持つ
- 鱗(うろこ)、または硬い皮膚で覆われている
- 体の表面は皺(しわ)があり、平坦ではない
頭部の特徴
目撃談によると、頭部の形状にはいくつかのパターンがあります。
- ヘビのような鋭い頭:細長い首と尖った鼻先を持つタイプ
- ワニのような頭:爬虫類的な特徴を持つタイプ
- ウマに似た頭:たてがみのような毛が生えているタイプ(「海馬」とも呼ばれる)
その他の特徴
- 口には鋭い歯がびっしりと並ぶ
- 証言によっては頭に角が生えている
- 赤っぽい目、または炎のような目をしている
特徴
シーサーペントには、他の海の生物とは異なる独特の行動パターンがあります。
泳ぎ方の謎
上下に波打つ動き
多くの目撃談で共通しているのが、その泳ぎ方です。
- 普通の魚類や爬虫類:体を左右にくねらせて泳ぐ
- シーサーペント:体を上下にくねらせて泳ぐ(哺乳類のような動き)
この泳ぎ方のせいで、長い胴体がいくつものコブや弧(こ)として海面上に現れるんですね。まるで巨大なジェットコースターが海の上を進んでいるような光景だったと言われています。
行動の特徴
目撃談から分かっている行動パターンをまとめると、こうなります。
攻撃性
- 船を襲うことがある
- 船に巻きつき、海中に引きずり込む
- 人間を飲み込んでしまうこともある
その他の習性
- クジラのように潮を吹く(哺乳類的な特徴)
- 肉食性と考えられる
- 海面近くを泳ぐことが多い
- 天候が崩れる前に現れることが多い
興味深いのは、哺乳類的な特徴(潮を吹く、上下に泳ぐ、たてがみのような毛)を持つという証言が多い点です。これは、シーサーペントの正体を探る重要な手がかりになっています。
伝承

シーサーペントには、世界各地で数多くの目撃談や遭遇事件が残されています。
古代の記録
旧約聖書のレヴィアタン
最古の伝承の一つが、旧約聖書に登場する海の怪物「レヴィアタン」です。『ヨブ記』や『イザヤ書』に記されており、古代オリエントの世界ではヘビやワニのような姿をした海の竜として恐れられていました。
アッシリア王の遭遇
紀元前8世紀、アッシリアの王サルゴン2世がキプロスへ向かう航海中にシーサーペントに遭遇したという記録も残っています。
1734年:ハンス・エーイェゼ司教の目撃
グリーンランド布教で知られるデンマーク=ノルウェーのハンス・エーイェゼ司教は、1734年7月6日に船上から恐ろしい怪物を目撃しました。
目撃時の状況
- 怪物は体を高く持ち上げ、頭が船のメインマスト(主檣)の頂上まで達した
- 長い首と鋭い鼻先を持っていた
- クジラのように潮を吹いていた
- 非常に幅広いヒレを持っていた
- 体は鱗か貝殻のようなもので覆われ、皺だらけだった
- 下半身はヘビのようだった
- 体の厚さは船と同じくらい、長さは船の3〜4倍あった
- 目は赤っぽく、まるで火が燃えているようだった
怪物は後ろ向きに水中へ潜り、船の全長ほど離れた場所で尾を水面に立てて消えたそうです。そして翌晩、激しい嵐がやってきました。
1915年:イベリアン号事件
第一次世界大戦中の1915年7月30日、大西洋でドイツの潜水艦U-28がイギリスの汽船イベリアン号を撃沈しました。
驚くべき目撃
船が爆発した瞬間、海中から巨大な生物が放り出されたんです。潜水艦の6人の乗組員全員がこれを目撃しています。
- 体長:約20メートル
- 姿:ワニのような爬虫類
- 特徴:細長い頭、みずかきのある肢(あし)
1964年:アメリカでの連続目撃
1964年は、シーサーペント史上特別な年でした。
マサチューセッツ州での事件
同じ海域で、わずか1日の間に2隻の船が同じ怪物を目撃したんです。
最初の目撃(ノルウェー漁船ブルーシー号)
- 船から約100メートル離れた場所を泳ぐ怪物を発見
- 体長は約20メートル
- ワニのような頭部
- 背中にコブがあった
船長は全米商業漁業局に報告し、翌日から沿岸警備隊や漁船が大規模な捜索を開始しました。3日後、「フレンドシップ号」も同じ怪物を目撃し、これは同一個体だと考えられています。
オーストラリアでの目撃(同年12月)
ホワイトサンデー島付近で、フランス人写真家ロベール・ル・セレックと友人たちが浅瀬を泳ぐ体長約20メートルの怪物を目撃し、写真撮影にも成功しました。ただし、この写真については後に偽物ではないかという疑いも出ています。
1977年:ニューネッシー事件
1977年4月25日、ニュージーランド沖で日本の漁船「瑞洋丸」が巨大な死骸を引き上げました。
発見時の状況
- 鮮明な写真が撮影された
- 組織のサンプルも採取された
- しかし、強い腐敗臭のため海に投棄された
写真に写った姿が中生代の首長竜プレシオサウルスに似ていたため、大きな話題となりました。東京水産大学の調査報告では、正体はウバザメである可能性が高いとされましたが、今でも謎が残っています。
起源
シーサーペントの概念は、人類の歴史とともに古くから存在してきました。
世界各地の神話との関連
シーサーペントのような海の怪物は、世界中の神話に登場しています。
主な神話上の海の怪物
- メソポタミア神話:ティアマト(原初の海の女神)
- ウガリット神話:ヤム、タンニン
- 旧約聖書:レヴィアタン、ラハブ
- ギリシャ神話:ケートス、ヒュドラ、スキュラ
- 北欧神話:ヨルムンガンド(世界を取り巻く大蛇)
- 東洋の伝説:竜(水と深い関係を持つ)
これらの伝説上の生物は、形や性質がシーサーペントと共通する部分が多いんですね。
中世以降の記録
航海図への記載
中世から近代にかけて作られた世界地図では、海洋部分にシーサーペントの絵が描かれることが一般的でした。これは単なる装飾ではなく、船乗りへの実際の警告だったとされています。
ポントピダン司教の分類(1752-1753年)
デンマーク=ノルウェーのベルゲン市の司教ポントピダンは、『ノルウェー博物誌』の中で2種類のシーサーペントについて詳しく記述しています。彼はエーイェゼ司教の目撃した生物を、通常のシーサーペントとは別種だと結論付けました。
ウードマンスの科学的研究(1892年)
オランダの動物学者A・C・ウードマンスは『大海蛇』という著書で、多数の目撃証言を科学的に検証しました。彼は、シーサーペントの正体は長い首と長い尻尾を持ったアザラシのような未知の生物だと結論付けています。
正体についての仮説
現代の研究者たちは、シーサーペントの正体について様々な説を唱えています。
有力な候補
- モササウルス:白亜紀に生息していた海棲爬虫類。ウミヘビのような細長い体つきで、動きの特徴がシーサーペントと共通
- バシロサウルス:原始的なクジラの祖先。細長い体を持つ
- 巨大ウナギ説:未発見の新種の超大型ウナギ
- リュウグウノツカイ:深海魚で、体長が数メートルに達する
- 巨大イカ説:触手を首と誤認した可能性
- メガロドン:絶滅した巨大なサメ
- クジラの誤認:特定の条件下でのクジラの目撃
現代の新しい説
2016年の研究論文では、漁具や海洋ゴミに絡まったクジラが、シーサーペントとして誤認された可能性が指摘されています。また、2023年の研究では、銛(もり)で刺されたマッコウクジラが転覆したボートと一体化し、奇妙な姿で海面を漂う様子が目撃されたのではないかという説も出ています。
重要なポイント
海は地球表面の約70%を占めていますが、人類が調査できたのはほんの一部に過ぎません。深海には、まだ発見されていない大型生物が潜んでいる可能性は十分にあるのです。
実際、比較的最近でも新種の大型生物が発見されています。
- 1976年:メガマウスザメ(体長4メートル以上)の発見
- 2001年:全長7メートルの新種イカの発見
- 2010年:新種のツチクジラの発見
まとめ
シーサーペントは、紀元前から現代まで、世界中で目撃され続けている海の怪物です。
重要なポイント
- 紀元前4世紀から記録が残る、歴史上もっとも目撃例の多い未確認生物
- 体長20〜60メートルのヘビのような細長い体を持つ
- 上下に波打つ独特の泳ぎ方が特徴
- 哺乳類的な特徴(潮を吹く、たてがみなど)を持つという証言が多い
- 中世の航海図にも描かれ、船乗りたちに恐れられた
- 正体は未知の海棲生物、絶滅種の生き残り、既知の生物の誤認など諸説ある
- 広大な海には、まだ発見されていない大型生物が存在する可能性がある
数千年にわたる目撃談の数々は、海の神秘と未知なる世界への人類の畏敬の念を物語っています。もしかしたら、今この瞬間も、どこかの海で巨大な影が静かに泳いでいるのかもしれませんね。