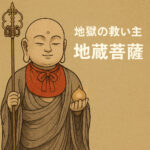お葬式で、棺の中に小銭を入れる風習を見たことはありませんか?
これは「六道銭(ろくどうせん)」と呼ばれるもので、亡くなった人があの世へ旅立つために必要な、いわば「旅費」なんです。
日本では古くから、死者が三途の川を渡るためには六文のお金が必要だと信じられてきました。この風習は単なる迷信ではなく、仏教の死生観や日本人の死者への思いやりが込められた、深い意味を持つ文化なんですね。
この記事では、死者に持たせる六道銭について、その由来や意味、三途の川との関係を分かりやすくご紹介します。
概要

六道銭(ろくどうせん) は、死者を葬る際に棺の中に入れる六文の銭貨のことです。
「六文銭」「六道の辻銭」とも呼ばれ、日本では平安時代末期から中世にかけて広まった風習なんですね。
六道銭の基本情報
- 枚数:基本的に6枚(時代や地域によって異なる場合もある)
- 目的:三途の川を渡るための渡し賃
- 起源:中国の葬送習俗が仏教と結びついて日本に伝わった
- 現代:本物の硬貨の代わりに、紙に印刷されたものを使うことが多い
六道銭という名前は、仏教の 「六道輪廻(ろくどうりんね)」 という考え方から来ています。六道とは、死後に生まれ変わる可能性のある6つの世界(天道・人道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道)のこと。死者はこの六道のいずれかに向かう旅の入り口で、お金が必要になるというわけです。
三途の川を渡るために
六道銭が最も必要とされるのが、三途の川(さんずのかわ) です。
三途の川とは?
三途の川は、この世(現世)とあの世(来世)の境界にあるとされる川なんです。
仏教の伝承によれば、人は死ぬと必ずこの川を渡らなければなりません。『地蔵菩薩発心因縁十王経』(通称『地蔵十王経』)という経典に、三途の川の詳しい描写が記されています。
奪衣婆と懸衣翁
三途の川のほとりには、奪衣婆(だつえば) という老婆の鬼と、懸衣翁(けんえおう) という老爺の鬼が待ち構えているんです。
この二人の役割はこうです。
三途の川の番人の仕事
- 奪衣婆が、川に到着した死者の着ている衣服を剥ぎ取る
- 懸衣翁が、その衣服を衣領樹(えりょうじゅ) という木の枝にかける
- 枝のしなり具合で、生前の罪の重さを測る
- 罪の重さによって、川を渡る方法が決まる
ここで重要なのが六道銭なんですね。
六道銭の役割
六文銭を持っている死者は、奪衣婆に渡し賃として支払うことで、船で川を渡ることができる とされています。
逆に、六文銭を持っていない死者は、衣服を剥ぎ取られ、服がない場合は身の皮まで剥がされてしまうという恐ろしい話も伝わっています。
三途の川には3つの渡り方があります。
三途の川の渡河方法
- 金銀七宝の橋:善人が渡る立派な橋
- 山水瀬(さんすいせ):軽い罪人が渡る浅瀬
- 強深瀬(ごうしんせ):重い罪人が渡る激流
六道銭は、この中でも特に船で渡る際の船賃として必要だと考えられてきました。
六道銭の由来と歴史

六道銭の風習は、どこから来たのでしょうか?
中国の葬送習俗
死者と共に銭貨を埋葬する習慣は、中国で古くから行われていました。
もともとは 金属の持つ呪力で悪霊を祓う ために始まったとされています。仏教が中国に伝わると、この習俗が仏教の死生観と結びつき、「冥界への旅費」という意味が加わりました。
中国では、本物の銭貨ではなく 「紙銭(しせん)」 という、銭貨を模して紙で作ったものを焼いて供養する習慣が発展したんです。
日本での受容
日本では、和同開珎の時代(708年以降)にはすでに墓地への銭貨の埋納が見られます。
ただし、平安時代までは5枚の整数倍が多く、これは 土地神(土公神)に対する土地購入の対価 と考えられていました。つまり、墓地という土地を神様から「買う」ための代金だったんですね。
平安時代末期以降、特に六道絵などによって六道思想が広まった中世以降、6枚の例が増えていきます。 これが六道銭の成立です。
遅くとも14世紀(室町時代初期)には、六道銭の習慣が確認できます。ただし、中世の段階ではまだ枚数が一定しておらず、近世(江戸時代)に至って6枚が通例 となりました。
使用された銭貨
江戸時代の六道銭には、次のような銭貨が使われました。
- 寛永通宝:江戸時代に広く流通した銭貨
- 念仏銭:絵銭の一種で、念仏の文字が刻まれたもの
- 題目銭:絵銭の一種で、日蓮宗の題目が刻まれたもの
現代では、本物の硬貨の代わりに 紙に印刷されたものを使用する ことが一般的になっています。
六道銭の意味──なぜ6枚なのか?
六道銭が6枚である理由については、いくつかの解釈があります。
三途の川の渡し賃
最もよく知られている解釈が、三途の川の渡し賃 という説です。
前述のように、奪衣婆に六文銭を渡すことで、川を船で渡ることができるというわけですね。
六道の旅費
別の解釈では、六道それぞれを旅する際に必要な路銀(旅費) だとされます。
死者は六道のいずれかに転生するまでの間、冥界を旅すると考えられていました。その旅の途中で必要な費用が六文だというわけです。
六地蔵への賽銭
さらに別の解釈として、六地蔵に一文ずつ賽銭を供える ためという説もあります。
六地蔵(ろくじぞう) とは、六道それぞれで衆生を救う6体の地蔵菩薩のことです。六道の入り口には六地蔵が立っていて、それぞれに一文ずつお賽銭を差し上げるために六文が必要だというんですね。
地蔵菩薩は 「六道能化(ろくどうのうげ)」 とも呼ばれ、六道すべてに現れて衆生を救うとされる菩薩。その地蔵菩薩への布施という意味合いもあったわけです。
複合的な意味
実際には、これらの意味が 複合的に重なり合って 六道銭の習慣が形成されたと考えられます。
三途の川の渡し賃であり、六道の旅費であり、地蔵菩薩への賽銭でもある──こうした多層的な意味を持つことで、六道銭は日本人の死生観に深く根付いていったのです。
実際の使用方法

では、六道銭は実際にどのように使われていたのでしょうか?
納棺の儀式
六道銭は、納棺(のうかん) の際に死者と共に棺に納められました。
具体的には、頭陀袋(ずだぶくろ) という小さな袋に六文銭を入れ、死者の首から掛けるか、手に持たせる形で納めたんです。
頭陀袋には、六道銭のほかに以下のようなものも入れられることがありました。
頭陀袋の中身
- 六道銭(六文銭)
- 納経帳(御朱印帳)
- 死出の旅に必要な品々
納経帳というのは、生前にお寺参りでいただいた御朱印が押された帳面のこと。これを閻魔大王に見せると、罪が軽くなるという信仰がありました。
現代の六道銭
現代の日本では、本物の硬貨ではなく、紙に印刷された六道銭 を使うことが一般的です。
これには実用的な理由があります。火葬が主流になった現代では、金属製の硬貨を入れると火葬炉を傷める可能性があるため、紙製の代用品が使われるようになったんですね。
また、地域によっては六道銭の習慣そのものが簡略化されたり、行われなくなったりしているケースもあります。
世界の類似風習
興味深いことに、死者にお金を持たせる風習は日本だけのものではありません。
古代ギリシャのオボロス硬貨
古代ギリシャにも、六道銭とよく似た習慣がありました。
ギリシャ神話では、死者は 冥府の入り口にあるアケロン川 を渡る必要があります。この川の渡し守が カロン という船頭で、彼に 1オボロス硬貨 を渡さないと川を渡してもらえないとされていました。
そのため、古代ギリシャでは 死者の口に1オボロス硬貨を入れる習慣 があったんです。
共通する死生観
日本の六道銭とギリシャのオボロス硬貨──この二つの習慣には、興味深い共通点があります。
共通する要素
- あの世とこの世の境界に川がある
- 川を渡るには渡し賃が必要
- 死者にあらかじめお金を持たせておく
これは、人類が普遍的に持つ「死後の旅」のイメージ を反映しているのかもしれません。
川という境界を越えることで、死者は新しい世界へと移行する。その通過儀礼には何らかの「対価」が必要だという考え方は、東洋と西洋に共通して見られる文化なんですね。
中国の紙銭文化
中国では、前述のように 紙銭を焼いて供養する習慣 が発達しました。
現代の中国や台湾、香港などでは、紙製の「冥銭(めいせん)」や「金銀紙」を燃やす習慣が今でも盛んに行われています。さらには、紙製の家や車、電化製品まで作って燃やし、あの世で死者が使えるようにする風習もあるんです。
これも、死者があの世で困らないようにという、生者の思いやりの表れといえるでしょう。
まとめ
六道銭は、死者があの世への旅路で困らないようにと持たせる、日本の伝統的な葬送習俗です。
重要なポイント
- 六道銭とは、死者に持たせる六文の銭貨
- 三途の川の渡し賃として必要とされる
- 奪衣婆に支払うことで、船で川を渡れる
- 中国の習俗が仏教と結びついて日本に伝わった
- 平安末期から中世にかけて広まり、江戸時代に定着
- 六道の旅費、六地蔵への賽銭など、複数の意味を持つ
- 現代では紙製の代用品を使うことが多い
- 古代ギリシャにも類似の習慣があった
六道銭という小さな風習の中には、仏教の死生観、日本人の死者への思いやり、そして人類普遍の「死後の世界」への想像力が込められています。
現代では簡略化されつつある習慣ですが、そこに込められた「死者が困らないように」という優しい心は、今も私たちが大切にすべき精神なのかもしれませんね。