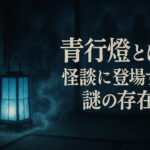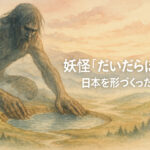「神社の鳥居や小さな社の屋根の上に、黒いものがこちらを見下ろしていた――」
そんな話を聞いたことはありませんか?これは古くから日本に伝わる妖怪「おとろし」にまつわる伝承です。
有名な妖怪とはいえないかもしれませんが、その分だけ不気味さと謎めいた魅力があり、古い集落や田舎の神社に行くと、ふと頭をよぎる存在です。
今回は、この「おとろし」の正体や由来、そしてどうして人々が恐れたのかを、わかりやすく解説します。
おとろしとはどんな妖怪?

基本的な姿と特徴
おとろしは、日本各地の伝承に登場する妖怪で、社(やしろ)や鳥居の上に潜み、下を通る人をじっと見下ろす存在です。
見た目は真っ黒な毛むくじゃらの姿で、顔には鋭い目や大きな口がついているとされます。
また、歯が異様に長く、赤黒い舌を垂らしているなど、地域によって細かな描写が異なりますが、総じて「恐ろしい姿」で語られるのが特徴です。
名前の由来
「おとろし」は、元々は「おどろおどろ」という名前でした。
一説では「おそろしい(恐ろしい)」がなまったものだとも言われています。
どちらにしろ、「恐怖そのもの」を表す妖怪ともいえるのです。
おとろしにまつわる伝承

昔から「神社の鳥居や社をくぐるとき、礼をしない者におとろしが降りかかる」と言われてきました。
無礼者を見つけると、屋根の上から大きな体をずしんと落とし、その人を驚かせたり、時には気絶させたりするとも伝えられます。
イタズラする子供の前に落ちてびっくりさせ、こらしめるという話もある。
まとめ
おとろしは、黒く毛むくじゃらの怪物として語られながらも、実は社や神様を守る大切な存在です。
こうした妖怪譚は、単に人を怖がらせるためのものではなく、自然や神聖なものへの畏れを忘れないようにする知恵でもあります。
次に神社を訪れるとき、鳥居の向こうから誰かに見られているような気がしたら――それはおとろしがあなたの作法をそっと見守っているのかもしれません。