夜の静まり返った町を、「火の用心」と声を上げながら拍子木を打って歩いている時、背後から同じような拍子木の音が聞こえてきたら…あなたはどう感じるでしょうか?
振り向いても誰もいない。でも確かに聞こえる、自分の拍子木に呼応するような音。
江戸時代の本所(現在の東京都墨田区)では、こうした不気味な体験が夜回りの人々を恐怖に陥れていました。
この記事では、本所七不思議の一つとして語り継がれる怪談「送り拍子木」について、その特徴や伝承を詳しくご紹介します。
概要
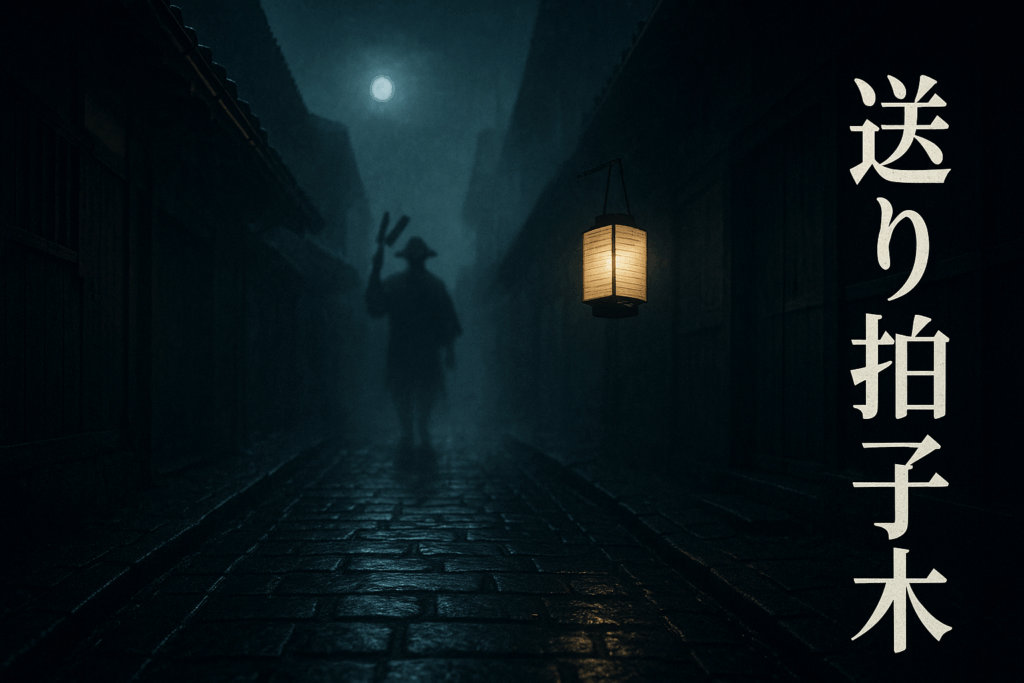
送り拍子木(おくりひょうしぎ)は、江戸時代の本所を舞台とした怪談で、本所七不思議の一つに数えられています。
本所七不思議というのは、江戸時代の本所という地域で起きたとされる七つの不思議な現象のことなんです。送り拍子木はその中でも特に有名な怪談として知られています。
どんな怪異なの?
この怪異の舞台となったのは、割下水(わりげすい)という場所の周辺でした。
夜回りの人が「火の用心」と声を上げながら拍子木を打って歩いていると、打ち終わったはずの拍子木の音が、同じような調子で背後から聞こえてくるというものです。
まるで誰かが自分を送っているかのような拍子木の音。でも振り向いても、そこには誰もいません。
音の正体は?
実は、この怪異には合理的な説明もあるんです。
静まり返った真夜中の町中で、拍子木の音が反響していただけという指摘もあります。建物や壁に音が跳ね返って、まるで別の誰かが打っているように聞こえたのかもしれませんね。
ただし、雨が降りしきる夜に、拍子木を打った覚えもないのに音が聞こえてきたという話も伝わっているので、すべてを音の反響だけで説明するのは難しいかもしれません。
伝承
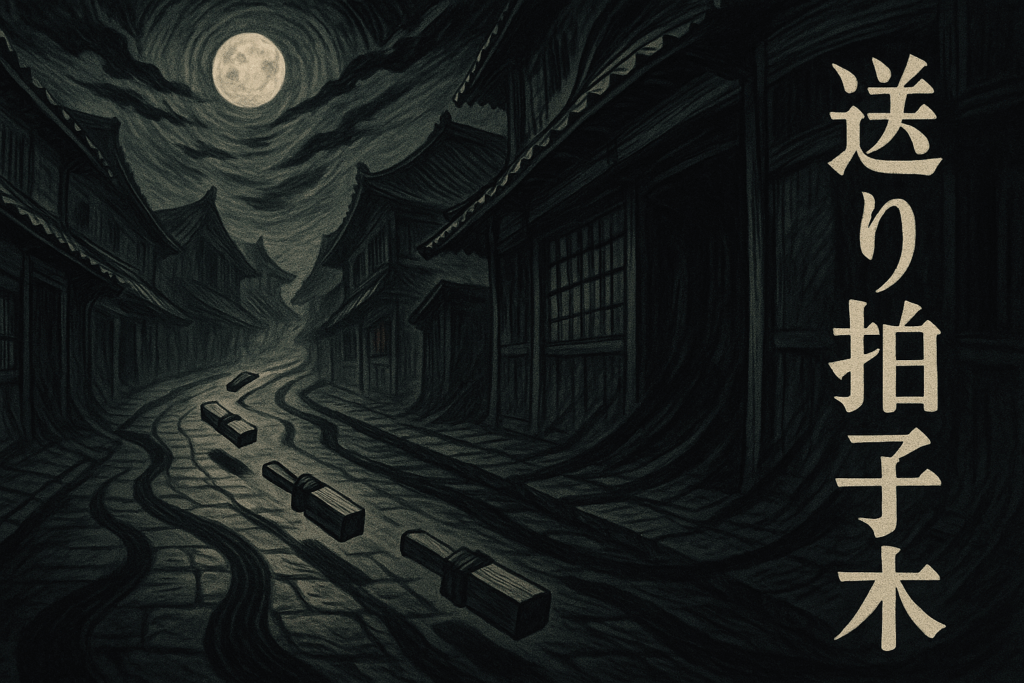
雨の夜の恐怖体験
ある雨の夜のこと、本所の町は普段にも増して静まり返っていました。
津軽藩の行灯(あんどん)が立っているだけで、その明かりがかえって不気味に感じられるような夜です。
こんな夜こそ町内の安全を守るために夜回りが出るのですが、夜回りをする人だって、こういう夜は気持ちのいいものではありません。
それでも笠の紐をしっかり締めて、恐る恐る足を踏み出しました。
不気味な呼応
「火の用心、さっしゃりやしょー……」
そう呼ばわると、どこからかチョン、チョンと拍子木の音が響いてきます。
「はて、まだ拍子木を打つ覚えはないのに」
そう思っていると、またチョーンと、どこか陰にも籠もるような響きが聞こえてくるんです。
逃げ出す夜回り
これはもはや気のせいではありません。
ぞっとした瞬間、体中がぶるぶると震えてきて、夜回りの人は逃げ出してしまいました。
当時の夜回りは、しばしばこういう目に遭ったと伝えられています。
似た怪異「送り提灯」
本所七不思議の中には、「送り提灯(おくりちょうちん)」という怪異もあります。
これは送り拍子木とほぼ同じ内容で、拍子木が提灯に変わっただけなんですね。
夜道を提灯を持って歩いていると、背後から別の提灯の明かりがついてくるけれど、振り向いても誰もいないという怪談です。
このように、本所では夜回りの人々を恐怖させる似たような怪異がいくつも語り継がれていたことが分かります。
まとめ
送り拍子木は、江戸時代の夜回りの人々が体験した不気味な音の怪異です。
重要なポイント
- 本所七不思議の一つとして江戸時代から語り継がれる
- 割下水付近が舞台となった怪談
- 拍子木を打つと、背後から同じような音が聞こえてくる
- 振り向いても誰もいないという恐怖体験
- 音の反響という合理的説明もあるが、すべてを説明できるわけではない
- 雨の日に拍子木を打っていないのに音が聞こえたという話も
- 送り提灯という類似の怪異も存在する
もし江戸時代に生まれていて、夜回りの役目が回ってきたら…静まり返った真夜中の町で、背後から聞こえてくる拍子木の音に、あなたは耐えられたでしょうか?
現代では夜回りという風習も少なくなりましたが、送り拍子木の怪談は、当時の人々の恐怖と不安を今に伝える貴重な民間伝承なんです。







