夕暮れの堀で釣りを楽しんでいたら、どこからともなく「置いてけ、置いてけ」という不気味な声が聞こえてくる…。
恐怖に駆られて逃げ帰り、家で魚籠を覗いてみると、あれほど釣れた魚が一匹も入っていない。
江戸時代の人々を震え上がらせたこの怪談は、本所七不思議の中でも特に有名な話として、今も語り継がれているんです。
この記事では、江戸の怪談「置いてけ堀」について、その伝承や正体の謎を詳しくご紹介します。
置いてけ堀ってどんな怪談なの?
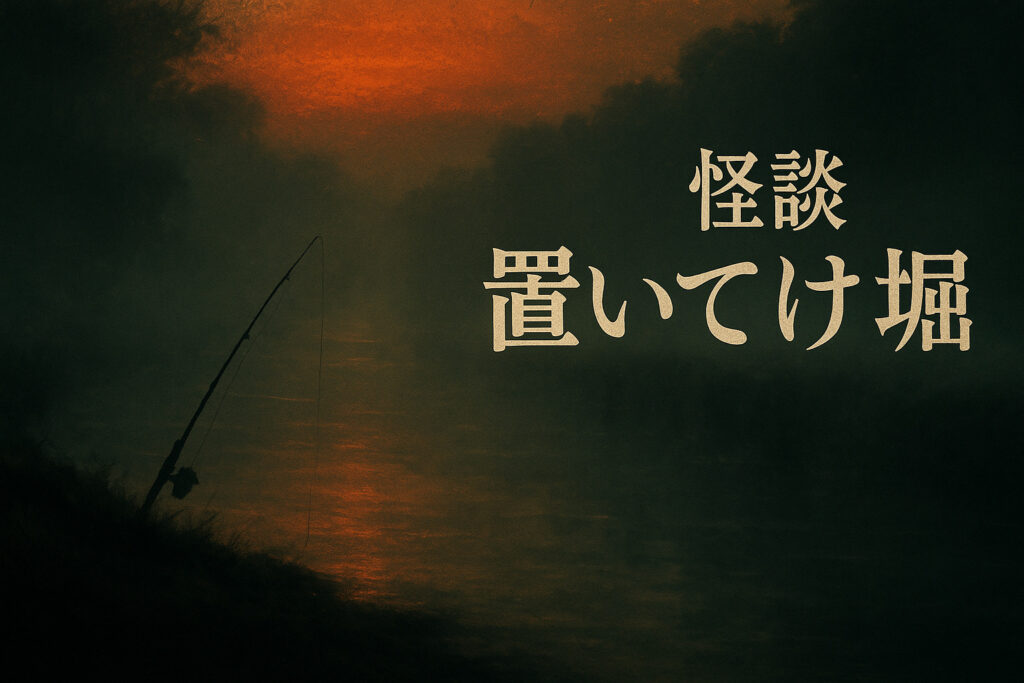
置いてけ堀(おいてけぼり)は、江戸時代の本所(現在の東京都墨田区南部)を舞台とした怪談です。
本所七不思議と呼ばれる奇談・怪談の一つで、全エピソードの中でも落語などに多用されて特に有名になりました。
実は「置いてけぼり」という言葉の語源になったともいわれているんですね。
基本的な話の内容
江戸時代の本所付近は水路が多く、魚がよく釣れる場所でした。
ある日、錦糸町あたりの堀で釣り糸を垂れていると、驚くほどよく釣れたそうです。
夕暮れになって気分良く帰ろうとすると、突然こんなことが起こります:
恐怖の展開
- 堀の中から「置いていけ」という恐ろしい声が聞こえる
- 恐怖に駆られて必死に逃げ帰る
- 家に着いて魚籠を覗くと、魚が一匹も入っていない
釣った魚を持って帰ろうとすると、必ず足がすくんだり、金縛りに遭ったりして、気がつけば魚がすべて消えてしまうというわけです。
舞台となった場所
置いてけ堀があったとされる場所は、正確には特定されていませんが、いくつかの候補地があります。
有力な候補地
- 錦糸町駅前の江東楽天地辺り
- 横綱の辺り
- 現在の墨田区江東橋付近
現在、墨田区江東橋の錦糸堀公園には河童像が建てられていて、この怪談の名残を今も見ることができます。
伝承
さまざまなバリエーション
置いてけ堀の話には、いくつかの派生バージョンが存在します。
どれも恐ろしい結末が待っているんです。
派生した物語
- 魚籠を現場に捨てて逃げ帰り、後で取りに戻ったら中身が空だった
- 友人が魚籠を持ったまま逃げようとしたら、水の中から手が伸びてきて堀に引きずり込まれた
- 釣り人以外にも、魚を持って堀を通りかかった人が魚を奪われた
- 声を無視していると金縛りに遭った
- 逃げた先でのっぺらぼうなどの別の怪異に遭遇した
特に恐ろしいのは、声に従わなかった人が命を落としたという話ですね。
各地に伝わる類似の伝説
実は置いてけ堀の伝説は、本所だけでなく他の地域にも伝わっているんです。
足立区の置いてけ堀
東武伊勢崎線の堀切駅近くにも、かつて「置いてけ堀」と呼ばれる池がありました。
こちらは千住七不思議の一つとされ、ちょっと違ったルールがあったそうです。
足立区版のルール
- 釣った魚を3匹戻せば無事に帰れる
- 1匹も返さないと蓬の草原に迷い込んで帰れなくなる
- または魚籠をひっくり返されて魚をすべて取られる
魚を返すという「代償」を払えば助かるという、交渉の余地があるバージョンですね。
台東区の伝説
台東区の蔵前一丁目にある椿神社付近にも「置いてけ堀」と呼ばれる溜め池がありました。
こちらの話は河童が主役です。
ある農民が河童の皿を釣り上げてしまい、河童が皿を返してほしくて「置いてけ」と叫んだというストーリーなんです。
埼玉県川越の伝説
川越では、小畔川の堀になった場所に置いてけ堀の伝説が伝わっています。
瀬見付近の河原を釣り人が通ると、「置いてけ、置いてけ」と呼ぶ淵があったそうで、川越版では釣った魚を返せと叫ぶのだとか。
正体は何だったのか?
この怪異の正体については、さまざまな説が唱えられています。
河童説
最も根強いのが河童の仕業という説です。
本所の隅田川や向島の源森橋、江東橋の錦糸堀、仙台堀などには河童の伝承が数多く残っているんですね。
魚を取られるという点も、水中に住む河童の仕業だと考えれば納得がいきます。
狸説
もう一つ有力なのが狸の仕業という説です。
隅田川の七福神めぐりの中にある多聞寺には狸塚が存在し、この地域では狸に存在感があったことが根拠とされています。
実は本所七不思議には狸にまつわる話が他にもあって:
- 狸囃子:近づいても囃子の音の主が分からない
- 燈無蕎麦:正体を狸とした話
- 足洗邸:屋敷から大足を突き出す怪異(狸の仕業とされる)
置いてけ堀の狸が、足洗邸と同じように大足を突き出す怪異を起こしたという話も残っているんです。
科学的な考察
「お魚博士」として知られる水産学者の末広恭雄氏は、科学的な視点から考察しています。
淡水魚のギバチという魚が、体表のトゲで大きな音を出すことに注目したんです。
実際にその音を化物と思って驚いた人がいたことから、置いてけ堀があった時代の堀にもギバチがいて、その音が怪異として恐れられたのではないかと推測しています。
そして魚が盗まれるのは、野良猫の仕業の可能性が強いと述べているんですね。
その他の説
他にも様々な説が唱えられています:
- 川獺(カワウソ)の仕業
- ムジナ(アナグマ)の仕業
- スッポンの仕業
- 猿の仕業
- 単なる追い剥ぎだった
追い剥ぎ説は、人間の犯罪者が怪異に見せかけて魚を奪っていたという、なんとも現実的な解釈ですね。
怪談が生まれた背景
置いてけ堀の舞台となった本所付近は、隅田川河口の低湿地を江戸時代に開拓した土地でした。
当時も水はけが悪く、葦原や淀みが多い環境だったそうです。
こうした薄暗く湿った環境が、怪談を生み出す舞台として最適だったんでしょうね。
この奇談は寛政年間(1789年~1801年)に創作されたといわれています。
まとめ
置いてけ堀は、江戸時代の人々の恐怖と不安を象徴する代表的な怪談です。
重要なポイント
- 本所七不思議の中で最も有名な怪談の一つ
- 「置いてけ、置いてけ」という声が聞こえ、魚が消える
- 足立区、台東区、川越など各地に類似の伝説が存在
- 正体は河童、狸、ギバチなど諸説ある
- 「置いてけぼり」という言葉の語源になったとされる
- 現在も錦糸堀公園に河童像が残る
もし夕暮れ時に釣りをしていて、どこからともなく「置いていけ」という声が聞こえてきたら…それは数百年前から語り継がれる怪異の声かもしれません。
釣った魚は、素直に置いていった方が安全かもしれませんね。







