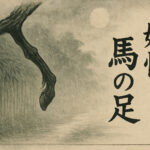空を火の車輪で駆け抜け、龍を倒し、自らの命を父に返して蓮の花から甦った少年神がいます。
中国神話に登場する哪吒(ナタ)は、まさに型破りな英雄なんです。
父との確執、龍王との戦い、そして驚きの復活劇。その波乱万丈な物語は、千年以上経った今でも中国の人々に愛され続けています。
この記事では、蓮の花の化身として知られる少年神「哪吒」について、その不思議な姿や特徴、衝撃的な伝承をやさしくご紹介します。
概要

哪吒(ナタ)は、中国の道教や仏教、民間信仰で崇められている神様です。
正式な道教での呼び名は中壇元帥(ちゅうだんげんすい)といいます。他にも太子爺、哪吒三太子、通天太師など、たくさんの尊称で呼ばれているんです。
哪吒は托塔天王(たくとうてんのう)こと李靖(りせい)の三男として生まれました。長兄は金吒(きんた)、次兄は木吒(もくた)といいます。
中国の古典小説『封神演義』や『西遊記』などに登場し、その勇敢な活躍ぶりで読者を魅了してきました。
特に注目すべきは、哪吒が蓮の花の化身だということ。一度命を失った後、師匠の力で蓮の花から新しい体を作ってもらい、復活を遂げたんです。
偉業・功績
哪吒の最も有名な功績は、九十六洞の妖魔を降伏させたことです。
『西遊記』によれば、哪吒は復活後に神通力を使って数多くの妖怪や魔物を退治しました。その武功により、三壇海会大神という高い位を天帝から授かっています。
また、『封神演義』では周王朝を助ける先鋒として活躍。数々の戦いで敵将を次々と倒し、周の天下統一に大きく貢献しました。
主な戦果
- 東海龍王の三太子・敖丙(ごうへい)を討伐
- 石磯娘々(せききじょうじょう)を九龍神火罩で焼き払う
- 多数の妖魔・魔王を降伏させる
- 周王朝の勝利に貢献
『西遊記』では孫悟空と互角に渡り合ったり、牛魔王を降伏させたりと、天界軍の主力として大活躍しています。
天界における哪吒の地位は非常に高く、玉皇大帝(天界の最高神)の三十六員第一総領使、つまり三十六人の天将の筆頭に任命されているんです。
系譜
哪吒の家族構成を見てみましょう。
哪吒の家系図
- 父:李靖(りせい)- 托塔天王、陳塘関の総兵
- 母:殷氏(いんし)または素知(そち)- 李靖の妻
- 長兄:金吒(きんた)- 釈迦如来の弟子
- 次兄:木吒(もくた)- 観音菩薩の弟子
- 本人:哪吒(ナタ)- 太乙真人の弟子
- 妹:貞英(ていえい)-『西遊記』にのみ登場
興味深いことに、哪吒の兄弟はそれぞれ別の師匠に弟子入りしているんですね。
父の李靖は、元々はインド神話の財宝神クベーラ(仏教では毘沙門天)と同一視された人物です。唐代の実在の武将・李靖をモデルにしたとも言われています。
哪吒自身の正体は、『封神演義』によれば霊珠子(れいじゅし)という宝物の生まれ変わりとされています。師匠の太乙真人から李靖夫婦に与えられ、人間として誕生したんです。
『三教源流捜神大全』では、元々は玉皇大帝の側近である大羅仙(大羅天の仙人、仙人の最高位)だったと記されています。
姿・見た目

哪吒の姿は、文献によって少し違いがあります。
基本的な外見
一般的に知られている哪吒の姿はこうです。
- 年齢:永遠の少年(7歳~15歳程度の見た目)
- 服装:蓮の花や蓮の葉で作られた衣装
- 身長:『封神演義』では1丈6尺(約5メートル)だが、見た目は少年
『封神演義』での姿
蓮の花びらを身にまとい、若々しい青少年の姿をしています。復活後の体は蓮の茎が骨、蓮根が肉、蓮の葉が衣となって作られたため、血肉も魂魄も持たない特殊な体なんです。
そのおかげで、魂や血液に直接ダメージを与える妖術が効かないという利点があります。
『西遊記』での姿
こちらではもっとワイルドな戦闘形態が描かれています。
三頭六臂(さんとうろっぴ)という姿に変身できるんです。
三頭六臂の姿
- 頭:3つの頭
- 顔:濃い青色で鋭い牙を持つ
- 髪:赤い
- 腕:6本(8本という説も)
- 武器:斬妖剣、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、綉球、火輪など6種類
この姿になると、武器を何千何万にも増やして、まるで兵器の雨のように敵を攻撃できるそうです。
『三教源流捜神大全』での姿
こちらはさらに壮大な姿が記されています。
- 身長:六丈(約18メートル)
- 頭:3つ
- 目:9つ
- 腕:8本
- 首飾り:金輪
一声叫べば雨雲が従い、天地が轟動するほどの力を持つ巨神として描かれているんです。
特徴
哪吒には他の神々にはない、独特の特徴がたくさんあります。
驚異的な成長速度
哪吒は生まれた時から特別でした。
- 誕生直後から歩くことも話すこともできた
- わずか3日後(7日後という説も)に海で遊んで東海龍王と争った
- 7歳で龍王の息子を倒すほどの戦闘力
普通の子供とは全く違う成長ぶりですね。
不思議な誕生
哪吒の誕生自体が非常に奇妙なんです。
母の殷氏は3年6ヶ月もの長い間、身ごもっていました。そして生まれてきたのは赤ちゃんではなく、巨大な肉の塊(肉球)だったんです。
父の李靖は妖怪だと思って剣で切り裂いたところ、中から元気な男の子が飛び出してきたという驚きの誕生劇。
その時、哪吒の左手には「哪」、右手には「吒」という文字が浮かんでいたので、その名前がつけられました。
最強の武器コレクション
哪吒が持つ宝具(武器)は、どれも特別な力を持っています。
哪吒の主な武器
- 風火輪(ふうかりん):火と風を起こす車輪。両足に装着して空を飛ぶ
- 火尖槍(かせんそう):炎を放つ槍。師匠の太乙真人から授かった
- 乾坤圏(けんこんけん):金色のリング。投げれば敵を必ず傷つける
- 混天綾(こんてんりょう):水を振動させたり、敵を縛る不思議な布
- 九龍神火罩(きゅうりゅうしんかしょう):9匹の火龍が入った法宝
- 金磚(きんせん):純金製の投擲武器
これらの武器を使いこなし、あらゆる妖怪を退治してきたんです。
毒や病気が効かない体
蓮の花から作られた体のため、哪吒は毒や疫病に対する完全な耐性を持っています。『封神演義』では、他の武将たちが次々と病に倒れる中、哪吒だけは平気だったという場面があります。
父との複雑な関係
哪吒の物語で最も印象的なのが、父・李靖との関係です。
龍を殺して問題を起こし、父に責められた哪吒は、自らの肉を切って母に返し、骨を抜いて父に返して自害しました。これは「生んでくれた恩を返す」という意味だったんです。
しかし復活後、李靖が哪吒の廟を焼き払ったことから、二人の対立は激化。哪吒は父に復讐しようとしますが、最終的には釈迦如来(または燃灯道人)の仲介で和解することになります。
李靖は釈迦如来から如意黄金宝塔という法宝を授かり、この塔の力で哪吒を抑えることができるようになったんです。だから「托塔李天王」(塔を持つ李天王)と呼ばれているんですね。
伝承
哪吒の物語で最も有名なのが、東海龍王との戦いです。
東海龍王との争い
ある暑い夏の日、7歳の哪吒は母の許しを得て海で遊びに出かけました。
使用人と一緒に九湾河という川で水遊びをしていた哪吒は、体を洗うために混天綾を水に浸しました。すると、この布の力で海底にまで震動が伝わり、東海龍王の宮殿が揺れ始めたんです。
驚いた龍王は、部下の夜叉・李良を派遣して様子を見に行かせます。
しかし李良は哪吒に対して横柄な態度を取ったため、怒った哪吒は乾坤圏で李良を一撃で倒してしまいました。
次に龍王の三男・敖丙が出動しますが、哪吒との戦いに敗れ、背筋を引き抜かれてしまいます。哪吒はその筋を父へのプレゼントにしようとしたんです(実際には父に怒られることを恐れて渡せなかった)。
石磯娘々事件
龍王事件の後、哪吒はまた別の事件を起こします。
陳塘関の城壁に登った哪吒は、黄帝の時代から伝わる神弓・乾坤弓を見つけました。興味本位で矢を放ったところ、遠く離れた白骨洞まで飛んでいき、そこにいた石磯娘々の弟子を射殺してしまったんです。
怒った石磯娘々は李靖を捕まえますが、哪吒の師匠・太乙真人が現れて、九龍神火罩の炎で石磯娘々を焼き払いました。
自害と復活
龍王たちは天帝に訴えようとし、李靖は息子のせいで一家が罰せられることを恐れました。
両親を守るため、哪吒は驚くべき決断をします。
「肉を切って母に返し、骨を抜いて父に返す」
つまり、自分の体を両親に返上して自害したんです。これは生んでもらった恩を返すという意味でした。
しかし話はここで終わりません。
哪吒の魂は師匠のもとへ向かい、太乙真人は蓮の茎を骨に、蓮根を肉に、蓮の葉を衣にして新しい体を作り、哪吒を復活させました。
復活した哪吒は以前よりも強力な力を得て、風火輪などの新しい武器も授かったんです。
『西遊記』での活躍
『西遊記』では、哪吒は天界の重要な武将として登場します。
孫悟空が天界で暴れた時、父の李靖と共に討伐に向かいました。巨霊神が負けた後、哪吒が出陣。
孫悟空は哪吒の子供のような外見を見て油断しますが、哪吒が三頭六臂の姿になると驚きます。悟空も同じ姿に変身し、30回以上も互角の戦いを繰り広げました。
その後も哪吒は、獨角兕大王や牛魔王との戦いで孫悟空を助けます。特に牛魔王との最終決戦では、哪吒が火輪で炎を吹きかけて巨大な牛を焼き、父の照妖鏡と協力して降伏させるという活躍を見せました。
出典・起源
哪吒のルーツは、実は中国ではなくインドにあるんです。
インド神話からの伝来
哪吒の原型は、インド神話に登場するナラクーバラ(Nalakuvara)という神様です。
ナラクーバラは、財宝の神クベーラの息子で、『ラーマーヤナ』などに登場する勇敢な夜叉の将軍でした。
クベーラが仏教に取り入れられて毘沙門天(びしゃもんてん)になると、その息子であるナラクーバラも一緒に仏教に吸収されたんです。
名前の変化
「ナラクーバラ」という名前が中国に伝わる過程で、少しずつ変化していきました。
名前の変遷
- 那羅鳩婆羅(ナラクーバラの音訳)
- 捺羅俱跋羅
- 那吒矩韈囉
- 那吒(ナタ)
- 哪吒(現在の表記)
「那」に口偏をつけた「哪」という字になって、現在の形になったんですね。
中国での発展
中国に伝わった後、哪吒の物語は大きく変化していきます。
晋代(3~5世紀)頃に中国での記録が始まり、宋代(10~13世紀)には道教の護法神として確立されました。
宋の洪邁が書いた『夷堅志』には、道士が「哪吒火球咒」という呪文を使って石の妖怪を撃退する話が載っています。
李靖との関係
哪吒の父・李靖は、唐代初期の実在の武将をモデルにしています。
この李靖が毘沙門天と同一視されたことで、毘沙門天の息子だったナラクーバラが、李靖の息子・哪吒として再構成されたんです。
元素のコバルトの名前も、鉱山に現れる精霊「コベル」(ナタの別名の一つ)に由来するという説があります。当時の鉱夫が扱いにくいコバルト鉱石を精霊のいたずらだと考えたからだそうです。
文学作品での完成
哪吒の物語は、明代(14~17世紀)の神怪小説で完成形を迎えます。
『三教源流捜神大全』で道教の神としての設定が確立され、『封神演義』で詳細な物語が語られ、『西遊記』で天界の武将として活躍する姿が描かれました。
これらの作品を通じて、インドから来た神様は完全に中国化され、中国神話の代表的なキャラクターとなったんです。
まとめ
哪吒は、インド神話から中国に渡り、独自の発展を遂げた少年神です。
重要なポイント
- インド神話のナラクーバラが起源の神様
- 托塔天王・李靖の三男で、蓮の花から生まれた
- 風火輪、火尖槍など多彩な武器を使う
- 東海龍王の息子を倒し、自害後に蓮の花で復活
- 父との確執と和解という人間臭い物語を持つ
- 九十六洞の妖魔を降伏させた天界の英雄
- 『封神演義』『西遊記』などの古典文学に登場
- 道教では中壇元帥として現在も崇拝されている
龍を倒し、自らの命を捨て、そして復活を果たした哪吒。その破天荒な物語は、千年以上経った今でも多くの人々を魅了し続けています。中国では子供の守護神として、今も篤く信仰されているんです。
参考文献
- 『封神演義』- 明代の神怪小説
- 『西遊記』- 明代の伝奇小説
- 『三教源流捜神大全』- 道教の神々を記録した書物
- 『平家物語』における類似の合成獣・鵺との比較
- Meir Shahar による哪吒の起源研究
- 各種仏教経典(『毘沙門儀軌』『佛說最上祕密那拏天經』など)