日本神話のはじまりに登場する「別天津神(ことあまつかみ)」という言葉を聞いたことがありますか?
名前は知っているけれど、具体的にどんな神さまたちなのか、どんな役割を持っていたのかは意外と知られていません。
この記事では、別天津神の基本から、登場する神話、現代とのつながりまでをわかりやすく解説します。読み終わるころには、日本の神話をもっと身近に感じられるはずです。
別天津神ってなに?
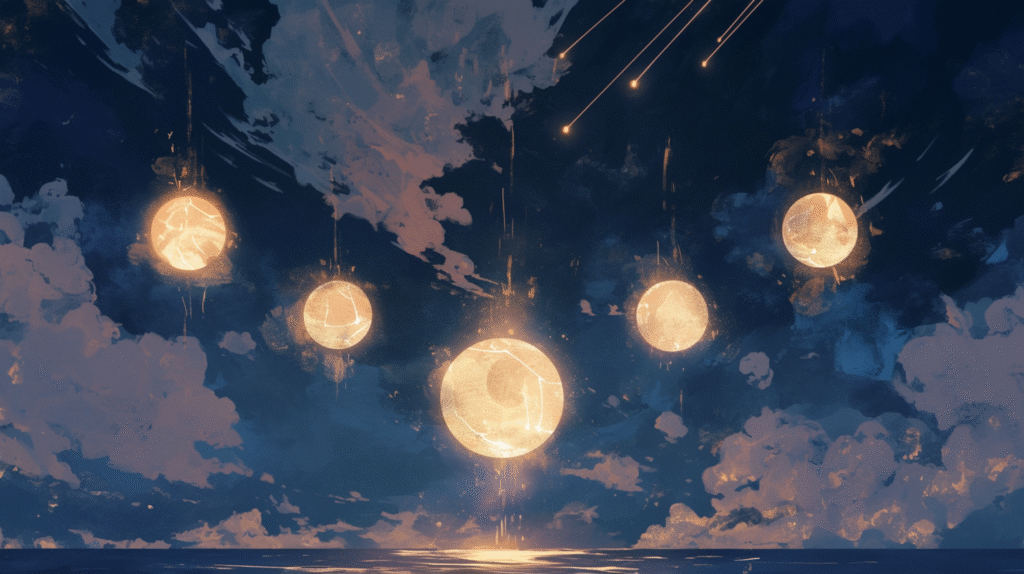
簡単に言うと…
別天津神(ことあまつかみ)は、『古事記』において天地がはじめて分かれたときに現れた、最初の五柱(いつはしら)の神さまたちの総称です。
「天津神(あまつかみ)」とは高天原(たかまのはら)にいる神々のことを指し、「別天津神」はその中でも特別に最初に現れた神々という意味なんです。
古事記・日本書紀での位置づけ
古事記では天地開闢(てんちかいびゃく)の際、まず別天津神が姿を現し、その後に多くの神々が生まれていく流れが描かれています。
これにより、別天津神は宇宙や自然のはじまりを司る、非常に重要な神々とされているんですね。
五柱の別天津神の名前と特徴
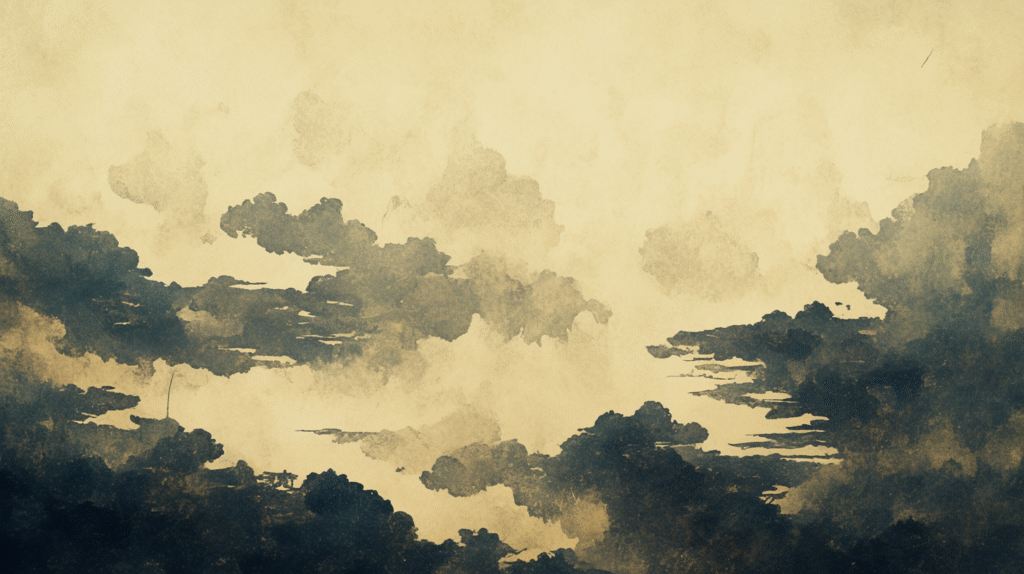
五柱の神々
別天津神は次の五柱です。
- 天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ):宇宙の中心
- 高御産巣日神(たかみむすひのかみ):生成・創造・高天原の重鎮
- 神産巣日神(かみむすひのかみ):生成・創造
- 宇摩志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこぢのかみ):生命力
- 天之常立神(あめのとこたちのかみ):天の永久性
どんな役割?
これらの神さまたちは、実は具体的な神話のエピソードにはほとんど登場しません。
主に宇宙の秩序をつくる存在として記されています。
他の神話との違い
ギリシャ神話や北欧神話では、神々が人間のように物語の中で活発に動きますが、日本神話の別天津神は「顕(あらわ)れただけ」で姿を隠します。
この点が、日本特有の神観念ともいえるでしょう。
現代での別天津神の信仰や影響
神社での祀られ方
別天津神を単独で祀る神社は少ないですが、天之御中主神を主祭神とする神社(例えば妙見社)があります。
また、高御産巣日神や神産巣日神は伊勢神宮や出雲大社の祭神と深く関わっています。
まとめ
別天津神は、日本神話のはじまりに現れた五柱の神さまたちです。
物語の中で活躍するタイプではありませんが、天地の秩序を司る特別な存在であり、日本の精神文化に深く根付いています。
こうした神話を知ることで、神社参拝や自然を見つめる視点も変わってくるかもしれません。







