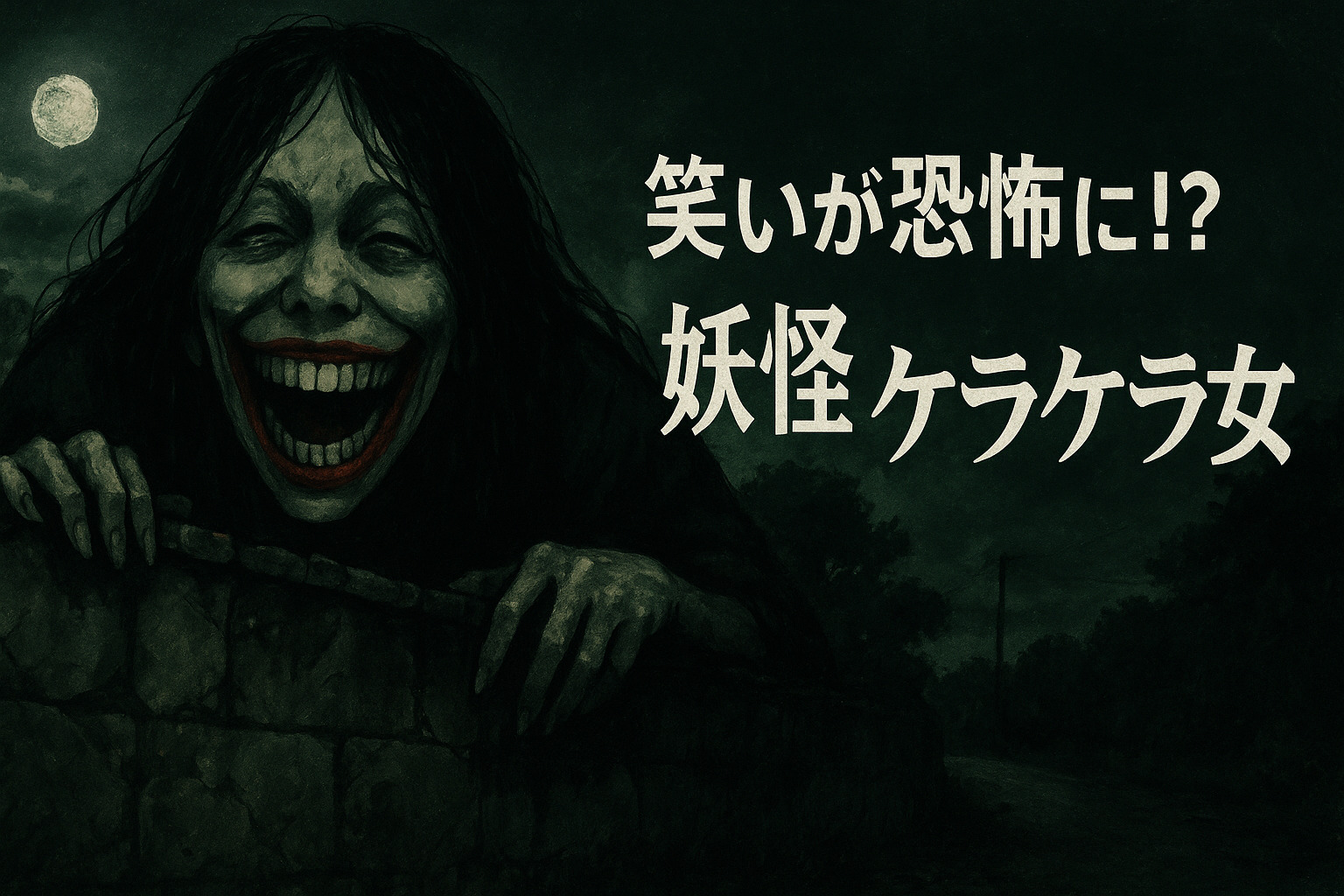夜道を一人で歩いているとき、どこからともなく「ケラケラ」という女性の笑い声が聞こえてきたら…あなたはどう感じるでしょうか?
普通なら楽しそうな笑い声のはずなのに、なぜかゾッとしてしまうかもしれません。
江戸時代から語り継がれる「ケラケラ女」は、まさにそんな不気味な笑い声で人を恐怖に陥れる妖怪です。
この記事では、江戸時代の妖怪画に登場する「ケラケラ女」について、その不気味な姿から心を不安にさせる特徴、そして現代まで続く恐ろしい笑い声の伝承まで、詳しくご紹介します。
ケラケラ女ってどんな妖怪?
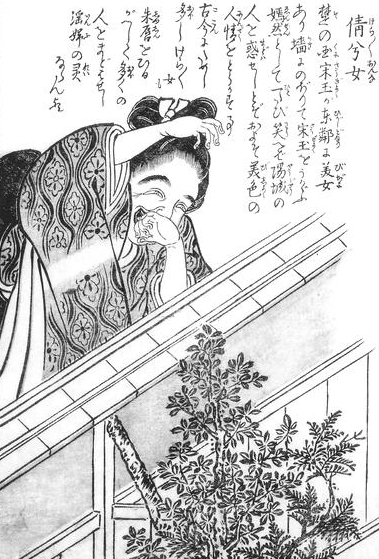
ケラケラ女とは、江戸時代から伝えられている妖怪で、「ケラケラ」という笑い声そのものが恐怖となって現れる存在です。
- 漢字表記:倩兮女
- 初出:江戸時代『画図百鬼夜行』(鳥山石燕作)
姿・見た目
以下は、基本的な外見の特徴です。
- 女性
- 赤い口紅を塗っている
- 体が大きく塀の上から覗いている
- 時に首だけの姿で現れる
特徴・伝承
ケラケラ女は塀の上から覗いて、大きな声で「ケラケラ」と笑い続けます。
現代では、人が通っていない道に現れ、通行人に笑いかけてくるそうです。
彼女は意味もなく笑い続けてくるので、とても不気味です。
さらに、その声は1人だけにしか聞こえないので、人をとても不安にさせます。
まとめ
ケラケラ女は、「笑い声」という本来ポジティブなはずの音を恐怖の対象に変えてしまう、非常にユニークな妖怪です。
重要なポイント
- 「ケラケラ」という笑い声が特徴
- 塀の上から覗く大きな女性の姿
- 意味のない笑い声で人を不安にさせる
- 一人だけに聞こえる恐怖