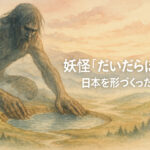「カッパ」と聞くと、ちょっと不気味だけどどこか愛嬌も感じる…。そんなイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。
川や池に住むと言われるカッパは、日本中に昔から伝わる有名な妖怪です。
でも実際はどんな名前の由来があって、どんな姿をしていて、どんな面白いエピソードがあるのか、知っている人は意外と少ないかもしれません。
この記事では
- 名前の由来
- 見た目の特徴
- 性格や行動のポイント
- 興味深い逸話
- カッパの起源
- なぜ生まれたのか?
を分かりやすく紹介します。
名前

カッパの語源は「かわっぱ」。
これは「川(かわ)」の「わっぱ(童)」で「川(かわ)の子ども」の意味
かわっぱが変化して「カッパ」になった。
また、カッパの呼び方は、地域によっていろいろ。
- ガタロ(関西)
- エンコ(関東)
- ミズチ(中部)
など、川や水に関係する名前、特定の動物に近しい名前が多いのが特徴です。
姿・見た目

カッパの見た目は、昔話や絵巻などによく描かれています。
カッパの基本的な姿
- 緑色の肌
- 亀の甲羅(こうら)
- 頭に「皿」がのっている(さらに水が入っている)
- くちばし
- 手足に水かき
一部伝承では、両腕が体内で繋がっている(片方を引っ張ると、もう一方が縮む)、お尻の穴が3つあると言われている。
特徴
カッパには、以下の特徴がある。
特徴
- いたずら好き
- 人を川に引きずり込もうとすることもある
- 頭の皿の水をこぼされたり、皿が割れると力が入らなくなる
- 相撲(すもう)やキュウリ(夏の野菜)が大好き
- しりこだまや人間の肝を食べる
しりこだまは人間の内臓の一つで、抜かれると死ぬと言われています。
逸話

日本各地にカッパの話は残っています。その多くは人間との不思議なやりとりを描いたものです。
カッパの伝説
- 川に落ちた子どもを助けてくれた話
- お供え物をしたら、溺れた人を助けてくれる話
- 相撲を取ったあと、礼儀正しく頭を下げて皿の水をこぼしてしまい負けた話
他にも全国各地にカッパの逸話や伝説が残されています。
「カッパと相撲」
カッパはとても相撲が強いらしいが、彼らに勝利する方法が2つある。
- 相撲の時に頭を下げる
カッパは律儀にお辞儀し返し、そのせいでお皿の水をこぼしてしまって力が出なくなる - 試合前に仏前にお供え物をする
カッパの起源

カッパの起源については諸説あるのだが、次の3つが主。
- 人形からカッパになった説
- 水神が格落ちしてカッパになった説
- 外国から渡来してきた説
溺死体
「カッパがなぜ生まれたのか?信じられたのか?」
という疑問があるかもしれません。
実は、カッパが生まれた経緯については、溺死体が大きく関わっているんじゃないかと言われています。
具体的な描写は避けますが、溺れた人の死体は見ない方がいいと言われるほどの状態。
また、溺死すると、肛門括約筋が弛緩し、お尻の穴が開いた状態になるらしい。
そんな異様な死体を見た昔の人が、カッパのような妖怪を生み出したのでしょう。
まとめ
今回は、妖怪カッパについて
- 名前の由来
- 見た目の特徴
- 性格や弱点
- 面白い逸話
をお話ししました。
昔から伝わる話には、人間と自然、そして見えないものへの畏れ(おそれ)が込められています。
川や池に行くときは、ちょっとカッパのことを思い出してみてくださいね