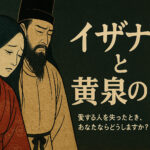愛する人を失ったとき、あなたならどうしますか?
日本の神話には、最愛の妻を失った神様が、死者の世界まで会いに行くという壮大な物語があります。それが「イザナギの黄泉国訪問」という神話なんです。
この記事では、日本神話における生と死、そして愛と別れを描いた「イザナギと黄泉の国」の物語を詳しくご紹介します。
概要

イザナギとイザナミは、日本列島を生み出した夫婦神です。
『古事記』や『日本書紀』という日本最古の書物に記された神話によると、二柱の神は協力して数々の島々や神々を生み出しました。しかし、イザナミが火の神を産んだときに大やけどを負って亡くなってしまい、イザナギは妻を追って死者の国「黄泉国(よみのくに)」を訪れることになります。
そこで起こる衝撃的な出来事は、生と死の境界、そして別れの必然性を表す重要な神話として、今も語り継がれているんです。
イザナギとイザナミの物語
まずは、二柱の神がどのような存在だったのか見ていきましょう。
国生みと神生み
イザナギ(伊邪那岐命)とイザナミ(伊邪那美命)は、天の浮橋という場所に立ち、天の沼矛(あめのぬぼこ)で海をかき混ぜました。すると、矛の先から滴り落ちた雫が島となり、これが日本列島の始まりとなったんです。
二柱の神が生み出したもの
- 淡路島や隠岐島をはじめとする日本の島々
- 海の神、風の神、山の神、木の神、船の神など
- 自然界を司る様々な神々
これは、海に風が吹き、山に木が育ち、川に船が行き交うようになった様子を表しているんですね。
悲劇の始まり
順調に見えた国づくりに、突然悲劇が訪れます。
イザナミが火の神・カグツチ(軻遇突智)を産んだとき、あまりの熱さに女陰に火傷を負ってしまったんです。病に臥したイザナミは、尿や糞、吐瀉物からも神々を生み出しながら、ついに息を引き取りました。
『古事記』によれば、イザナミの遺体は出雲と伯耆の境にある比婆山に葬られたとされています。
黄泉の国への訪問
愛する妻を失ったイザナギは、どうしてもイザナミに会いたくなりました。
決断
イザナギは、死者の国である黄泉国へと向かう決断をします。黄泉国とは、地下にある暗黒の世界で、すべての死者が向かうとされた場所なんです。
黄泉国の特徴
- 地下世界にある死者の国
- あたりは真っ暗で、火を灯さなければ何も見えない
- 生前の罪をつぐなう地獄ではなく、すべての死者が行く場所
- 黄泉比良坂(よもつひらさか)という坂で現世と隔てられている
戸口での約束
イザナギが黄泉国の入り口に着くと、イザナミが出迎えました。
イザナミは悲しげにこう言いました。
「私はもう黄泉の食べ物を食べてしまったので、現世には戻れません。でも、あなたがわざわざ来てくださったので、黄泉の神と相談してみます。その間、決して私の姿を見ないでください」
黄泉戸喫(よもつへぐい)という、黄泉国の食べ物を口にすると、もう現世には帰れなくなるという決まりがあったんですね。
恐ろしい姿との遭遇
しかし、イザナギは待ちきれなくなってしまいます。
禁忌を破る
長い時間待たされたイザナギは、我慢できずに火を灯して中を覗いてしまいました。
そこで見たものは、想像を絶する光景でした。
イザナミの変わり果てた姿
- 体中にウジ虫がわいている
- 全身から八柱の雷神(やくさのいかずち)が生じている
- かつての美しい姿は完全に失われている
この恐ろしい光景に、イザナギは恐怖で逃げ出してしまったんです。
追跡劇と脱出

自分の姿を見られたイザナミは激怒しました。
黄泉醜女の追跡
「私に恥をかかせた!」
イザナミは予母都志許売(よもつしこめ)という黄泉国の鬼女たちに、イザナギを追わせます。
イザナギの防御方法
- 黒御蔓(くろみかずら)を投げる → 山葡萄が生えて、鬼女たちがそれを食べている間に逃げる
- 湯津津間櫛(ゆつつまぐし)を投げる → 筍(たけのこ)が生えて、またその間に逃げる
さらに千五百もの黄泉軍が追ってきましたが、イザナギは黄泉比良坂にあった桃の実を投げつけて退散させました。
桃の霊力
古代中国の道教では、桃は魔除けや不老不死の効能があるとされる神聖な果物でした。日本に桃が伝わった8世紀初頭、この思想も一緒に取り入れられたんですね。
イザナギは桃に「葦原中国にいる人々が苦しんでいるときは助けるように」と告げて、意富加牟豆美命(おおかむづみのみこと)という名前を与えました。
黄泉比良坂での別れ
ついにイザナミ自身が追ってきました。
永遠の別離
イザナギは、千人がかりで引くほどの巨大な岩「千引の石(ちびきのいわ)」を黄泉比良坂に引いて、道を塞ぎました。
岩を挟んで、二柱の神は最後の会話を交わします。
イザナミ:「愛しい夫よ、こんなひどいことをするなら、私は一日に千人の人間を殺すでしょう」
イザナギ:「愛しい妻よ、それなら私は一日に千五百の産屋を建てて、千五百人の子どもを産ませよう」
この会話は、人間の生と死を説明する神話的な意味を持っているんです。毎日人は死ぬけれど、それ以上に新しい命が生まれる。だから人類は続いていくという考え方なんですね。
こうして二柱の神は永遠に別れることになり、イザナミは黄泉津大神(よもつおおかみ)、道敷大神(ちしきのおおかみ)と呼ばれるようになりました。
禊と新たな神々の誕生
黄泉国から戻ったイザナギは、汚れを清めるために水で禊(みそぎ)をしました。
このとき、左目を洗うと天照大神(あまてらすおおみかみ)が、右目を洗うと月読命(つくよみのみこと)が、鼻を洗うと須佐之男命(すさのおのみこと)が生まれました。
死と別れから、新たな生命が誕生する。これは世界中の古代神話によく登場するテーマなんです。
黄泉の国とは何か
黄泉国について、もう少し詳しく見てみましょう。
黄泉の特徴
黄泉という言葉は、もともと中国の古典『春秋左氏伝』や『史記』などに見られる漢語から借用されたものです。
日本では「ヨミ」または「ヨモ」と読まれていましたが、この言葉の本当の意味については諸説あります。
語源の説
- 「夜見」:暗黒の国という意味
- 「四方(よも)つ国」:地上世界を取り巻く国
- 「忌み籠る国」:忌むべき国
場所の伝承
『古事記』では、黄泉比良坂は「出雲国の伊賦夜坂(いふやさか)」だとされています。現在の島根県松江市東出雲町揖屋には、黄泉比良坂の伝承地があり、「千引きの磐座」と呼ばれる岩が残されているんです。
また、『出雲国風土記』には出雲郡の猪目洞窟が「黄泉の坂・黄泉の穴」として記録されています。この洞窟からは弥生時代から古墳時代の人骨や副葬品が発見されており、古代の葬送地だったことが分かっています。
このように、出雲地方には黄泉国と関連する伝承が数多く残されているんですね。
黄泉国の住人たち
黄泉国には、イザナミを頂点とする様々な存在がいました。
黄泉国の神々と存在
- 黄泉津大神:黄泉国の主宰神(イザナミのこと)
- 予母都志許売:黄泉国の鬼女たち
- 八雷神:イザナミの体から生じた八柱の雷神
- 黄泉軍:千五百の軍勢
興味深いのは、『古事記』ではこれらの神々に「命(みこと)」という尊称がつけられていない点です。死者の国の神々に対する、当時の人々の複雑な態度が反映されているんですね。
世界に共通する死者の国の物語
実は、イザナギの物語と似た神話が世界中にあるんです。
ギリシャ神話のオルペウス
最も有名な類似例が、ギリシャ神話の「オルペウスとエウリュディケ」の物語です。
オルペウス神話のあらすじ
- 琴の名手オルペウスの妻エウリュディケが死んでしまう
- オルペウスは冥府の神ハデスに琴を奏でて懇願する
- ハデスは「冥界から出るまで決して振り返ってはならない」という条件で承諾
- しかし出口直前で不安に駆られたオルペウスは振り返ってしまう
- 妻は永遠に冥界に戻ってしまう
イザナギが「見てはいけない」という約束を破ったのと、オルペウスが「振り返ってはいけない」という約束を破ったのは、驚くほどよく似ていますよね。
共通するテーマ
これらの神話に共通するのは、以下のようなテーマです。
- 愛する者を取り戻したいという強い願い
- 死者の世界への訪問
- 守らなければならない禁忌(タブー)
- 禁忌を破ることによる永遠の別れ
- 生者と死者は決して一緒にはなれないという教訓
古代の人々は、世界中で同じような死生観を持っていたのかもしれません。
まとめ
イザナギと黄泉の国の神話は、生と死、愛と別れを描いた日本神話の根幹をなす物語です。
重要なポイント
- イザナギとイザナミは日本列島と神々を生み出した夫婦神
- イザナミは火の神を産んで亡くなり、黄泉国へ行く
- イザナギは妻を追って黄泉国を訪問するが、約束を破って妻の変わり果てた姿を見てしまう
- 追跡劇の末、千引の石で黄泉比良坂を塞ぎ、二柱は永遠に別れる
- 「一日千人殺す」「一日千五百人産む」という会話で、人間の生死の循環が説明される
- イザナギの禊から天照大神などの重要な神々が誕生する
- 黄泉国は出雲地方に入り口があるとされ、今も伝承地が残る
- 世界中に類似した「死者の国訪問」神話が存在する
この神話は、愛する者を失った時の悲しみ、取り戻したいという願い、そして生者と死者は決して交わることができないという厳しい現実を教えてくれています。同時に、死から新たな生命が生まれるという希望も表現されているんです。
島根県に行く機会があれば、ぜひ黄泉比良坂の伝承地を訪れてみてください。数千年前の人々が感じた生と死の境界に、思いを馳せることができるかもしれませんね。