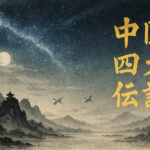夜空に輝く天の川を見たことはありますか?
日本では七夕の夜、この天の川を挟んで年に一度だけ会える織姫と彦星の物語が語り継がれています。実はこの伝説、中国から伝わった「牛郎織女(ぎゅうろうしょくじょ)」という古い物語が元になっているんです。
天を統べる神々に引き裂かれた二人の愛、年に一度だけ許される再会、そして二人の橋渡しをする鳥たちの物語。今から2000年以上も前から語り継がれてきたこの伝説には、いくつかのバージョンがあり、時代とともに変化してきました。
この記事では、中国四大民間伝説の一つ「牛郎織女」について、その物語の内容や起源、日本の七夕との関係まで分かりやすくご紹介します。
概要
牛郎織女(ぎゅうろうしょくじょ)は、中国で古くから伝わる恋愛説話です。
天界の機織り(はたおり)の名手である織女(しょくじょ)と、地上で牛飼いをしていた牛郎(ぎゅうろう)が恋に落ちて結婚しますが、天の掟を破ったことで天帝や西王母(せいおうぼ)に引き裂かれてしまいます。天の川の両岸に離れ離れにされた二人は、年に一度、7月7日だけカササギ(鵲)が架ける橋を渡って再会することを許されました。
この物語は中国四大民間伝説の一つとされ、七夕(たなばた)祭りの起源となった伝説です。日本では織女を「織姫(おりひめ)」、牛郎を「彦星(ひこぼし)」と呼んでいますね。
紀元前の『詩経』にも牽牛星と織女星への言及があり、3世紀頃には現在の物語の原型ができていたとされる、非常に歴史の長い伝説なんです。
登場人物
この物語には、個性豊かな登場人物たちが出てきます。
織女(しょくじょ)
天界で雲や錦を織る仕事をしている美しい女性です。
中国では「織女星」として知られ、西洋の星座ではこと座の一等星ベガ(Vega)にあたります。多くの物語では天帝(てんてい)の孫娘、あるいは西王母の娘として描かれています。
機織りの名手で、毎日一生懸命に美しい布を織っていました。真面目で働き者ですが、牛郎と出会ってからは恋に落ち、仕事をおろそかにしてしまいます。
牛郎(ぎゅうろう)
地上で牛の世話をしていた誠実な若者です。
中国では「牽牛星(けんぎゅうせい)」として知られ、西洋の星座ではわし座の一等星アルタイル(Altair)にあたります。日本では「彦星」という名前で親しまれていますね。
貧しい牛飼いですが、心優しく勤勉な性格。多くのバージョンでは、飼っている牛(実は金牛星という星の化身)の助言によって織女と出会うことになります。
西王母(せいおうぼ)/王母娘娘(おうぼにゃんにゃん)
天界を統べる最高位の女仙です。
織女の祖母や母として描かれることが多く、人間と神仙の恋を厳しく禁じています。物語の中では、二人を引き裂く役割を果たす厳格な存在として登場します。
かんざし(金簪)を抜いて空を裂き、天の川を作り出したという描写が有名です。
小青/青青(しょうせい)
織女に仕えている侍女で、物語によっては青蛇の精とされることもあります(これは別の伝説「白蛇伝」との混同かもしれません)。
金牛/老牛(きんぎゅう/ろうぎゅう)
牛郎が飼っている牛で、実は金牛星という星の化身です。
人間の言葉を話すことができ、牛郎に織女との出会い方を教えたり、天に昇る方法を伝えたりします。自分の命を犠牲にして牛郎を助ける、忠実で知恵のある存在です。
カササギ(鵲)
毎年7月7日に天の川に橋を架けて二人を会わせる鳥です。
中国では「鵲橋(じゃっきょう)」と呼ばれるこの橋は、無数のカササギが羽を広げて作ると言われています。この日にカササギを見かけると、頭の羽が抜けているとも伝えられています(橋を作るのに使ったため)。
物語の内容
牛郎織女の物語には、いくつかのバージョンがありますが、ここでは代表的な二つの型をご紹介します。
第一の型:天界の夫婦
この型では、織女も牛郎も元々は天界にいた存在として描かれます。
織女は天の川の東で雲の錦を織り、牛郎は天の川の西で牛の世話をしていました。二人とも真面目に働いていたので、天帝は二人の労をねぎらって結婚を許しました。
ところが結婚してからというもの、二人は恋に夢中になってすっかり仕事を怠けるようになってしまったんです。織女は機織りをやめ、牛郎は牛の世話をしなくなりました。
これに怒った天帝は、二人を天の川で隔て、年に一度だけ会うことを許したのです。
面白いのは、この罰を伝えたのが烏(カラス)だったという点。烏が「七日に一度会える」というメッセージを「七月七日に一度だけ会える」と間違えて伝えてしまったため、二人は年に一度しか会えなくなってしまったとも言われています。
第二の型:天と地の恋
こちらのバージョンの方が、現代でよく知られている物語に近いものです。
運命の出会い
織女は西王母の孫娘で、天界で毎日美しい雲の布を織っていました。ある日、姉妹たち(七人の天女)と一緒に地上の湖(碧蓮池)に降りて水浴びをしていました。
一方、地上では牛飼いの牛郎が、飼っている老牛から不思議な助言を受けます。「天女たちが水浴びをしているから、その羽衣(はごろも)を一枚取ってきなさい」と。
牛郎はその通りにして、紫色(あるいは桃色)の羽衣を隠しました。水浴びを終えた天女たちが帰ろうとしましたが、一人だけ羽衣がなくて天に帰れません。それが織女だったのです。
幸せな結婚生活
困っていた織女に、牛郎は羽衣を返す条件として結婚を申し込みました。地上に残ることになった織女は、やがて牛郎の誠実さに心を開き、結婚を受け入れます。
二人は男耕女織(だんこうじょしょく)、つまり夫が畑を耕し、妻が機を織るという、理想的な夫婦生活を送りました。やがて一男一女の子供にも恵まれ、幸せな日々が続きました。
引き裂かれる運命
しかし、この幸せは長くは続きませんでした。
天界で織女を探していた西王母(王母娘娘)は、織女が人間の男と結婚して地上にいることを知って激怒します。天界の掟を破ったとして、天兵(天の軍隊)を送って織女を捕らえ、天界に連れ戻してしまいました。
残された牛郎は悲しみに暮れます。そのとき、年老いた牛が牛郎に告げました。
「私が死んだら、私の皮で靴を作りなさい。その靴を履けば、天に昇ることができます」
牛が死んだ後、牛郎は言われた通りに牛の皮で靴を作り、二人の子供を天秤棒で担いで天界へと昇っていきました。
天の川の誕生
織女に追いつこうとする牛郎を見た西王母は、頭からかんざし(金簪)を抜いて一振りしました。するとそこに大きな川が現れ、二人の間を隔ててしまったのです。これが天の川です。
天の川を挟んで、織女と牛郎は互いに呼び合いますが、川を渡ることはできません。その様子があまりに哀れだったため、西王母は年に一度、7月7日だけは会うことを許しました。
カササギの橋
その日になると、どこからともなく無数のカササギが飛んできて、天の川に橋を架けます。この鵲橋(じゃっきょう)を渡って、二人は年に一度の再会を果たすのです。
中国では、7月7日にカササギを見ると頭の羽が抜けているという言い伝えがあります。これは橋を作るために羽を使ったからだと言われているんですね。
物語の起源と変遷
牛郎織女の伝説は、2000年以上の長い歴史を持っています。
最古の記録
最も古い記録は、紀元前11世紀から紀元前6世紀頃に成立したとされる『詩経(しきょう)』です。
その中の「小雅・大東」という詩に、こんな一節があります。
「天に天の川があり、明るく輝いている。あの織女は、一日中七回も機を動かす。七回動かしても、美しい模様は完成しない。あの牽牛は、車を引くこともできない」
この時点では、織女と牽牛(牛郎)は夜空の星の名前として登場するだけで、まだ恋愛の物語にはなっていません。
夫婦としての描写
戦国時代(紀元前5世紀〜紀元前221年)の秦の時代の竹簡『日書』には、すでに二人が夫婦として描かれています。
「牽牛が織女を娶ろうとしたが、うまくいかず、三度捨てられた」という記述があり、この頃には二人の関係が語られ始めていたことが分かります。
七夕との結びつき
後漢(25年〜220年)の『古詩十九首』には、「迢迢牽牛星(ちょうちょうけんぎゅうせい)」という詩があります。
ここでは天の川に隔てられた織女が、牽牛を思って泣いている様子が描かれています。まだ会えない理由は明確ではありませんが、悲しい恋の物語になっているんですね。
西晋(265年〜316年)の時代になると、傅玄という詩人が「七月七日、牽牛と織女が天の川で会う」と明記しました。ここで初めて7月7日という日付が登場するんです。
カササギの橋
南北朝時代(420年〜589年)の梁の時代に書かれた『小説』(殷芸著)では、現在知られる物語の骨格が完成します。
天帝の娘である織女が、天の川の西の牽牛と結婚するが、結婚後に機織りをやめたため天帝が怒り、天の川を隔てて年に一度だけ会うことを許した、という筋書きです。
また、唐代(618年〜907年)の『風俗通』では、カササギが橋を架けるという要素が加わります。「織女は七夕の日にカササギを橋として川を渡らなければならない」という記述があり、ここで鵲橋の伝説が確立したんですね。
羽衣伝説との融合
時代が下ると、織女の物語に「羽衣伝説」の要素が混ざってきます。
晋代の『搜神記』には「毛衣女(もういじょ)」という話があります。男が田んぼで六、七人の女性を見つけ、その中の一人の羽衣を隠して結婚するという内容です。これは日本の「天人女房」や「羽衣伝説」と同じタイプの物語ですね。
この要素が牛郎織女の伝説に取り込まれて、「牛郎が水浴びをしている織女の羽衣を取る」という展開が生まれたと考えられています。
現代の物語へ
清代(1644年〜1912年)末期から民国時代にかけて、京劇『天河配(てんがはい)』などの演劇が作られ、物語がさらに詳細化されました。
現代の私たちが知っている「牛郎織女」は、こうした長い歴史の中で、様々な要素が組み合わさってできあがった物語なんです。
日本の七夕との関係
日本の七夕祭りは、この牛郎織女の伝説が元になっています。
奈良時代(710年〜794年)に中国から伝わった牛郎織女の伝説は、日本の「棚機津女(たなばたつめ)」という神事と結びつきました。棚機津女とは、神様のために機を織る巫女のことです。
7月7日の夜、織女星と牽牛星に技芸の上達を祈る「乞巧奠(きっこうでん)」という行事も中国から伝わり、これらが融合して現在の七夕祭りが生まれました。
日本では織女を「織姫(おりひめ)」、牛郎を「彦星(ひこぼし)」と呼び、短冊に願い事を書いて笹に飾るという独自の風習が発展していったんですね。
まとめ
牛郎織女は、2000年以上の歴史を持つ中国を代表する恋愛伝説です。
重要なポイント
- 天界の織女と地上の牛郎が恋に落ちるが、天の掟により引き裂かれる
- 天の川を隔てられた二人は、年に一度7月7日だけ再会を許される
- カササギが橋を架けて二人の再会を助ける
- 紀元前の『詩経』から記録があり、時代とともに物語が発展
- 日本の七夕祭りの起源となった伝説
- 中国四大民間伝説の一つとして現代まで語り継がれている
仕事に励む二人が恋に落ち、引き裂かれながらも愛を貫く物語。夜空を見上げたとき、天の川の両岸に輝く二つの明るい星が、今も変わらず互いを見つめ合っていることに、古代の人々はロマンを感じたのでしょう。
毎年7月7日の夜、もし晴れていたら夜空を見上げてみてください。織姫と彦星が、年に一度の再会を喜んでいる姿が想像できるかもしれませんね。