「ドワーフって、どこから来たの?」
ファンタジー世界でよく見かける種族「ドワーフ」は、小柄で屈強、鍛冶や鉱山に精通した存在として描かれることが多いです。
しかし、そのルーツをたどると、意外にも神話や民間伝承に根ざした深い歴史があるのです。
現代のファンタジー作品でドワーフを見かけるとき、こんな疑問を持ったことはありませんか?
「なぜドワーフはいつも髭を生やしているの?」
「どうして鍛冶が得意という設定が多いの?」
「エルフと対立することが多いのはなぜ?」
「そもそもドワーフという名前の意味は?」
これらの疑問の答えは、数千年前の北欧神話にまでさかのぼることができます。
ドワーフという存在は、単にファンタジー作家が思いついたキャラクターではなく、古代から現代まで続く長い文化的変遷の産物なのです。
この記事では、ドワーフの起源や進化の過程、そして現代文化への影響をわかりやすく解説します。
ドワーフの語源と基本的な特徴

ドワーフという言葉の語源
各言語での呼び方
現代の呼び方:
- 英語:Dwarf(ドワーフ)
- 複数形:Dwarfs または Dwarves
- ドイツ語:Zwerg(ツヴェルク)
- オランダ語:Dwerg(ドヴェルフ)
古代の語源
古ノルド語:
- 原語:Dvergr(ドヴェルグ)
- 発音:「ドヴェルグル」に近い音
現代に共通するドワーフのイメージ
身体的特徴
一般的な描写:
- 身長は人間の半分から3分の2程度
- がっしりとした筋肉質な体型
- 豊かな髭(男性の場合)
- 頑丈で持久力に優れる
性格的特徴
典型的な性格:
- 頑固で伝統を重んじる
- 名誉と誇りを大切にする
- 友情に厚く、裏切りを嫌う
- 職人気質で完璧主義
技能と文化
得意分野:
- 金属加工と鍛冶技術
- 鉱山の採掘と宝石の加工
- 石工事と建築技術
- 戦闘技術(特に斧やハンマー)
住環境:
- 山岳地帯や地下都市
- 洞窟や岩山の要塞
- 鉱山や工房が併設された居住地
これらの基本イメージは、実は北欧神話に登場する存在から発展したものです。現代のファンタジー作品で見られる「鍛冶の名人」「地下に住む種族」というイメージは、何千年も前の神話に起源を持っているのです。
北欧神話におけるドワーフの起源

神話の中でのドワーフの誕生
創世神話での位置づけ
北欧神話におけるドワーフの起源は、『エッダ』という古代アイスランドの文献に記録されています。
『散文のエッダ』による創造神話:
- 神々が原初の巨人ユミルを倒す
- ユミルの死体から世界を創造する
- 死体が腐敗する過程で虫が湧く
- 神々がその虫にドワーフとしての知性と姿を与える
神話での重要な役割
神々との関係:
- 神々に劣らない技術力を持つ存在
- 神々の武器や宝物の製作者
- 時には神々と対等に交渉する知恵者
北欧神話の有名なドワーフたち
ブロック(Brokkr)とエイトリ(Sindri/Eitri)
業績:
- トールの神槌「ミョルニル」の製作者
- オーディンの槍「グングニル」の製作者
- フレイの黄金の猪「グッリンブルスティ」の製作者
神話での描写:
この兄弟は、ロキとの賭けに勝つために最高の宝物を作り上げました。
彼らの作品は、神々にとって不可欠な武器となったのです。
ドヴァリン(Dvalin)
特徴:
- 「詩のエッダ」に登場する重要なドワーフ
- 魔剣「ティルヴィング」の製作者とされる
- 高い知識と技術を持つ賢者
アルヴィース(Alviss)
神話での役割:
- トールの娘フルーズとの結婚を望んだドワーフ
- トールとの知恵比べに挑戦
- 最終的にトールの策略により石に変えられる
アルヴィースの物語は、ドワーフが神々に匹敵する知識を持ちながらも、最終的には神々の力に及ばないことを示しています。
アンドヴァリ(Andvari)
特徴:
- 水中に住むドワーフ
- 魔法の指輪「ドラウプニル」の所有者
- ロキに財宝を奪われ、呪いをかけた
アンドヴァリの呪いは、後にワーグナーの楽劇「ニーベルングの指環」の原型となりました。
神話におけるドワーフの特殊な性質
昼と夜の制約
重要な設定:
- ドワーフは日光に当たると石になる
- そのため主に夜間や地下で活動
- この設定は後の民間伝承にも引き継がれる
知識と技術の象徴
神話での位置づけ:
- 単なる職人ではなく、魔法的な技術の担い手
- 神々でさえ頼りにする技術力の持ち主
北欧神話では、ドワーフは単なる小人ではなく、神々に匹敵する技術力を持つ存在として描かれています。
現代のファンタジーでドワーフが「鍛冶の名人」として描かれるのは、この神話的背景があるからなのです。
民間伝承と文学作品におけるドワーフの変遷
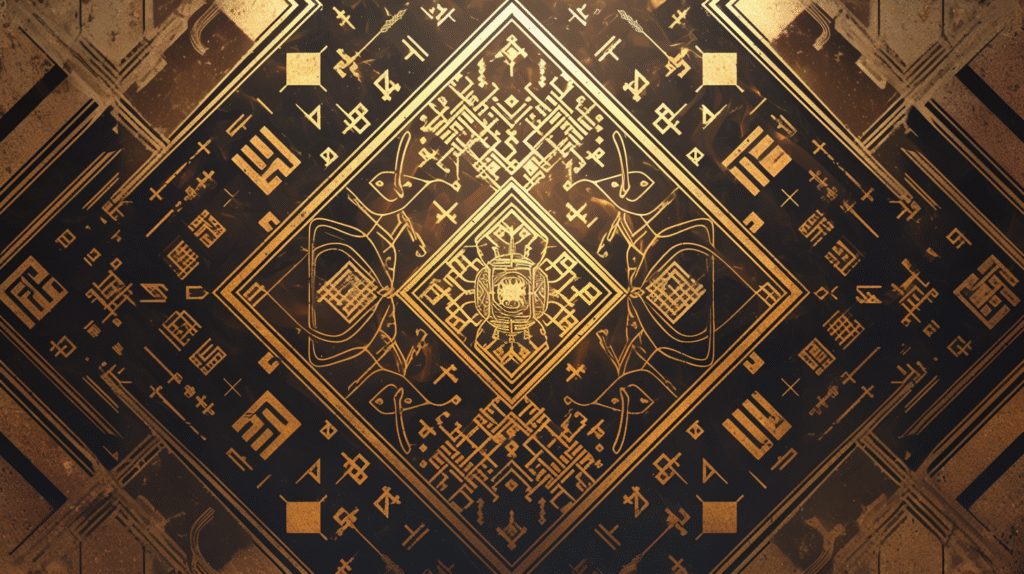
中世ヨーロッパでの民間伝承
鉱山の守護霊として
ドイツ・オーストリア地方:
- 鉱山で働く小さな精霊として信じられる
- 「ベルクメンライン」(山の小人)と呼ばれる
- 鉱夫たちの安全を守ったり、危険を知らせたりする存在
具体的な信仰:
- 鉱山で不思議な音が聞こえるのはドワーフの作業音
- 鉱脈を見つけるのを手伝ってくれる
- 敬意を払わないと鉱山事故を起こす
他の妖精との関係
名称の混同:
- ノーム:地の精霊、庭の守護者
- コボルト:家や鉱山の精霊(ドイツ語圏)
- トロル:北欧の巨人族(時にドワーフと混同)
これらの存在は地域によって混同されることも多く、「小さくて地下に住む」「人間に恩恵をもたらす」といった共通の特徴を持っていました。
グリム童話での新しいイメージ
「白雪姫」での描写
19世紀の変化:
- 7人の小人として登場
- 善良で勤勉な鉱山労働者
- 人間の女性(白雪姫)を保護する存在
従来との違い:
- 神話的な恐ろしさが薄れる
- より親しみやすく、人間的な存在に
- 労働者としての側面が強調される
J.R.R.トールキンによる革命的再定義
『ホビットの冒険』での描写
新しいドワーフ像:
- 王族と庶民の区別がある社会
- 個性豊かな13人のドワーフ
- 勇敢な冒険者としての側面
主要なキャラクター:
- トーリン・オーケンシールド:誇り高い王族
- バーリン:年長で知恵のある戦士
- ボンブール:料理上手な陽気なドワーフ
『指輪物語』での発展
より複雑な文化設定:
- 独自の言語(クズドゥル語)
- 詳細な歴史と王朝
- 他種族との複雑な関係
重要なキャラクター:
- ギムリ:旅の仲間として活躍
- ダイン2世:エレボールの王
- グローイン:ギムリの父
トールキンの影響
現代ファンタジーへの決定的影響:
- ドワーフの社会構造の確立
- エルフとの対立関係の設定
- 斧を主武器とする戦士のイメージ
- 地下都市「モリア」のような壮大な建築
トールキンの描写が、現在のファンタジー作品におけるドワーフの標準イメージを決定づけたと言っても過言ではありません。
20世紀の他の重要な作品
C.S.ルイス『ナルニア国物語』
独自の解釈:
- より小さく、土の精霊に近い存在
- 善良で親しみやすいキャラクター
- 自然との調和を重視
ロード・ダンセイニの作品
幻想文学での描写:
- より神秘的で魔法的な存在
- 人間世界との境界にいる存在
- 古い魔法の知識を持つ
現代ファンタジーにおけるドワーフの位置づけ

テーブルトークRPGでの標準化
『ダンジョンズ&ドラゴンズ』の影響
D&Dでの基本設定:
- プレイヤーキャラクターとして選択可能な種族
- 戦士やクレリック(僧侶)に適した能力値
- 魔法に対する抵抗力
- 地下視や毒・病気への耐性
能力的特徴:
- 筋力と耐久力が高い
- 魅力(カリスマ)は低め
- 工芸技能と鑑定技能にボーナス
- 斧やハンマーの扱いに長ける
ステータス重視の描写
ゲーム的な単純化:
- 数値で表現される能力
- 明確な得意・不得意分野
- 他種族との差別化
コンピューターゲームでの展開
RPGでの定番化
- 『ファイナルファンタジー』シリーズ
- 『ドラゴンクエスト』シリーズ
- 『エルダースクロールズ』シリーズ
アニメ・漫画での描写
日本のファンタジー作品
『ロードス島戦記』:
- 西洋ファンタジーの日本への本格導入
- ギムを中心とした詳細なドワーフ文化描写
- 職人としての誇りと技術力を強調
『ゴブリンスレイヤー』:
- 鉱人(こうじん)として登場
- より現実的で地味な描写
- 職人気質と実用主義を重視
その他:
- 『転生したらスライムだった件』
- 『DRIFTERS』
近年の注目作品
『ダンジョン飯』:
- ドワーフの食文化に焦点
- センシというキャラクターを通じた深い描写
- 料理の知識を組み合わせた独特な設定
まとめ
今回は「ドワーフの由来とその歴史」について、神話時代から現代まで詳しく解説しました。
重要なポイント:
- 北欧神話のドヴェルグが起源で、神々に匹敵する技術力を持つ存在
- 中世ヨーロッパで鉱山の守護霊として信仰される
- グリム童話で親しみやすいキャラクターに変化
- トールキン作品で現代ファンタジーの基準が確立
文化的変遷:
- 神話:超自然的な技術者
- 民間伝承:地域の守護精霊
- 近代文学:善良な労働者
- 現代ファンタジー:勇敢な戦士・職人






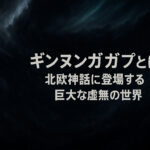

元々はウジ虫から生まれた存在だと考えると、すっごい変化をとげてますよね。