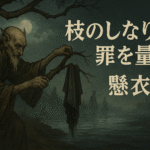死んだ後、最初に出会うのは誰だと思いますか?
実は、閻魔大王より先に出会う存在がいるんです。
それが、三途の川のほとりで亡者を待ち受ける老婆の鬼「奪衣婆(だつえば)」なんです。
名前を聞くとちょっと怖そうですが、江戸時代には病気を治してくれる神様として大人気だったという意外な一面も持っています。
この記事では、地獄の入り口で重要な役割を果たす奪衣婆について、その姿や特徴、伝承をわかりやすくご紹介します。
奪衣婆ってどんな存在なの?

奪衣婆(だつえば)は、あの世とこの世の境目にある「三途の川」で、死者の衣服を剥ぎ取る老婆の鬼です。
仏教では、人が亡くなると霊魂となって死者の国へ旅立つと考えられています。その旅の途中で必ず渡らなければならないのが三途の川で、その川のほとりで待っているのが奪衣婆なんですね。
奪衣婆の別名
- 脱衣婆(だつえば)
- 葬頭河婆(そうづかば)
- 正塚婆(しょうづかのばば)
- 姥神(うばがみ)
- 優婆尊(うばそん)
地域によって呼び名は違いますが、どれも同じ奪衣婆のことを指しています。
姿・見た目
奪衣婆の姿は、想像通りの怖そうな鬼婆といった感じです。
多くの地獄絵図では、こんな姿で描かれています。
奪衣婆の外見的特徴
- 容貌魁偉な老婆(見た目が恐ろしい老女)
- 胸元をはだけた姿
- 獄卒の鬼よりも大きな体
- すべての罪を見透かすような鋭い目つき
でも意外なことに、お寺に安置されている奪衣婆の像を見ると、怖いけれどどこか憎めない表情をしているものが多いんです。江戸時代の人々に親しまれていた証拠かもしれませんね。
特徴

奪衣婆の最大の特徴は、亡者の衣服を剥ぎ取って「罪の重さを量る」という重要な仕事をしていることです。
奪衣婆の仕事の流れ
- 亡者が三途の川に到着すると、奪衣婆が待ち構えている
- 衣服をすべて剥ぎ取って、亡者を丸裸にする
- 剥ぎ取った衣服を**懸衣翁(けんえおう)**という老爺の鬼に渡す
- 懸衣翁が衣服を**衣領樹(えりょうじゅ)**という大木の枝にかける
- 枝のしなり具合で、その人の生前の罪の重さが分かる
つまり、奪衣婆と懸衣翁は夫婦で協力して、閻魔大王の裁判の前に罪の重さを調べる「地獄の審判官」として働いているんです。
特別な能力
- 盗人の両手の指を折る(盗みを戒めるため)
- 衣服がない亡者からは身の皮を剥ぐ
- 六文銭を持たない亡者の衣服を問答無用で剥ぎ取る
なかなか厳しい仕事ぶりですが、これも死後の世界の秩序を守るための大切な役割なんでしょうね。
伝承と起源

奪衣婆が文献に登場したのは、12世紀末に日本で作られた『仏説地蔵菩薩発心因縁十王経』という経典が最初です。
でも実は、それ以前から似たような存在は語られていました。平安時代の『法華験記』(1043年)には「媼の鬼」という、奪衣婆とそっくりな役割を持つ鬼女が登場しているんです。
江戸時代の大人気ぶり
鎌倉時代以降、奪衣婆は説教や絵解きの定番キャラクターとなりました。そして江戸時代になると、なんと信仰の対象として大ブレイクしたんです!
江戸時代の奪衣婆信仰
- 疫病除けや咳止めの神様として信仰された
- 特に子供の百日咳に効果があると言われた
- 参拝客が焚く線香の煙が多すぎて火事と間違われたほどの人気
- 東京の正受院では「綿のおばあさん」と親しまれた
意外な説:閻魔大王の妻?
近世になると、奪衣婆は単なる地獄の役人ではなく、閻魔大王の妻という説も現れました。
落語の『地獄八景亡者戯』では、奪衣婆は閻魔様の愛人として、なかなかの美人熟女として描かれているんです。
日本古来の信仰との融合
民俗学者の柳田国男は、奪衣婆信仰は日本に古くからあった「姥神信仰」が仏教と習合して生まれたものだと考察しています。
つまり、外来の仏教思想と日本独自の信仰が混ざり合って、今の奪衣婆像ができあがったというわけです。
まとめ
奪衣婆は、単なる恐ろしい地獄の鬼ではなく、死後の世界で重要な役割を果たす存在です。
奪衣婆の重要ポイント
- 三途の川で亡者の衣服を剥ぎ取る老婆の鬼
- 懸衣翁と夫婦で罪の重さを量る審判官
- 鎌倉時代から庶民に親しまれた存在
- 江戸時代には病気平癒の神様として大人気
- 日本独自の信仰と仏教が融合した存在
怖い見た目とは裏腹に、江戸時代の人々から愛され、現代でも多くのお寺で祀られている奪衣婆。
地獄の入り口で厳しく罪を裁きながらも、どこか人間味のある存在として、今も私たちの文化の中に生き続けているんですね。