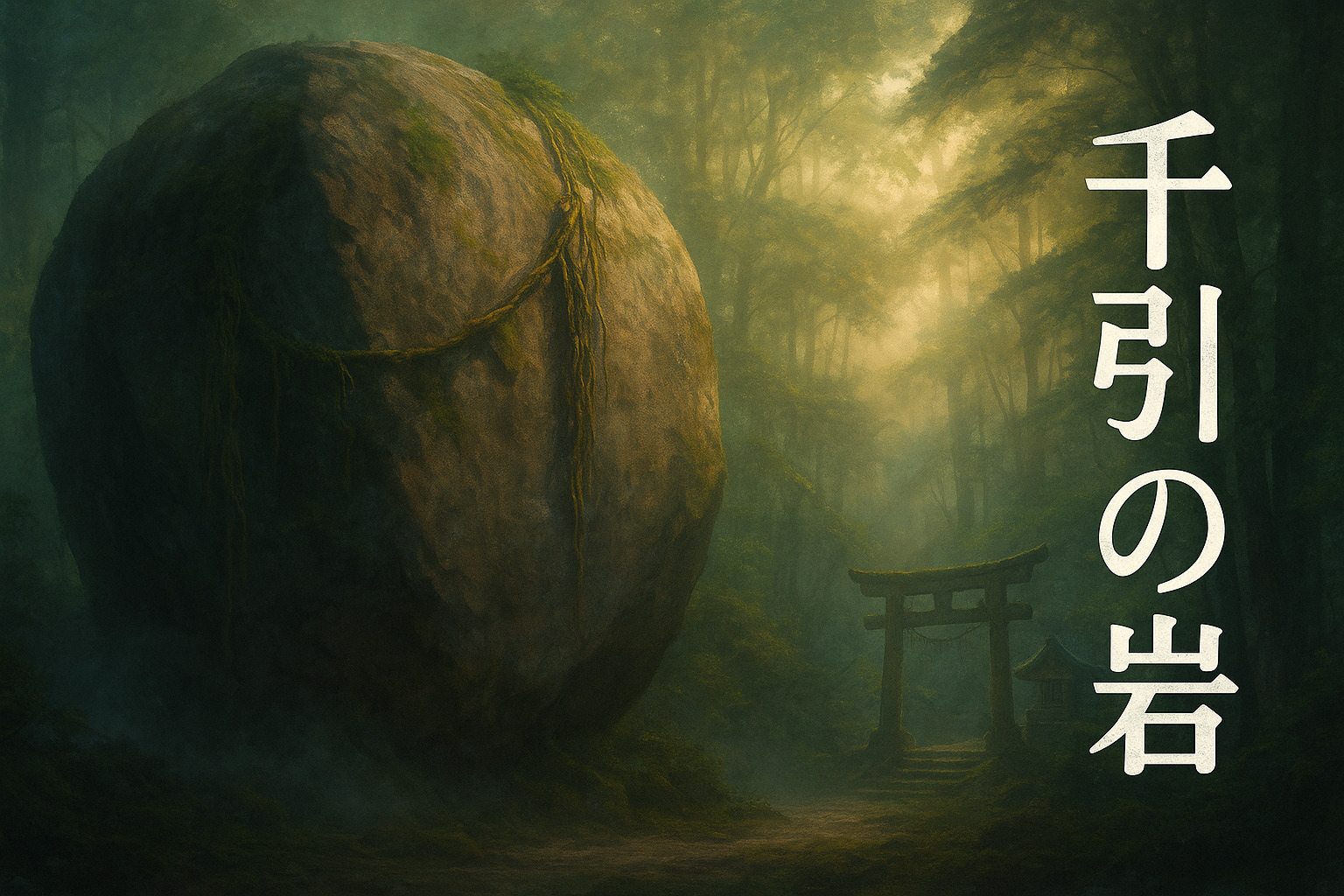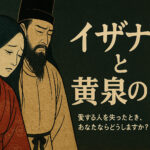「大切な人に、もう一度会いたい」
そう願ったことはありませんか?
日本神話の神イザナギも、亡くなった妻イザナミに会いたくて、死者の国である黄泉の国まで追いかけていきました。しかし、そこで見たものは想像を絶する恐ろしい光景だったんです。命からがら逃げ帰ったイザナギが、二度と死者の世界と現世が交わらないように置いた巨大な岩——それが「千引の岩」なのです。
この記事では、生と死の境界を象徴する「千引の岩」について、その神話での役割や意味を分かりやすく解説します。
概要
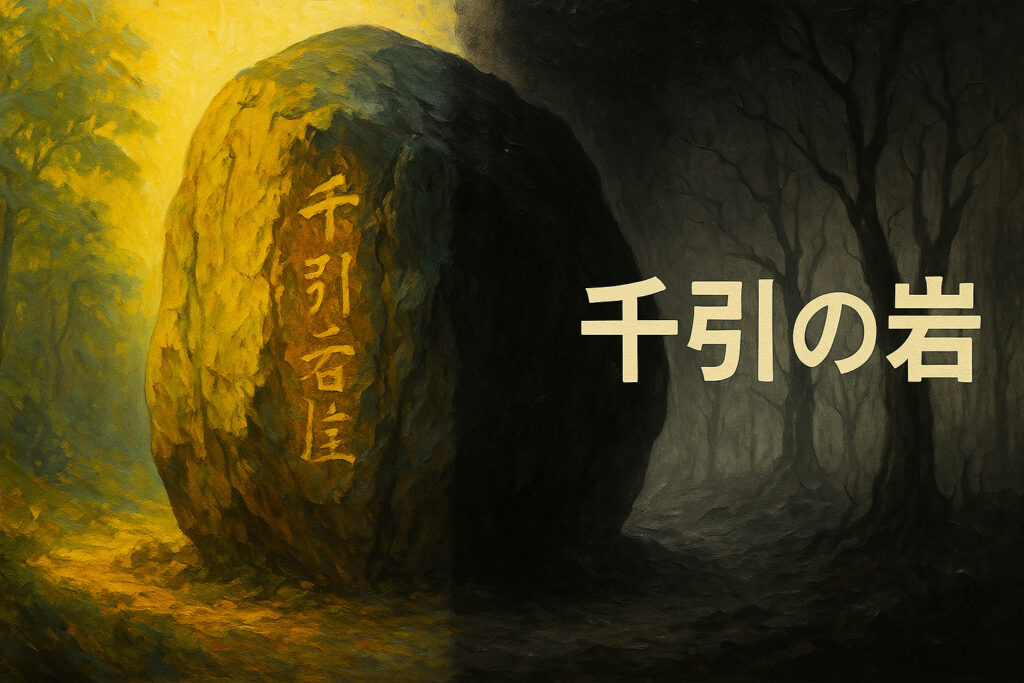
千引の岩(ちびきのいわ)は、『古事記』や『日本書紀』に登場する巨大な岩です。
イザナギが黄泉の国から逃げ帰る際、黄泉比良坂(よもつひらさか)という坂に置いて、死者の世界への入り口を完全に塞いだとされています。
「千引」とは、千人もの人を動員して引くほど大きいという意味なんですね。つまり、人間の力では到底動かせないほどの巨石だったわけです。
現在も島根県松江市東出雲町揖屋に、その伝承地があり、「千引きの磐座(いわくら)」と呼ばれる大きな岩が残されています。
千引の岩はどんな岩?
千引の岩は、ただの大きな石ではありません。生者の住む現世と、死者の住む黄泉の国を永遠に隔てる境界の岩なんです。
岩の大きさと重要性
- 千人がかりで引く必要があるほどの巨石
- 一度置かれたら二度と動かせない重さ
- 物理的にも霊的にも境界を作る役割
『古事記』には「千引石(ちびきのいわ)」、『日本書紀』には「千人所引磐(ちびきのいわ)」と表記されています。どちらも同じ意味で、その巨大さを強調しているんですね。
神話での登場シーン

千引の岩が登場するのは、日本神話の中でも特に有名な「黄泉国訪問」の物語です。
物語のあらすじ
1. イザナミの死
国生みの最中、イザナミは火の神カグツチを産んだ際に火傷を負って亡くなり、黄泉の国へ行ってしまいました。
2. イザナギの追跡
最愛の妻を失ったイザナギは、イザナミに会いたい一心で、黄泉の国まで追いかけていきます。黄泉比良坂という坂を通って、死者の世界に入ったんです。
3. 約束を破る
イザナミは「黄泉の神と相談するので、決して私を見ないでください」と頼みました。しかし、待ちきれなくなったイザナギは火を灯して中を覗いてしまったんですね。
4. 恐怖の光景
そこにいたのは、ウジ虫がたかり、全身から雷神を生じさせた、変わり果てたイザナミの姿でした。
5. 命がけの逃走
驚いたイザナギは逃げ出します。怒ったイザナミは黄泉醜女(よもつしこめ)や黄泉軍を差し向けて追いかけさせました。イザナギは髪飾りを投げると山葡萄が生え、櫛を投げると筍が生えて、追手がそれを食べている間に逃げ続けたんです。
6. 千引の岩で封印
ついに黄泉比良坂まで逃げ帰ったイザナギは、千引の岩をその坂に置いて、黄泉の国への入り口を完全に塞ぎました。岩を挟んで、イザナギとイザナミは最後の言葉を交わします。
イザナミ:「愛しい人よ、こんなことをするなら、私は1日に1000人の人間を殺しましょう」
イザナギ:「愛しい人よ、それなら私は1日に1500の産屋を建てて、子を産ませよう」
こうして二人は永遠に別れ、千引の岩によって生者と死者の世界は完全に分かたれたのです。
桃の実の役割
実は、千引の岩を置く直前、イザナギは黄泉比良坂のそばに生えていた桃の実を投げて追手を追い払っています。
古代中国の道教では、桃は魔除けや不老不死の力があるとされる神聖な果物でした。この信仰が日本にも伝わり、桃には邪悪なものを退ける力があると考えられていたんですね。
イザナギは桃に「意富加牟豆美命(オオカムヅミノミコト)」という名を与え、「人々が苦しむときは助けるように」と命じました。
千引の岩の意味と象徴
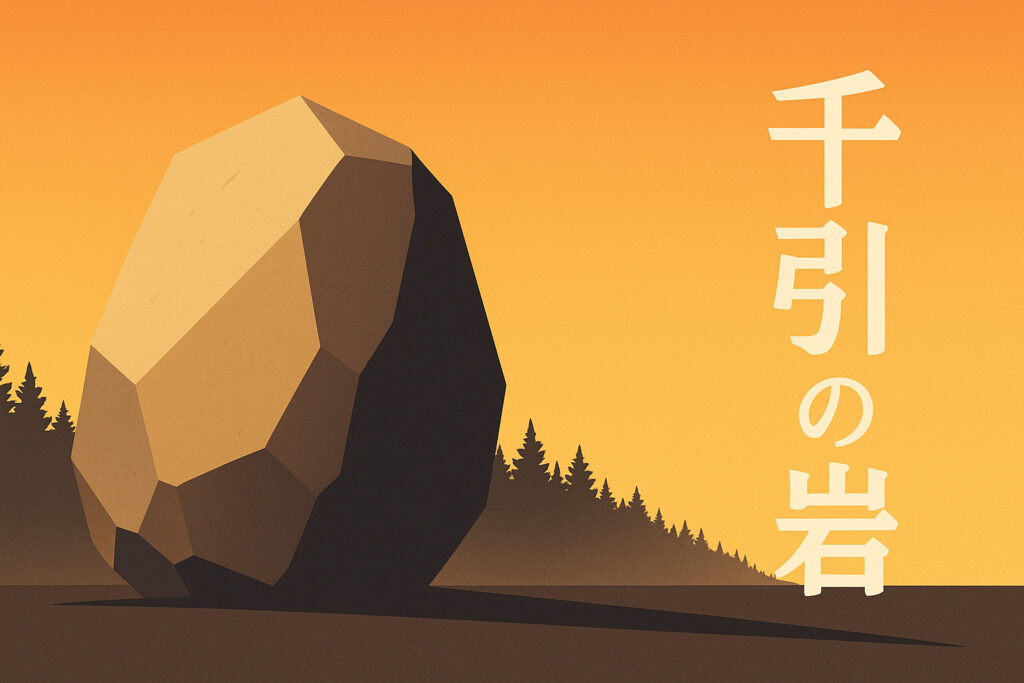
千引の岩には、古代日本人の死生観が深く反映されています。
生と死の明確な境界
千引の岩が置かれることで、現世(葦原中国)と黄泉の国は完全に分離されました。
つまり、生きている人間は死者の世界に行けなくなり、死者もこちらの世界には戻ってこられなくなったんです。これは「死は不可逆的なもの」という考え方を示しています。
事戸を渡す
『古事記』では、千引の岩を置くことを「事戸を渡す(ことどをわたす)」と表現しています。
これは「絶縁する」「完全に縁を切る」という意味なんですね。イザナギとイザナミは夫婦として離縁し、生者と死者としても永遠に別れたわけです。
古墳文化との関連
興味深いことに、古墳時代の横穴式石室でも、入り口を巨大な石で塞ぐ習慣がありました。
これは千引の岩の思想と共通していて、死者の霊が外に出ないように、また悪霊が墓に入らないように、石で封じるという信仰があったんです。
境界の神
千引の岩を置いた後、イザナギはその場所に岐神(ふなどのかみ)という境界の神を祀りました。
この神は、道の分岐点や境界を守る存在で、悪いものが侵入してこないように守る役割があります。村の入り口などに祀られる「道祖神」の原型とも考えられているんですね。
現在の伝承地
千引の岩の伝承は、今でも島根県に残っています。
黄泉比良坂の伝承地
『古事記』には「出雲国の伊賦夜坂(いふやざか)である」と記されており、島根県松江市東出雲町揖屋がその場所だとされています。
現地には実際に「千引きの磐座」と呼ばれる大きな岩があり、神秘的な雰囲気を醸し出しています。国道9号線から南へ約300メートル、緩やかな坂を上った静かな木立の中にあるんです。
揖夜神社
伝承地の近くには、イザナミを祀る揖夜神社(いやじんじゃ)もあります。
1940年(昭和15年)には、佐藤忠次郎によって黄泉比良坂の石碑が建立されました。
その他の候補地
実は『出雲国風土記』には、別の場所も黄泉の国への入り口として記録されています。
出雲市猪目町の猪目洞窟も、古くから「黄泉の坂・黄泉の穴」と呼ばれてきました。この洞窟は実際に弥生時代から古墳時代の墓地として使われており、人骨や副葬品も発見されています。
『出雲国風土記』には「夢の中でこの磯の窟のあたりに至る者は必ず死ぬ」という不吉な記述もあるんです。
まとめ
千引の岩は、生者と死者の世界を永遠に分かつ境界の象徴です。
重要なポイント
- 千人で引くほどの巨大な岩
- イザナギが黄泉比良坂に置いて黄泉の国を封印
- 生と死の境界を物理的・霊的に示す存在
- 「事戸を渡す」=完全な絶縁を意味する
- 古墳の石室文化とも深い関連がある
- 島根県松江市東出雲町揖屋に伝承地が残る
- 境界を守る岐神が祀られた
愛する人を失った悲しみと、死の不可逆性を受け入れる——千引の岩の物語は、古代日本人の深い死生観を今に伝えているのです。