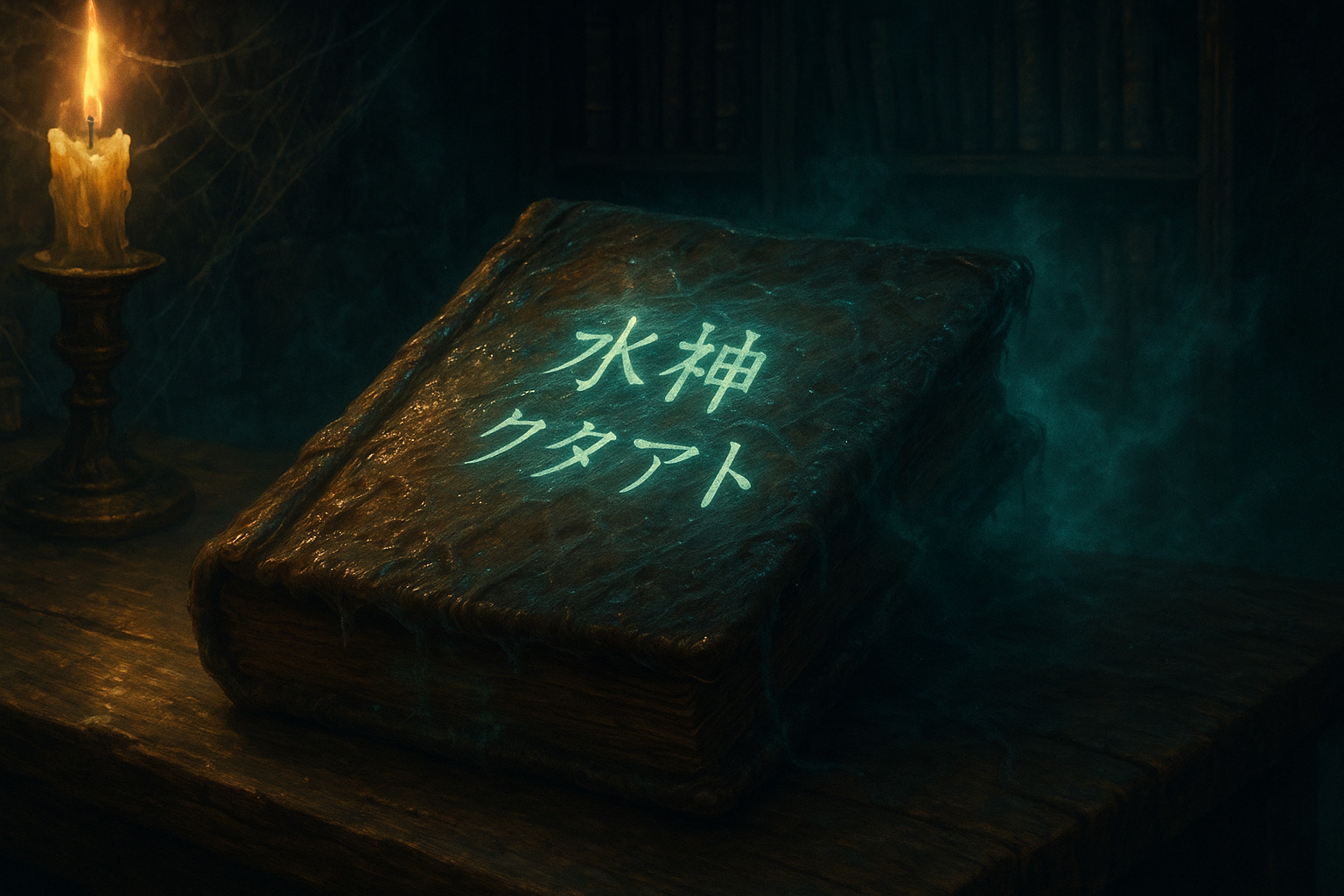古びた図書館の奥深く、厳重に保管された一冊の本。
その表紙に触れた瞬間、まるで生きているかのように湿り気を帯び始めたら、あなたはどう感じるでしょうか?
中世ヨーロッパで著された「水神クタアト」は、海や川、湖に潜む恐ろしい存在たちについて記した禁断の書物です。人間の皮膚で装丁され、天候によって汗をかくという、その異様な特徴だけでも背筋が凍るような一冊なんです。
この記事では、クトゥルフ神話に登場する謎多き魔導書「水神クタアト」について、その内容や歴史、奇妙な特徴を分かりやすくご紹介します。
概要
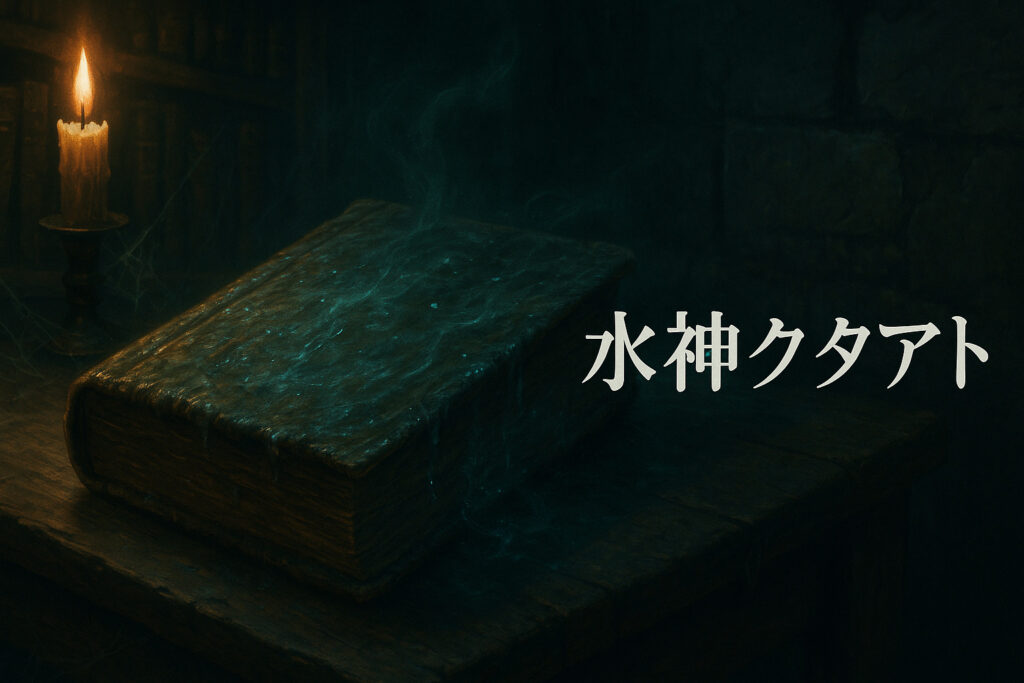
水神クタアト(すいじんクタアト)は、クトゥルフ神話に登場する架空の魔導書です。
正式名称は「Cthäat Aquadingen」(クタアト・アクアディンゲン)といい、この「Aquadingen」という言葉は、ドイツ語の「Wasser」(水)とラテン語の「aqua」(水)を組み合わせた造語で、「水域のもの」という意味を持っています。
11世紀から12世紀頃に書かれたとされ、著者は不明のまま。海や湖、川といった水の中に隠れ潜む謎めいた生物や種族についての膨大な知識が詰め込まれた、まさに「水棲怪物の百科事典」とも言える一冊なんですね。
この本は、イギリスの作家ブライアン・ラムレイによって創造され、彼の小説『地を穿つ魔』(原題: The Burrowers Beneath)などの作品に登場します。
特徴・見た目
水神クタアトの最大の特徴は、その恐ろしい装丁にあります。
人皮で装丁された書物
なんと、この本の表紙は人間の皮膚で作られているんです。
同じくクトゥルフ神話に登場する『ルルイエ異本』という魔導書も人皮装丁として知られていますが、水神クタアトもまた、この悍ましい特徴を共有しています。中世ヨーロッパでは実際に人皮装丁の本が存在したという記録もありますが、魔導書の場合はより不吉な意味を持つとされてきました。
汗をかく本
さらに驚くべきことに、この本は生きているかのように汗をかくんです。
具体的には:
- 雨が降る前に湿り気を帯びる
- 周囲の気温が下がるとうっすらと汗をかく
- 天候の変化に反応して表面が湿る
まるで本そのものが生命を持っているかのような、不気味な性質を持っているわけです。図書館の司書でさえ、この本に触れることを躊躇してしまうほど。普通の人なら、手に取ることすら拒んでしまうかもしれませんね。
内容
では、この奇妙な本には一体何が書かれているのでしょうか?
水棲種族についての記述
水神クタアトは、水に関連する怪物や種族について詳しく記録した文献です。
主な記述内容:
- 「深きものども」:海底に住む半魚人のような種族
- ダゴン:深きものどもが崇拝する海神で「父なるダゴン」と呼ばれる
- ハイドラ:ダゴンと対をなす「母なるハイドラ」
- クトゥルフ:太平洋の海底都市ルルイエで眠る、邪悪な存在
- その他の水棲生物:海、川、湖に潜む様々な怪物たち
召喚術と儀式
さらに恐ろしいことに、この本には実用的な魔術も含まれています。
- 水棲の旧支配者(クトゥルフ神話における強大な存在)を呼び出す呪文
- 召喚のための術式や儀式の手順
- これらの存在を葬送するための方法
つまり、読んだだけで危険なだけでなく、実際に使えてしまう知識が書かれているんですね。
ヨーロッパの暗黒伝承
研究者の中には、本書の内容について「ヨーロッパの暗黒伝承をまとめただけに過ぎない」と指摘する声もあります。つまり、完全なオリジナルではなく、それ以前に存在していた様々な書物の内容と似ている部分が多いというわけです。
一方で、水棲生物に関する専門性の高さから、中世から近世のイギリス海洋学者たちの間で密かに読まれていたという説もあるんです。
歴史と現存状況
原本の成立
水神クタアトが最初に書かれたのは、11世紀から12世紀頃のこと。
原本はラテン語で執筆されましたが、著者については一切不明のまま。どんな人物が、なぜこのような恐ろしい知識をまとめたのか、今でも謎に包まれています。
英訳版の登場
時代が下って14世紀、イギリスでこの本の英語翻訳版が発行されました。
ラテン語が読めない人々にも内容が広まったわけですが、それだけ危険な知識も拡散してしまったことになりますね。
現存する写本
現在、水神クタアトのラテン語版は3部が現存していると言われています。
その所在は:
- 1部:イギリスの大英博物館で厳重に保管
- 残り2部:イギリス国内の個人蒐集家(コレクター)の手元
大英博物館の写本は、危険性を考慮して一般公開されておらず、特別な許可がなければ閲覧できません。また、英訳版も少なくとも1部は大英博物館に収蔵されています。
タイタス・クロウの所持
クトゥルフ神話の登場人物であるタイタス・クロウ(邪神と戦う神秘学者)も、一時期この本を保管していたとされています。
ただし、クロウが持っていた写本は、1999年に「神秘の力」によって破壊されてしまったという設定になっています。禁断の知識があまりに危険だったため、超自然的な力が介入して破壊したのかもしれませんね。
影響を受けた人々
フィリップ・ヘンリー・ゴッスの悲劇
水神クタアトにまつわる最も有名なエピソードが、19世紀イギリスの海洋博物学者フィリップ・ヘンリー・ゴッスの物語です。
輝かしい経歴
ゴッスは当初、非常に優れた科学者でした。
彼の功績:
- 世界初の海棲生物図鑑を制作(死んだ標本ではなく、生きたままの姿を描いた)
- 飼育方法についても詳しく解説
- 「Aquarium(アクアリウム)」という言葉を造語(後に「水族館」を意味する正式な英語になった)
これらの業績により、ゴッスはイギリス随一の海洋博物学者として高い名声を博していました。
奇書の発表
ところが、その後ゴッスは『オンパロス』という奇妙な本を発表します。
この本は、聖書の記述と化石の存在を両立させるという「前時間説」を提唱するもの。科学者としての彼の評判は地に落ち、それまでの名声は一気に失われてしまいました。
水神クタアトとの関連
なぜゴッスはこんな奇妙な主張をしたのでしょうか?
クトゥルフ神話の設定では、ゴッスが大英博物館で水神クタアトを読んでしまったことが原因とされています。そこに記された海の怪物たちの存在があまりに衝撃的で、彼はその恐怖から逃れるために、キリスト教の世界観へと逃げ込もうとしたのではないか、と考えられているんです。
科学的事実と宗教的信仰の板挟みになり、精神的に追い詰められたゴッス。水神クタアトは、優れた科学者の人生さえも狂わせてしまう、恐ろしい力を持った本だったわけですね。
朝松健の作品での展開
日本のホラー作家朝松健の作品では、さらに興味深い設定が加えられています。
彼の小説『聖ジェームズ病院』では、水神クタアトという名前の邪神そのものが存在するという設定になっているんです。つまり、本のタイトルが実は邪神の名前だったという衝撃的な展開。本を読むことで、その邪神と繋がってしまうのかもしれません。
また、『神蝕地帯』という作品でも言及されており、日本のクトゥルフ神話作品においても重要な位置を占める魔導書となっています。
まとめ
水神クタアトは、海と水に潜む恐怖を記録した、クトゥルフ神話屈指の禁断の書です。
重要なポイント
- 11〜12世紀にラテン語で書かれた水棲怪物についての魔導書
- 人間の皮膚で装丁され、気温や湿度で汗をかくという異様な特徴を持つ
- 深きものども、ダゴン、ハイドラ、クトゥルフなど水に関連する存在について詳述
- 召喚術や儀式も含まれる実用的な魔術書
- 現存するのはラテン語版3部と英訳版で、大英博物館などに所蔵
- 19世紀の海洋学者フィリップ・ヘンリー・ゴッスの人生を狂わせたという伝説
- ブライアン・ラムレイによって創造された架空の書物
図書館の奥深くで眠るこの本は、今も静かに汗をかきながら、次に手に取る者を待っているのかもしれません。もし古書店や図書館で人皮装丁の本を見かけたとしても、決して軽い気持ちで開いてはいけませんよ。