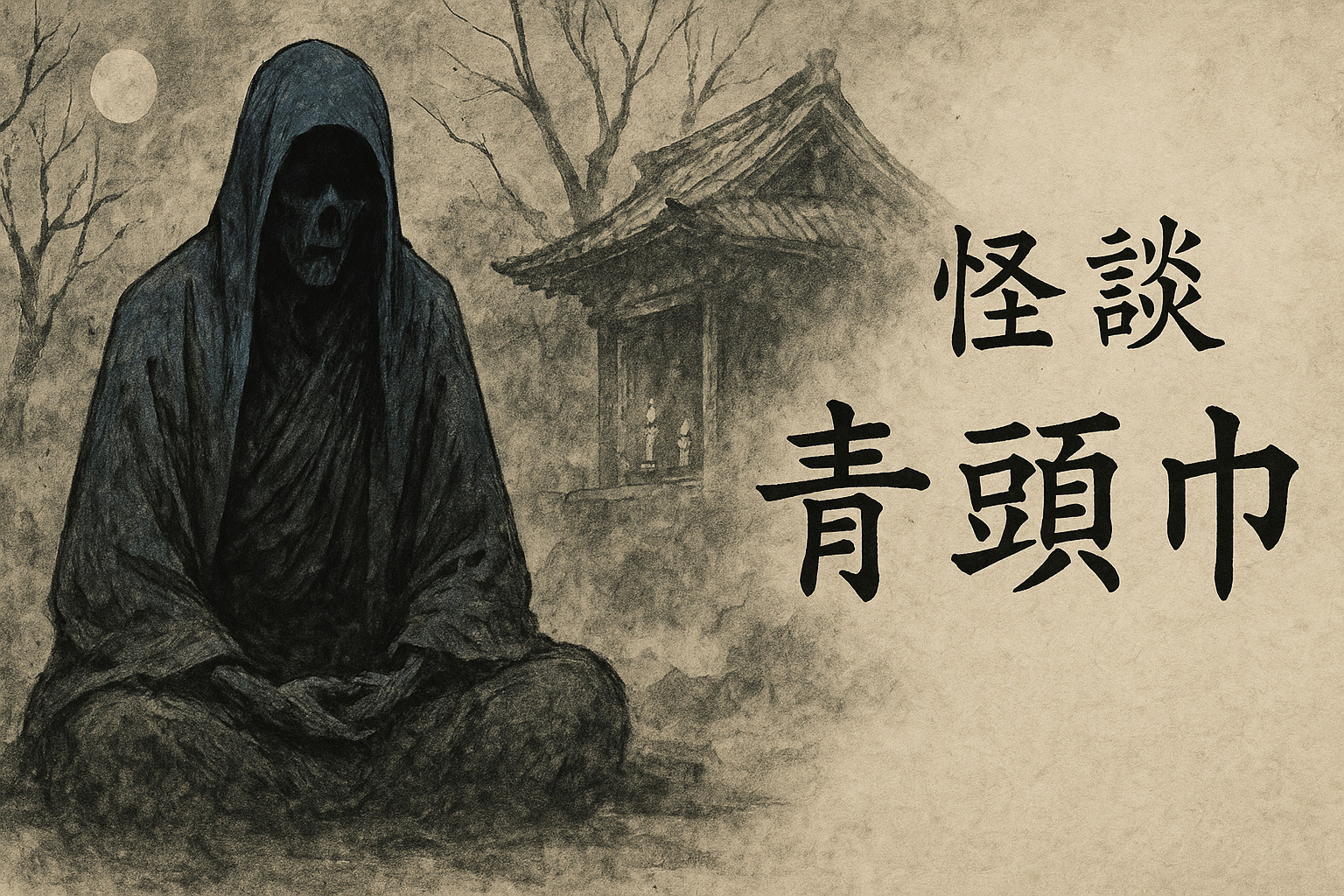もし深く愛した人を失ったら、あなたはどこまで正気でいられるでしょうか?
室町時代、ある高僧が愛する稚児を失った悲しみのあまり、その遺体を食べて鬼と化してしまいました。
これは江戸時代の怪談集『雨月物語』に収録された、愛執が狂気へと変貌する恐ろしくも哀しい物語です。
この記事では、日本の怪談史に残る名作「青頭巾」について詳しくご紹介します。
概要

青頭巾(あおずきん)は、上田秋成の『雨月物語』に収録された怪談の一つです。
稚児への愛執から人肉食に耽るようになった僧侶が、快庵禅師によって救済されるという物語なんです。
舞台は現在の栃木県にある大中寺で、実在の寺院が物語の舞台となっています。
愛欲と執着が人を鬼に変えてしまうという、仏教の教えを含んだ怪談として知られているんですね。
姿・見た目
物語に登場する鬼と化した僧侶の姿は、通常の人間とは異なる恐ろしいものでした。
鬼と化した僧侶の特徴
- 外見は僧侶のままだが、正気を失っている
- 目は血走り、人を人と認識できない
- 夜中に徘徊し、踊り狂う姿が目撃される
- 墓を暴いて死体を貪る様子は、まさに餓鬼そのもの
ただし、完全に怪物になったわけではなく、朝になると一時的に正気に戻るという、人と鬼の間を彷徨う存在だったんです。
特徴
青頭巾の鬼には、他の妖怪とは異なる独特の特徴があります。
主な行動パターン
- 夜になると鬼と化す(昼は正気に戻ることもある)
- 墓を暴いて死体を食べる
- 生きた人間も襲う危険な存在
- 仏法の力には反応する(禅師の前では姿が見えなくなる)
重要なのは、この鬼が元は徳の高い僧侶だったという点です。
愛欲に溺れたことで、仏の道から外れて鬼道に堕ちてしまったんですね。
伝承

青頭巾の物語は、快庵禅師による鬼の救済が中心となっています。
物語のあらすじ
下野国富田の里を訪れた快庵禅師は、山寺に食人鬼が出るという話を聞きました。 その鬼は元々は篤学の高僧でしたが、越の国から連れ帰った美少年の稚児を深く愛するようになったんです。
しかし稚児が病で亡くなると、悲しみのあまり遺体に寄り添い続け、ついにはその死肉を食べてしまいました。
それ以来、僧侶は鬼と化し、里の墓を暴いては死体を食べるようになったといいます。
禅師による救済
快庵禅師は山寺を訪れ、一晩中坐禅を組んで待ちました。 真夜中、鬼と化した僧侶が現れましたが、禅師の姿は見えず、疲れ果てて倒れてしまいます。
朝になって正気に戻った僧侶に、禅師は青頭巾を被せ、公案を授けました。
「江月照松風吹 永夜清宵何所為(こうげつてらし しょうふうふく えいやせいしょう なんのしょいぞ)」
一年後、禅師が再び訪れると、僧侶はまだ公案を唱え続けていました。
禅師が「何の所為ぞ」と杖で頭を叩くと、僧侶の体は消え、青頭巾と人骨だけが残ったのです。
こうして僧侶の妄執は消え去り、快庵禅師はこの寺を曹洞宗に改めて大中寺として再興したといいます。
起源
青頭巾の物語は、1776年に上田秋成が著した『雨月物語』に収められています。
物語の背景
- 実在の人物:快庵禅師(改庵妙慶)は室町時代に実在した曹洞宗の高僧
- 実在の寺院:栃木市の大中寺が舞台
- 時代設定:室町時代の出来事として描かれる
『雨月物語』は江戸時代の代表的な怪談集で、全九編の中でも「青頭巾」は仏教的な救済をテーマにした作品として特徴的です。
まとめ
青頭巾は、愛欲の執着が人を鬼に変えてしまう恐ろしさと、仏法による救済を描いた深い物語です。
重要なポイント
- 『雨月物語』の代表的な怪談の一つ
- 愛する稚児を失った悲しみから食人鬼と化した僧侶の物語
- 実在の快庵禅師と大中寺が舞台
- 青頭巾と公案によって鬼は成仏を遂げる
- 愛執の恐ろしさと仏教的救済がテーマ
単なる怪談ではなく、人間の執着心の恐ろしさと、それを超越する仏の教えを説いた、江戸時代の傑作なんです。