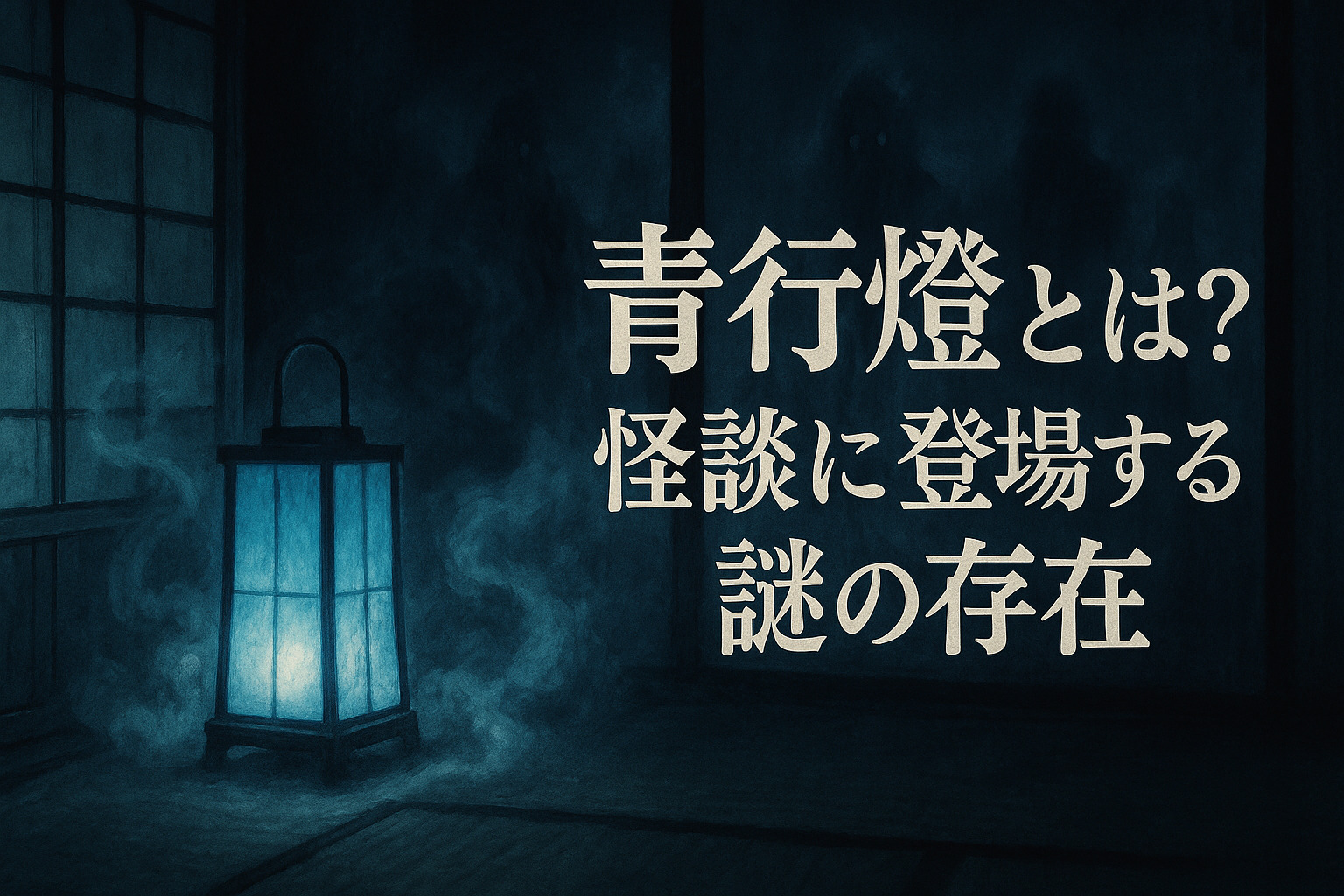夏になると、怪談話や百物語(ひゃくものがたり)が話題になりますよね。そんな怪談の場に必ずと言っていいほど登場するのが「青行燈(あおあんどん)」です。
でも、そもそも青行燈ってどんなもの?
ただの道具なのか、それとも妖怪や幽霊のような存在なのか…。
この記事では、青行燈の正体や意味をわかりやすく解説します。
青行燈とは?
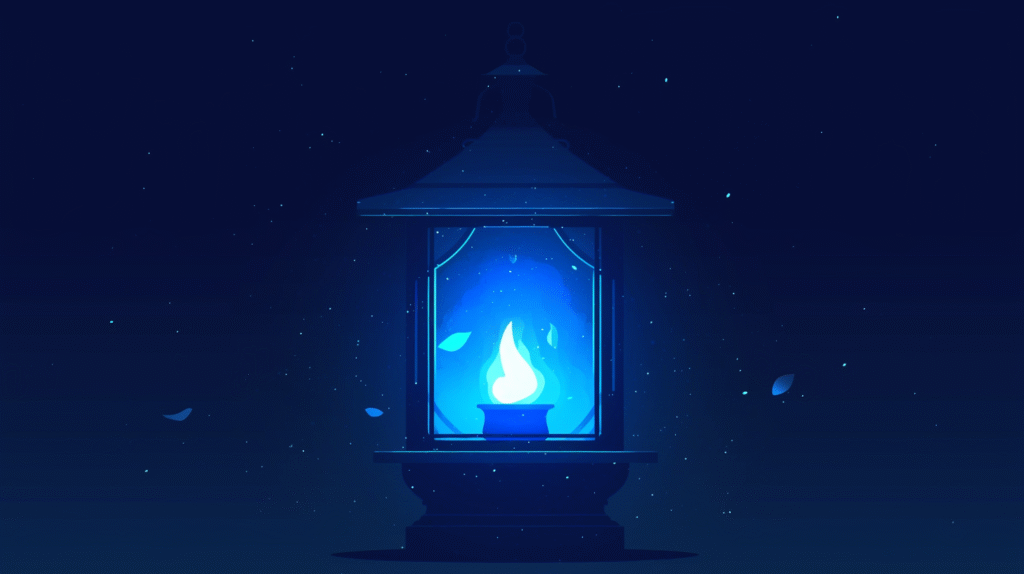
青行燈とは、百物語の会に現れるとされる日本の妖怪です。
百話目になろうとするとき、または百話目が終わったときに現れるとされています。
百物語をするときには、雰囲気を出すために行燈に青い紙を貼っていたと言われており、
この青白い光の中で怪談を語ると、空気がいっそう不気味になり、幽霊や妖怪を呼び寄せるとも信じられていました。
鳥山石燕の『今昔百鬼拾遺』

江戸時代の絵師・鳥山石燕の妖怪画集『今昔百鬼拾遺』(1781年)では、黒くて長い髪の白装束の鬼女の姿で描かれています。
石燕は「鬼を談ずれば、怪にいたるといへり」と言っているので、青行燈は特定の妖怪ではなくて、百物語が終わると現れる存在(もしくは起こる現象)なのではないかとも言われる。
終わろうとする時

青行燈は前記のように終わった後に出る他、終わりに近づくと出てくるパターンもあります。
- 『怪談老の杖』では、83話目が終わってから様子がおかしくなり、首吊り女性が現れた
- 『宿直草』では百話目で天井から手が現れた
まとめ
青行燈は、百物語の百話目に現れるとされる謎の妖怪です。
鳥山石燕によって鬼女の姿で描かれています。
具体的な記録はほとんど残されておらず、青行燈と名指しで登場することはないのですが、百物語が終わる(または終わろうとする)時に何かしら起こったのでしょう。