人魚が描いた蝋燭が、町に繁栄をもたらす——。
そんな美しい導入から始まるこの物語は、やがて人間のエゴイズムが引き起こす悲劇へと転じていきます。
『赤い蝋燭と人魚』は、「日本のアンデルセン」と呼ばれた小川未明の代表作にして、日本児童文学史に燦然と輝く名作です。
この記事では、物語のあらすじから作品に込められたテーマ、作者・小川未明の背景、そして舞台のモデルとなった新潟の地まで、幅広く解説していきます。
概要
『赤い蝋燭と人魚(あかいろうそくとにんぎょ)』は、1921年(大正10年)に発表された小川未明による創作童話です。
人間の優しさを信じた人魚の母親が、我が子を人間に託したものの、やがて欲に目がくらんだ人間に裏切られるという悲劇を描いています。
東京朝日新聞に連載されて大きな反響を呼び、小川未明の出世作となりました。
子ども向けの童話でありながら、大人が読んでも胸に迫る深いテーマ性を持つ作品として、100年以上にわたって読み継がれています。
あらすじ
人魚の母の願い
物語の舞台は、北の冷たく暗い海です。
そこに身重の人魚が棲んでいました。
人魚の母は、暗く寂しい海での暮らしを我が子にさせたくないと願い、「人間は優しく慈悲深い心を持つ」という話を信じて、陸の神社の石段のもとに赤ん坊を産み落とします。
海の生き物でありながら、人間の世界に希望を託すという、母の切ない決断から物語は動き出します。
老夫婦との暮らし
翌朝、神社のそばで蝋燭屋を営む老夫婦が赤ん坊を発見しました。
子どものいなかった老夫婦は、「神様からの授かりもの」と信じ、人魚の赤ん坊を大切に育て始めます。
やがて美しい娘に成長した人魚は、育ててくれた老夫婦への恩返しとして、白い蝋燭に赤い絵具で魚や貝、海草の絵を描き始めました。
この蝋燭が不思議な力を持っていたのです。
絵蝋燭の評判
娘の描いた蝋燭は、たちまち評判になりました。
山の上の神社に納めて火を灯し、その燃えさしを持ち帰って漁に出ると、どんなに海が荒れても無事に帰ってこられるというのです。
蝋燭屋は大繁盛し、遠方からも船乗りや漁師が蝋燭を求めてやってくるようになりました。
神社と町は栄え、人々は蝋燭の恩恵を享受します。
しかし、手が痛くなるのも我慢して絵を描き続ける娘のことを心配する者は、誰一人としていませんでした。
疲れ果てた娘は、いつしか月夜に窓から遠い北の海を眺めては涙を浮かべるようになります。
香具師の登場と裏切り
そんな折、この評判を嗅ぎつけた香具師(やし)——見世物興行を生業とする行商人——が町にやってきました。
人魚の娘を見世物にして金を稼ごうと企んだ香具師は、老夫婦に大金を持ちかけて娘を売ってほしいと頼みます。
老夫婦は最初、「神様からの授かりものだから」と断りました。
けれども、香具師が「昔から人魚は不吉なものだ」と吹き込み、さらに法外な金額を提示すると、老夫婦の心は揺らぎ、ついに娘を手放す決断をしてしまいます。
悲しみの赤い蝋燭
ある月の明るい夜、鉄格子のはまった大きな箱(檻)を載せた車がやってきました。
何も知らずに蝋燭に絵を描いていた娘は、老夫婦から突然「さあ、お前は行くのだ」と告げられます。
娘は必死に懇願しますが、欲に心を奪われた老夫婦は耳を貸しません。
絵を描く暇も与えられなかった娘は、手にしていた蝋燭をすべて真紅に塗りつぶし、悲しい思い出の形見として残していきました。
町の滅亡
娘が連れ去られた後、一人の女が蝋燭屋を訪れ、真紅に塗られた蝋燭を選んで銭を払い去っていきます。
ところがその銭は、灯りの下でよく見ると貝殻だったのです。
その直後、穏やかだった夜は大嵐へと一変しました。
娘を檻に入れて船に乗せ、南の国へ向かっていた香具師の船は、この暴風雨で難破したとされています。
それ以来、赤い蝋燭は不吉の象徴となりました。
赤い蝋燭の火が毎夜、波の上から山の神社へと昇っていくのを見た者がいたといいます。
幾年も経たないうちに、その町は滅びてしまったのでした。
作品のテーマと魅力
人間のエゴイズムと異形の者の悲しみ
『赤い蝋燭と人魚』の核心にあるのは、人間に潜むエゴイズムと、異形の者が抱く怨念の対比です。
人魚の母は「人間は慈悲深い」と信じて我が子を託しました。
老夫婦も最初は娘を「神様からの授かりもの」として愛情深く育てています。
しかし、蝋燭が評判を呼んで利益を生むようになると、娘は「恩恵をもたらす存在」として消費されるようになり、やがて「金に換えられる商品」へと転落していくのです。
娘の優しさや献身に対して、町の人々も老夫婦も誰一人として報いようとしなかった——この構図は、弱い立場の者が搾取される社会の縮図として読むことができます。
「赤」の象徴性
作品を貫く「赤」という色彩には、重層的な意味が込められています。
娘が蝋燭に描いた赤い絵は、海と生命の美しさを伝えるものでした。
けれども物語の終盤、娘が絵を描く暇もなく真紅に塗りつぶした蝋燭は、怒り・悲しみ・怨念の象徴へと変わります。
同じ「赤」が、美しさから恐ろしさへと反転する構成は、この作品の優れた点の一つといえるでしょう。
子どもに向けた、大人のための物語
小川未明自身、童話について次のように述べています。
「私等が、何等かの幻想や、連想によって、既に少年の時代に失はれた世界をもう一度取り返すことが出来たらどんなにか仕合わせでありませう」
未明の童話は、子どものための物語であると同時に、大人が失ってしまったものを取り戻すための文学でもありました。
『赤い蝋燭と人魚』が100年以上にわたって読者の心を打ち続けるのは、この二重の射程を持っているからこそなのかもしれません。
作者・小川未明について
生い立ちと風土
小川未明(おがわ みめい、1882年〜1961年)は、新潟県高田(現在の上越市)に生まれた小説家・児童文学作家です。
本名は小川健作といいます。
父の澄晴は修験者であり、戦国武将・上杉謙信を深く崇拝していた人物でした。
澄晴は春日山神社の創建に奔走し、未明も15歳頃から20歳頃まで神社境内の住居で暮らしています。
また祖母から「羽衣」や「浦島」といった民話の読み聞かせを受けて育ちました。
こうした雪国の厳しい自然、神道の世界観、そして幼少期に触れた民話の数々が、のちの創作の源泉となったとされています。
文学の師との出会い
早稲田大学(当時は東京専門学校)に進学した未明は、坪内逍遥やラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の教えを受けました。
「未明」という号は逍遥から授かったもので、正しくは「びめい」と読みます。
在学中の1904年に処女作「漂浪児」を発表して注目を集め、小説家としてのキャリアをスタートさせました。
怪談文学で知られる小泉八雲の影響も大きく、卒業論文でも八雲を論じています。
日常と非日常の境界を描く八雲の手法は、未明の童話にも色濃く反映されているといえるでしょう。
童話への専念
未明が童話に比重を移していったのは、30代後半のことです。
2人の子どもを相次いで亡くすという悲しみを経て、「弱い者、子どものために書きたい」という思いが強まったとされています。
1921年に『赤い蝋燭と人魚』を発表し、大きな評価を得ました。
挿絵は漫画家の岡本一平(岡本太郎の父)が手がけています。
1926年には東京日日新聞に「今後を童話作家に」と題する宣言を発表し、以後は童話の創作に専念。
生涯でおよそ1200編もの童話を創り、浜田広介、坪田譲治とともに「児童文学界の三種の神器」と称されました。
評価と再評価
1946年には日本児童文学者協会の初代会長に就任し、1951年には日本芸術院賞を受賞、文化功労者にも選ばれています。
しかし1953年頃から、鳥越信や古田足日らによる「少年文学宣言」で「古い児童文学」として批判を受け、書店から未明の作品が姿を消していく時期もありました。
その後、1970年頃になって再評価が始まり、文芸評論家の柄谷行人らも未明の作品における「風景としての児童の発見」に注目しています。
現在も賛否両論の中にある作家ですが、『赤い蝋燭と人魚』をはじめとする作品群が色あせない輝きを放っていることに変わりはありません。
作品の舞台とモデル
新潟県上越市・雁子浜の人魚伝説
『赤い蝋燭と人魚』は、新潟県上越市大潟区の雁子浜(がんごはま)に伝わる人魚塚伝説をモチーフにしたと考えられています。
この伝説は、神社の常夜灯を目当てに佐渡が島から毎夜通ってくる美しい女性と、地元の若者との悲恋の物語です。
ある夜、母親に引き留められた若者が常夜灯を灯さなかったところ、女性は海辺で命を落としてしまいます。
後悔した若者は後を追って海に身を投げ、村人が二人を弔って建てた比翼塚が、いつしか「人魚塚」と呼ばれるようになったといいます。
児童文化研究家の上笙一郎は、「無意識的にもせよ未明が大潟町の人魚伝説に拠ったことは疑いを容れない」と記しています。
未明が主宰した文芸誌『北方文学』2号(1912年)にこの伝説が「人魚塚」として掲載されており、のちの創作への影響は間違いないものとされています。
未明の幼少期との重なり
未明の作品世界には、故郷・上越市での体験が色濃く投影されています。
未明は生まれてすぐ、地方の因習によって隣家の丸山家に里子に出されました。
この丸山家の家業が蝋燭づくりであったという事実は、物語の蝋燭屋の設定と重なります。
また、父が建立に奔走した春日山神社の存在は、物語の「山の上のお宮」を彷彿とさせるものです。
上越教育大学の小埜裕二教授は、未明の作品について「雪や冷たい風、海鳴りなどの高田の自然と、義を重んじる武士階級の価値観が繰り返し登場する」と指摘しています。
厳しい日本海の自然、人間の意志を超えた大きな力を持つ風土が、未明の作品に独特の暗さと美しさを与えているのです。
現在に残る物語のゆかり
上越市内には『赤い蝋燭と人魚』にちなんだ人魚像が9体も設置されており、物語の世界を身近に感じることができます。
船見公園にある人魚像は、日本海を見渡す高台に設置され、絵蝋燭を手にして海を眺める姿が印象的です。
また、雁子浜には「人魚伝説公園」が整備され、人魚伝説の碑が建てられています。
高田城址公園の一角にある「小川未明文学館」では、未明の業績と作品の紹介、生い立ちや時代背景に関する展示が行われており、未明文学に触れる入り口として訪れる価値があります。
絵本としての広がり
『赤い蝋燭と人魚』は、複数の著名な画家によって絵本化されています。
中でも、いわさきちひろが手がけた絵本は、ちひろの絶筆として知られています。
病床にありながら北の海のスケッチのために現地を訪れたちひろの姿は、作品に対する深い共感を物語るものでしょう。
童心社から刊行された『赤い蝋燭と人魚(若い人の絵本)』は、未明の文章とちひろの絵が織りなす静謐な世界観で、長く読み継がれています。
また、偕成社から刊行された酒井駒子による絵本版は、無国籍な風景の中に物語を置き換え、幻想的な雰囲気で新たな読者層を獲得しました。
文章だけで読むとおどろおどろしい印象もある物語ですが、絵本を通すことで人魚の切なさや哀しみがより繊細に伝わってきます。
アンデルセン『人魚姫』との比較
「人魚」を主題とする文学作品としてまず思い浮かぶのは、アンデルセンの『人魚姫』でしょう。
両作品にはいくつかの共通点と、決定的な違いがあります。
『人魚姫』では、人魚自身が人間の世界に憧れ、愛する王子のために声を犠牲にします。
一方、『赤い蝋燭と人魚』では、人魚の母が我が子の幸せを願って人間の世界に託すという構図になっています。
つまり、前者は人魚自身の意志による選択であるのに対し、後者は母の願いと第三者の裏切りによって悲劇が生まれるのです。
結末も対照的です。
『人魚姫』は人魚が泡となって消えるという個人の悲劇で幕を閉じますが、『赤い蝋燭と人魚』では町全体が滅びるという、より大きなスケールの報いが描かれます。
異形の者を裏切った社会全体が罰を受けるという構図は、未明独自の視点といえるでしょう。
未明が「日本のアンデルセン」と呼ばれるのは、単に人魚をモチーフにしたからだけではありません。
メルヘンという手法を用い、生涯を通じて子どものための物語を創り続けたという姿勢そのものが、アンデルセンに通じるものだったのです。
まとめ
『赤い蝋燭と人魚』は、美しく悲しい物語の中に、現代にも通じる普遍的なテーマを秘めた作品です。
最後に、この作品の要点を整理します。
- 1921年に東京朝日新聞で連載された小川未明の代表作であり出世作
- 人間の優しさを信じた人魚の母と、欲に負けて裏切る人間のエゴイズムを描く
- 新潟県上越市の雁子浜に伝わる人魚伝説がモチーフとされている
- 未明自身の幼少期の体験(里子先の蝋燭屋、父が建てた神社)が色濃く反映されている
- いわさきちひろや酒井駒子など、多くの画家によって絵本化されている
- 100年以上にわたって読み継がれ、日本児童文学史上の不朽の名作として評価されている
原文は青空文庫で無料公開されています。
短い作品ですので、まだ読んだことがない方はぜひ一度、原文に触れてみてください。
参考情報
関連記事
この記事で参照した情報源
一次資料(原典)
- 小川未明『赤い蝋燭と人魚』東京朝日新聞、1921年2月16日〜20日連載 – 青空文庫で全文公開
信頼できる二次資料(専門家による研究・批評)
- 小埜裕二『小川未明に親しむ』蒼丘書林 – 上越教育大学教授による未明研究の基礎文献
- 松岡正剛「73夜 『赤いろうそくと人魚』 小川未明童話集より」千夜千冊 – 未明の生涯と作品の時代背景を詳述
参考になる外部サイト
- Wikipedia「赤い蝋燭と人魚」 – 作品の概要、あらすじ、人魚伝説との関係
- Wikipedia「小川未明」 – 作者の生涯と業績
- 小川未明文学館(上越観光Navi) – 上越市の文学館の公式情報
- 人魚伝説公園(上越観光Navi) – 雁子浜の人魚塚伝説と公園の紹介
- 新潟文化物語「弱き者のために。日本近代童話の父・小川未明」 – 未明の生い立ちと創作の背景を詳述





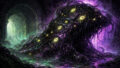


コメント