「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」――この有名すぎるセリフ、実はマリー・アントワネットが言ったという証拠はありません。
それどころか、彼女が生まれる前にすでに存在していた言い回しでした。
マリー・アントワネット(Marie Antoinette)は、フランス国王ルイ16世(Louis XVI)の王妃であり、フランス革命という歴史の大転換の渦中で命を落とした人物です。
華やかな宮廷生活の象徴として語られることが多い一方、近年の研究では、時代の犠牲者としての側面も明らかになってきています。
この記事では、マリー・アントワネットの誕生から処刑までの生涯を、史実に基づいてわかりやすく解説します。
概要
マリー・アントワネットは、1755年にオーストリアのウィーンで生まれ、1793年にパリで処刑されたフランス王妃です。
神聖ローマ皇帝フランツ1世(Franz I.)とオーストリア女帝マリア・テレジア(Maria Theresia)の第15子として生まれました。
14歳でフランス王太子ルイに嫁ぎ、19歳でフランス王妃となっています。
フランス革命の象徴的な犠牲者として、彼女の名前は歴史に深く刻まれました。
その生涯は、多くの小説・映画・漫画の題材として現代まで語り継がれています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本名 | マリア・アントーニア・ヨーゼファ・ヨハンナ(Maria Antonia Josepha Joanna) |
| フランス名 | マリー=アントワネット=ジョゼフ=ジャンヌ・ド・アプスブール=ロレーヌ(Marie-Antoinette-Josèphe-Jeanne de Habsbourg-Lorraine) |
| 生年月日 | 1755年11月2日 |
| 出生地 | オーストリア・ウィーン |
| 没年月日 | 1793年10月16日(37歳) |
| 没地 | フランス・パリ(ギロチンによる処刑) |
| 父 | フランツ1世(神聖ローマ皇帝) |
| 母 | マリア・テレジア(オーストリア女帝) |
| 配偶者 | ルイ16世(フランス国王) |
| 子女 | 4人(マリー・テレーズ、ルイ・ジョゼフ、ルイ・シャルル、ソフィー) |
| 在位 | 1774年〜1792年(フランス王妃として) |
出生と幼少期:ハプスブルク家の皇女
マリー・アントワネットは、1755年11月2日にウィーンで誕生しました。
奇しくも、その前日の11月1日にはポルトガルのリスボンで大地震が発生し、推定3万人が犠牲になっています。
父フランツ1世と母マリア・テレジアの間に生まれた16人の子どものうち、第15子(第11女)でした。
マリア・テレジアは、当時のヨーロッパで最も有能な君主の一人として知られる女帝です。
啓蒙専制君主として国家の近代化を推進し、教育改革や行政改革を断行した人物でした。
幼少期のマリー・アントワネット(当時の名はマリア・アントーニア)は、ウィーンのシェーンブルン宮殿(Schönbrunn)で育ちました。
音楽やダンスの素養があり、作曲家モーツァルトとも幼少期に出会ったという逸話が残っています。
一方で、学問にはあまり熱心ではなかったとされています。
フランス語の習得が遅れていたため、結婚が決まった後にオルレアン司教ヴェルモン神父のもとで本格的な学習を始めました。
政略結婚:14歳でフランスへ
オーストリアとフランスの同盟
当時のヨーロッパでは、プロイセンの急速な台頭が各国にとって大きな脅威となっていました。
これに対抗するため、長年の宿敵であったオーストリアとフランスは、伝統的な敵対関係を捨てて同盟を結びます。
マリア・テレジアはハプスブルク家伝統の政略結婚を画策し、娘マリア・アントーニアをフランス王太子ルイ・オーギュスト(Louis-Auguste、のちのルイ16世)に嫁がせることを決めました。
この結婚は、純粋に外交政策の一環として計画されたものです。
ヴェルサイユ宮殿での結婚式
1770年4月19日、マリア・アントーニアが14歳のとき、まずウィーンで代理人による結婚式が行われました。
その後フランスへ向かい、1770年5月16日、ヴェルサイユ宮殿の王室礼拝堂にて正式な結婚式が挙行されています。
オーストリアの皇女マリア・アントーニアは、フランス王太子妃マリー・アントワネットとなりました。
パリ市民も当初は彼女に好意的で、祝宴は5月30日まで続いたと記録されています。
しかし、新婚生活は必ずしも順調ではありませんでした。
夫のルイは温厚な人柄ながら内向的で、若く社交的なマリー・アントワネットとは対照的な性格だったのです。
フランス王妃としての日々
即位と宮廷生活
1774年、ルイ15世の崩御に伴い、ルイ16世が即位しました。
マリー・アントワネットは19歳にしてフランス王妃となります。
王妃となったマリー・アントワネットは、ヴェルサイユ宮殿の厳格な儀礼を窮屈に感じていたようです。
朝の接見を簡素化したり、王族の食事風景の公開を廃止したりと、宮廷の伝統的な慣習をいくつも緩和させました。
しかし、フランスの絶対王政では、こうした儀式や特権が貴族たちの忠誠心を支える重要な仕組みでした。
その廃止は宮廷内の反感を招き、マリー・アントワネットの孤立を深める一因となっています。
華やかな生活と批判
マリー・アントワネットは、当時のファッションリーダーとして知られていました。
大きなかつら(ポーフ)や華麗なドレスを好み、舞踏会や観劇、賭博にも熱心だったと伝えられています。
特に有名なのが、プチ・トリアノン(Petit Trianon)での暮らしです。
ヴェルサイユ宮殿の敷地内にあるこの離宮で、マリー・アントワネットは宮廷の堅苦しい慣習から離れた私的な時間を過ごしました。
さらに1783年頃には、画家ユベール・ロベール(Hubert Robert)のデザインに基づく「王妃の村里」(Hameau de la Reine)と呼ばれる模擬農村を建設させています。
こうした暮らしぶりは、すでに財政難に苦しんでいたフランスの民衆から強い批判を浴びることになりました。
とはいえ、ブリタニカ百科事典(Encyclopædia Britannica)が指摘するように、マリー・アントワネットの浪費はフランスの財政赤字のごく一部に過ぎなかったのも事実です。
国家財政を圧迫した主な原因は、アメリカ独立戦争への参戦費用をはじめとする18世紀の対外戦争にありました。
子どもたち
マリー・アントワネットとルイ16世の間には、結婚から7年間にわたって子どもが生まれませんでした。
後継ぎを産むことが王妃の最重要任務であった当時、これは深刻な問題だったのです。
1777年、マリー・アントワネットの長兄であるヨーゼフ2世(Joseph II.、神聖ローマ皇帝)がパリを訪問し、夫婦に助言を与えたとされています。
その後、二人の間には4人の子が生まれました。
| 名前 | 生年 | 没年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マリー・テレーズ・シャルロット(Marie-Thérèse-Charlotte) | 1778年 | 1851年 | 革命から唯一生き延びた子 |
| ルイ・ジョゼフ(Louis-Joseph) | 1781年 | 1789年 | 王太子。結核により8歳で死去 |
| ルイ・シャルル(Louis-Charles) | 1785年 | 1795年 | のちの「ルイ17世」。幽閉中に10歳で死去 |
| ソフィー・ベアトリス(Sophie-Béatrice) | 1786年 | 1787年 | 生後11か月で死去 |
長女マリー・テレーズのみが成人し、革命を生き延びました。
「パンがなければお菓子を食べればいいじゃない」の真相
マリー・アントワネットを象徴する言葉として広く知られるこのセリフですが、彼女が実際に発言したという証拠は存在しません。
この逸話の出典は、哲学者ジャン=ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau)の自伝『告白』(Les Confessions)です。
『告白』の執筆は1766年頃とされており、当時マリー・アントワネットはまだ11歳でした。
ルソーはこの発言を「ある大公妃」(une grande princesse)のものとして記しており、特定の人物名は挙げていません。
つまり、この発言がマリー・アントワネット以前から存在していたことは確実です。
フランス革命期の扇動家たちが、王妃への民衆の憎悪を煽るためにこの言葉を彼女に結びつけたと考えられています。
首飾り事件:王妃の評判を決定的に傷つけたスキャンダル
1785年、フランス革命の4年前に起きた「首飾り事件」(Affaire du collier de la reine)は、マリー・アントワネットの評判に致命的なダメージを与えたスキャンダルです。
事件の発端
宝石商シャルル・ベーマー(Charles Boehmer)とポール・バッサンジュ(Paul Bassenge)は、先王ルイ15世が愛妾デュ・バリー夫人(Madame du Barry)のために注文した豪華な首飾りを製作していました。
大小540個のダイヤモンドからなり、価格は160万リーブルという途方もない金額です。
しかし、ルイ15世の急逝により注文は立ち消えとなりました。
宝石商たちはマリー・アントワネットに売り込もうとしましたが、王妃はこれを拒否しています。
詐欺の全容
没落貴族のジャンヌ・ド・ラ・モット伯爵夫人(Jeanne de La Motte)が、この首飾りを巡る大がかりな詐欺を企てました。
ラ・モット伯爵夫人は、王妃との関係修復を望んでいたロアン枢機卿(Cardinal de Rohan)に近づきます。
そして「王妃が密かに首飾りを欲しがっている」という虚偽の情報を伝え、枢機卿に代理購入を持ちかけました。
さらに巧妙だったのは、マリー・アントワネットに似た女性を王妃の替え玉として仕立て上げ、夜のヴェルサイユ庭園でロアン枢機卿と「面会」させたことです。
偽造された手紙も用意されており、枢機卿はすっかり騙されてしまいました。
事件の結末と影響
ロアン枢機卿が首飾りを代理購入してラ・モット伯爵夫人に渡すと、首飾りはバラバラに分解されて売りさばかれてしまいます。
事件が発覚した後、裁判でラ・モット伯爵夫人は有罪、ロアン枢機卿は無罪となりました。
マリー・アントワネット自身は事件に一切関与していませんでしたが、世論は王妃の潔白を信じようとしませんでした。
ドイツの文豪ゲーテ(Goethe)はこの事件について、「王室の威厳を破壊した」と述べ、フランス革命の直接的な序章と評しています。
フランス革命と王妃の転落
革命の勃発
1789年7月14日、パリの民衆がバスティーユ牢獄を襲撃し、フランス革命が始まりました。
フランスは長年の対外戦争と財政赤字に苦しんでおり、国民の不満は頂点に達していたのです。
同年10月5日、パリから数千人の男女がヴェルサイユ宮殿に押し寄せ、国王一家をパリに連れ戻しました。
王室はテュイルリー宮殿(Palais des Tuileries)に移されることとなります。
ヴァレンヌ逃亡事件
1791年6月20日夜、ルイ16世とマリー・アントワネットは家族とともにパリからの脱出を試みました。
変装して馬車でフランス東部の国境を目指しましたが、途中のヴァレンヌ(Varennes)で身元が発覚し、パリに連れ戻されています。
この「ヴァレンヌ逃亡事件」は、国王一家が国を見捨てて外国の力で革命を潰そうとしていると民衆に確信させることになりました。
国民の信頼は完全に失われたのです。
マリー・アントワネットは、ひそかにオーストリアの兄レオポルト2世(Leopold II.)に手紙を送り、軍事介入を要請していたことも後に明らかになりました。
こうした行動が「オーストリア女」(l’Autrichienne)という蔑称への憎悪をさらに激化させたのです。
王権の停止と幽閉
1792年4月、フランスはオーストリアに宣戦布告します。
戦況が悪化するなか、同年8月10日、パリ市民と義勇兵がテュイルリー宮殿を襲撃しました。
国王一家はタンプル塔(Tour du Temple)に幽閉されます。
タンプル塔での生活は、幽閉とはいえ家族で過ごす束の間の穏やかな時間でもありました。
チェスを楽しんだり、楽器を演奏したり、子どもの勉強を見たりする日々があったと記録されています。
1792年9月21日、フランスは共和国を宣言し、王政は正式に廃止されました。
裁判と処刑
ルイ16世の処刑
1793年1月21日、ルイ16世が革命広場(現在のコンコルド広場)でギロチンにより処刑されました。
夫の死後、マリー・アントワネットは息子ルイ・シャルルと引き離され、コンシェルジュリ(Conciergerie)監獄の独房に移されます。
彼女の健康は急速に悪化し、白髪が増え、出血に悩まされたと伝えられています。
革命裁判
1793年10月14日、マリー・アントワネットは革命裁判所に出廷しました。
告発の内容には、国庫の浪費、敵国との共謀に加え、息子ルイ・シャルルへの性的虐待という根拠のない中傷まで含まれていたのです。
この不当な告発に対し、マリー・アントワネットは毅然として反論しました。
傍聴席の母親たちに向かって「すべての母親に聞きたい」と訴えたその姿は、裁判に居合わせた人々の心を揺さぶったといわれています。
しかし、判決は最初から決まっていたも同然でした。
15時間に及ぶ審理の末、全会一致で有罪が宣告されています。
最期の時
1793年10月16日早朝、死刑判決が言い渡されました。
マリー・アントワネットは処刑の直前、ルイ16世の妹エリザベート宛に遺書を書き残しています。
その中で彼女は、「犯罪者にとって死刑は恥ずべきものだが、無実の罪で断頭台に送られるなら恥ずべきものではない」と記しました。
同日正午頃、マリー・アントワネットは革命広場でギロチンにかけられ、37歳の生涯を閉じました。
ルイ16世が荘厳な馬車で処刑場に向かったのに対し、彼女は罪人用の粗末な荷車に乗せられていたと記録されています。
しかし、その最期の歩みは落ち着きと威厳に満ちたものだったとされています。
マリー・アントワネットの再評価
「浪費家の王妃」像の見直し
かつてマリー・アントワネットは、ただの浪費家で軽薄な王妃というイメージが強い人物でした。
しかし、20世紀以降の歴史研究では、このイメージに修正が加えられています。
オーストリアの作家シュテファン・ツヴァイク(Stefan Zweig)は1932年の伝記で、マリー・アントワネットを「偉大な聖女でもなければ淫売でもなく、平凡な性格の持ち主」と評しました。
革命派が誇張した「悪女」のイメージと、王党派が美化した「殉教者」のイメージ、その両方から彼女を解放しようとしたのです。
イギリスの歴史家アントニア・フレイザー(Antonia Fraser)も2001年の伝記『マリー・アントワネット』で、より公平な視点から彼女の生涯を再構成しています。
誤解と真実
マリー・アントワネットについては、いくつかの重要な事実がしばしば見過ごされてきました。
まず、彼女の浪費がフランスの財政破綻の主因であったかのように語られますが、国家の財政赤字の主な原因はアメリカ独立戦争への参戦費用でした。
王妃の支出は、確かに批判されるべきものでしたが、国家財政のごく一部に過ぎません。
また、マリー・アントワネットは芸術のパトロンとしての側面も持っていました。
音楽を愛し、約5,000冊の蔵書を収集していたことが英語版Wikipediaに記録されています。
歴史書や音楽関連の書籍を好み、宮殿内でサロンコンサートを主催するなど、文化面での貢献もありました。
さらに、アメリカ独立戦争においてフランスの支援を実現させるために、オーストリアとロシアの協力を取り付けるなど、政治的な役割を果たしていたことも近年の研究で注目されています。
外国人として生きた苦悩
マリー・アントワネットの悲劇を理解するうえで、彼女が終生「外国人」として扱われ続けたことは見逃せません。
「オーストリア女」(l’Autrichienne)という蔑称が示すように、フランス国民にとって彼女は最後まで「よそ者」でした。
革命期に流布した中傷パンフレット(リベル)は、王妃の性的な放蕩を誇張する内容に満ちていましたが、その多くは事実無根のプロパガンダだったとされています。
彼女が女性であり外国人であったことが、スケープゴートの標的にされやすい条件を揃えていたのです。
マリー・アントワネットを題材にした作品
マリー・アントワネットの波乱の生涯は、多くの創作作品に影響を与えてきました。
池田理代子の漫画『ベルサイユのばら』(1972年連載開始)は、日本でマリー・アントワネットの名を広く知らしめた代表的作品です。
架空のキャラクターであるオスカルを軸にしながら、マリー・アントワネットの生涯とフランス革命を劇的に描きました。
映画では、2006年にソフィア・コッポラ(Sofia Coppola)監督が『マリー・アントワネット』を製作しています。
キルスティン・ダンスト(Kirsten Dunst)が王妃を演じ、現代的な視点から彼女の孤独と苦悩を描いた作品として話題となりました。
ツヴァイクの伝記小説『マリー・アントワネット』(1932年)は、小説と史実の間を行く名作として今も読み継がれています。
日本語では岩波文庫版、角川文庫版、河出文庫版など複数の翻訳が出版されています。
また、遠藤周作も『王妃マリー・アントワネット』のなかで、首飾り事件をはじめとするエピソードを取り上げました。
まとめ
マリー・アントワネットの生涯を振り返ると、以下のポイントが浮かび上がります。
- 1755年にオーストリアのウィーンで、ハプスブルク家の皇女として生まれた
- 14歳で政略結婚によりフランスに嫁ぎ、19歳でフランス王妃となった
- 華やかな宮廷生活で「浪費家」と批判されたが、フランスの財政赤字の主因は対外戦争費用だった
- 1785年の首飾り事件で、無実にもかかわらず評判を決定的に失った
- フランス革命のなかで王政の象徴として民衆の憎悪を一身に浴びた
- 1793年10月16日、37歳でギロチンにより処刑された
- 「パンがなければお菓子を」の発言は、彼女のものではないことが明らかになっている
- 近年の研究では、時代と状況の犠牲者としての側面が再評価されている
マリー・アントワネットの人生は、王室外交の駒として生まれ、革命の嵐に飲み込まれた一人の女性の物語です。
彼女が残した遺書の言葉は、最期まで尊厳を保とうとした意志の表れとして、今も多くの人々の心に残っています。
参考情報
関連記事
- ナポレオンとは?天才軍人にしてフランス皇帝の波乱の生涯をわかりやすく解説 – フランス革命後に台頭したナポレオンの生涯
この記事で参照した情報源
学術資料・百科事典
- Encyclopædia Britannica「Marie-Antoinette」 – マリー・アントワネットの生涯と歴史的評価に関する包括的な解説
- World History Encyclopedia「Marie Antoinette」 – 学術的にレビューされたマリー・アントワネットの伝記記事
- HISTORY.com「Marie Antoinette」 – 生涯の概要と「パンがなければ〜」の逸話の検証
- Library of Congress「Marie Antoinette – France: Women in the Revolution」 – 米国議会図書館によるフランス革命期の女性としてのマリー・アントワネット研究ガイド
Wikipedia(出典確認済み)
- Wikipedia「マリー・アントワネット」 – 日本語版。生涯の詳細な年表と出来事の記録
- Wikipedia「Marie Antoinette」 – 英語版。政治的役割や芸術パトロンとしての活動を含む
- Wikipedia「首飾り事件」 – 事件の詳細と経緯
主要な伝記・研究書(参考文献として)
- シュテファン・ツヴァイク(Stefan Zweig)『マリー・アントワネット』(1932年) – 革命派・王党派双方のイメージから解放した先駆的伝記
- アントニア・フレイザー(Antonia Fraser)『Marie Antoinette: The Journey』(2001年) – 現代の代表的な学術伝記





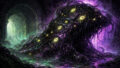

コメント