Outlookが突然動かなくなった、メールの送受信がおかしい、起動に時間がかかる…そんな時、「プロファイルを再作成してください」と言われたことはありませんか?
プロファイルの再作成と聞くと難しそうに感じますが、実は手順通りにやれば誰でもできる作業なんです。
そして、この再作成によって多くのOutlookの問題が解決します。
この記事では、Outlookのプロファイル再作成について、事前準備から実際の手順、データの引き継ぎ方まで初心者の方にも分かりやすくご紹介します。
概要

Outlookの「プロファイル再作成」とは、壊れたり不具合が出ているプロファイルを削除して、新しいプロファイルを作り直すことです。
パソコンで言えば、「初期化して再インストール」するようなイメージですね。
プロファイルって何?
プロファイルは、Outlookの設定情報をまとめた「設定ファイル」のようなものです。
プロファイルに含まれる情報
- メールアカウントの設定
- データファイル(PSTファイル)の場所
- 署名の設定
- 仕分けルールやクイック操作
- アドレス帳の設定
- 表示設定やカスタマイズ
これらの設定が一つにまとまって、「プロファイル」として保存されています。
なぜ再作成が必要なの?
プロファイルが壊れると、Outlookに様々な問題が発生します。
プロファイル再作成が必要な症状
- Outlookが起動しない、または起動が非常に遅い
- メールの送受信ができない
- エラーメッセージが頻繁に表示される
- フリーズや強制終了が頻発する
- アカウント設定が保存されない
- 検索機能が使えない
こういった問題の多くは、プロファイルを再作成することで解決するんです。
再作成で何が起こるの?
プロファイルを再作成すると、設定がリセットされます。
再作成によってリセットされるもの
- アカウント設定(再設定が必要)
- 署名(再作成が必要)
- 仕分けルール(再設定が必要)
- 表示設定(デフォルトに戻る)
- カスタマイズした内容
再作成でも保持されるもの
- メール本体(PSTファイルに保存されている)
- 連絡先
- カレンダーの予定
- タスク
つまり、「設定はリセットされるけど、データは残る」ということです。
再作成とアカウント削除の違い
「アカウントを削除して追加し直す」のと何が違うのでしょうか?
アカウント削除・再追加
- プロファイル自体は残る
- プロファイルが壊れていると問題が解決しないことがある
- 比較的簡単
プロファイル再作成
- プロファイルごと作り直す
- より根本的な解決になる
- より確実に問題が解決する
アカウント削除で解決しない場合は、プロファイル再作成を試すのが効果的です。
作業時間の目安
プロファイル再作成にかかる時間は、環境によって異なります。
作業時間の目安
- 準備(情報確認):10~15分
- プロファイル削除・作成:5~10分
- アカウント設定:5~10分(自動設定の場合)
- データ接続・確認:5~10分
- 合計:30分~1時間程度
複数のアカウントがある場合や、手動設定が必要な場合は、もう少し時間がかかります。
事前準備
プロファイル再作成を始める前に、必ず以下の準備をしましょう。
【最重要】メールアカウント情報を控える
再作成後にアカウントを設定し直すため、以下の情報が必要です。
必須情報リスト
- メールアドレス
- パスワード
- 受信メールサーバー(POPまたはIMAP)
- 送信メールサーバー(SMTP)
- ポート番号
- セキュリティの種類(SSL/TLSなど)
GmailやOutlook.comなどの一般的なサービスは、メールアドレスとパスワードだけでOKです。
会社のメールの場合は、IT部門から情報をもらっておきましょう。
データファイル(PSTファイル)の場所を確認
メールデータがどこに保存されているか確認しておきます。
PSTファイルの場所確認手順
- Outlookで「ファイル」→「アカウント設定」→「アカウント設定」を開く
- 「データファイル」タブをクリック
- 各データファイルの場所をメモする
- 通常は以下の場所にあります:
C:\Users\[ユーザー名]\Documents\OutlookファイルC:\Users\[ユーザー名]\AppData\Local\Microsoft\Outlook
この場所を覚えておけば、後でデータを再接続できます。
署名をバックアップする
メールの署名は、テキストファイルに保存しておきましょう。
署名のバックアップ方法
- Outlookで「ファイル」→「オプション」→「メール」を開く
- 「署名」ボタンをクリック
- 各署名の内容をコピー
- メモ帳などに貼り付けて保存
画像入りの署名の場合は、スクリーンショットを撮っておくと便利です。
仕分けルールをエクスポートする
仕分けルールも、事前にエクスポートしておくと安心です。
仕分けルールのエクスポート手順
- 「ファイル」→「仕訳ルールと通知の管理」を開く
- 「オプション」ボタンをクリック
- 「仕訳ルールのエクスポート」を選択
- 保存場所を指定してファイルを保存
後で「仕訳ルールのインポート」を使えば、同じルールを復元できます。
連絡先をエクスポートする
念のため、連絡先もエクスポートしておきましょう。
連絡先のエクスポート手順
- 「ファイル」→「開く/エクスポート」→「インポート/エクスポート」
- 「ファイルにエクスポート」を選択
- 「カンマ区切り(CSV)」を選択
- 「連絡先」フォルダーを選択
- 保存場所を指定
CSV形式で保存しておけば、様々な形式で復元できます。
カレンダーをバックアップする
カレンダーの予定も念のためバックアップします。
カレンダーのバックアップ手順
- カレンダー画面を開く
- 「ファイル」→「予定表の保存」を選択
- ファイル名と保存場所を指定
- 「保存」をクリック
iCalendar形式(.ics)で保存されます。
再作成の手順
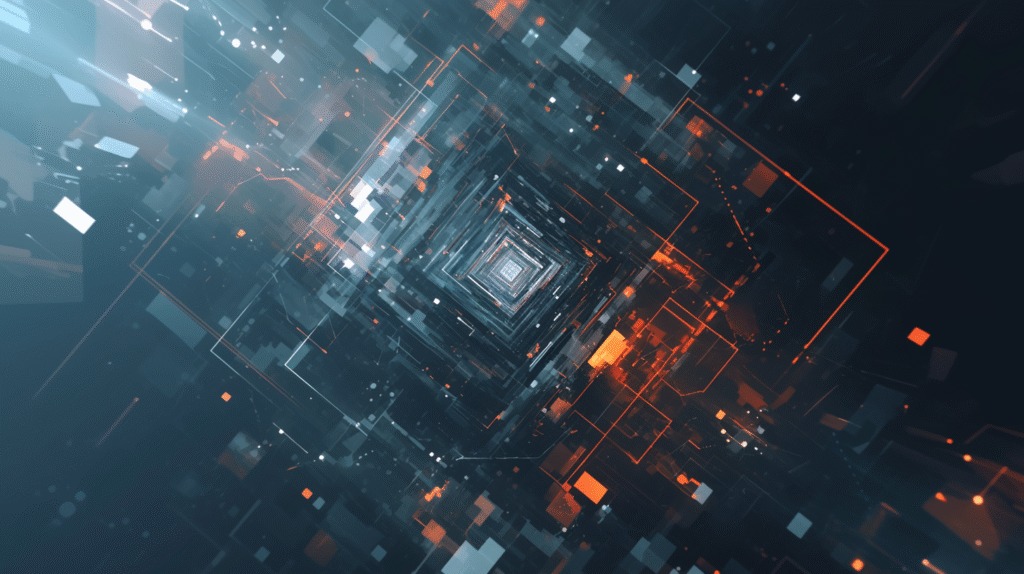
それでは、実際にプロファイルを再作成していきましょう。
【手順1】Outlookを完全に終了する
まず、Outlookを完全に終了させます。
完全終了の方法
- Outlookの画面を閉じる
- タスクバー右下の通知領域を確認
- Outlookのアイコンがあれば右クリック→「終了」
- タスクマネージャー(Ctrl + Shift + Esc)を開く
- Outlookが動作していないか確認
- 残っていれば選択して「タスクの終了」
バックグラウンドで動作していると、プロファイル操作ができません。
【手順2】コントロールパネルを開く
プロファイル管理は、コントロールパネルから行います。
コントロールパネルの開き方
- Windowsキー + R を押す
- 「control」と入力してEnter
- または、スタートメニューから「コントロールパネル」を検索
コントロールパネルが開いたら、表示方法を「大きいアイコン」または「小さいアイコン」に変更します。
【手順3】Mail設定を開く
Mail設定の開き方
- コントロールパネルで「Mail (Microsoft Outlook)」を探す
- ダブルクリックして開く
- 「メールセットアップ – Outlook」ウィンドウが開く
ここからプロファイル管理ができます。
【手順4】既存のプロファイルを削除する
古いプロファイルを削除します。
削除の手順
- 「プロファイルの表示」ボタンをクリック
- 「メール」ウィンドウが開く
- 現在のプロファイル(通常は「Outlook」という名前)を選択
- 「削除」ボタンをクリック
- 確認メッセージで「はい」をクリック
これで古いプロファイルが削除されました。データファイルは削除されていません。
【手順5】新しいプロファイルを作成する
次に、新しいプロファイルを作成します。
新規作成の手順
- 「メール」ウィンドウで「追加」ボタンをクリック
- 「新しいプロファイル」ウィンドウが開く
- プロファイル名を入力(例:「Outlook」「新しいプロファイル」など)
- 「OK」をクリック
- 「アカウントの追加」ウィンドウが自動的に開く
プロファイル名は何でも構いませんが、分かりやすい名前にしましょう。
【手順6】メールアカウントを設定する
新しいプロファイルにメールアカウントを追加します。
自動設定の場合
- メールアドレスを入力
- 「接続」をクリック
- パスワードを入力
- 必要に応じて2段階認証を完了
- 「完了」をクリック
Gmail、Outlook.com、Yahoo!メールなどは自動設定されます。
手動設定が必要な場合
- 「詳細オプション」をクリック
- 「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェック
- 「接続」をクリック
- POPまたはIMAPを選択
- サーバー情報を入力
- 「次へ」→「接続」をクリック
事前に控えた情報を使って設定します。
【手順7】既存のデータファイルを接続する
過去のメールを見られるようにするため、既存のPSTファイルを接続します。
データファイル接続手順
- Outlookを起動
- 「ファイル」→「アカウント設定」→「アカウント設定」を開く
- 「データファイル」タブをクリック
- 「追加」ボタンをクリック
- 事前に確認したPSTファイルの場所に移動
- PSTファイルを選択
- 「OK」をクリック
左側のフォルダー一覧に、古いメールフォルダーが表示されます。
【手順8】データファイルを既定に設定する
新しいメールが正しい場所に保存されるようにします。
既定設定の手順
- 「データファイル」タブで、メインで使いたいPSTファイルを選択
- 「既定に設定」ボタンをクリック
- 「OK」をクリック
これで、新しいメールがこのファイルに保存されるようになります。
【手順9】複数アカウントを追加する
複数のメールアカウントを使っている場合は、追加します。
追加アカウント設定手順
- 「ファイル」→「アカウントの追加」をクリック
- 次のメールアドレスを入力
- 同じ手順で設定を進める
- 必要な数だけ繰り返す
すべてのアカウントを追加し終えるまで繰り返しましょう。
【手順10】署名を再設定する
バックアップしておいた署名を再設定します。
署名の再設定手順
- 「ファイル」→「オプション」→「メール」を開く
- 「署名」ボタンをクリック
- 「新規作成」をクリック
- 署名名を入力
- バックアップしたテキストを貼り付け
- 「OK」で保存
複数の署名がある場合は、すべて再作成します。
【手順11】仕分けルールをインポートする
エクスポートしておいた仕分けルールを読み込みます。
インポート手順
- 「ファイル」→「仕訳ルールと通知の管理」を開く
- 「オプション」ボタンをクリック
- 「仕訳ルールのインポート」を選択
- 保存しておいたファイルを選択
- 「開く」をクリック
これで、以前と同じ仕分けルールが復元されます。
【手順12】その他の設定を調整する
必要に応じて、その他の設定も調整しましょう。
調整したい主な設定
- 表示設定(閲覧ウィンドウの位置など)
- クイック操作
- カテゴリの色設定
- 迷惑メールフィルター
- 送受信の間隔
これらは「ファイル」→「オプション」から設定できます。
確認とトラブル解決
再作成後に確認すべきことと、よくある問題の解決方法です。
動作確認をする
すべての設定が完了したら、動作を確認しましょう。
確認チェックリスト
- Outlookが正常に起動するか
- メールの送受信ができるか
- 過去のメールが表示されるか
- 連絡先が表示されるか
- カレンダーが表示されるか
- 署名が正しく挿入されるか
テストメールを送って、すべて正常に動作するか確認してください。
過去のメールが表示されない
PSTファイルを接続したのに、メールが見えない場合です。
解決方法
- 左側のフォルダー一覧を確認
- フォルダーが折りたたまれていないか確認
- データファイル名の左にある矢印をクリックして展開
- または、検索機能でメールを探してみる
データファイルは接続されているが、フォルダーが表示されていないだけの場合が多いです。
メールの送信はできるが受信ができない
送信はできても受信できない場合の対処法です。
解決方法
- アカウント設定を再確認
- 受信サーバーの情報が正しいか確認
- ポート番号が正しいか確認
- ファイアウォールがブロックしていないか確認
- 「送受信」ボタンを手動でクリックしてみる
会社のメールの場合は、IT部門に設定を確認してもらいましょう。
検索機能が使えない
Outlook内の検索が機能しない場合です。
解決方法
- Windows検索のインデックスを再構築
- 「コントロールパネル」→「インデックスのオプション」を開く
- 「変更」ボタンをクリック
- Outlookにチェックが入っているか確認
- 「詳細設定」→「再構築」で再構築
インデックスの再構築には数時間かかる場合があります。
古いプロファイルのデータが必要になった
削除した古いプロファイルの設定が必要になった場合です。
残念ながら、削除したプロファイルの設定は復元できません。
ただし、PSTファイルは残っているので、メールデータ自体は問題ありません。
まとめ
Outlookのプロファイル再作成は、様々な問題を解決する効果的な方法です。
重要なポイント
- プロファイル再作成は設定をリセットする作業
- メールデータ(PSTファイル)は削除されない
- 事前にアカウント情報、署名、仕分けルールをバックアップ
- コントロールパネルの「Mail」から操作する
- 古いプロファイルを削除→新しいプロファイルを作成
- 既存のPSTファイルを再接続すれば過去のメールも見られる
- 署名や仕分けルールは再設定が必要
作業の流れ
- 事前準備(情報確認・バックアップ)
- Outlookを完全終了
- 古いプロファイルを削除
- 新しいプロファイルを作成
- メールアカウントを設定
- 既存のデータファイルを接続
- 署名・仕分けルールを復元
- 動作確認
最初は大変に感じるかもしれませんが、手順通りに進めれば誰でもできます。
プロファイル再作成で、Outlookが見違えるほど快適に動くようになることも多いんです。
Outlookの調子が悪い時は、ぜひこの方法を試してみてください。
不安な場合は、会社のIT部門やパソコンに詳しい人に相談しながら作業することをおすすめします!







