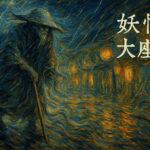夜道を歩いていて、ふと空を見上げたら、巨大な女性の首が浮かんでいた…。
そんな恐ろしい体験をした人が、江戸時代には実際に何人もいたというのです。
お歯黒をつけた大きな顔がにこにこと笑いかけてくる様子は、想像するだけでも背筋が凍りますよね。
この記事では、江戸時代の人々を震え上がらせた妖怪「大首」について、その不気味な姿や恐ろしい伝承を詳しくご紹介します。
大首ってどんな妖怪なの?

大首(おおくび)は、空中や古城などに巨大な女性の生首が現れるという日本の妖怪です。
江戸時代の絵師・鳥山石燕が描いた妖怪画集『今昔画図続百鬼』に登場することで広く知られるようになりました。
石燕の解説文には「大凡物の大なるもの皆おそるべし。いはんや雨夜の星明かりに鉄漿をくろくつけたる女の首おそろし」とあり、雨の夜に現れる巨大な顔の恐ろしさが強調されています。
姿・見た目
大首の外見には、はっきりとした特徴があるんです。
大首の外見的特徴
- 大きさ:約3メートル(一丈)前後の巨大な顔
- 性別:ほとんどが女性
- お歯黒:既婚女性の証として黒々としたお歯黒をつけている
- 髪:すだれのように長く垂れ下がっている
- 表情:にこにこ、にやにやと不気味に笑いかける
特に印象的なのが、真っ黒なお歯黒なんです。江戸時代、お歯黒は既婚女性がするものだったので、大首は既婚女性の首だと考えられていました。
文献によって大きさには多少のばらつきがありますが、だいたい1.8メートルから3メートルほど。人間の身長をはるかに超える巨大な顔が空中に浮かんでいる様子は、まさに悪夢のような光景だったでしょう。
特徴
大首には、他の妖怪とは違う独特の特徴があります。
大首の行動パターン
- 出現場所:古城の跡、夜道、塀の上など
- 出現時間:夜、特に雨上がりの夜が多い
- 行動:じっと人を見つめながら笑いかける
- 害:息を吹きかけられると黄色く腫れて体調が悪くなる
大首は基本的に人を襲ったりはしませんが、その存在自体が恐怖なんですね。ただし、金沢での事例では、大首の息を吹きかけられた人が黄色く腫れて具合が悪くなり、医者の薬湯で治療したという記録もあります。
正体
大首の正体については、いくつかの説があるんです。
考えられる正体
- 人間の怨霊や執念:恨みを持って死んだ女性の霊が妖怪化したもの
- 動物の化身:キツネやタヌキが化けたもの
- 超常現象:原因不明の怪異現象
特に『近世怪談霜夜星』という読本では、策略に陥れられて命を絶った女性の怨霊が、鎌倉の地で巨大な大首となって現れた様子が描かれています。
伝承

大首にまつわる伝承は、江戸時代の怪談集や随筆に数多く残されています。
山口県岩国の恐怖体験
最も有名なのが、山口県岩国に伝わる『岩邑怪談録』の「古城の化物の事」という話です。
御城山での出来事
上口という土地に住む、ある家の下働きの女性がいました。彼女は毎朝、御城山という古城跡でワラビ取りをするのが日課だったんです。
ある朝、いつものように御城山に登ったときのこと。
どこからともなく、約3メートルもある巨大な女の首が現れました。その首は古城の台の上から女性を見下ろし、にやにやと笑いかけてきたのです。
女性は恐怖のあまり、転がるようにして山を下り、以後二度とその山には近づかなかったといいます。
この話から分かるのは、大首は特定の場所(古城跡など)に出現する傾向があるということです。
金沢の雷と大首
江戸時代の俳人・堀麦水による奇談集『三州奇談』には、金沢での不思議な体験が記されています。
雨上がりの夜の恐怖
雨上がりの夜、月が顔を出し始めた頃のことでした。
突然、雷鳴とともに6〜7尺(約1.8〜2メートル)の大首が現れたというのです。
ある時には塀の上に大きな首が乗っていたこともあったそうで、その不気味さは想像に難くありません。
さらに恐ろしいのは、この大首に息を吹きかけられた人の話です。息をかけられた場所が黄色く腫れ上がり、具合が悪くなってしまったとか。医者に診てもらい、薬湯を処方されてようやく治ったといいます。
稲生平太郎と物置の大首
『稲生物怪録』という妖怪物語を描いた絵巻には、「大首の怪」として次のような話が記されています。
勇敢な若武者の対応
主人公の稲生平太郎が物置の戸を開けると、なんと巨大な老婆の顔が出現したのです。
普通なら逃げ出すところですが、平太郎は勇敢にも火箸でその顔を突いてみました。
ところが、大首は少しも動じることなく、ねばねばとした不思議な感触だったといいます。
この話から、大首は物理的な攻撃では退治できない存在だということが分かりますね。
平安時代の「面女」
実は、大首のような妖怪は江戸時代よりもずっと前から存在していたんです。
平安時代には「面女(つらおんな)」と呼ばれる、巨大な女の首の妖怪が出現したという記録があります。
恋川春町の黄表紙『妖怪仕打評判記』によると、平清盛が福原に遷都した夜にも、この面女が現れたとされています。
つまり、巨大な女の首という恐怖は、平安時代から脈々と受け継がれてきた日本独特の妖怪観なんですね。
まとめ

大首は、江戸時代の人々を恐怖に陥れた代表的な妖怪の一つです。
重要なポイント
- 空中に浮かぶ約3メートルの巨大な女性の生首
- お歯黒をつけた既婚女性の姿が特徴的
- 雨の夜や古城跡に現れることが多い
- にこにこと不気味に笑いかける恐ろしい存在
- 人間の怨霊やキツネ・タヌキの化身とされる
- 山口県岩国や金沢など各地に目撃談がある
- 平安時代から続く日本独特の妖怪伝承
鳥山石燕が描いた大首の絵は、現代でも日本の妖怪文化を代表するイメージとして親しまれています。
もし夜道で空を見上げたとき、巨大な顔が浮かんでいたら…。それは数百年前から語り継がれてきた「大首」かもしれませんね。