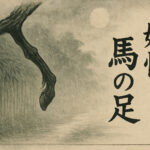大切に飼っていた馬を、ある日突然粗末に扱ってしまった…そんなとき、あなたはどうなると思いますか?
江戸時代の日本では、馬を虐待したり殺したりした人が、死んだ馬の霊に取り憑かれて苦しむという恐ろしい怪異が信じられていました。
取り憑かれた人は、まるで馬のように振る舞い、最後には精神に異常をきたして死んでしまうというのです。
この記事では、死んだ馬の復讐を描いた日本の怪異「馬憑き」について詳しくご紹介します。
馬憑きってどんな怪異なの?
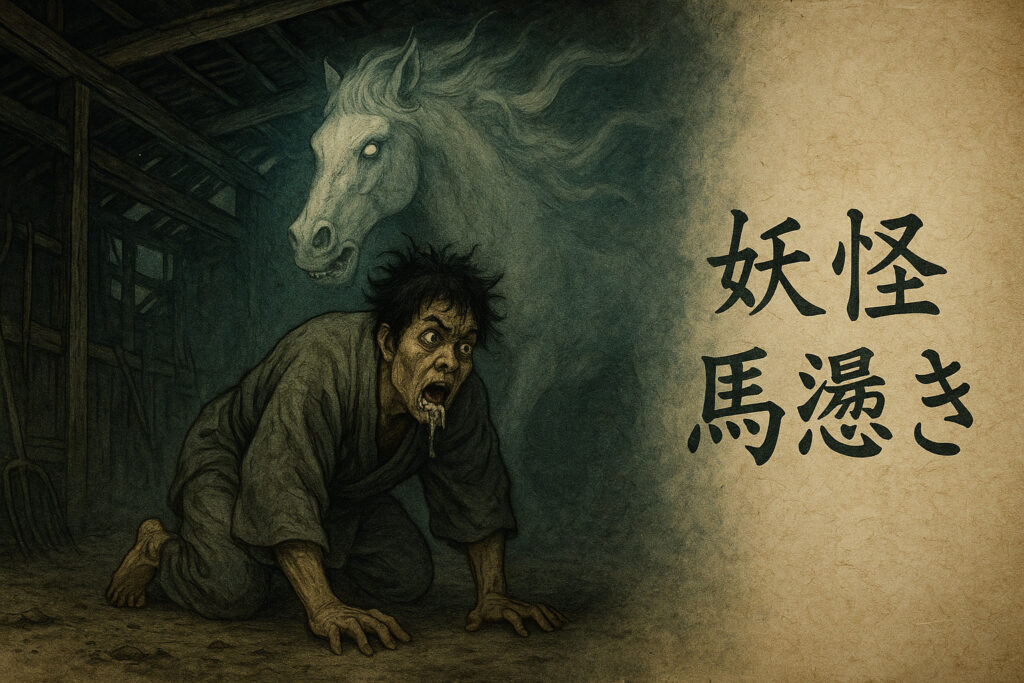
馬憑き(うまつき)は、死んだ馬の霊が人間に取り憑いて苦しめるという日本の怪異です。
江戸時代の仏教説話集『因果物語』や随筆『新著聞集』、明治時代の民俗学者・早川孝太郎の著書『三州横山話』など、多くの文献に記録が残っています。
馬憑きの基本的なパターンは明確で、馬を粗末に扱ったり虐待したりした人が、馬の霊に取り憑かれるというものなんです。
取り憑かれた人の症状は、とても特徴的です。
馬憑きの症状
- 突然、馬のように嘶く(いななく)ようになる
- 馬屋に入り込んで馬のような行動をとる
- 桶から雑水(馬用の水)を飲み干す
- 目をむいて馬のような表情をする
- 最終的には精神に異常をきたして死ぬ
妖怪研究家の多田克己氏によると、仏教国である日本では、獣を殺したり獣肉を食べることは五戒(仏教の基本的な戒律)に触れる行為とされていました。
殺生を行った者は地獄に堕ちるという俗信が、馬憑きのような憑き物伝承の背景にあると考えられているんですね。
伝承

40年後の復讐:太郎助の話(『因果物語』より)
三州中村(現在の愛知県田原市赤羽根)に、太郎助という男がいました。
若い頃、馬同士の争いを止めようとして、誤って馬を殺してしまったことがありました。その時は特に何も起こらなかったのですが…。
40年以上も経った後、40歳代半ばになった太郎助に異変が起きます。
突然、馬屋に入って馬のように鳴き始め、雑水を飲み干し、そのまま死んでしまったというんです。
この話で恐ろしいのは、何十年も経ってから突然、馬の霊が復讐に来たという点ですね。
法師の受けた報い(『因果物語』より)
同じく三州の江村という地に、受泉という法師が住んでいました。
若い頃、馬工郎(馬を扱う仕事)として働いていた受泉は、寛永16年(1639年)の春から突然、おかしな行動を始めたんです。
受泉の異常行動
- 目をむいて嘶く
- 桶から雑水を飲む
- まるで馬そのもののような挙動
周囲の人々は最初、悪ふざけだろうと思っていました。しかし、その動きは本当に馬そのもので、とても演技でできるようなものではありませんでした。
心配して見守る人々の前で、受泉はまもなく死んでしまいます。周囲の人々は、法師でありながら若い頃の仕事の行いが悪かったため、生きながら畜生道(地獄の一つ)へ堕ちたのだと噂したそうです。
殿様の虐待と馬屋の者の死(『新著聞集』より)
阿波国(現在の徳島県)の国主・松平阿波守が、飼い馬をひどく虐待したところ、馬は病気で死んでしまいました。
すると間もなく、馬屋で働いていた者に異変が起きます。
その者は叫び始めました:
「殿様は馬を十分に飼い馴らすまで乗らないと言っていたのに、俺を偽り、責め立てて殺してしまった。この怨みはいつか晴らす。思い知れ!」
この馬屋の者は、まるで死んだ馬の霊が乗り移ったかのように訴え続け、精神に異常を来たしたまま死んでしまったというんです。
ここで興味深いのは、虐待した本人ではなく、馬屋の者に憑いたという点ですね。
父の業を受けた息子(『新著聞集』より)
武蔵国八王子(現在の東京都八王子市)の原半左衛門という人物は、馬に焼印を押すことを非常に好んでいました。
ある年の元旦、彼の息子・灌太郎が従者と共に神社へ参拝に出かけたところ、鳥居の前で奇妙なことを言い始めます。
「なんと馬の血が多い場所だ。祠の前まで血だらけで足の踏み場もない。参拝どころではないので帰ろう」
従者の目には何も見えないのに、灌太郎には馬の血の海が見えているというんです。結局、鳥居の外で参拝を済ませて帰りました。
その日から灌太郎は病に侵され、馬の鳴き真似をするようになります。7日後に正気に戻った灌太郎は言いました。
「父が馬を苦しめ続けた報いで畜生道に堕ちる羽目になった、無念だ」
その後、再び悶え苦しみ始め、遂に死んでしまったそうです。
この話では、父親が行った虐待の報いを、息子が受けるという形になっているのが特徴的ですね。
馬肉を食べ続けた長者の末路:塩の長司(『絵本百物語』より)
加賀国(現在の石川県)に、塩の長司(しおのちょうじ)という長者がいました。
彼は自宅に300頭もの馬を飼っていましたが、常々悪食を好み、死んだ馬の肉を味噌漬けや塩漬けにして、毎日のように食べていたんです。
ある日、馬肉が尽きると、長司は役に立たなくなった老馬を打ち殺して食べてしまいました。
その夜の出来事
長司の夢の中に、殺された老馬が現れて、長司の喉に食いついたのです。
それ以降、長司が老馬を殺した時刻になると、老馬の霊が現れて口の中に入り込み、腹の中を荒らし回るようになりました。
その苦痛は相当なもので、長司は苦し紛れに悪口雑言を吐き、自分が今まで犯した悪事やありとあらゆる戯言を叫び続けました。
医療や祈祷など様々な手段を試みましたが、一向に効果はありません。
百日ほど経って遂に死んでしまい、その死に様は、まるで重い荷物を背負った馬のような姿だったといいます。
馬の報せに反応する男(『三州横山話』より)
遠江国(現在の静岡県西部)にハヤセの梅という男がいました。
彼は馬に憑かれて精神に異常を来たして以来、三河国(現在の愛知県東部)に住み始めました。
50歳ほどで常に口から涎を垂らしており、馬の死の報せを聞くと、きまって自分の腕に食らいつき、その報せを追いかけたというんです。
そのために彼の腕は常に赤く腫れ上がっていたそうです。
この話は、馬憑きの長期的な影響を示す珍しい事例ですね。
祖母の罪を孫娘が償う(『耳嚢』より)
播磨国姫路藩中(現在の兵庫県姫路市)の村田弥左衛門には、16、7歳になる娘がいました。
ある日、娘が乱心したように何かに恨みがあるような発言をし始めます。加持祈祷をしても効果がありません。
父親が「狐狸の類か?」と尋ねると、娘は否定して言いました。
「娘の祖母が私を情けなく殺した恨みから家を祟るのだ。娘を殺し、血筋を絶やす」
話を聞くと、この家に飼われていた馬が老いて役立たずになったため、祖母の命令で天狗谷という場所に捨てられ、餓死してしまったというのです。
憑いた馬の霊は訴えました:
「役立つ時は愛したのに、役立たなくなった途端にこのような不仁をする」
その後、追善供養を行ったところ、娘の病気は治ったそうです。
この話では供養によって救われるという、比較的救いのある結末になっているのが特徴的です。
まとめ
馬憑きは、動物への残酷な仕打ちに対する報いを描いた、教訓的な怪異です。
重要なポイント
- 死んだ馬の霊が人間に取り憑く日本の怪異
- 馬を虐待・殺害した者やその親族に起こる
- 取り憑かれると馬のように振る舞うようになる
- 最終的には精神に異常をきたして死ぬ
- 仏教の「殺生の報い」という教えが背景にある
- 何十年も経ってから症状が現れることもある
- 追善供養で救われる場合もある
馬は古来より日本人にとって、農耕や運搬、戦での重要なパートナーでした。
そんな大切な動物を粗末に扱うことへの戒めとして、馬憑きの伝承は語り継がれてきたんですね。
現代では馬を飼う機会は少なくなりましたが、この伝承に込められた「生き物を大切にする」という教えは、今も変わらず大切なものだと言えるでしょう。