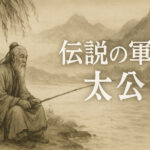海から引き上げられた、長い首を持つ不思議な生物の死骸。
その姿は、まるで絶滅したはずの古代生物のようでした。
1977年、日本の漁船が偶然発見したこの謎の死骸は、日本中を巻き込む大騒動へと発展していったのです。
この記事では、「ニューネッシー」と名付けられた謎の生物について、発見の経緯から科学的調査の結果まで詳しくご紹介します。
概要

ニューネッシーとは、1977年4月25日に日本のトロール漁船「瑞洋丸」がニュージーランド沖で引き上げた、巨大な腐乱死体のことです。
トロール漁船というのは、大きな網を海中に引いて魚を捕る漁船のこと。瑞洋丸は大洋漁業が所有する2460トンの大型船で、87名の乗組員が乗っていました。
発見場所は、ニュージーランドのクライストチャーチから東へ約50キロ離れた太平洋上でした。
長い首のような部分を持つ姿が、スコットランドのネス湖に棲むと言われる怪獣「ネッシー」に似ていたことから、「ニュー・ネッシー」と名付けられました。この「ニュー」は、発見場所のニュージーランドにもかけているんですね。
日本に帰港後、約3か月後の7月20日(海の記念日)に大々的に報道され、日本中が未知の生物発見に沸き立ちました。
姿・見た目
ニューネッシーの姿は、とにかく奇妙で印象的なものでした。
基本データ
- 全長:約10メートル
- 重量:約1,800キログラム(1.8トン)
- 首の長さ:約1.5メートル
- 尾の長さ:約2.0メートル
外見の特徴としては、長い首のような部分、四つの大きな赤みがかったヒレ、そして長い尾が確認されました。
背びれは一見すると無いように見えましたが、後に写真を詳しく調べると、実は存在していたことが分かりました。
死骸はすでに腐敗が進んでおり、胸の部分や内臓は腐って開いていました。しかし、肉や脂肪の部分はまだある程度残っていたそうです。
何より特徴的だったのは、その激しい腐敗臭でした。乗組員たちは口々に「あの臭いは、どんな魚のものとも違っていた」と証言しています。
特徴

ニューネッシーをめぐる出来事には、いくつかの重要な特徴があります。
保存できなかった理由
瑞洋丸は商業漁船であり、調査船ではありませんでした。そのため、このような巨大な腐敗物を保存する設備がなかったんです。
さらに、死骸から発せられる激しい腐臭が船内に広がり、貴重な漁獲物を台無しにする恐れがありました。船長の田中明氏は苦渋の決断として、死骸を再び海に投棄することを決めました。
残された貴重な証拠
しかし、幸運なことに、臨時の栄養管理士として乗船していた矢野道彦氏がこの発見の重要性に気づきました。
矢野氏が残した記録
- 死骸の写真を5枚撮影
- ヒレに付着していた繊維質の「ヒゲ」のようなものを約40本採取
- 死骸の大きさや形状を計測・記録
これらの証拠は、後の科学的調査で非常に重要な役割を果たすことになります。
発見からわずか1時間後、謎の巨大生物は再び海の中へと消えていきました。その後、大洋漁業は全船に対して死骸の再発見を命じましたが、残念ながら成功しませんでした。
伝承
ニューネッシーの発見は、日本社会に大きな影響を与えました。
報道と社会現象
1977年7月20日、大洋漁業が記者会見を開き、ニュージーランド沖での怪事件を公表しました。
公開された写真には、クレーンで吊り上げられた奇妙な形の死骸が写っており、これが全国のマスコミで大々的に報じられました。
その姿が絶滅したはずの首長竜「プレシオサウルス」の復元想像図に似ていたことから、「もしかして古代生物の生き残りでは?」という期待が膨らみました。
首長竜説の盛り上がり
一部の専門家たちも、首長竜である可能性を示唆しました。
横浜国立大学の志賀徳夫教授は「プレシオサウルスの遺体である」と確信し、東京水産大学の安田富士郎博士も「写真は先史時代の動物の遺体を示している」と述べたのです。
この「未知の生物発見」というニュースは、日本中を「プレシオサウルス・ブーム」とも呼べる熱狂の渦に巻き込みました。
しかし、より慎重な科学者たちは懐疑的でした。スウェーデンの古生物学者ハンス・クリスチャン・ビエリング博士は「プレシオサウルスだという主張には疑問を持つべきだ」と指摘しています。
起源
科学的な調査の結果、ニューネッシーの正体はほぼ解明されました。
科学的調査の実施
矢野氏が持ち帰った写真とサンプルをもとに、複数の研究機関が調査を行いました。
調査に参加した主な研究者
- 東京水産大学:佐々木忠義氏、木村茂氏
- 国立科学博物館:小畠郁生氏、尾崎博氏
- 東京大学海洋研究所:粕谷俊雄氏
1978年8月、佐々木・木村グループは調査報告書「瑞洋丸に収容された未確認動物について」を発表しました。
ウバザメ説の根拠
調査の結果、正体はウバザメの腐乱死体である可能性が最も高いと結論付けられました。
その根拠は以下の通りです。
アミノ酸分析の結果
保存された繊維組織を化学分析したところ、1000個のアミノ酸のうち40個のチロシンが含まれていることが判明しました。
生物は種類ごとに特有の「アミノ酸指数」を持っています。ニューネッシーのアミノ酸指数は113で、軟骨魚類(サメの仲間)の116に極めて近い数値だったのです。
参考までに、他の動物のアミノ酸指数は、硬骨魚類が97、爬虫類が62、鳥類が46となっています。
コラーゲン分析による確証
さらに決定的だったのが、コラーゲン(体を構成するタンパク質)の分析です。
ニューネッシーのヒゲから採取したコラーゲンをモルモットに投与する実験を行ったところ、モルモットはウバザメのコラーゲンに対して免疫反応を示しました。これは、ニューネッシーがウバザメである強力な証拠となりました。
ウバザメの腐敗パターン
ウバザメは軟骨魚類で、腐敗が進むと特徴的な変化が起こります。
腐敗による変化
- 下あごが最初に脱落
- エラの部分が崩れ落ちる
- 背びれと尾びれが取れる
- 残った部分が首長竜のような姿に見える
実際、サメを扱う業者は写真と骨格から「これはウバザメだ」と断言しており、実際のサメで首長竜のような形態になることを再現することにも成功しています。
さらに、ニューネッシーが引き上げられた海域は、ウバザメの生息域と重なっていることも確認されました。
首長竜説が否定される理由
一部の研究者は首長竜説を唱え続けましたが、いくつかの問題点があります。
首長竜には、首が長く頭の小さい「プレシオサウルス類」と、首が短く頭が大きい「プリオサウルス類」の二系統があります。
しかし、ニューネッシーの体の比率(全長10メートルに対して首の長さ1.5メートル)は、どちらの首長竜とも合致しないのです。
プレシオサウルス類は首の長さが全長の半分近くを占めるため、ニューネッシーの首は短すぎます。逆にプリオサウルス類の場合、頭部が2メートル前後と非常に大きいのですが、ニューネッシーの頭部は約50センチしかありません。
また、「骨が正方形の硬いブロック状だった」という証言も、矢野氏本人が「海に捨てた後で、踏んだ感触を思い出して描いたもの」と述べており、直接確認したわけではないことが分かっています。
まとめ
ニューネッシーは、1977年の日本を熱狂させた海洋ミステリーです。
重要なポイント
- 1977年4月25日、日本の漁船「瑞洋丸」がニュージーランド沖で発見
- 全長約10メートル、重量1.8トンの巨大な腐乱死体
- 長い首とヒレを持ち、首長竜に似た姿から「ニューネッシー」と命名
- 激しい腐臭のため1時間後に海へ投棄されたが、写真とサンプルが残された
- 日本で大きな社会現象となり、古代生物発見への期待が高まった
- 科学的調査の結果、ウバザメの腐乱死体である可能性が最も高いと判明
- アミノ酸分析とコラーゲン分析がウバザメ説を裏付けている
未知の生物への憧れと科学的検証のはざまで、ニューネッシーは今も人々の記憶に残る興味深い事例となっています。もし瑞洋丸が調査船だったら、あるいは死骸を持ち帰ることができていたら、もっと多くのことが分かったかもしれませんね。