夜中の森の奥深くで、黒い石を囲んで人々が狂ったように踊り狂う光景を想像してみてください。
そこには、涎を垂らしながらクスクスと笑う巨大な怪物が鎮座しています。
これが、ハンガリーやユカタンの地で恐れられた暗黒の神「ゴル=ゴロス」なんです。
この記事では、クトゥルフ神話に登場する恐ろしい旧支配者「ゴル=ゴロス」について、その異形の姿や特徴、残忍な崇拝の実態を詳しくご紹介します。
概要

ゴル=ゴロスは、クトゥルフ神話に登場する旧支配者の一柱です。
旧支配者というのは、人類が誕生する遥か昔から存在する超自然的な神々のことで、ゴル=ゴロスはその中でも特に不気味な存在として知られています。
別名を「忘れ去られた古のもの」「黒い石の主」「狂宴の王」といい、ハンガリーの山間部やメキシコのユカタン半島など、世界各地で崇拝されてきました。
特にハンガリーでは「魔女の村」と呼ばれる集落で、黒い石柱を神体として祀られ、残酷な儀式の対象となっていたんです。
地下深くの神殿か、地球外の宮殿に住んでいるとされ、めったに姿を現すことはありません。しかし、その存在が知られているだけで、人々は恐怖に震えたといいます。
系譜
ゴル=ゴロスの誕生には、ちょっと複雑な歴史があります。
創造者と神話への組み込み
この神を最初に生み出したのは、アメリカの小説家ロバート・E・ハワード(1906-1936年)です。
彼は1931年に発表した『バル=サゴスの神々』という短編小説の中で、大西洋上の古代王国バル=サゴスで崇められる神々の主神として、ゴル=ゴロスを登場させました。
その後、別の作家リン・カーターが、この神をクトゥルフ神話の世界観に正式に組み込んだんですね。
クトゥルフ神話というのは、アメリカの作家H・P・ラヴクラフトが作り出した恐怖小説の世界観で、多くの作家たちが設定を共有して作品を書いています。ゴル=ゴロスも、そうして神話の一部となったわけです。
グロス=ゴルカとの混同
実は、ゴル=ゴロスにはグロス=ゴルカという別の神との混同がありました。
グロス=ゴルカは怪鳥の姿をした「鳥の神」で、『バル=サゴスの神々』の中で主人公たちに退治されています。
リン・カーターが最初に書いた作品では、鳥の神を「ゴル=ゴロス」と誤って書いてしまったことがあったんです。後に研究家のロバート・M・プライスが、これはカーターの間違いだったと指摘し、修正されました。
関連する存在
- ムノムクア:カーターの設定では兄弟とされる
- クームヤーガ:シャンタク鳥の長で、ゴル=ゴロスに従う眷属
- 大地の妖蛆:世界各地でゴル=ゴロスを信仰する半人間の集団
姿・見た目
ゴル=ゴロスの姿は、見る者すべてを恐怖に陥れる異形そのものなんです。
基本的な外見
ゴル=ゴロスの身体的特徴
- 全体像:巨大なヒキガエル(蟾蜍)のような体
- 皮膚:ぬるぬるとした鱗に覆われている
- 口:牙が生えた大きな口
- 涎:常にだらしなく涎を垂らしている
- 表情:クスクスと卑しく笑い続けている
この基本的な姿だけでも十分に不気味なのですが、さらに奇妙な特徴があります。
異形の四肢
普通のヒキガエルとは決定的に違う点があるんです。
- 後ろ足:蛙の足ではなく、蹄(ひづめ)になっている
- 前足:腕がなく、代わりに何本もの触手が首や肩から不気味に垂れ下がっている
つまり、カエルのような体に、馬のような蹄と、タコのような触手を持った、まさに悪夢のような合成獣なんですね。
移動方法
その異様な体で、ゴル=ゴロスは這うようにして移動します。
短い距離であれば直立して歩くこともできるそうですが、基本的には地面を這って進むんです。その巨体が地面を這う様子は、想像するだけでもぞっとしますね。
特徴
ゴル=ゴロスの恐ろしさは、その姿だけではありません。崇拝の方法が極めて残忍で狂気に満ちているんです。
黒い石と崇拝
ゴル=ゴロスは黒い石柱と深く結びついています。
ハンガリーの山間部にあった「魔女の村」(ズトゥルタン村)では、碑文が刻まれた黒い角形の石柱が立っていました。この石柱の上に、ゴル=ゴロスが鎮座していたと伝えられています。
興味深いことに、似たような碑文が刻まれた黒い石が、遠く離れた中米ユカタン半島やホンジュラスの遺跡でも発見されているんです。これは、ゴル=ゴロス信仰が世界規模で広がっていた証拠かもしれません。
狂気の儀式
ゴル=ゴロスへの崇拝儀式は、まさに狂気そのものでした。
儀式の内容
- 司祭:人間と獣の要素を兼ね備えた異形の者が務める
- 踊り:原始的で荒々しいリズムで狂ったように踊る
- 鞭打ち:司祭が小枝の束で自らの体を残忍に打つ
- 詠唱:名状しがたい言葉と、ゴル=ゴロスの名を反芻する
- 動き:およそ人間の動きとは思えない激しい身振り
参加者たちは腕を激しく振り回しながら、黒い石を囲んで狂乱の踊りを続けたといいます。
生贄の儀式
最も恐ろしいのは、若い娘を生贄に捧げる儀式でした。
暴力と性の陶酔の中で行われるこの儀式は、まさに狂宴と呼ぶにふさわしいものです。だからこそ、ゴル=ゴロスは「狂宴の王」という別名を持っているんですね。
住処
ゴル=ゴロスは、普段は人間の目に触れることのない場所に潜んでいます。
- 地下深くの神殿:黒い石柱は地下深くまで続く巨大な建造物の一部だという説がある
- 地球外の宮殿:別の世界や次元に住んでいるともいわれる
黒い石は、異界への扉の鍵であり、ゴル=ゴロスはその扉の向こうからやってきた存在なのかもしれません。
伝承
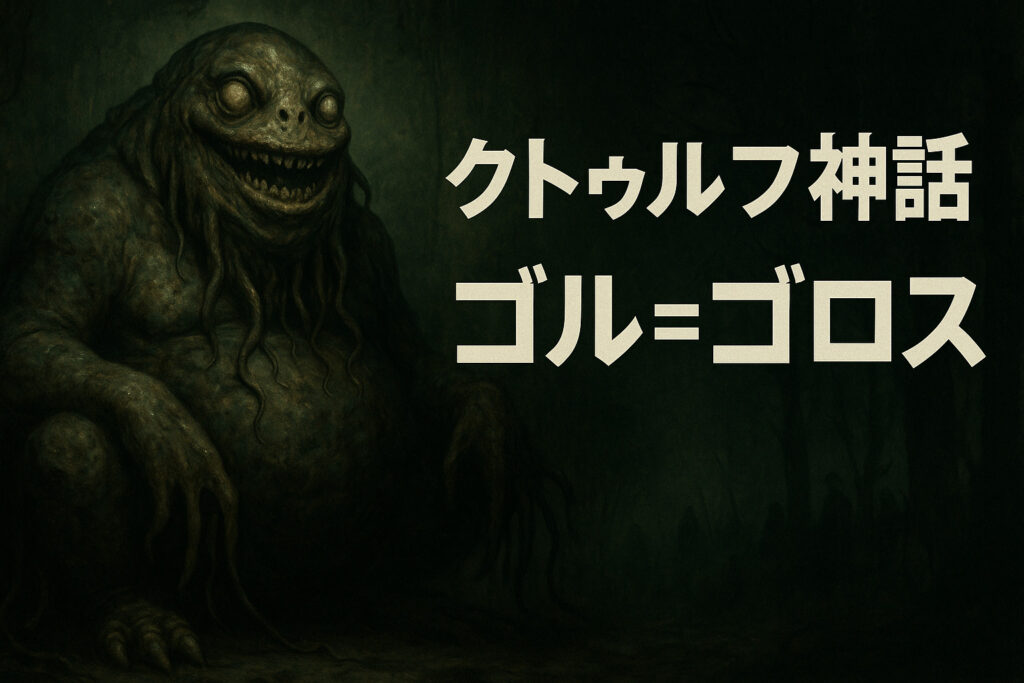
ゴル=ゴロスにまつわる伝承は、恐怖と狂気に満ちています。
ハンガリー「魔女の村」の伝説
最も有名なのが、ハンガリーの山間部にあったズトゥルタン村の伝説です。
この村は「魔女の村」として知られ、住民たちはゴル=ゴロスを崇拝する異端の集団でした。彼らは半人間とも呼ばれる異形の者たちで、黒い石柱を中心に忌まわしい儀式を繰り返していたんです。
村人たちは夜ごと、黒い石の周りで狂乱の踊りを踊り、若い娘を次々と生贄に捧げました。その残虐な儀式の様子は、後に詩人ジャスティン・ジョフリの詩の中で暗示されています。
トルコ軍による退治
この恐ろしい崇拝に終止符を打ったのが、16世紀のトルコ軍でした。
ハンガリーを侵攻したトルコ軍が、たまたまこの村を発見したんです。そして、ゴル=ゴロスの異様な姿を目撃した彼らは、イスラムの聖剣と太古の呪文を使って、この神を退治したと伝えられています。
崇拝者たちも消え去り、今では影も形もありません。しかし、黒い石柱だけは今でも丘の上に立ち、不気味な威容を誇っているそうです。
『バル=サゴスの神々』での登場
作家ロバート・E・ハワードの短編小説『バル=サゴスの神々』では、ゴル=ゴロスは少し異なる形で登場します。
この物語では、大西洋上の古代王国バル=サゴスで崇められる神々の主神として描かれているんです。ただし、作中では石像のみが登場し、その姿は明らかにされていません。
主人公の戦士ターロウ・オブライエンが冒険する中で、ゴル=ゴロスの神殿や神像が重要な役割を果たします。
世界各地の痕跡
興味深いことに、ゴル=ゴロス崇拝の痕跡は世界中に散らばっています。
- ハンガリー:ズトゥルタン村の黒い石柱
- ユカタン半島(メキシコ):似た碑文を持つ巨岩
- ホンジュラス:「蟇の神殿」と呼ばれる遺跡
これらの遺跡に刻まれた記号や文字が似ていることから、古代の先住民族の間で、ゴル=ゴロス信仰が広く行われていた可能性があります。
文学作品での言及
ゴル=ゴロスは、いくつかの文学作品で言及されています。
- 『黒の碑』(ロバート・E・ハワード):ハンガリーでの崇拝が詳しく描かれる
- 『屋根の上に』(ロバート・E・ハワード):ホンジュラスの神殿が舞台
- 『夜の末裔』(ロバート・E・ハワード):ゴル=ゴロスへの言及がある
詩人ジャスティン・ジョフリの詩の中にも、ゴル=ゴロスへの暗示が含まれているとされています。
出典
本記事は以下の文献を参考にしています。
- 『暗黒神伝』第1章「ゴル=ゴロス」
- ロバート・E・ハワード『黒の碑』(1931年)
- ロバート・E・ハワード『バル=サゴスの神々』(1931年)
- リン・カーター『深淵への降下』(『エイボンの書』収録)
- ロバート・M・プライスによる研究および解説
- クトゥルフ神話TRPG『マレウス・モンストロルム』
まとめ
ゴル=ゴロスは、狂気と恐怖を象徴する暗黒の神です。
重要なポイント
- クトゥルフ神話の旧支配者の一柱で、別名「狂宴の王」
- 巨大なヒキガエルのような姿に蹄と触手を持つ異形の存在
- 常に涎を垂らしクスクスと笑う不気味な神格
- 黒い石柱を神体として世界各地で崇拝された
- 狂乱の踊りと生贄の儀式で知られる残忍な信仰
- 16世紀にトルコ軍によって退治されたとされる
- ロバート・E・ハワード創造、リン・カーターがクトゥルフ神話に組み込んだ
今でもどこかの地下深くで、黒い石の傍らに潜んでいるかもしれないゴル=ゴロス。その狂気の残響は、古代の遺跡に刻まれた碑文の中に、今も静かに息づいているのです。







