病気で苦しんでいるとき、あなたは誰に助けを求めますか?
平安時代の人々は、ある特別な仏様に祈りを捧げました。
それが「薬師如来(やくしにょらい)」です。左手に薬壺を持ち、万病を治してくれるという医療の専門家のような仏様として、古くから人々の信仰を集めてきました。
この記事では、現世の苦しみから救ってくれる慈悲深い仏「薬師如来」について、その姿や十二の大願、そして日本での信仰の歴史を詳しくご紹介します。
概要
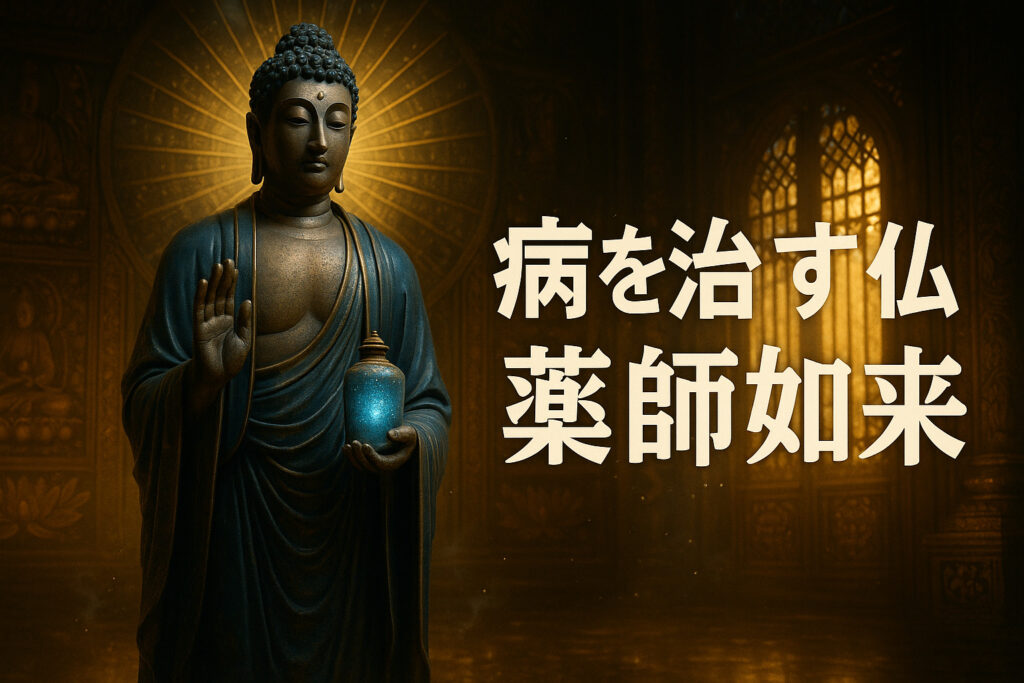
薬師如来は、大乗仏教における東方浄瑠璃世界(とうほうじょうるりせかい)の教主です。
サンスクリット語では「バイシャジヤグル」と呼ばれ、正式名称は「薬師瑠璃光如来(やくしるりこうにょらい)」といいます。
「薬師」という名前が示す通り、この仏様は医療や薬の専門家なんです。病気を治し、人々の寿命を延ばすことを誓った、まさに「仏界の名医」として知られています。
別名として「大医王仏(だいいおうぶつ)」や「医王善逝(いおうぜんぜい)」とも呼ばれますが、どちらも「名医中の名医」という意味を持つんですね。
西方と東方の仏様
阿弥陀如来が西方極楽浄土の主であるのに対し、薬師如来は東方浄瑠璃世界の主です。東方には七つの仏国土が並んでおり、最も遠い場所に薬師如来の世界があるとされています。
瑠璃(るり)という宝石で青く澄み切った、最も清らかで不浄なものがない静寂な世界だといわれているんです。
姿・見た目
薬師如来の像は、一般的な如来と同じような姿をしていますが、はっきりとした特徴があります。
薬師如来像の特徴
- 右手:施無畏印(せむいいん)を結ぶ(恐れを取り除く手の形)
- 左手:薬壺(やっこ)を持つ、または与願印を結ぶ
- 姿勢:坐像(座っている)と立像(立っている)の両方がある
- 服装:三衣(さんえ)という仏教僧の衣をまとう
左手に持つ薬壺には、あらゆる病を治す霊薬が入っているとされています。ただし、奈良時代の古い像には薬壺を持たないものもあるんです。これは、薬壺を持つ像が造られるようになったのは、後の時代からだと考えられています。
脇侍と眷属
薬師如来は、単独で祀られることもありますが、多くの場合は両脇に日光菩薩(にっこうぼさつ)と月光菩薩(がっこうぼさつ)を従えた三尊像として安置されます。
- 日光菩薩:日輪(太陽)を戴いた蓮華を持ち、昼を担当
- 月光菩薩:月輪(三日月)を乗せた蓮華を持ち、夜を担当
この二人が従うことで、薬師如来が昼夜を問わず24時間体制で人々を守護することを示しているんですね。
また、十二神将(じゅうにしんしょう)という十二体の武神を眷属(けんぞく、従者のこと)とすることも多いです。
特徴
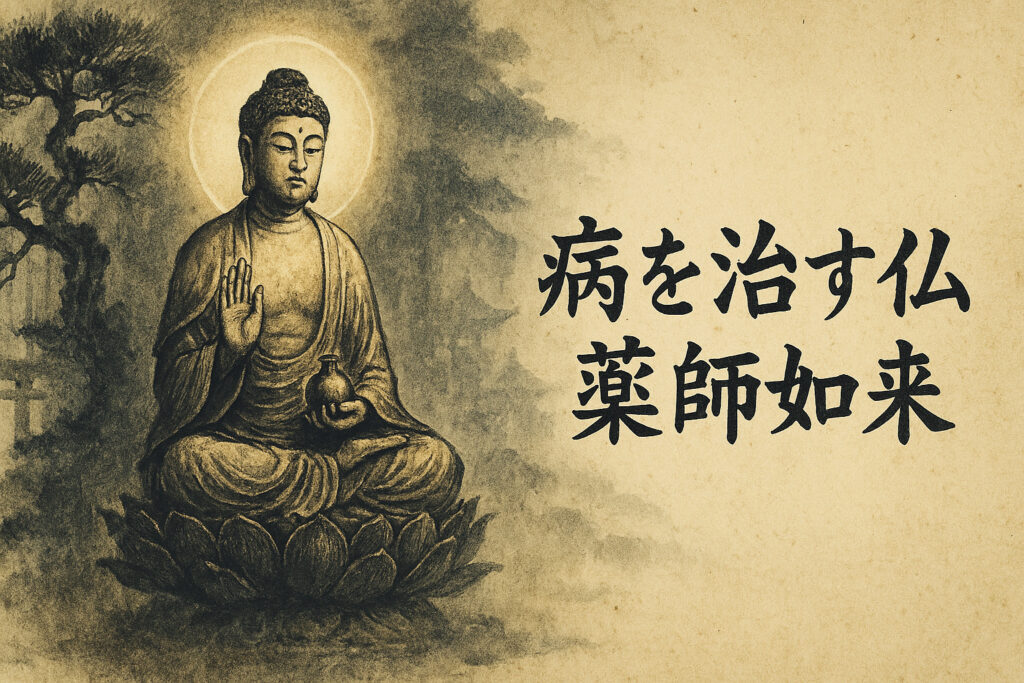
薬師如来の最大の特徴は、現世利益(げんせりやく)の仏であることです。
現世と来世の違い
- 阿弥陀如来:死後に極楽浄土へ連れて行ってくれる(来世の救済)
- 薬師如来:今、現在の苦しみから救ってくれる(現世の救済)
今も昔も、多くの人々は「今すぐ助けてほしい」と願うもの。だからこそ、薬師如来は長い間、変わらぬ信仰を集めてきたんです。
十二の大願
薬師如来は、まだ菩薩だった修行時代に十二の大願(じゅうにのたいがん)を立てました。そして、その誓いをすべて実現する力を持つ如来になったとされています。
十二の大願の主な内容:
- 光明普照(こうみょうふしょう):すべての人を悟りに導く
- 随意成弁:光明で人々の願いを叶える
- 施無尽:人々に無尽蔵の物資を与える
- 安立正法:すべての人を大乗仏教の教えに導く
- 安立正見:精神的苦痛や煩悩を浄化する
- 善根具足:身体の障害や苦痛、病気をなくす
- 除病安楽:医療や薬を供給して万病を治す
- 転女成男:女性の苦しみを解放する
- 正見:邪見から正しい見方へ導く
- 苦悩解脱:災難や刑罰から解放する
- 飽食安楽:飢えや渇きに苦しまないようにする
- 美衣満足:衣服を与え、寒さや困窮から救う
この中でも特に有名なのが第七願の除病安楽です。衣食を満たし、医療や薬を供給して万病を治すという、まさに薬師如来らしい誓いなんですね。
十二神将は、この十二の大願をそれぞれ守護する存在だとされています。
伝承
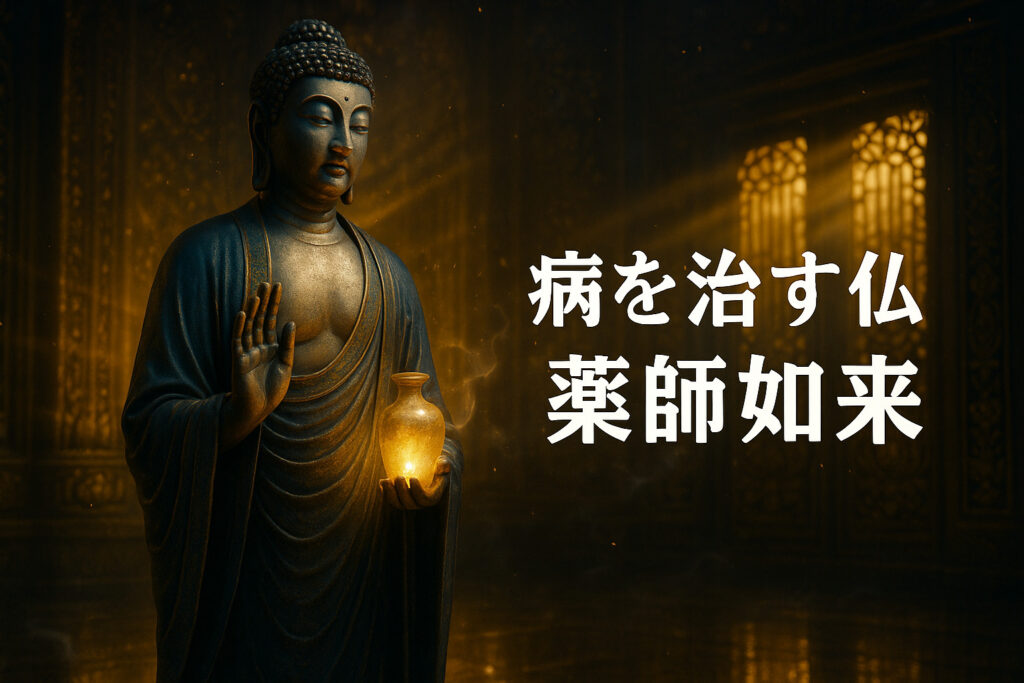
薬師如来にまつわる日本の伝承には、皇族との深い関わりがあります。
用明天皇と法隆寺の薬師如来
飛鳥時代、用明天皇(第31代天皇)が重い病に倒れました。
天皇は自らの病気平癒(へいゆ、病気が治ること)を願って、寺と薬師如来像を造ることを誓いました。しかし、完成を見ることなく崩御してしまったんです。
その後、推古天皇(第33代天皇)と聖徳太子が遺志を継ぎ、607年(推古15年)に法隆寺と薬師如来像を完成させました。
法隆寺金堂の薬師如来像は、光背(仏像の背後にある飾り)に造立の由来が刻まれており、これが日本最古の薬師如来像とされています。
天武天皇と薬師寺
680年(天武天皇8年)、天武天皇が持統天皇(当時は妃)の病気平癒を願って建立したのが、奈良の薬師寺です。
病気で苦しむ最愛の人のために、薬師如来を祀る寺を建てる。こうした信仰の形が、飛鳥時代から続いてきたんですね。
眼病治療の薬師さま
時代が下ると、特定の病気に特別な効験があるとされる薬師如来が各地に現れました。
その代表例が、東京・梅照院(通称・新井薬師)の薬師如来像です。
江戸時代、徳川秀忠の娘が眼病に苦しんでいました。彼女が新井薬師に眼病平癒を祈願したところ、見事に回復したんです。このことから、眼病治癒に特別な利益があるとして信仰を集めるようになりました。
『今昔物語集』の奇跡
平安時代の説話集『今昔物語集』にも、薬師如来の不思議な話が残っています。
ある村に、幼い娘を持つ盲目の女性がいました。女性は薬師堂にお参りし、必死に目の治癒を願いました。
すると、なんと薬師如来像の胸から桃の油のようなものが垂れてきたんです。女性がそれを口にしたところ、長年見えなかった目が見えるようになったというのです。
信仰と歴史
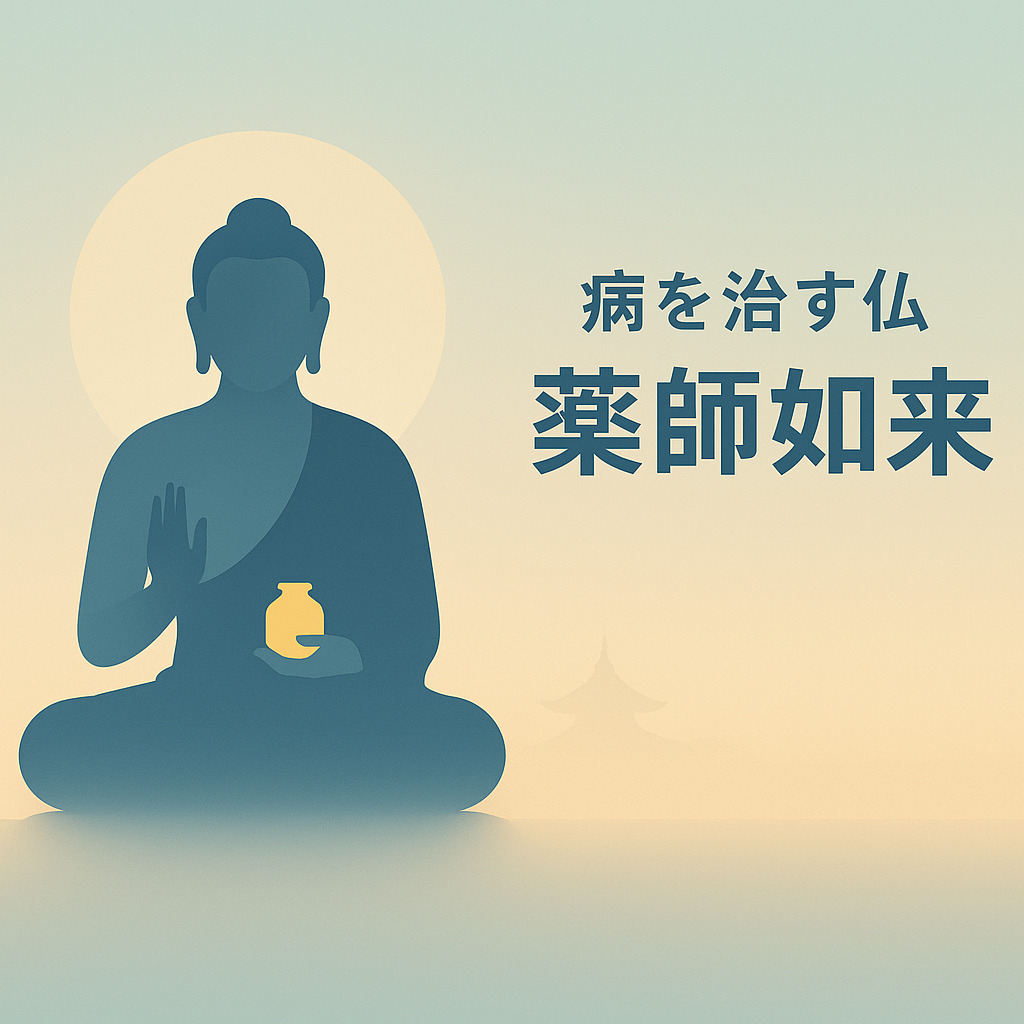
薬師如来の信仰は、日本仏教伝来の飛鳥時代から始まりました。
経典の成立
薬師如来について説かれた主な経典は、4世紀ごろに成立したと考えられています。
日本で広く読まれたのは、玄奘三蔵が650年に訳した『薬師瑠璃光如来本願功徳経』(薬師経)です。
七仏薬師
密教では、薬師如来を含む七体の仏様を祀る七仏薬師(しちぶつやくし)の信仰がありました。
天台密教では、七仏薬師を本尊として延命・息災・安産を祈る修法(しゅほう、儀式のこと)が重視され、平安時代の藤原摂関家を中心に広まったんです。
各地に広がる信仰
平安時代になると、『日本霊異記』などの記録から、民間にも薬師信仰が広く浸透していたことが分かります。
中世以降は、さらに信仰が促進され、各地に霊験あらたかな薬師如来が祀られるようになりました。
有名な例としては:
- 八幡護国寺、延暦寺、東寺などの七仏薬師
- 蛸薬師、石薬師など、霊験縁起にちなんだ名称で親しまれた薬師如来
- 三河鳳来寺の薬師如来(『浄瑠璃物語』で有名)
特に眼病への治癒効果があると信じられ、願いが叶うと絵馬を納める風習も残っています。
徳川家康と東照大権現
江戸時代には、興味深い信仰の形が生まれました。
徳川家康の生母・於大の方が、鳳来寺(愛知県)の薬師如来に祈願して家康を授かったという伝説があります。
そして家康の死後、天海大僧正らの働きにより、家康は薬師如来を本地とする権現(神様の仮の姿)とされ、朝廷から「東照大権現」の神号を授かりました。
こうして家康は、全国の東照宮で「権現様」として崇拝されるようになったのです。
まとめ
薬師如来は、現世の苦しみから私たちを救ってくれる、慈悲深い仏様です。
重要なポイント
- 東方浄瑠璃世界の教主で、万病を治す医療の仏
- 左手に薬壺を持つのが特徴
- 十二の大願を立て、特に病気治療を誓った
- 日光菩薩と月光菩薩が昼夜を問わず守護
- 現世利益の仏として、今の苦しみを救う
- 飛鳥時代から日本で信仰され、法隆寺や薬師寺の由来となった
- 眼病治療など、特定の病気に霊験があるとされる薬師如来も存在
死後の極楽往生を約束する阿弥陀如来に対し、薬師如来は「今、ここ」で苦しむ人々を救う仏様です。だからこそ、時代を超えて多くの人々の信仰を集めてきたんですね。
もし病気や困難に直面したとき、薬師如来の慈悲の心を思い出してみてはいかがでしょうか。



