天皇に愛されることが、逆に不幸を招くことがあるって、信じられますか?
平安時代の宮廷では、身分の低い女性が帝の寵愛を一身に受けたばかりに、周りから激しい嫉妬といじめを受け、ついには命を落としてしまうという悲劇が起きました。
これが、日本文学の最高峰『源氏物語』の始まりとなった「桐壺」の物語です。
この記事では、光源氏の母・桐壺更衣の悲恋と、平安時代の宮廷の光と闇について詳しく解説します。
概要
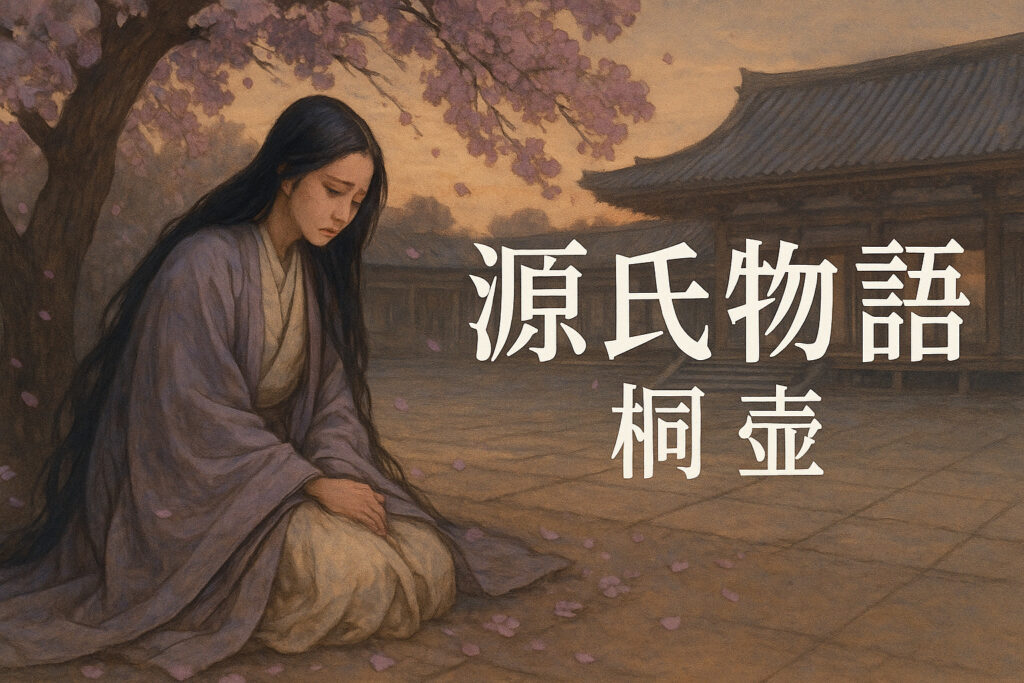
桐壺(きりつぼ)は、紫式部が書いた『源氏物語』全54帖の第1帖で、物語全体の出発点となる巻です。
ある帝の時代、それほど高い身分ではない桐壺更衣(きりつぼのこうい)という女性が、帝から特別な寵愛を受けていました。二人の間には後の光源氏となる美しい皇子が生まれますが、更衣は他の妃たちの激しい嫉妬といじめに苦しみ、わずか3歳の皇子を残して亡くなってしまいます。
深い悲しみに沈む桐壺帝は、亡き更衣にそっくりな藤壺を新たに迎え入れ、光源氏は12歳で元服して左大臣家の葵の上と結婚するまでが描かれています。
桐壺更衣ってどんな人?
身分と立場
桐壺更衣は、亡くなった按察大納言(あぜちだいなごん)の娘でした。
平安時代の天皇の妃には、以下のような序列がありました:
天皇の妃の序列
- 皇后(中宮) – 最も高い地位
- 女御(にょうご) – 摂政関白や大臣の娘から選ばれる
- 更衣(こうい) – 大納言以下の娘から選ばれる
つまり、桐壺更衣は妃の中では最下位の身分だったんです。
しかも、父親はすでに亡くなっていたため、後ろ盾となる有力者がいませんでした。母の強い希望で入内(宮中に入ること)しましたが、これが悲劇の始まりとなってしまうんです。
住まいの場所が物語る立場
更衣の住んでいた淑景舎(しげいしゃ)は、庭に桐の木があったことから「桐壺」と呼ばれていました。
ここがポイントなんですが、桐壺は帝が日常を過ごす清涼殿(せいりょうでん)から最も離れた場所にあったんです。帝に会いに行くには、他の妃たちの住まいの前を通らなければならず、これが後に悲劇を招くことになります。
なぜ桐壺更衣は憎まれたのか
身分不相応な寵愛
桐壺更衣が他の妃たちから激しく憎まれた理由は、「身分に見合わない寵愛を受けたから」でした。
当時の宮廷では、こんな暗黙のルールがあったんです:
- 高い身分の妃が優先的に寵愛を受けるべき
- 後ろ盾のない低い身分の妃は目立ってはいけない
- 皇子を産んでも、その子が天皇になる可能性は低い
ところが桐壺帝は、これらのルールを全部無視して、桐壺更衣ばかりを愛してしまったんですね。
陰湿ないじめの実態
桐壺更衣が受けたいじめは、想像を絶するものでした:
桐壺更衣が受けたいじめ
- 通路の扉を閉められて閉じ込められる
- 廊下に汚物をまかれる
- 着物に汚れをつけられる
- 精神的な嫌がらせを繰り返される
清涼殿に行くために他の妃の住まいを通らなければならなかった桐壺更衣は、毎日このような仕打ちを受けていたんです。
光源氏の誕生と運命

美しすぎる皇子
桐壺更衣は、輝くように美しい第二皇子を産みました。これが後の光源氏です。
しかし、母の身分が低く後ろ盾もない光源氏は、皇位継承の道から外されることになります。桐壺帝は愛する息子を守るため、「源」という姓を与えて臣籍降下(皇族から臣下の身分に下ること)させました。
高麗の相人の予言
興味深いことに、桐壺帝は光源氏の将来を占わせています。
高麗(朝鮮半島の国)から来た占い師は、こう予言しました:
「この子には天皇となる相があるが、もしそうなれば世が乱れるだろう」
この予言が、光源氏を臣籍降下させる決め手になったとも言われています。
歴史的なモデル
楊貴妃との類似
物語の中で、桐壺更衣は中国の楊貴妃にたとえられています。
楊貴妃も身分が低いながら玄宗皇帝の寵愛を受け、最後は悲劇的な死を遂げました。紫式部は『長恨歌』という楊貴妃の物語を下敷きにして、日本版の悲恋物語を作り上げたんですね。
実在の人物モデル
桐壺更衣には、実在の人物モデルがいたとされています:
可能性のあるモデル
- 藤原定子 – 一条天皇の中宮で、父の死後に不遇な最期を遂げた
- 藤原忯子 – 花山天皇に寵愛されたが、過度の寵愛により体を壊して亡くなった
- 藤原沢子 – 仁明天皇の女御で、光孝天皇の母
特に藤原忯子は、父が大納言であることや、帝の過度な寵愛により命を落としたことなど、桐壺更衣との共通点が多いんです。
物語が問いかける深い意味

政治システムへの批判
「桐壺」の巻は、単なる恋愛悲劇ではありません。
紫式部は、娘を天皇に入内させて権力を得ようとする摂関政治の残酷さを、美しい物語の中に織り込んでいるんです。桐壺更衣の死に際の歌「限りとて別るる道の悲しきに いかまほしきは命なりけり」(これで最後と別れる道の悲しさに、生きていたいのは命なのだった)という未練の言葉は、システムの犠牲になった女性の本音を表しています。
「紫の縁」の始まり
桐壺更衣の死は、物語全体を貫く「紫の縁(ゆかり)」という重要なテーマの始まりでもあります。
光源氏は生涯、母に似た女性を追い求めることになります:
- 藤壺 – 桐壺更衣に生き写しの女性
- 若紫(紫の上) – 藤壺に似た少女
この母への思慕が、光源氏の恋愛遍歴の原動力となっていくんですね。
まとめ
桐壺は、『源氏物語』の出発点として、愛と政治、美と権力の複雑な関係を描いた深い物語です。
重要なポイント
- 身分の低い桐壺更衣が帝の寵愛を独占したことで悲劇が始まった
- 後ろ盾のない更衣は他の妃たちの激しい嫉妬といじめを受けた
- わずか3歳の光源氏を残して病死してしまった
- 光源氏は母を守れなかった無力感から、生涯母の面影を追い求める
- 物語は平安時代の摂関政治の残酷さを浮き彫りにしている
- 楊貴妃の『長恨歌』を下敷きにした日本独自の悲恋物語
桐壺更衣の悲劇は、単なる昔話ではなく、権力構造の中で犠牲になる人々の普遍的な物語として、現代の私たちにも多くのことを問いかけています。







