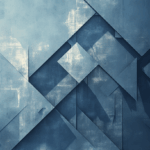パソコンのハードディスクやSSDの容量を調整したり、新しいパーティションを作りたいと思ったことはありませんか?
「パーティションって何?」「間違えてデータを消したらどうしよう」「難しそうで手が出せない…」と感じている方も多いはずです。
実は、GPartedは、ディスクのパーティション管理を視覚的に分かりやすく行える、Linux環境で最も信頼されているパーティション編集ツールなんです。まるで、ケーキを切り分けるように、ディスクを自由に分割・調整できるんですよ。
この記事では、GPartedの基本から実践的な使い方まで、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説していきます。
画面の見方から具体的な操作手順まで、ステップバイステップで説明しますので、安心してついてきてくださいね!
GPartedとは?その基本を知ろう

基本的な説明
GParted(ジーパーテッド)は、「GNOME Partition Editor」の略称で、ディスクのパーティションを作成・削除・リサイズできるフリーのパーティション編集ソフトです。
2004年から開発が続けられている、歴史と実績のあるツールなんです。
GUIツール:
グラフィカルなインターフェースで、視覚的に分かりやすく操作できます。コマンドを覚える必要はありません。
オープンソース:
完全無料で、誰でも自由に使えます。
パーティションって何?
パーティションとは、一つの物理的なディスクを、論理的に複数の領域に分割することです。
身近な例:
本棚の仕切り:
大きな本棚を、「小説」「漫画」「参考書」のように仕切りで区切るイメージです。
マンションの部屋:
一つの建物(ディスク)を、複数の部屋(パーティション)に分けている状態ですね。
なぜパーティションを分けるの?
データの整理:
OSとデータを別のパーティションに分けると、再インストール時にデータを残せます。
デュアルブート:
WindowsとLinuxを一つのPCにインストールできます。
効率的な管理:
用途別に領域を分けると、管理しやすくなります。
GPartedでできること
パーティションの作成:
新しいパーティションを作成できます。
パーティションの削除:
不要なパーティションを削除できます。
リサイズ(サイズ変更):
パーティションのサイズを拡大・縮小できます。
移動:
パーティションの位置を移動できます。
ファイルシステムの変更:
ext4、NTFS、FAT32など、様々な形式に対応しています。
ラベルの設定:
パーティションに名前を付けられます。
チェックとエラー修復:
ファイルシステムのエラーをチェックして修復できます。
まるで、ディスクの「外科医」のようなツールなんですね。
インストール方法
Ubuntu/Debianの場合
コマンドでインストール:
sudo apt update
sudo apt install gpartedたった2行で、インストール完了です。
Fedora/CentOS/RHELの場合
sudo dnf install gpartedまたは
sudo yum install gpartedArch Linuxの場合
sudo pacman -S gpartedGParted Live USBの作成
GParted Liveは、USBメモリから起動できる専用のLinux環境です。
いつ使う?
- OSがインストールされているパーティションを編集したい
- Windowsしか入っていないPCで使いたい
- OSが起動しないトラブルを修復したい
ダウンロード:
https://gparted.org/download.php
書き込みツール:
- Rufus(Windows)
- Etcher(Windows/Mac/Linux)
- ddコマンド(Linux)
手順(Rufus使用):
- GPartedのISOファイルをダウンロード
- Rufusを起動
- USBメモリを選択
- ISOファイルを選択
- 「スタート」をクリック
これで、どのPCでも起動できるGParted環境の完成です。
GPartedの起動方法
通常のLinux環境から起動
方法1:アプリケーションメニューから
- アプリケーションメニューを開く
- 「GParted」または「ディスク」で検索
- クリックして起動
方法2:コマンドから
sudo gparted重要: 必ず sudo を付けて実行してください。root権限が必要です。
パスワード入力:
ユーザーパスワードを入力すると、GPartedが起動します。
GParted Liveから起動
手順:
- USBメモリをPCに挿入
- BIOSの起動順序でUSBを最優先に設定
- PCを再起動
- GPartedのブートメニューが表示される
- デフォルト設定でEnterキーを押す
- 言語選択で「Japanese」を選択
- キーボード配置を選択(通常は「Don’t touch keymap」)
- 「0」を選択してGUIを起動
少し待つと、GPartedの画面が表示されます。
インターフェースの見方
メイン画面の構成
GPartedを起動すると、以下のような画面が表示されます。
上部:メニューバーとツールバー
各種操作のメニューとボタンが並んでいます。
中央上部:グラフィカルビュー
パーティションが色分けされた棒グラフで表示されます。
中央下部:リストビュー
各パーティションの詳細情報が表形式で表示されます。
下部:保留中の操作
実行予定の操作が一覧表示されます。
ディスクの選択
右上のドロップダウンメニューで、操作対象のディスクを選択できます。
表示例:
/dev/sda:1台目のSATA/SSDディスク/dev/sdb:2台目のディスク/dev/nvme0n1:NVMe SSD/dev/mmcblk0:SDカードやeMMC
注意: 間違えると大変なので、慎重に選びましょう。
パーティション情報の読み方
リストビューの列:
デバイス: /dev/sda1 のようなデバイス名
ファイルシステム: ext4、NTFS、FAT32など
マウントポイント: /、/home など(マウントされている場合)
ラベル: パーティションに付けた名前
サイズ: パーティションの容量
使用量: 実際に使われている容量
未使用: 空き容量
フラグ: boot(起動用)、hiddenなど
色の意味
グラフィカルビューの色:
薄い緑: ext4(Linuxの標準ファイルシステム)
青色: NTFS(Windowsのファイルシステム)
ピンク: FAT32/FAT16
黄色: スワップ領域(仮想メモリ)
灰色: 未割り当て領域
赤い縞模様: ロックされた領域(編集不可)
色を見るだけで、パーティションの種類が分かるんです。
基本操作:パーティションの作成
前提条件
未割り当て領域が必要:
パーティションを作成するには、「未割り当て」(灰色)の領域が必要です。
データのバックアップ:
念のため、重要なデータは必ずバックアップしてください。
手順
ステップ1:未割り当て領域を右クリック
グラフィカルビューまたはリストビューで、灰色の「未割り当て」領域を右クリックします。
ステップ2:「新規作成」を選択
コンテキストメニューから「新規作成」または「New」を選択します。
ステップ3:パーティションの設定
ダイアログボックスが表示されます:
新しいサイズ(MiB):
パーティションのサイズを指定します。スライダーで調整できます。
空き領域の前(MiB):
パーティションの前にどれだけ空きを残すか
空き領域の後(MiB):
パーティションの後にどれだけ空きを残すか
作成:
- 基本パーティション:通常はこれを選択
- 拡張パーティション:5個以上作る場合に必要
- 論理パーティション:拡張パーティション内に作成
ファイルシステム:
- ext4:Linux用(推奨)
- NTFS:Windows用
- FAT32:Windows/Linux/Mac共通(4GB以下のファイル)
- exFAT:Windows/Linux/Mac共通(大容量ファイル対応)
- スワップ:仮想メモリ用
ラベル:
分かりやすい名前を付けます(例:「Data」「Backup」)
ステップ4:「追加」をクリック
設定を確認して、「追加」ボタンをクリックします。
ステップ5:変更を適用
ツールバーの緑のチェックマークボタン(✓)をクリックします。
確認ダイアログ:
「本当に実行しますか?」と聞かれるので、「適用」をクリックします。
実行中:
進行状況バーが表示されます。完了するまで待ちましょう。
完了:
「すべての操作が正常に完了しました」と表示されたら成功です!
基本操作:パーティションのリサイズ
パーティションを縮小する
使用例:
500GBのパーティションを300GBに縮小して、200GBの空き領域を作る。
手順:
1. パーティションのアンマウント(必須)
マウントされているパーティションは編集できません。
sudo umount /dev/sda1または、GParted上で右クリック→「アンマウント」
注意: OSが起動しているパーティション(/)は、GParted Liveから起動しないと編集できません。
2. パーティションを右クリック
縮小したいパーティションを右クリックします。
3. 「リサイズ/移動」を選択
4. サイズを調整
スライダーを左にドラッグして、パーティションを小さくします。
または、「新しいサイズ(MiB)」に数値を直接入力します。
空き領域の配置:
- 前に作る:パーティションの前に空き領域
- 後ろに作る:パーティションの後ろに空き領域(一般的)
5. 「リサイズ/移動」ボタンをクリック
6. 変更を適用
ツールバーの緑のチェックマーク(✓)をクリックして、変更を確定します。
パーティションを拡大する
前提条件:
拡大したいパーティションのすぐ隣に未割り当て領域が必要です。
手順:
1. アンマウント
必要に応じてアンマウントします。
2. パーティションを右クリック
3. 「リサイズ/移動」を選択
4. サイズを拡大
スライダーを右にドラッグして、未割り当て領域を取り込みます。
5. 変更を適用
チェックマークをクリックして確定します。
注意点:
パーティションの前側に未割り当て領域がある場合、そこに拡大すると「移動」が伴うため、時間がかかります。
可能であれば、後ろ側の空き領域を使うのが効率的ですね。
基本操作:パーティションの削除
手順
警告:削除するとデータはすべて失われます!
必ずバックアップを取ってから実行してください。
1. アンマウント
削除するパーティションをアンマウントします。
2. パーティションを右クリック
3. 「削除」を選択
4. 確認
本当に削除して良いか、もう一度確認しましょう。
5. 変更を適用
チェックマークをクリックして確定します。
削除されたパーティションは、「未割り当て」領域になります。
ファイルシステムの種類と選び方
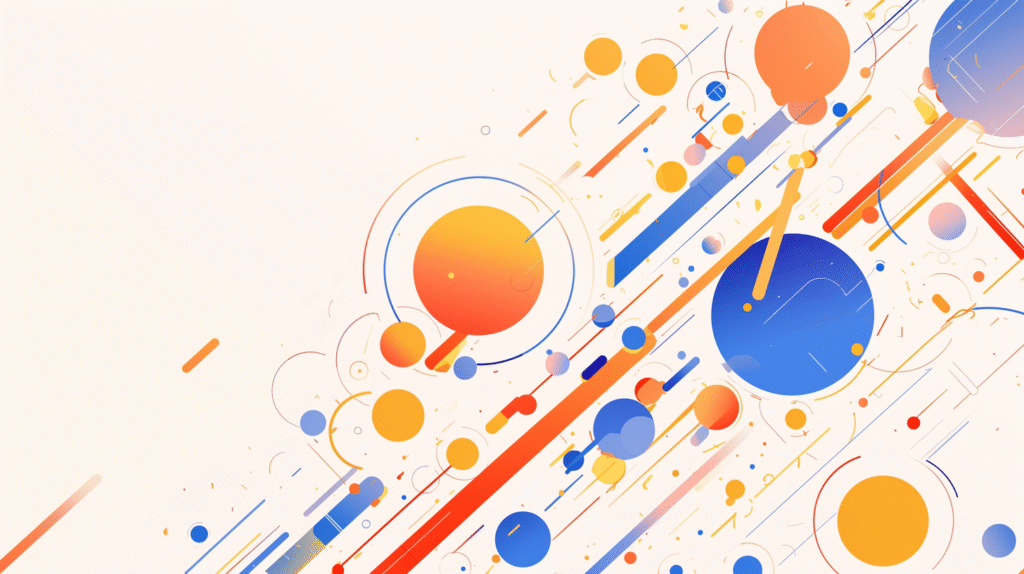
主なファイルシステム
ext4(Fourth Extended Filesystem)
用途: Linux専用
特徴:
- Linuxの標準ファイルシステム
- 高速で安定
- ジャーナリング機能(データ保護)
- 大容量対応(1EB = 100万TB)
推奨: Linuxのシステムパーティションやデータ用
NTFS(New Technology File System)
用途: Windows専用
特徴:
- Windowsの標準ファイルシステム
- 大容量ファイル対応
- アクセス権限管理
- Linuxからも読み書き可能(ntfs-3gが必要)
推奨: WindowsとLinuxのデュアルブート環境で共有
FAT32(File Allocation Table 32)
用途: Windows/Linux/Mac共通
特徴:
- どのOSでも読み書き可能
- USBメモリやSDカードで一般的
- 制限: 4GB以上のファイルは保存不可
- 制限: 最大32GB(Windowsでフォーマット時)
推奨: USBメモリ、小容量の共有ドライブ
exFAT(Extended FAT)
用途: Windows/Linux/Mac共通
特徴:
- FAT32の後継
- 4GB以上のファイルに対応
- 大容量ストレージ向け
推奨: 大容量USBメモリ、外付けHDD
スワップ(Linux Swap)
用途: Linuxの仮想メモリ
特徴:
- RAMが足りない時に使用
- ファイルは保存できない
- 休止状態の保存に使用
推奨サイズ:
- RAM 4GB以下:RAM容量の2倍
- RAM 4GB〜16GB:RAM容量と同じ
- RAM 16GB以上:4GB〜8GBで十分
Btrfs(B-tree File System)
用途: Linux専用(次世代FS)
特徴:
- スナップショット機能
- データ圧縮
- RAIDサポート
- まだ発展途上
推奨: 上級者向け
選択の基準
Linux専用 → ext4
Windowsとの共有 → NTFS
複数OSでの共有 → exFAT
USBメモリ(小ファイル)→ FAT32
USBメモリ(大ファイル)→ exFAT
仮想メモリ → スワップ
使用目的に応じて、適切なファイルシステムを選びましょう。
実践例:WindowsとLinuxのデュアルブート環境構築
シナリオ
500GBのSSDに、WindowsとLinuxを共存させたい。
目標構成:
- Windows用:250GB(NTFS)
- Linux用:200GB(ext4)
- スワップ:8GB
- データ共有:42GB(exFAT)
手順
前提: Windowsはすでにインストールされていて、500GB全体を使用している状態。
ステップ1:GParted Liveで起動
OSが起動している状態では編集できないため、GParted Live USBから起動します。
ステップ2:Windowsパーティションを縮小
/dev/sda1(WindowsのCドライブ)を右クリック- 「リサイズ/移動」を選択
- 新しいサイズを250GB(256000 MiB)に設定
- 「リサイズ/移動」をクリック
注意: Windowsを起動して、事前にディスクの最適化(デフラグ)をしておくと、より多く縮小できます。
ステップ3:Linuxルートパーティション作成
- 未割り当て領域を右クリック
- 「新規作成」を選択
- サイズ:200GB(204800 MiB)
- ファイルシステム:ext4
- ラベル:「Linux」
- 「追加」をクリック
ステップ4:スワップパーティション作成
- 残りの未割り当て領域を右クリック
- 「新規作成」を選択
- サイズ:8GB(8192 MiB)
- ファイルシステム:linux-swap
- ラベル:「Swap」
- 「追加」をクリック
ステップ5:データ共有パーティション作成
- 残りの未割り当て領域を右クリック
- 「新規作成」を選択
- サイズ:残り全部
- ファイルシステム:exFAT
- ラベル:「Data」
- 「追加」をクリック
ステップ6:変更を適用
チェックマーク(✓)をクリックして、すべての変更を実行します。
完了!
これで、WindowsとLinuxが共存できる環境が完成しました。
次は、Linuxをインストールする際に、作成したext4パーティションを選択すればOKです。
重要な注意点
1. 必ずバックアップを取る
パーティション操作は危険が伴います。
予期しないエラーや停電で、データが失われる可能性があります。
バックアップ方法:
- 外付けHDDにコピー
- クラウドストレージに保存
rsyncやddコマンドでイメージ化
重要なデータは二重、三重にバックアップしておきましょう。
2. 電源を切らない
操作中に絶対に電源を切ってはいけません。
ノートPCの場合:
- ACアダプターを接続しておく
- バッテリー残量を十分に確保
デスクトップの場合:
- UPS(無停電電源装置)の使用を推奨
途中で止まると、ディスク全体が使えなくなる可能性があります。
3. システムパーティションは慎重に
起動パーティションやOSがインストールされているパーティションを削除・縮小すると、起動できなくなります。
確認:
/マウントポイントがあるパーティションbootフラグが立っているパーティション- Windowsの
C:ドライブ
これらは特に慎重に扱いましょう。
4. 空き容量の確認
パーティションを縮小する時:
実際に使用している容量より小さくはできません。
例:
- パーティション容量:500GB
- 使用量:300GB
- 縮小可能な最小サイズ:約300GB
余裕を持って、使用量の1.2倍程度のサイズにするのが安全です。
5. 変更は即座に反映されない
GPartedでは、操作を「キュー」に追加して、最後にまとめて実行します。
チェックマーク(✓)をクリックするまでは変更されません。
逆に言えば、間違えても「編集」→「すべての操作を取り消す」で元に戻せます。
トラブルシューティング
問題1:パーティションがアンマウントできない
症状:
「パーティションがマウントされています」というエラーが出て、操作できない。
原因:
OSが使用中のパーティションは、アンマウントできません。
解決策:
方法1:GParted Liveで起動
USBメモリからGParted Liveを起動すれば、どのパーティションでも編集可能です。方法2:別のパーティションに切り替え
# システムを別のパーティションで起動
# 例:Live USBやインストールメディア問題2:変更が適用されない
症状:
緑のチェックマークが押せない、または反応しない。
原因:
- 保留中の操作がない
- エラーが発生している
解決策:
下部の「保留中の操作」を確認:
何か操作が登録されていますか?
エラーメッセージを確認:
赤い×マークがある場合、エラーの詳細を読みましょう。
問題3:「ファイルシステムのサポートがありません」
症状:
NTFSやexFATで「サポートされていません」と表示される。
原因:
必要なパッケージがインストールされていません。
解決策:
NTFSサポートを追加:
sudo apt install ntfs-3gexFATサポートを追加:
sudo apt install exfat-fuse exfat-utils
# または(新しいシステム)
sudo apt install exfatprogsBtrfsサポートを追加:
sudo apt install btrfs-progsインストール後、GPartedを再起動してください。
問題4:操作が途中で止まる
症状:
プログレスバーが進まない。
原因:
- ディスクエラー
- 容量不足
- ハードウェアの問題
対処法:
待つ:
大容量パーティションの移動には、数時間かかることもあります。
ログを確認:
「表示」→「操作の詳細」でエラーログを確認します。
ディスクチェック:
sudo fsck /dev/sda1問題5:起動しなくなった
症状:
パーティション操作後、OSが起動しない。
原因:
- ブートローダーが壊れた
- システムパーティションを誤って削除
解決策:
GRUBの修復(Linux):
# Live USBで起動
sudo mount /dev/sda2 /mnt
sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi # EFIの場合
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
sudo update-grubWindowsブートローダーの修復:
Windowsインストールメディアから起動して、「スタートアップ修復」を実行します。
よくある質問
Q1: Windowsでも使える?
A: GPartedはLinuxソフトですが、GParted Live USBを使えばWindowsからも起動できます。
Windows環境では、別途「MiniTool Partition Wizard」や「EaseUS Partition Master」などの代替ソフトがあります。
Q2: データは消える?
A: リサイズや移動では消えませんが、削除やフォーマットは完全に消えます。
念のため、常にバックアップを取りましょう。
Q3: パーティションはいくつまで作れる?
A:
MBR形式: 最大4つの基本パーティション(拡張パーティションを使えば事実上無制限)
GPT形式: 最大128個(実用上は十分)
最近のディスクは、ほとんどがGPT形式です。
Q4: どれくらい時間がかかる?
A:
パーティション作成・削除: 数秒〜数分
リサイズ(縮小): 10分〜1時間
リサイズ(拡大): 数分(移動を伴わない場合)
移動: 数時間(容量による)
大容量ほど時間がかかります。夜中に実行するのも一つの手ですね。
Q5: スマートフォンやSDカードでも使える?
A: はい、使えます。
USBカードリーダー経由でSDカードを接続すれば、GPartedで編集できます。
Androidのストレージ拡張などに活用できますよ。
GPartedの代替ツール
コマンドライン版
fdisk:
昔ながらのパーティション編集ツール。
sudo fdisk /dev/sdaparted:
GPartedのベースとなっているコマンドラインツール。
sudo parted /dev/sdagdisk:
GPTディスク専用。
sudo gdisk /dev/sdaGUIツール
GNOME Disks(gnome-disk-utility):
GNOMEデスクトップ標準のディスク管理ツール。
gnome-disksシンプルで使いやすいですが、機能は少なめです。
KDE Partition Manager:
KDEデスクトップ向け。GPartedと同等の機能があります。
まとめ
GPartedは、ディスクのパーティションを視覚的に分かりやすく管理できる、強力で信頼性の高いツールです。
この記事のポイント:
- GPartedはLinuxの定番パーティション編集ツール
- パーティションの作成・削除・リサイズが可能
- グラフィカルで分かりやすいインターフェース
- ext4、NTFS、FAT32、exFATなど多数対応
- GParted Live USBでどのPCでも使用可能
- 操作は「保留」され、チェックマークで一括適用
- 必ずデータのバックアップを取る
- 電源を切らない、システムパーティションは慎重に
- WindowsとLinuxのデュアルブート環境構築に最適
- トラブル時はGParted Liveで起動して修復
パーティション操作は、最初は怖く感じるかもしれません。でも、基本を理解して慎重に操作すれば、ディスクを自由自在に管理できるようになります。
初めての方へのアドバイス:
まずは古い不要なUSBメモリやSDカードで練習してみてください。実際に触ってみることで、理解が深まりますよ。
ディスク管理の技術は、Linux使いにとって必須のスキルです。GPartedをマスターして、より快適なPC環境を構築しましょう!