パソコンの動作を速くしたい、大容量のストレージが欲しい——そんな要望を叶える技術の1つがストライプボリュームです。
「ストライプ?縞模様と何か関係があるの?」と思われるかもしれませんが、実はデータの保存方法に由来する名前なんです。
この技術を使うと、複数のハードディスクやSSDを組み合わせて、データの読み書き速度を大幅に向上させることができます。
今回は、ストライプボリュームの仕組みからメリット・デメリット、実際の活用方法まで分かりやすく解説していきますね。
ストライプボリュームとは?基本を理解しよう
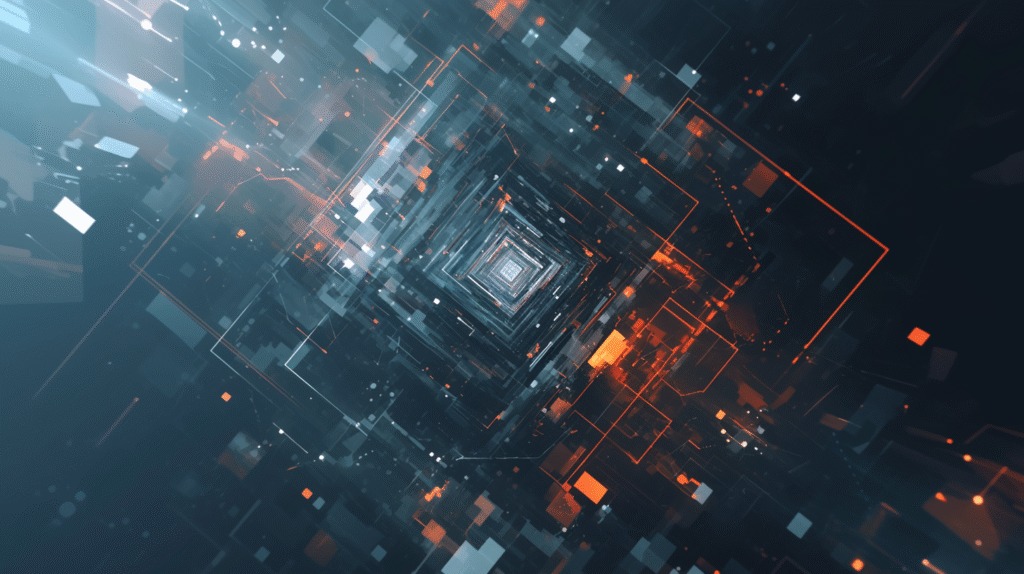
データを分散して保存する技術
ストライプボリュームとは、複数のディスク(ハードディスクやSSD)にデータを分散して保存する技術のことです。
1つのファイルを複数のディスクに「縞模様(ストライプ)」のように分割して書き込むため、この名前が付けられています。
例えば、100MBのファイルを保存する場合:
- 通常:1台のディスクに100MB全体を書き込む
- ストライプボリューム:2台のディスクにそれぞれ50MBずつ分散して書き込む
この仕組みにより、複数のディスクが同時に動作するため、読み書きの速度が向上するんです。
RAID 0との関係
ストライプボリュームは、RAID 0(レイドゼロ)とも呼ばれています。
RAIDとは「Redundant Array of Independent Disks」の略で、複数のディスクを組み合わせて使う技術の総称です。
RAID 0の「0」は、データの冗長性(バックアップ機能)がゼロであることを示しています。
つまり、ストライプボリュームは速度重視でバックアップ機能を持たない構成なんですね。
ストライプボリュームの仕組み
データがどのように保存されるのか
ストライプボリュームでは、データがブロック単位で分割されて各ディスクに保存されます。
具体例:
ファイルAを2台のディスク(ディスク1とディスク2)に保存する場合
- 1ブロック目 → ディスク1に保存
- 2ブロック目 → ディスク2に保存
- 3ブロック目 → ディスク1に保存
- 4ブロック目 → ディスク2に保存
このように交互に保存していくことで、2台のディスクが同時に読み書きを行えるため、処理速度が向上します。
複数のディスクが協力して動作
ストライプボリュームでは、OSからは1つの大きなドライブとして認識されます。
しかし実際には、複数のディスクが並行して動作しているんです。
2台のディスクを使った場合:
- 理論上、読み書き速度は約2倍
- 容量は2台分の合計(例:1TB × 2台 = 2TB)
3台以上でも構成可能:
- 台数が増えるほど速度向上の効果が期待できる
- ただし、後述するリスクも増加する
ストライプボリュームのメリット
高速なデータ転送速度
最大のメリットは、読み書き速度の向上です。
通常の1台のディスクと比較して:
- シーケンシャル読み書き(連続したデータの処理)が高速化
- 大容量ファイルの転送時間が短縮
- 動画編集やデータベース処理などで効果を実感しやすい
実際の速度は、使用するディスクの性能や台数、接続方式によって異なりますが、2台構成なら1.5〜1.8倍程度の速度向上が期待できます。
ディスク容量を無駄なく活用
複数のディスクの容量を合算して使えるため、容量の有効活用ができます。
例:
- 500GBのSSD × 2台 = 1TBのストライプボリューム
- 1TBのHDD × 3台 = 3TBのストライプボリューム
異なる容量のディスクも組み合わせられますが、最も小さいディスクの容量に合わせられるため注意が必要です。
構築が比較的簡単
Windowsの標準機能である「ディスクの管理」ツールで、簡単にストライプボリュームを作成できます。
専用のハードウェアやRAIDカードが不要な場合も多く、コストを抑えられる点も魅力です。
ストライプボリュームのデメリット
データの冗長性がない(重要)
これが最大のデメリットです。
ストライプボリュームでは、データが複数のディスクに分散されているため、1台でもディスクが故障すると、全てのデータが失われます。
通常のディスク:
- 1台故障 → そのディスク内のデータのみ失われる
ストライプボリューム:
- 1台故障 → ボリューム全体のデータが失われる
2台構成なら故障リスクは2倍、3台構成なら3倍になると考えておきましょう。
バックアップが必須
ストライプボリュームを使用する場合、定期的なバックアップが絶対に必要です。
- 外付けHDDへの定期バックアップ
- クラウドストレージへの自動同期
- NAS(ネットワークストレージ)への保存
バックアップなしでストライプボリュームを使うのは、非常にリスクの高い行為です。
データ復旧が困難
1台でもディスクが故障した場合、データ復旧業者でも復旧できない可能性が高くなります。
通常のディスクであれば部分的に復旧できるケースでも、ストライプボリュームでは全体が読み取れなくなるためです。
ストライプボリュームの適した使用場面
動画編集やクリエイティブ作業
大容量の動画ファイルを扱う編集作業では、ストライプボリュームの高速性が活きてきます。
- 4K・8K動画の編集
- RAW画像の一括処理
- 3DCGのレンダリング用ストレージ
ただし、作業データは必ず別のストレージにバックアップしておきましょう。
ゲームのインストール先
大容量のゲームタイトルを多数インストールする場合にも有効です。
- ゲームの起動時間短縮
- ロード時間の短縮
- 大容量ストレージの確保
ゲームデータは再ダウンロード可能なため、万が一の故障時でも再インストールできる点は安心材料になります。
一時作業領域(スクラッチディスク)
Adobe製品などの一時ファイル保存領域として活用するのも効果的です。
- Photoshopのスクラッチディスク
- Premiere Proのキャッシュ領域
- データベースの一時テーブル
一時ファイルなので、失っても作業をやり直せばいい——という割り切りができる用途には向いています。
不向きな用途
以下の用途には絶対に使用しないでください:
- 重要な文書やデータの保管
- 写真や動画の長期保存
- バックアップが困難なデータ
- 業務で使用する基幹システム
Windowsでストライプボリュームを作成する方法
事前準備
作成前に確認すべきポイント:
- 2台以上の未使用ディスクが必要(または未割り当て領域がある)
- ディスク内のデータは全て消去されるため、必要なデータは事前にバックアップ
- Windowsのエディションを確認(一部の機能はProエディション以上で利用可能)
基本的な作成手順
1. ディスクの管理を開く
- キーボードの「Windows + X」を押す
- メニューから「ディスクの管理」を選択
2. 未割り当て領域を確認
- ストライプボリュームに使用するディスクに未割り当て領域があることを確認
- 未割り当て領域がない場合は、既存のボリュームを削除(データは消えます)
3. ストライプボリュームの新規作成
- 未割り当て領域の1つを右クリック
- 「新しいストライプボリューム」を選択
- ウィザードに従って設定を進める
4. ディスクの選択
- ストライプボリュームに含めるディスクを選択
- 各ディスクから使用する容量を指定(通常は同じサイズを推奨)
5. フォーマットと完了
- ドライブレター(DドライブやEドライブなど)を割り当てる
- ファイルシステム(通常はNTFS)を選択
- フォーマットを実行して完了
設定後の確認
作成後は必ず以下を確認しましょう:
- エクスプローラーで新しいドライブが表示されるか
- ファイルの読み書きが正常に行えるか
- 速度が期待通り向上しているか(ベンチマークソフトで測定可能)
ストライプボリューム使用時の注意点
定期的な健全性チェック
ディスクの健全性を定期的に確認することが重要です。
CrystalDiskInfoなどの無料ソフトウェアを使用して:
- S.M.A.R.T.情報をチェック
- 異常な兆候(温度上昇、エラー発生)を早期発見
- 警告が出たら速やかにバックアップを取り、ディスクを交換
UPS(無停電電源装置)の使用
停電や突然の電源断は、ストライプボリュームにとって致命的です。
UPSを導入することで:
- 突然の電源断からシステムを保護
- 安全にシャットダウンする時間を確保
- データ破損のリスクを軽減
ディスクの同時交換は避ける
古くなったディスクを交換する際は、1台ずつ順番に交換しないでください。
ストライプボリュームでは全てのディスクが揃っていないとデータが読めないため、複数台を同時に外すとデータが完全に失われます。
ディスクを交換したい場合は:
- 全データをバックアップ
- ストライプボリュームを削除
- ディスクを交換
- 新たにストライプボリュームを作成
- データを復元
という手順が必要です。
ストライプボリュームの代替手段

RAID 5(パリティ付きストライピング)
データの冗長性を持たせたい場合は、RAID 5が選択肢になります。
- 3台以上のディスクが必要
- 1台が故障してもデータは保護される
- 速度はストライプボリュームより低下するが、安全性は向上
RAID 10(ミラー+ストライプ)
速度と安全性の両立を目指すならRAID 10です。
- 4台以上のディスクが必要
- ミラーリングとストライピングを組み合わせた構成
- 高速かつデータ保護も可能だが、コストは高い
単体の高速SSD
最近のNVMe SSDは単体でも非常に高速です。
- ストライプボリュームの複雑さを避けられる
- 故障リスクは1台分のみ
- 管理が簡単
用途によっては、複数の遅いディスクでストライプを組むより、1台の高速SSDの方が実用的な場合もあります。
まとめ:速度と引き換えにリスクを理解して使おう
ストライプボリュームは、複数のディスクを組み合わせて高速化を実現する魅力的な技術です。
この記事のポイント:
- ストライプボリューム(RAID 0)は複数のディスクにデータを分散して高速化する技術
- 読み書き速度が向上し、大容量のストレージを構築できる
- 1台でも故障すると全データが失われる重大なデメリットがある
- バックアップは絶対に必須!定期的に実施すること
- 動画編集やゲームインストール先など、一時的な高速ストレージとして活用するのが賢い使い方
- 重要なデータの保管には絶対に使用しない
「速度は欲しいけど、データは守りたい」という方は、RAID 5やRAID 10などの冗長性を持つ構成や、単体の高速SSDを検討するのが良いでしょう。
ストライプボリュームは正しく理解して使えば便利な技術ですが、リスクをしっかり認識した上で活用してくださいね。






