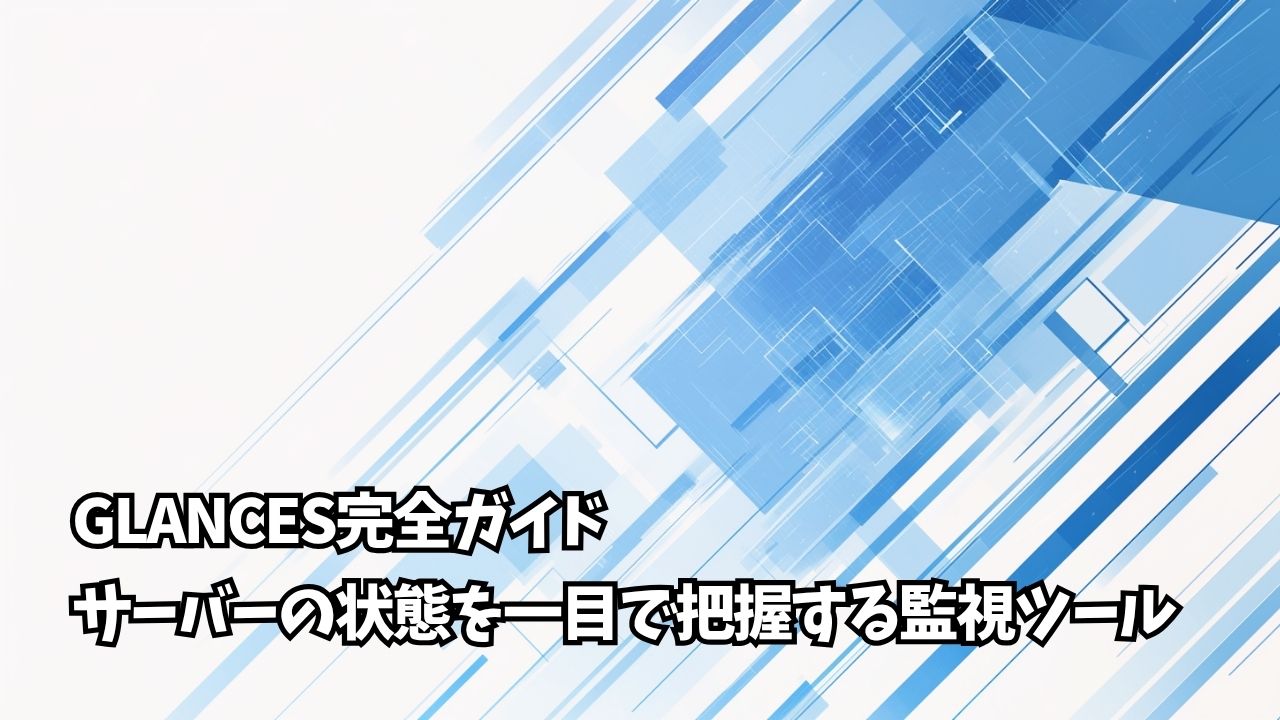「サーバーが重い気がする…でも原因がわからない」
「CPUとメモリ、どっちがボトルネックなんだろう?」
「複数のコマンドを使わないと全体像が見えない」
サーバー管理をしていると、こんな悩みに直面しますよね。
システムの状態を把握するには、topやfree、dfなど、複数のコマンドを使う必要があります。でも、それぞれ別々に実行するのは面倒ですし、全体像がつかみにくいんです。
そこで活躍するのがGlances(グランシズ)です。
この記事では、システムの状態を一画面で美しく表示してくれる監視ツール「Glances」について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。サーバー管理が格段に楽になる知識をお届けしますよ。
Glancesとは?システムの「健康診断」ツール

Glancesは、LinuxやmacOS、Windowsで動作するシステム監視ツールです。
Pythonで作られたオープンソースソフトウェアで、誰でも無料で使えます。
一画面で全てを表示
Glancesの最大の特徴は、システムの様々な情報を一つの画面にまとめて表示できることです。
- CPU使用率
- メモリ使用量
- ディスクI/O
- ネットワークトラフィック
- プロセス一覧
- ディスク使用状況
- センサー情報(温度など)
これらをリアルタイムで、色分けして見やすく表示してくれるんです。
Glancesという名前の由来
「Glance」は英語で「ちらっと見る」「一目見る」という意味です。
その名の通り、一目でシステムの状態を把握できるツールなんですね。
topやhtopとの違い
似たようなツールとの違いを見ていきましょう。
top:標準的なプロセス監視ツール
topは、ほとんどのLinuxシステムに標準でインストールされています。
プロセスのCPU使用率やメモリ使用量を表示できますが、情報量は限定的です。
見た目も少し古めかしいですね。
htop:topの改良版
htopは、topをより見やすく、使いやすくしたツールです。
マウスでの操作に対応し、カラフルな表示で情報を整理してくれます。
ただし、プロセス管理に特化しており、ネットワークやディスクの詳細情報は表示されません。
Glances:オールインワンの監視ツール
Glancesは、htopの見やすさに加えて、さらに幅広い情報を表示できます。
Glancesならではの機能:
- ネットワークインターフェースごとの通信量
- ディスクI/Oの詳細
- センサー情報(温度、ファン速度)
- Dockerコンテナの監視
- Webインターフェース
- リモート監視機能
- 警告・アラート機能
より総合的なシステム監視が可能なんです。
Glancesのインストール方法
各OSでのインストール方法を紹介します。
Ubuntu/Debianの場合
sudo apt update
sudo apt install glancesパッケージマネージャーから簡単にインストールできます。
CentOS/RHELの場合
sudo yum install epel-release
sudo yum install glancesEPELリポジトリを有効にしてからインストールします。
macOSの場合
Homebrewを使ってインストールできます。
brew install glancespipを使う方法
Pythonのパッケージマネージャーpipを使えば、どのOSでも最新版をインストールできます。
pip install glancesまたは
pip3 install glancesこの方法なら、最新の機能をすぐに試せますよ。
Glancesの基本的な使い方
インストールしたら、実際に使ってみましょう。
起動方法
ターミナルで以下のコマンドを実行するだけです。
glancesすると、システム情報が一画面に表示されます。
画面の見方
Glancesの画面は、いくつかのセクションに分かれています。
上部:
- CPU使用率(コアごと)
- メモリ使用量とスワップ
- ロードアベレージ
中央:
- ネットワーク通信量
- ディスクI/O
- ファイルシステムの使用状況
下部:
- 実行中のプロセス一覧
各項目は色分けされていて、緑・黄・赤で状態を判断できます。
色の意味
Glancesは、リソースの使用状況に応じて色を変えてくれます。
- 緑色:正常(使用率が低い)
- 青色:注意(やや高い)
- 紫色:警告(高い)
- 赤色:危険(非常に高い)
一目で問題箇所が分かるので便利ですね。
便利なキーボードショートカット
Glances起動中に使える、便利なキー操作を紹介します。
基本操作
q または ESC
Glancesを終了します。
h
ヘルプを表示します。どんなキーが使えるか確認できますよ。
スペース
画面の更新を一時停止します。じっくり確認したいときに便利です。
表示の切り替え
1
各CPUコアの使用率を表示/非表示
2
ネットワークインターフェースを表示/非表示
3
センサー情報(温度など)を表示/非表示
d
ディスクI/Oを表示/非表示
f
ファイルシステム情報を表示/非表示
n
ネットワークの詳細表示モードに切り替え
プロセス管理
a
プロセスの自動ソートを有効/無効
c
CPUでソート
m
メモリでソート
k
選択したプロセスを終了(killコマンド)
E
プロセスの詳細情報を表示
これらを使いこなせば、効率的にシステムを監視できます。
Webインターフェースモード
Glancesには、ブラウザからアクセスできるWebインターフェースがあります。
起動方法
glances -wこのコマンドで、Webサーバーモードで起動します。
デフォルトでは、http://localhost:61208でアクセスできますよ。
Webインターフェースの利点
リモートアクセス
別のPCやスマートフォンからでもアクセスできます。
常時表示
ダッシュボードとして、別のモニターに常時表示しておくことも可能です。
複数人での共有
チームメンバーが同時にサーバーの状態を確認できます。
サーバールームに入らなくても、デスクからサーバーの状態を監視できるんですね。
クライアント・サーバーモード
Glancesは、リモートマシンの監視にも対応しています。
サーバー側の設定
監視したいサーバーで、以下のコマンドを実行します。
glances -sこれで、Glancesがサーバーモードで起動します。
デフォルトではポート61209で待ち受けます。
クライアント側の接続
監視する側のPCから接続します。
glances -c サーバーのIPアドレス例えば:
glances -c 192.168.1.100これで、リモートサーバーの情報をローカルと同じように表示できます。
複数のサーバーを管理している場合に便利ですよ。
REST APIとエクスポート機能
Glancesは、データをJSON形式で出力できます。
REST API
Webモードで起動すると、REST APIも利用可能になります。
curl http://localhost:61208/api/3/cpuこのようにAPIを叩くと、CPU情報がJSON形式で返ってきます。
エクスポート先
取得したデータを、様々な外部サービスに送信できます。
対応しているサービス:
- InfluxDB(時系列データベース)
- Elasticsearch(検索エンジン)
- CSV ファイル
- StatsD
- Prometheus
監視システムと統合して、長期的なデータ分析も可能なんです。
アラート機能
Glancesには、しきい値を超えたときに警告を出す機能があります。
自動アラート
デフォルトで、リソース使用率が高くなると色が変わります。
これだけでも、異常に気づきやすいですね。
カスタムアラート
設定ファイルで、独自のアラート条件を定義できます。
例えば、「CPU使用率が90%を5分間超えたら通知」といった設定が可能です。
Dockerコンテナの監視
Glancesは、Dockerコンテナの監視にも対応しています。
表示方法
glances通常通り起動すれば、Dockerがインストールされている場合、自動的にコンテナ情報も表示されます。
Dキーを押すと、コンテナビューに切り替わります。
表示される情報
- コンテナ名
- CPUとメモリ使用量
- ネットワークトラフィック
- 実行時間
マイクロサービス構成のシステムでは、非常に役立つ機能ですね。
設定ファイル
Glancesの動作は、設定ファイルでカスタマイズできます。
設定ファイルの場所
Linux/macOSの場合:
~/.config/glances/glances.confまたは
/etc/glances/glances.conf主な設定項目
更新間隔の変更:
デフォルトは2秒ですが、より頻繁に更新したり、逆に負荷を下げるために間隔を長くしたりできます。
しきい値の調整:
色が変わる使用率のしきい値を変更できます。
表示項目の制御:
表示したくない情報を非表示にできます。
必要に応じて、自分好みにカスタマイズしてみてください。
実用的な活用例
実際にGlancesをどう使うか、シーンごとに見てみましょう。
例1:パフォーマンスボトルネックの特定
アプリケーションが遅いとき、Glancesを起動すれば原因がすぐに分かります。
- CPU使用率が高い → 計算処理が重い
- メモリが足りない → メモリ増設が必要
- ディスクI/Oが高い → SSDへの換装を検討
- ネットワークが詰まっている → 帯域不足
一目で判断できるので、対策も立てやすいんです。
例2:サーバーの常時監視
Webモードで起動して、モニターに常時表示しておけば、異常にすぐ気づけます。
色が赤くなったら、すぐに対処できますね。
例3:複数サーバーの一元管理
クライアント・サーバーモードを使えば、複数のサーバーを切り替えながら監視できます。
データセンターに何十台もサーバーがある場合でも、デスクから管理可能です。
例4:トラブルシューティング
「さっきから急に重くなった」というとき、Glancesを起動すれば犯人がすぐ分かります。
プロセス一覧を見て、異常にCPUを消費しているプロセスを特定できるんですよ。
Glancesのメリット
このツールを使う利点をまとめました。
1. 情報の一元化
複数のコマンドを使わなくても、一画面で全てが分かります。
時間の節約になり、ストレスも減りますね。
2. 直感的な視覚化
色分けされた表示により、問題箇所が一目瞭然です。
数字を読み解く必要がありません。
3. クロスプラットフォーム
Linux、macOS、Windowsのどれでも使えます。
環境が変わっても、同じツールで監視できるんです。
4. 軽量
Glances自体は非常に軽量で、システムへの負荷がほとんどありません。
常時起動していても問題ないレベルです。
5. 拡張性
REST APIやエクスポート機能により、他のツールと連携できます。
本格的な監視システムの一部として組み込むことも可能ですよ。
Glancesの注意点
便利なGlancesですが、いくつか知っておくべきことがあります。
リアルタイム監視に特化
長期的なデータの保存や、グラフ化には向いていません。
過去のデータを分析したい場合は、PrometheusやGrafanaなどの専用ツールと組み合わせましょう。
セキュリティ
Webモードやサーバーモードを使う場合、認証設定をしないと誰でもアクセスできます。
パスワード保護やファイアウォール設定を忘れずに行ってください。
依存関係
一部の高度な機能には、追加のPythonパッケージが必要です。
例えば、Docker監視にはdockerパッケージのインストールが必要になります。
他の監視ツールとの組み合わせ
Glancesは、他のツールと組み合わせることで、さらに強力になります。
Nagios/Zabbix
企業向けの本格的な監視システムと併用できます。
Glancesで日常的な監視を行い、重要なアラートは監視システムで管理するという使い分けですね。
Grafana
GlancesのデータをInfluxDBに送り、Grafanaで美しいダッシュボードを作成できます。
長期的なトレンド分析に最適です。
Ansible/Puppet
構成管理ツールで、複数のサーバーに一括でGlancesをインストール・設定できます。
まとめ:Glancesでシステム監視を快適に
Glancesは、システム管理者にとって必須のツールです。
この記事のポイント:
- Glancesはシステムリソースを一画面で表示する監視ツール
- CPU、メモリ、ディスク、ネットワークなど総合的に監視可能
- topやhtopより多機能で視覚的にも優れている
- 色分け表示で異常に気づきやすい
- Webインターフェースとリモート監視に対応
- Dockerコンテナの監視も可能
- REST APIで他のシステムと連携できる
- クロスプラットフォームで軽量
サーバー管理の現場では、「今何が起きているか」を素早く把握することが重要です。
Glancesを使えば、複雑なコマンドを覚えなくても、直感的にシステムの状態を理解できます。
インストールも使い方も簡単なので、今日からでもすぐに試せますよ。
ぜひGlancesを活用して、快適なサーバー管理ライフを送ってくださいね。