パソコンの電源を入れると、WindowsやLinuxが起動しますよね。でも、OSが起動する前に、実は重要な「準備作業」が行われているんです。
この準備作業を担当するのが、EFIシステムパーティション(ESP)という特別な領域。ハードディスクやSSDの中に確保された、「パソコンの玄関」のような存在です。
ESPがないと、最新のパソコンは起動できません。でも、普段は目に見えない場所にあるので、多くの人はその存在すら知らないかもしれません。
この記事では、EFIシステムパーティションの役割から、トラブル時の対処法まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
EFIシステムパーティション(ESP)って何?
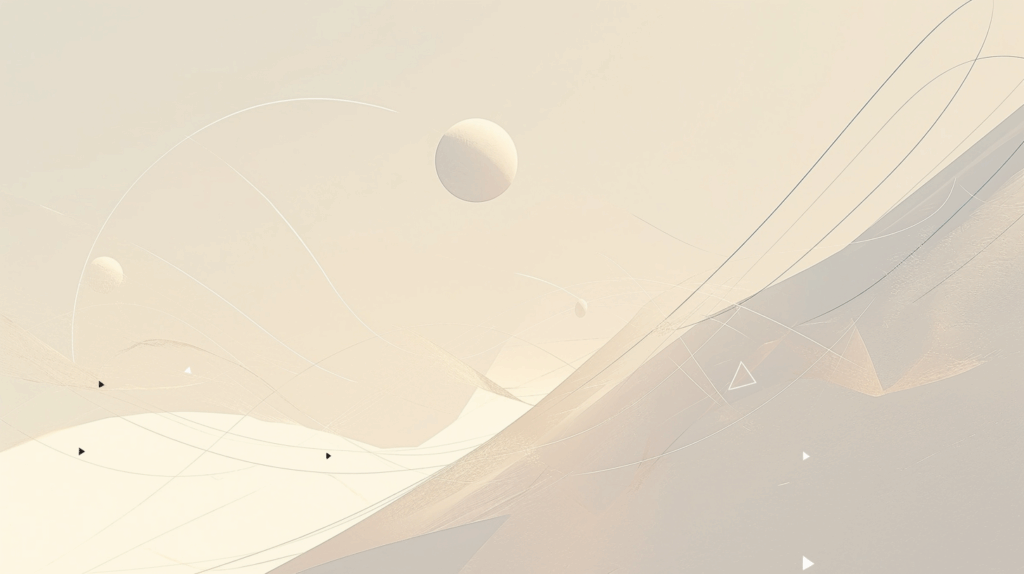
EFIシステムパーティション(ESP:EFI System Partition)は、UEFI対応のコンピュータで、起動に必要なファイルを保存する専用のパーティションです。
パーティションとは?
まず、「パーティション」について簡単に説明しましょう。
パーティションは、1つのハードディスクやSSDを、論理的にいくつかの区画に分けたものです。
たとえ:
500GBのハードディスクを、「Cドライブ300GB」と「Dドライブ200GB」に分けるイメージ。物理的には1台のディスクですが、論理的には2つの独立した領域として扱えます。
ESPの役割
ESPの主な役割:
- UEFIファームウェアが最初に読み込むファイルを保存
- ブートローダー(OSを起動するプログラム)を格納
- OSの起動に必要な設定情報を保持
- 複数OSのブートマネージャーを管理
つまり、「パソコンの電源を入れてからOSが起動するまでの橋渡し」をする場所なんです。
BIOSとUEFIの違い:時代の変化
ESPを理解するには、BIOSとUEFIの違いを知っておく必要があります。
BIOS時代(〜2010年頃)
BIOS(Basic Input/Output System)は、1980年代から使われてきた古い起動システムです。
特徴:
- 16ビットモードで動作
- 2TBまでのディスクしか扱えない
- 起動が遅い
- セキュリティ機能が弱い
- MBR(マスターブートレコード)を使用
BIOSでは、ディスクの最初の512バイトに起動情報を書き込んでいました。
UEFI時代(2010年頃〜現在)
UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)は、BIOSの後継として開発された新しい規格です。
特徴:
- 32ビット/64ビットモードで動作
- 2TB以上の大容量ディスクに対応
- 高速起動
- セキュアブート機能
- GPT(GUIDパーティションテーブル)を使用
- ESPを使用
UEFIでは、専用のパーティション(ESP)に起動ファイルを保存する方式に変わったんです。
なぜ変わったのか?
大容量ディスクへの対応
2TB以上のハードディスクが普及し、BIOSでは扱えなくなりました。
セキュリティの向上
マルウェアによるブートキットやルートキット攻撃を防ぐため、セキュアブート機能が必要になりました。
起動速度の改善
最新のハードウェア性能を活かすため、より効率的な起動方式が求められました。
ESPの構造と内容
ESPの中には、実際にどんなファイルが入っているのでしょうか。
基本的な仕様
ファイルシステム:FAT32またはFAT16
互換性を最優先するため、シンプルなFATファイルシステムが使われます。
推奨サイズ:
- 最小:100MB
- 推奨:200〜300MB
- Windows 11推奨:260MB以上
場所:
通常、ディスクの最初の方に配置されます。
ディレクトリ構造
ESPの中は、こんな構造になっています。
/EFI/
├── Boot/
│ └── bootx64.efi(デフォルトのブートローダー)
├── Microsoft/
│ └── Boot/
│ └── bootmgfw.efi(Windowsブートマネージャー)
├── ubuntu/
│ └── grubx64.efi(Ubuntuのブートローダー)
└── [その他のOS]各OSが自分専用のフォルダを持っています。
重要なファイル
bootx64.efi
UEFIが最初に実行するデフォルトのブートローダー。
bootmgfw.efi
Windowsのブートマネージャー。Windowsを起動する時に使います。
grubx64.efi
GRUB(Linuxでよく使われるブートローダー)の実行ファイル。
BCD(Boot Configuration Data)
Windows用の起動設定データベース。
GPTパーティションテーブルとの関係
ESPは、GPTパーティションテーブルと深い関係があります。
MBRとGPT
MBR(Master Boot Record)
BIOSで使われていた古いパーティション方式。
- 最大4つのプライマリパーティション
- 2TBまでのディスクに対応
- パーティション情報がディスクの先頭1箇所だけ
GPT(GUID Partition Table)
UEFIで使われる新しいパーティション方式。
- 実質無制限のパーティション数
- 大容量ディスクに対応
- パーティション情報がディスクの複数箇所に保存(冗長性)
- ESPが必須
GPTの構造
GPTディスクには、次のような構造があります。
- 保護MBR:古いツールとの互換性のため
- プライマリGPTヘッダー:パーティション情報
- EFIシステムパーティション(ESP):起動ファイル
- その他のパーティション:OSやデータ
- バックアップGPTヘッダー:冗長性のため
ESPは、GPT構造の中で特別な役割を持つパーティションなんです。
Windowsでの扱い

WindowsでESPがどう使われるか見てみましょう。
Windowsインストール時
Windowsをインストールすると、自動的にESPが作成されます。
作成されるパーティション:
- 回復パーティション(450MB程度)
- EFIシステムパーティション(100〜260MB)
- MSR(Microsoft Reserved)(16〜128MB)
- Windowsパーティション(残りの容量)
ESPは2番目に作成されるのが一般的です。
ESPの確認方法
通常、ESPはエクスプローラーに表示されません。確認するには:
ディスクの管理を使う:
- Windowsキー + X を押す
- 「ディスクの管理」を選択
- 「EFIシステムパーティション」と表示されている領域を確認
ドライブ文字は割り当てられていない
セキュリティのため、通常はドライブレターが付いていません。
ESPをマウントする方法
必要な場合、管理者権限で手動マウントできます。
コマンドプロンプト(管理者)で:
diskpart
list disk
select disk 0
list partition
select partition 1(ESPの番号)
assign letter=S
exitこれでSドライブとしてアクセスできるようになります。
注意:
不用意にファイルを削除すると、パソコンが起動しなくなります。十分注意してください。
Linuxでの扱い
Linux環境でのESPの扱いを見てみましょう。
マウントポイント
Linuxでは、ESPを/boot/efiにマウントするのが一般的です。
fstabエントリの例:
UUID=XXXX-XXXX /boot/efi vfat defaults 0 1インストール時の処理
既存のESPを使う
Windowsが既にインストールされている場合、同じESPを共有します。
新規ESPを作成
空のディスクにインストールする場合、新しいESPが作成されます。
GRUB2の配置
多くのLinuxディストリビューションは、GRUB2というブートローダーを使います。
ファイルの配置:
/boot/efi/EFI/ubuntu/grubx64.efi
/boot/efi/EFI/ubuntu/grub.cfgデュアルブート環境でのESP
WindowsとLinuxを両方インストールする場合、ESPはどうなるのでしょうか。
1つのESPを共有
通常、複数のOSで1つのESPを共有します。
構成例:
/EFI/
├── Boot/
│ └── bootx64.efi
├── Microsoft/
│ └── Boot/(Windowsブートマネージャー)
└── ubuntu/
└── grubx64.efi(Ubuntuブートローダー)各OSが自分専用のフォルダを持ち、互いに干渉しません。
ブートマネージャーの選択
UEFI ブートメニュー
パソコン起動時にF12やF2などのキーを押すと、起動するOSを選べます。
GRUBによる管理
Linuxをインストールすると、GRUBが全OSの起動メニューを管理してくれることが多いです。
注意点
Windowsの更新
Windows更新時に、ブート設定が変更され、Linuxが起動できなくなることがあります。その場合、Live USBから起動して修復が必要です。
OSの削除
一方のOSを削除する時は、ESPの該当フォルダだけを削除します。ESP自体は残します。
よくあるトラブルと対処法
ESPに関連するトラブルの解決方法です。
「No bootable device」エラー
症状:
起動時に「起動可能なデバイスが見つかりません」と表示される。
原因:
- ESPが破損している
- ブートローダーが削除された
- UEFI設定が間違っている
対処法:
Windowsの場合:
- インストールメディアから起動
- 「コンピューターを修復する」を選択
- 「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→「スタートアップ修復」
手動修復:
コマンドプロンプトで:
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcdESPが満杯になった
症状:
Windowsの更新に失敗する、または警告が出る。
原因:
古いブートファイルや回復ファイルが蓄積している。
対処法:
- ESPをマウント
- 古いバージョンのフォルダを削除(慎重に)
- 不要なブートエントリを削除
注意:
現在使用中のブートファイルは絶対に削除しないでください。
デュアルブート後にLinuxが起動しない
原因:
Windowsの更新でブート順序が変更された。
対処法:
UEFI設定で起動順序を変更:
- UEFI設定画面に入る(起動時にF2、Del、F12など)
- Boot順序の設定を開く
- Linuxのブートローダー(ubuntu、grubなど)を優先順位1に
またはGRUBを再インストール:
Live USBから起動して、grub-installコマンドを実行します。
ESPのバックアップと復元
重要なESPは、バックアップしておくと安心です。
バックアップ方法
Windowsの場合:
- ESPをマウント(前述の方法)
- ESP全体を別の場所にコピー
コマンド例:
robocopy S:\ C:\ESP_Backup /ELinuxの場合:
sudo mkdir /mnt/esp_backup
sudo mount /dev/sda1 /mnt/esp
sudo cp -a /mnt/esp/* /mnt/esp_backup/復元方法
バックアップから復元する時は、同様の手順で逆方向にコピーします。
注意:
- パーティションサイズが同じであること
- UUIDなどの識別子が変わる場合があること
ESPの削除や移動はできる?
基本的に、ESPは削除してはいけません。
削除するとどうなる?
パソコンが起動しなくなります。OSはディスク上に存在していても、起動する手段がないためです。
移動や再作成
必要なケース:
- ディスクを換装する時
- パーティション構成を変更する時
手順:
- 新しいESPパーティションを作成(FAT32、100MB以上)
- 古いESPの内容を新しいESPにコピー
- ブート設定を更新
専門知識が必要なので、慎重に行うか、専門家に相談してください。
最新のセキュリティ:セキュアブート
ESPとセキュアブートの関係を見てみましょう。
セキュアブートとは?
セキュアブートは、UEFI 2.3.1から導入されたセキュリティ機能です。
仕組み:
- ESPのブートローダーにデジタル署名が付いている
- UEFI起動時に署名を検証
- 正規の署名がないブートローダーは実行されない
目的:
マルウェアによるブートキット攻撃を防ぐ。
Windows 11とセキュアブート
Windows 11では、セキュアブートが必須要件になりました。
セキュアブートが有効でないと、Windows 11はインストールできません。
Linuxとセキュアブート
最近のLinuxディストリビューションは、セキュアブートに対応しています。
- Ubuntu 16.04以降
- Fedora 18以降
- openSUSE Leap 42.1以降
署名されたShimブートローダーを経由することで、セキュアブート環境でも動作するんです。
まとめ:ESPはパソコンの玄関
EFIシステムパーティションは、現代のパソコンに不可欠な存在です。
この記事のポイント:
- ESPはUEFI対応パソコンで起動ファイルを保存する専用領域
- BIOSからUEFIへの移行で生まれた仕組み
- FAT32でフォーマットされた100〜300MB程度の小さなパーティション
- 各OSが専用フォルダを持ち、ブートローダーを配置
- GPTパーティションテーブルと組み合わせて使う
- デュアルブート環境では1つのESPを共有
- 通常はユーザーから見えない場所にある
- 破損するとパソコンが起動しなくなる
- セキュアブートのセキュリティ基盤
- 定期的なバックアップが推奨される
ESPとの付き合い方:
- 普段は触らない
- トラブル時だけ対処
- 削除や変更は慎重に
- バックアップを忘れずに
ESPは「縁の下の力持ち」的な存在。普段は意識しませんが、パソコンが起動するたびに、黙々と重要な仕事をしてくれているんですね。







