「MBRって何?」
「GPTとMBRって何が違うの?」
「2TBを超えるディスクが使えないって本当?」
パソコンやサーバーのストレージ設定をしていると、こんな用語や疑問に出会うことがあります。
実は、MBR(Master Boot Record)は、コンピュータが起動する最初の一歩を担う重要な仕組みなんです。この記事では、MBRの基本から最新のGPTとの違いまで、初心者の方にも分かりやすく解説します。
読み終わる頃には、ディスクの起動メカニズムがしっかり理解できますよ!
MBR(Master Boot Record)とは?ディスクの「目次ページ」

MBR(Master Boot Record)とは、ハードディスクやSSDの最初の512バイトに書き込まれる特別なデータ領域のこと。
本で言えば「目次ページ」のようなもので、以下の情報が記録されています:
- パーティション情報(ディスクがどう分割されているか)
- ブートコード(OSを起動するための小さなプログラム)
- ブートシグネチャ(正しいMBRであることを示す印)
コンピュータの電源を入れると、BIOSやUEFIがまずこのMBRを読み込んで、どのパーティションからOSを起動するかを判断するんです。
MBRの構造:たった512バイトに詰まった重要情報
MBRは非常に小さな領域ですが、以下の3つの部分で構成されています。
1. ブートストラップコード(446バイト)
最初の446バイトには、ブートローダーの第一段階プログラムが格納されています。
役割:
アクティブ(起動可能)なパーティションを見つけて、そこに記録された次の段階のブートローダーに処理を渡すこと。
実例:
WindowsならNTLDR、LinuxならGRUBの最初の部分がここに入ります。
2. パーティションテーブル(64バイト)
続く64バイトには、ディスクのパーティション情報が記録されています。
記録内容:
- パーティションの開始位置
- パーティションのサイズ
- パーティションのタイプ
- ブートフラグ(起動可能かどうか)
重要な制限:
64バイトという制限のため、最大4つのプライマリパーティションしか作れません。
3. ブートシグネチャ(2バイト)
最後の2バイトには、固定値「0x55AA」が記録されています。
役割:
このMBRが有効であることを示す「印鑑」のようなもの。BIOSはこの値をチェックして、正しいMBRかどうかを判断します。
MBRのパーティションテーブル:4つの制限
MBRの大きな特徴(制約)が、パーティションの扱い方です。
プライマリパーティションは最大4つ
MBRでは、プライマリパーティションを最大4つまでしか作れません。
プライマリパーティションとは:
直接OSをインストールできる独立したパーティションのこと。
実例:
- パーティション1:Windows(C:ドライブ)
- パーティション2:Linux ルート(/)
- パーティション3:データ用
- パーティション4:バックアップ用
これで上限に達します。
拡張パーティションで制限を回避
4つ以上のパーティションが必要な場合は、拡張パーティションを使います。
仕組み:
- プライマリパーティションの1つを「拡張パーティション」として確保
- その中に複数の「論理パーティション」を作成
- 結果的に4つ以上のパーティションが使える
実例:
- パーティション1:Windows(プライマリ)
- パーティション2:Linux /(プライマリ)
- パーティション3:拡張パーティション
- 論理パーティション1:/home
- 論理パーティション2:/var
- 論理パーティション3:データ用
こうすれば、実質的に4つ以上使えます。
MBRの最大の制限:2TBの壁
MBRには、現代のストレージには厳しい制限があります。
2TBまでしか扱えない
MBRでは、2TB(テラバイト)を超えるディスク容量を認識できません。
原因:
パーティションテーブルが32ビットのアドレッシングを使っているため。セクタサイズ512バイトと組み合わせると、2^32 × 512バイト = 2TBが上限になります。
実例:
4TBのハードディスクをMBRでフォーマットすると、残りの2TBは使えない領域として無駄になってしまいます。
現代では大きな問題
最近のハードディスクは4TB、8TB、それ以上の容量が当たり前。MBRではこれらを有効活用できないんです。
GPT(GUID Partition Table)との違い
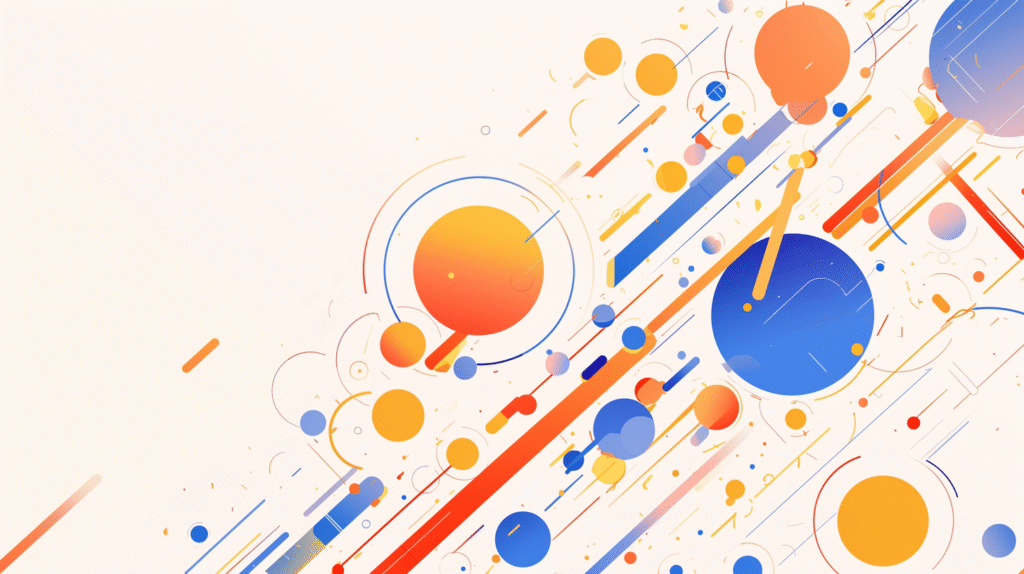
MBRの制限を克服するために登場したのがGPT(GUID Partition Table)です。
比較表
| 項目 | MBR | GPT |
|---|---|---|
| 最大ディスク容量 | 2TB | 9.4ZB(実質無制限) |
| パーティション数 | 4つ(拡張で増やせる) | 128個以上 |
| パーティション名 | なし | 名前を付けられる |
| データ保護 | 冗長性なし | バックアップあり |
| BIOS対応 | ○ | △(互換モードあり) |
| UEFI対応 | △(制限あり) | ◎ |
| 登場時期 | 1983年 | 2000年代 |
GPTの主な利点
1. 容量制限がほぼない
実質的に無制限の容量に対応。現代の大容量ディスクも問題なく使えます。
2. パーティション数が多い
標準で128個のパーティションを作成可能。実用上、制限を感じることはありません。
3. 冗長性がある
パーティション情報がディスクの先頭と末尾に二重保存されるため、一方が壊れても復旧できます。
4. CRCエラー検出
データの整合性をチェックする機能があり、破損を検出できます。
MBRとGPT、どちらを選ぶべき?
現代のシステムでは、基本的にGPT推奨です。
GPTを選ぶべきケース(ほとんどの場合)
- 2TB以上のディスクを使う
- UEFIシステム(2010年以降のPC)
- Windows 11(GPT必須)
- 現代的なLinuxディストリビューション
- 将来性を重視
MBRを選ぶ必要があるケース(限定的)
- 古いBIOSシステム(2010年以前のPC)
- Windows XP以前のOS
- 一部の古い機器との互換性が必要
- 2TB以下の小容量ディスクで互換性重視
MBRの確認方法
自分のシステムがMBRかGPTか確認してみましょう。
Windows での確認方法
方法1:ディスクの管理
- 「Win + X」キーを押す
- 「ディスクの管理」を選択
- ディスクを右クリック→「プロパティ」
- 「ボリューム」タブで「パーティションのスタイル」を確認
方法2:コマンドプロンプト
diskpart
list diskGPTディスクには「*」マークが「GPT」列に表示されます。
Linux での確認方法
方法1:fdiskコマンド
sudo fdisk -l出力例(MBR):
Disklabel type: dos出力例(GPT):
Disklabel type: gpt「dos」と表示されたらMBR、「gpt」と表示されたらGPTです。
方法2:gdiskコマンド
sudo gdisk -l /dev/sdaMBRの場合、「MBR: MBR only」と表示されます。
方法3:partedコマンド
sudo parted /dev/sda print「Partition Table」の行に「msdos」(MBR)か「gpt」が表示されます。
MBRからGPTへの変換
MBRディスクをGPTに変換することもできます。
Windows での変換(データ消去なし)
Windows 10/11では、MBR2GPTツールが使えます。
注意:
Windows 10 バージョン1703以降が必要です。
手順:
- 管理者としてコマンドプロンプトを開く
- 以下のコマンドを実行
mbr2gpt /validate /disk:0
mbr2gpt /convert /disk:0「/disk:0」の数字は、変換したいディスク番号に変更してください。
重要:
- データはそのまま残りますが、念のためバックアップ推奨
- BIOS設定をUEFIモードに変更する必要あり
Linux での変換
gdiskを使う方法:
sudo gdisk /dev/sdagdisk内で「w」コマンドを実行すると、MBRをGPTに変換できます。
注意:
データが消える可能性があるため、必ずバックアップを取ってから実行してください。
MBRのトラブルシューティング
MBRが破損すると、システムが起動しなくなります。
問題:起動時に「Operating System not found」
原因:
MBRのブートコードが破損しています。
解決方法(Windows):
- Windowsインストールメディアから起動
- 「コンピューターを修復する」を選択
- 「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→「コマンドプロンプト」
- 以下のコマンドを実行
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /rebuildbcd解決方法(Linux):
- LiveUSBから起動
- ターミナルを開く
- GRUBを再インストール
sudo mount /dev/sda1 /mnt
sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda
sudo update-grub問題:パーティションが認識されない
原因:
パーティションテーブルが破損しています。
解決方法:
TestDiskという無料ツールを使って、パーティションテーブルを復旧できます。
sudo apt install testdisk
sudo testdisk画面の指示に従って、失われたパーティションを検索・復元します。
MBRのバックアップと復元
万が一に備えて、MBRのバックアップを取っておくことをおすすめします。
Linux でのバックアップ
MBR全体をバックアップ:
sudo dd if=/dev/sda of=mbr-backup.img bs=512 count=1このコマンドで、MBR全体(512バイト)を「mbr-backup.img」として保存します。
パーティションテーブルのみバックアップ:
sudo sfdisk -d /dev/sda > partition-table-backup.txtテキスト形式でパーティション情報を保存します。
復元方法
MBRを復元:
sudo dd if=mbr-backup.img of=/dev/sda bs=512 count=1パーティションテーブルを復元:
sudo sfdisk /dev/sda < partition-table-backup.txtMBRの歴史と今後
MBRの誕生
MBRは1983年にIBM PC DOS 2.0で初めて導入されました。当時のハードディスクは数十MBという時代。2TBの制限なんて、誰も想像できなかったんです。
40年以上の活躍
それから40年以上、MBRはコンピュータ業界の標準として活躍してきました。シンプルで信頼性が高く、互換性も抜群でした。
GPTへの移行
しかし、ストレージの大容量化に伴い、MBRの限界が明らかに。
2000年代にGPTが登場し、現在は主流がGPTに移りつつあります。
Windows 11では、GPTが必須要件になっており、MBRの時代は終わりつつあると言えるでしょう。
よくある質問
Q1. MBRディスクにWindowsとLinuxをデュアルブートできる?
はい、できます。ただし、プライマリパーティションの制限(4つまで)に注意が必要です。拡張パーティションを使えば、複数のOSをインストールできます。
Q2. MBRはSSDでも使える?
技術的には可能ですが、現代のSSDは容量が大きいため、GPTを使う方が適切です。特に512GB以上のSSDではGPT推奨です。
Q3. MBRが破損する原因は?
主な原因は以下の通りです:
- ウイルス感染
- 不適切なシャットダウン
- ディスクの物理的な障害
- パーティション編集ソフトの誤操作
Q4. ハイブリッドMBR/GPTって何?
GPTディスクに互換性のためのMBR情報も記録する方式。古いBIOSシステムからも起動できるようにする手法ですが、推奨されません。
まとめ:MBRの理解がディスク管理の第一歩
MBR(Master Boot Record)は、コンピュータ起動の基礎となる重要な仕組みです。
MBRの重要ポイント:
- ディスクの最初の512バイトに記録
- ブートコード、パーティションテーブル、シグネチャで構成
- 最大4つのプライマリパーティション
- 2TBまでの容量制限
MBRの制限:
- 2TB以上のディスクが使えない
- パーティション数が少ない
- データ保護機能がない
- 古い技術(1983年登場)
GPTとの比較:
- GPT:実質無制限の容量、128個以上のパーティション、冗長性あり
- MBR:2TB制限、4パーティション、シンプル
推奨:
- 新しいシステム:GPT
- 古いBIOSシステム:MBR
- 2TB以上のディスク:必ずGPT
確認方法:
- Windows:ディスクの管理、diskpartコマンド
- Linux:fdisk -l、gdisk、partedコマンド
40年以上の歴史を持つMBRですが、現代のストレージ環境ではGPTへの移行が進んでいます。ただし、MBRの仕組みを理解しておくことは、ディスク管理やトラブルシューティングに役立ちます。
自分のシステムがどちらを使っているか確認して、適切に管理していきましょう!
安定したシステム運用を!







