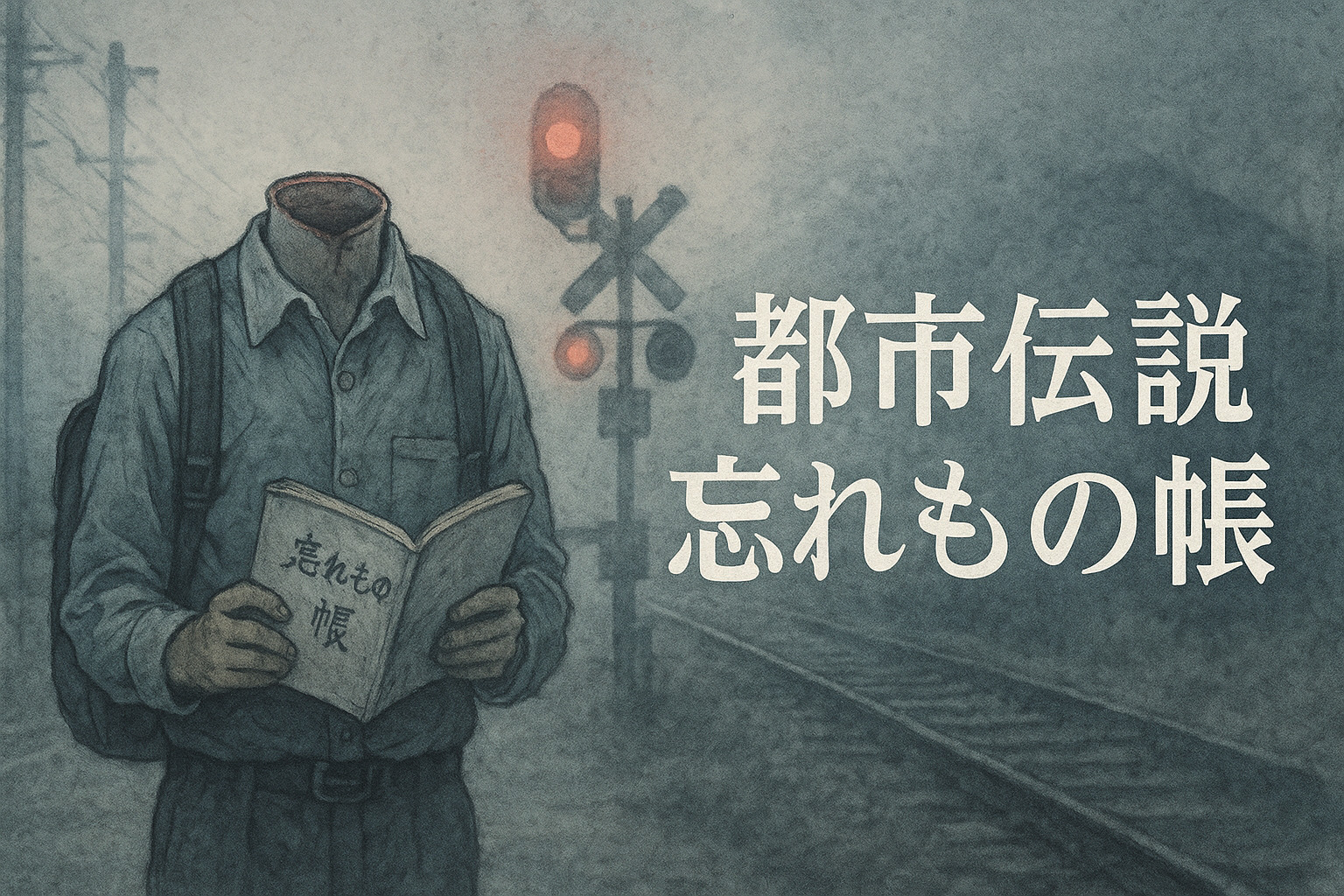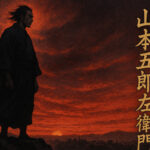あなたは学校に行くとき、忘れ物をしないようにメモを取ったことはありますか?
忘れ物を減らすための工夫は、誰もがやったことがあるはずです。
でも、ある少年が使っていた「忘れもの帳」には、最後に恐ろしい一文が残されていました。
この記事では、日本で語り継がれる現代の怖い都市伝説「忘れもの帳」について詳しくご紹介します。
概要

忘れもの帳は、現代日本で語り継がれる都市伝説の一つなんです。
北海道のある市で起きたとされる、小学2年生の少年をめぐる悲しい事故の話として知られています。
忘れ物ばかりする少年のために用意された一冊のノートが、最終的に不気味な予言のようなメッセージを残すことになった物語です。
『学校の怪談』シリーズなどで紹介され、子どもたちの間で広まった怖い話として、今でも語り継がれています。
伝承
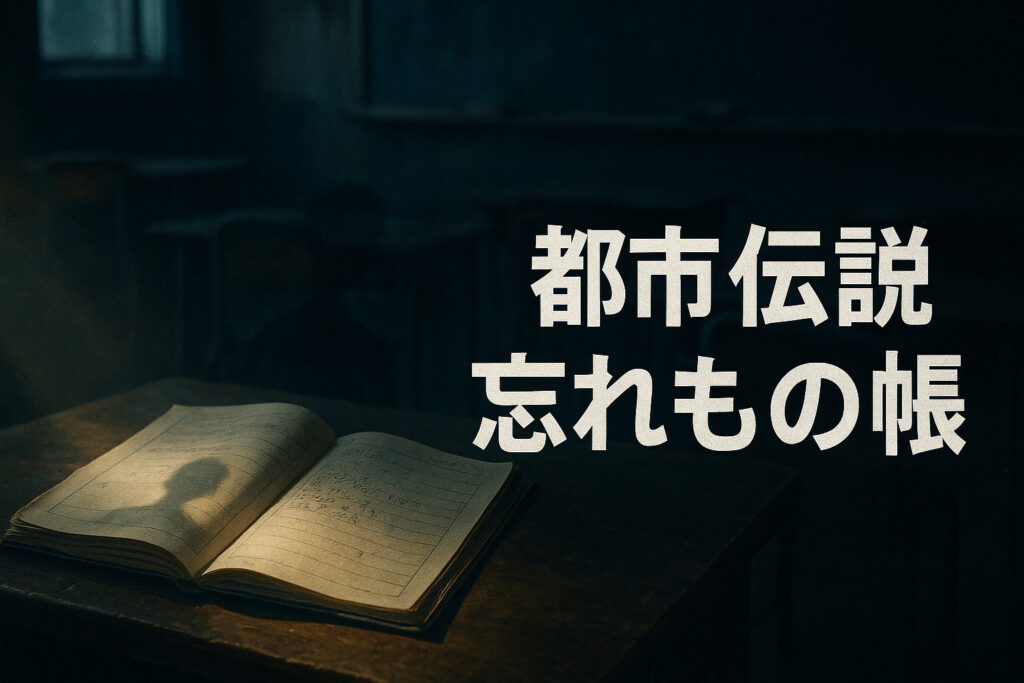
忘れもの帳の物語は、一人の小学生から始まります。
忘れ物が多い少年
ある小学校に通う2年生の男の子は、毎日必ず何かを忘れてしまう子どもでした。
教科書、筆箱、体操着…本当に毎日何かを学校に持ってくるのを忘れていたんです。
困った担任の先生と母親は話し合って、一つの解決策を考え出しました。
「忘れもの帳」の誕生
それが「忘れもの帳」と表紙に大きく書かれたノートでした。
このノートの使い方はシンプルです。
忘れもの帳の使い方
- 翌日学校に持っていくものを前日に書く
- 朝、家を出る前にノートを確認する
- 忘れ物があったらノートに記録する
この方法が功を奏して、少年の忘れ物は少しずつ減っていきました。
先生も母親も、これで一安心だと思っていたんですね。
運命の朝
ところが、ある日の朝のことです。
少年は登校の途中で、体操着を忘れたことに気づいてしまいました。
急いで家に引き返そうと走り出しましたが、途中の踏切で遮断機が下り始めていたんです。
学校に遅刻したくない。そう思った少年は、危険を承知で遮断機をくぐり抜けようとしました。
悲劇の瞬間
しかし、線路に足を引っかけて転んでしまったのです。
電車が完全に止まったのは、踏切をかなり過ぎてからでした。
事故の直後、すぐに遺体の回収が行われましたが、不思議なことがありました。
少年の頭部だけが、どこにも見つからなかったのです。
残されたメッセージ
数日後、母親が少年の持ち物を整理していると、ランドセルの中からあの忘れもの帳が出てきました。
何気なくページをめくった母親は、最後のページを見て凍りつきました。
そこには少年の字で、こう書かれていたんです。
「わすれもの:ぼくのあたま」
少年は一体いつ、この文字を書いたのでしょうか。
事故の後に書けるはずがありません。でも、事故の前に書いていたとしたら…?
今も少年の頭部は見つかっていないといいます。
まとめ
忘れもの帳は、日常的な習慣が恐怖につながる現代の都市伝説です。
重要なポイント
- 北海道のある市で起きたとされる都市伝説
- 忘れ物が多い小学2年生の少年の物語
- 忘れもの帳によって忘れ物は減っていった
- 踏切事故で少年が亡くなり、頭部だけが見つからなかった
- ノートの最後に「わすれもの:ぼくのあたま」と書かれていた
- 『学校の怪談』シリーズで広く知られるようになった
誰もが経験する忘れ物という身近なテーマだからこそ、この話は多くの人の心に残り続けているのかもしれませんね。