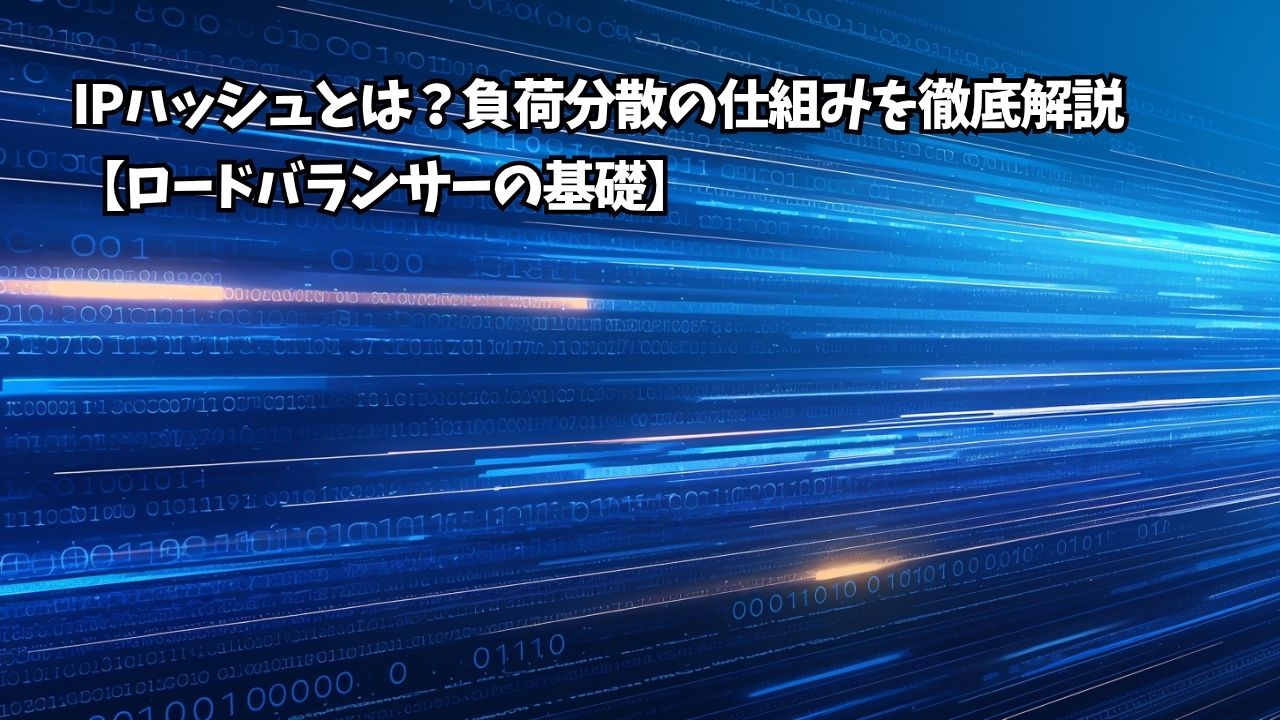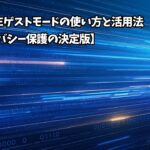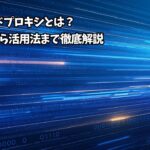「大量のアクセスを複数のサーバーで分散させたいけど、どうすればいい?」
「ロードバランサーの設定で『IPハッシュ』って出てきたけど、何のこと?」
Webサイトやアプリケーションの規模が大きくなると、1台のサーバーでは処理しきれなくなってきます。そこで登場するのが「負荷分散」という技術です。
その中でも、IPハッシュは重要な負荷分散方式の一つ。セッション維持が必要なシステムで、非常に役立つ仕組みなんです。
この記事では、IPハッシュの基本から実際の活用方法、他の方式との違いまで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます!
IPハッシュとは?基本を理解しよう

一言で説明すると
IPハッシュとは、クライアントのIPアドレスを元にして、接続先のサーバーを決定する負荷分散方式です。
同じIPアドレスからのアクセスは、常に同じサーバーに振り分けられるのが最大の特徴になります。
身近な例で考えてみよう
スーパーのレジを想像してください。
通常の負荷分散(ラウンドロビン方式):
- お客さんが来るたびに「1番レジ、2番レジ、3番レジ」と順番に案内
- 1回目は1番レジ、2回目は2番レジに並ぶ
IPハッシュ方式:
- お客さんの顔(IPアドレス)を覚えておく
- 同じお客さんが来たら、必ず同じレジ番号に案内
- 1回目も2回目も、ずっと1番レジに並ぶ
この「同じ人を同じ場所に案内する」仕組みが、IPハッシュなんです。
IPハッシュの仕組み
ハッシュ関数って何?
まず、「ハッシュ」という言葉を理解しましょう。
ハッシュ関数とは、入力されたデータを一定の規則で変換して、固定長の数値や文字列を生成する仕組みです。
具体例:
入力:192.168.1.100(IPアドレス)
↓ ハッシュ関数で計算
出力:3475892(ハッシュ値)同じ入力からは、必ず同じ出力が得られます。これがポイントです!
IPハッシュの処理フロー
実際の動作を見ていきましょう。
ステップ1:クライアントからリクエストが来る
ユーザーがWebサイトにアクセスします。クライアントのIPアドレスは「192.168.1.100」だとしましょう。
ステップ2:ロードバランサーがIPアドレスをハッシュ化
ロードバランサーは、このIPアドレスをハッシュ関数で計算します。
hash(192.168.1.100) = 3475892ステップ3:サーバー番号を算出
利用可能なサーバーが3台ある場合、ハッシュ値をサーバー数で割った余り(剰余)を使います。
3475892 % 3 = 1結果は「1」なので、サーバー1番に接続されます。
ステップ4:次回も同じサーバーへ
同じIPアドレスから再度アクセスがあると:
- 同じハッシュ値が計算される
- 同じ剰余が得られる
- 結果として同じサーバーに接続される
こうして、セッションの継続性が保たれるんです。
IPハッシュのメリット
1. セッションの維持が簡単
最大のメリットは、セッション維持が自動的にできることです。
セッション維持が必要なケース:
- ログイン状態の保持
- ショッピングカートの内容
- アップロード中のファイル処理
- ゲームのプレイ状態
サーバー側でセッション情報を共有する仕組みがなくても、同じサーバーに接続されるため問題ありません。
2. 設定がシンプル
他のセッション維持方法(スティッキーセッション)と比べて、設定が簡単です。
不要な設定:
- Cookieの管理
- セッションIDの追跡
- データベースでのセッション共有
IPアドレスだけを見れば良いので、実装がシンプルになります。
3. パフォーマンスへの影響が小さい
ハッシュ計算は非常に高速なため、ロードバランサーへの負荷がほとんど増えません。
大量のトラフィックを処理する場合でも、パフォーマンスの低下を心配する必要はないでしょう。
4. 予測可能な動作
どのIPアドレスがどのサーバーに接続されるかが、計算で決まります。
トラブルシューティング時に、特定のユーザーがどのサーバーを使っているか追跡しやすいのもメリットです。
IPハッシュのデメリット
1. 負荷が偏る可能性
クライアントのIPアドレス分布によって、特定のサーバーに負荷が集中することがあります。
偏りが発生するケース:
- 特定のプロキシサーバー経由のアクセスが多い
- 企業ネットワークからの大量アクセス
- モバイルキャリアのIPアドレス帯域が限定的
完全に均等な負荷分散にはならない点に注意が必要です。
2. 動的なIPアドレスへの対応
モバイルユーザーなど、IPアドレスが頻繁に変わる環境では効果が薄れます。
IPアドレスが変わると:
- 別のサーバーに振り分けられる
- セッションが切れる
- 再ログインが必要になる
Wi-Fiとモバイルネットワークを切り替えたりすると、この問題が起こりやすいでしょう。
3. サーバー増減時の影響
サーバーを追加・削除すると、ハッシュ値の計算結果が変わってしまいます。
例:3台→4台に増やした場合
元の計算:hash値 % 3 = 1(サーバー1)
新しい計算:hash値 % 4 = 3(サーバー3)同じユーザーが異なるサーバーに接続され、セッションが切れる可能性があります。
4. 地理的な最適化が難しい
IPアドレスだけで判断するため、サーバーの地理的な位置を考慮できません。
日本のユーザーが海外のサーバーに接続されてしまう、といった非効率が起こる可能性があるんです。
他のロードバランシング方式との比較

ラウンドロビン方式
仕組み:
リクエストを順番に各サーバーへ振り分けます。
メリット:
- 最もシンプル
- 完全に均等な分散
デメリット:
- セッション維持ができない
- 同じユーザーが毎回別サーバーに接続される
向いているケース:
セッション情報を持たない静的コンテンツの配信
最小接続方式(Least Connections)
仕組み:
その時点で最も接続数が少ないサーバーに振り分けます。
メリット:
- 実際の負荷に応じた分散
- サーバー性能差に対応できる
デメリット:
- セッション維持の仕組みが別途必要
- ロードバランサーの処理が複雑
向いているケース:
処理時間がリクエストごとに大きく異なるアプリケーション
重み付けラウンドロビン
仕組み:
サーバーごとに重み(優先度)を設定し、その比率で分散します。
メリット:
- サーバー性能差を考慮できる
- 段階的なサーバー追加が可能
デメリット:
- 設定が複雑
- セッション維持は別途必要
向いているケース:
性能が異なる複数世代のサーバーを混在させる場合
IPハッシュとCookieベースの比較
Cookieベースのスティッキーセッション:
- ブラウザのCookieでサーバーを識別
- IPアドレス変更に強い
- Cookieが無効だと動作しない
IPハッシュ:
- IPアドレスで識別
- Cookieに依存しない
- IPアドレス変更に弱い
用途に応じて使い分けることが重要です。
IPハッシュの実装例
Nginx での設定
Nginxは人気のあるWebサーバー兼ロードバランサーです。
設定例:
http {
upstream backend {
ip_hash;
server 192.168.1.10:80;
server 192.168.1.11:80;
server 192.168.1.12:80;
}
server {
listen 80;
location / {
proxy_pass http://backend;
}
}
}ポイント:
ip_hash;の一行を追加するだけ- upstreamブロック内に記述
- とてもシンプルな設定
HAProxy での設定
HAProxyも広く使われているロードバランサーです。
設定例:
frontend http-in
bind *:80
default_backend servers
backend servers
balance source
server server1 192.168.1.10:80 check
server server2 192.168.1.11:80 check
server server3 192.168.1.12:80 checkポイント:
balance sourceがIPハッシュに相当- sourceはクライアントのIPアドレスを意味する
AWS Elastic Load Balancer での設定
AWSのApplication Load Balancer(ALB)でも使えます。
設定方法:
- ターゲットグループの設定で「スティッキーセッション」を有効化
- スティッキータイプで「アプリケーションベースのCookie」または「期間ベースのCookie」を選択
- または、Network Load Balancer(NLB)でフローハッシュアルゴリズムを使用
AWSでは純粋なIPハッシュより、Cookieベースのセッション維持が推奨されています。
IPハッシュの活用シーン
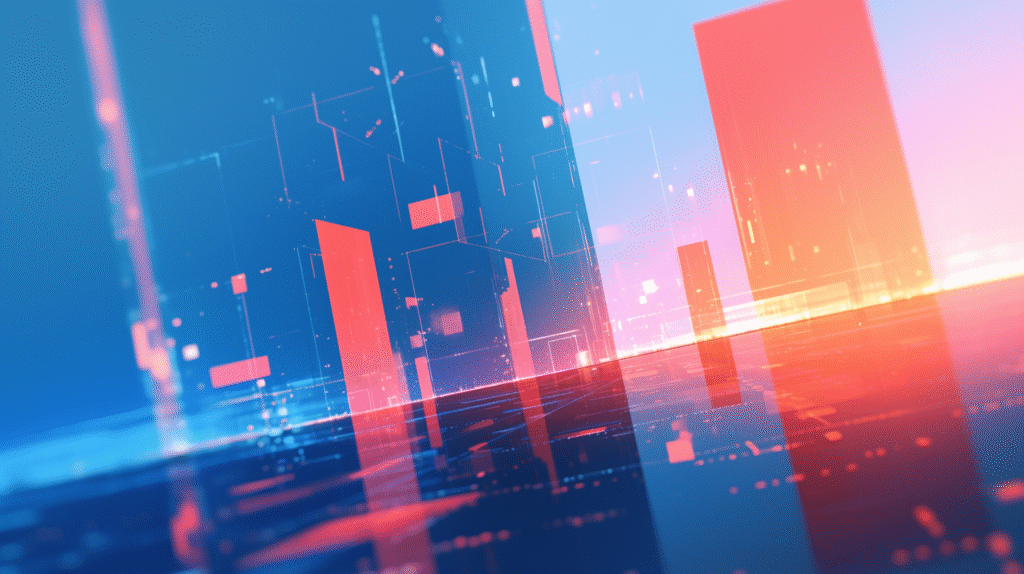
ケース1:オンラインショッピングサイト
課題:
ユーザーがカートに商品を入れた状態を維持したい
IPハッシュの活用:
- 同じユーザーは常に同じサーバーに接続
- カート情報がサーバーのメモリに保持される
- データベース共有が不要で高速
ケース2:オンラインゲーム
課題:
プレイヤーのゲーム状態を維持しながら、負荷分散したい
IPハッシュの活用:
- プレイヤーごとに専用のサーバーに接続
- ゲーム状態の整合性を保つ
- リアルタイム性を確保
ケース3:Webアプリケーションのセッション管理
課題:
ログイン状態を維持しつつ、複数サーバーで運用したい
IPハッシュの活用:
- セッション情報をサーバーローカルに保存
- データベースへのアクセスを減らせる
- レスポンス速度が向上
ケース4:アップロードの継続処理
課題:
大きなファイルのアップロード中、同じサーバーで処理を続けたい
IPハッシュの活用:
- アップロード中も同じサーバーに接続
- 一時ファイルの管理が簡単
- 処理の中断リスクが減る
トラブルシューティング
特定のサーバーだけ負荷が高い
原因:
IPアドレスの分布が偏っている可能性があります。
対処法:
- クライアントのIPアドレス分布を分析
- 必要に応じて別のアルゴリズムに変更
- ハッシュ関数を変更(可能な場合)
サーバー追加後にセッションが切れる
原因:
サーバー台数が変わると、ハッシュ計算の結果が変わります。
対処法:
- メンテナンス時間帯にサーバー追加を実施
- 一貫性ハッシュ(Consistent Hashing)の採用を検討
- 段階的な移行計画を立てる
モバイルユーザーのセッションが不安定
原因:
モバイル環境ではIPアドレスが頻繁に変わります。
対処法:
- Cookieベースのセッション維持に変更
- セッション情報をデータベースで共有
- Redis などの分散キャッシュを利用
一貫性ハッシュとの違い
一貫性ハッシュ(Consistent Hashing)とは
IPハッシュの進化版とも言える技術です。
特徴:
- サーバー増減時の影響を最小化
- 再配置されるキー(接続)が少ない
- 大規模分散システムに適している
仕組み:
ハッシュ空間を円(リング)として考え、サーバーとクライアントを配置します。サーバーが増減しても、影響を受けるのは隣接する範囲だけになるんです。
どちらを選ぶべき?
通常のIPハッシュが適している:
- 小〜中規模のシステム
- サーバー台数が固定的
- シンプルさを優先
一貫性ハッシュが適している:
- 大規模分散システム
- サーバーの頻繁な追加・削除
- スケーラビリティを重視
多くの一般的なWebアプリケーションでは、通常のIPハッシュで十分対応できます。
よくある質問
Q1. IPv6でもIPハッシュは使えますか?
はい、使えます。
IPv6アドレスも同様にハッシュ化できるため、問題なく動作します。ただし、IPv6はアドレス空間が非常に広いため、より均等な分散が期待できるでしょう。
Q2. プロキシサーバー経由のアクセスはどうなりますか?
プロキシサーバーのIPアドレスで判断されます。
そのため、同じプロキシを使っている複数のユーザーが、全て同じサーバーに振り分けられる可能性があります。負荷が偏る原因になるので注意が必要です。
Q3. IPハッシュとセッションアフィニティの違いは?
セッションアフィニティは広い概念で、「セッションを特定のサーバーに固定する仕組み全般」を指します。
IPハッシュは、セッションアフィニティを実現する方法の一つです。他にもCookieベース、URLパラメータベースなどがあります。
Q4. サーバーがダウンした場合はどうなりますか?
ダウンしたサーバーに割り当てられていたクライアントは、別のサーバーに再配置されます。
その結果、セッション情報は失われる可能性があります。ヘルスチェック機能と組み合わせて、異常なサーバーを自動的に除外する設定が重要です。
Q5. ハッシュ関数は変更できますか?
ロードバランサーの実装によります。
Nginxなどでは基本的に固定されていますが、HAProxyなどでは異なるハッシュアルゴリズムを選択できる場合があります。
まとめ:IPハッシュで効率的な負荷分散を実現
IPハッシュについて、基礎から実践まで詳しく解説してきました。
重要ポイントのおさらい:
- IPハッシュはセッション維持に最適
同じIPアドレスを常に同じサーバーに振り分ける - 設定がシンプルで導入しやすい
Nginxなら1行追加するだけで実装可能 - メリットとデメリットを理解する
負荷の偏りやサーバー増減時の影響に注意 - 用途に応じて他の方式と使い分け
静的コンテンツならラウンドロビン、モバイル対応ならCookieベース - 大規模システムでは一貫性ハッシュも検討
頻繁なスケーリングが必要なら進化版を選択
IPハッシュは、シンプルながら強力な負荷分散方式です。セッション維持が必要なWebアプリケーションで、データベース共有の複雑さを避けたい場合に特におすすめします。
この記事を参考に、あなたのシステムに最適なロードバランシング方式を選んでくださいね!