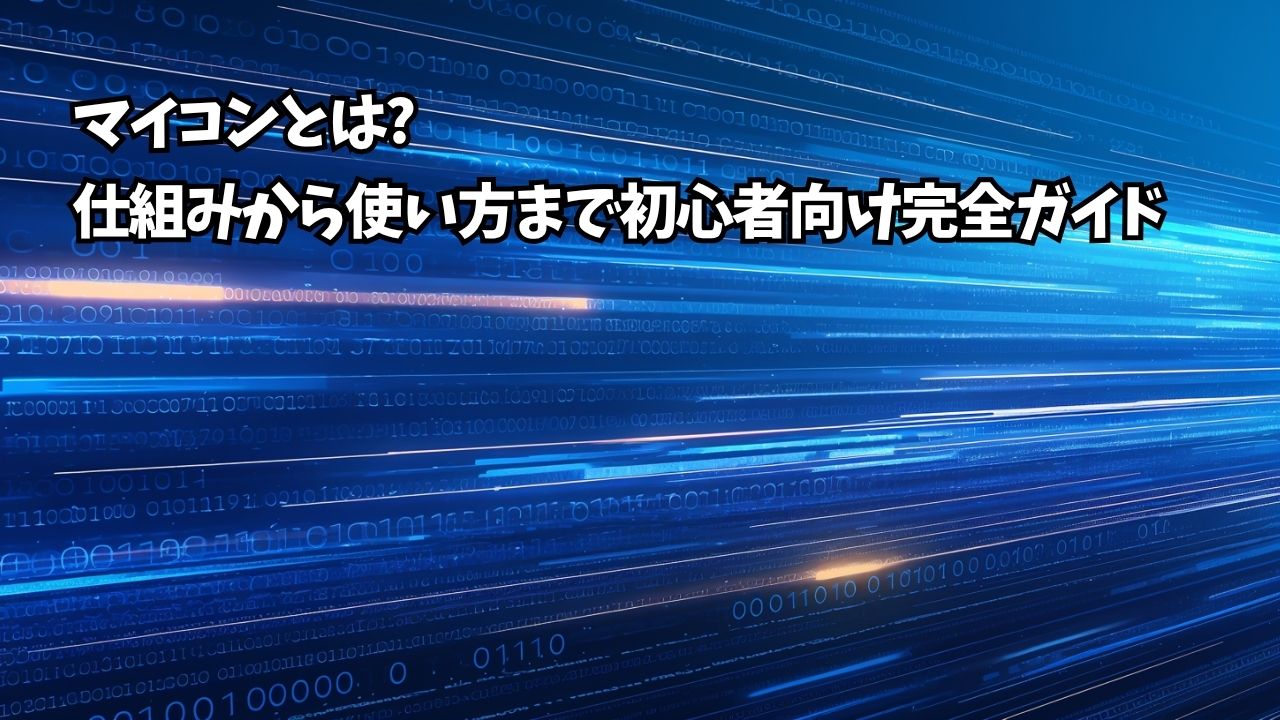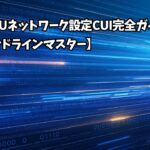「マイコン」という言葉、聞いたことはありますか?
家電製品、自動車、スマホ、ゲーム機など、私たちの身の回りにある電子機器のほとんどに、実はマイコンが組み込まれています。目には見えませんが、現代社会を支える重要な技術なんですよ。
「でも、マイコンって難しそう…」と思うかもしれませんね。確かに専門的な分野ですが、基本を理解すれば、初心者でも電子工作やIoTデバイス作りに挑戦できるんです。
この記事では、マイコンの基礎知識から実際の使い方まで、分かりやすく丁寧に解説していきます。
マイコンとは?基本を理解しよう

マイコンの正式名称と定義
マイコンは「マイクロコンピュータ」または「マイクロコントローラー」の略称です。英語では「MCU(Micro Controller Unit)」と呼ばれます。
簡単に言うと
マイコンは、小さなコンピュータが1つのチップに収まったものです。
身近な例で説明
あなたの部屋にあるエアコンのリモコンを想像してください。
ボタンを押すと、エアコンが反応して温度を変えたり、風量を調整したりしますよね。
この「ボタンの信号を受け取って、適切な動作を実行する」という処理をしているのがマイコンなんです。
マイコンとパソコンの違い
どちらもコンピュータですが、役割が大きく違います。
パソコン(PC)の特徴
- 汎用性が高い(いろいろなことができる)
- ワード、ゲーム、動画編集など多目的
- 高性能なCPU、大容量メモリ、ストレージを搭載
- OSが必要(WindowsやmacOS)
- 価格が高い(数万円~)
マイコンの特徴
- 特定の用途に特化(一つの仕事をする)
- センサーの値を読む、モーターを動かすなど
- 低消費電力、小型、安価
- OSは不要(プログラムを直接実行)
- 価格が安い(数百円~数千円)
例え話
パソコンは万能なスイスアーミーナイフのようなもの。
マイコンは特定の作業に特化した専用工具のようなものですね。
マイコンとマイクロプロセッサ(CPU)の違い
これも混同しやすいポイントです。
マイクロプロセッサ(CPU)
- 計算処理を行う「頭脳」だけ
- メモリやI/O(入出力)機能は外部に必要
- パソコンやスマホに使われる
- 例:Intel Core、AMD Ryzen
マイコン(MCU)
- CPU + メモリ + I/O機能が1チップに統合
- これだけで動作できる
- 組み込み機器に使われる
- 例:Arduino、PICマイコン
分かりやすい比喩
マイクロプロセッサは「料理人」だけ。
マイコンは「料理人+キッチン+調理器具」が全部セットになった「ミニキッチン」です。
マイコンの仕組みと構造
マイコンの基本構成要素
マイコンは、以下の要素が1つのチップに詰まっています。
CPU(中央処理装置)
- プログラムを実行する頭脳
- 計算や判断を行う
- 動作速度はクロック周波数で表される(例:16MHz、48MHz)
メモリ
マイコンには2種類のメモリがあります。
- ROM(フラッシュメモリ)
- プログラムを保存する場所
- 電源を切っても消えない
- 容量:数KB~数MB
- RAM(作業用メモリ)
- プログラム実行中のデータを一時保存
- 電源を切ると消える
- 容量:数百バイト~数百KB
I/O(入出力)ポート
外部デバイスと通信するための端子です。
- GPIO(汎用入出力)
- LEDを光らせる、ボタンの状態を読むなど
- デジタル信号(0または1)を扱う
- アナログ入力(ADC)
- センサーのアナログ信号をデジタル値に変換
- 温度センサー、光センサーなどの読み取り
- PWM(パルス幅変調)
- モーターの速度制御
- LEDの明るさ調整
通信インターフェース
他のデバイスと通信するための機能です。
- UART(シリアル通信)
- I2C(アイ・スクエア・シー)
- SPI(エスピーアイ)
- USB
- 無線通信(Wi-Fi、Bluetooth)
これらが揃って、初めてマイコンとして機能するんですよ。
マイコンの動作原理
マイコンがどのように動くのか、順を追って説明しますね。
ステップ1:プログラムの書き込み
- パソコンでプログラムを作成
- コンパイル(人間の言葉→機械語に翻訳)
- マイコンのROMに書き込む
ステップ2:電源投入
- マイコンに電源を供給
- CPUがROMからプログラムを読み込む
- プログラムの実行開始
ステップ3:プログラム実行
- センサーから値を読み取る
- 読み取った値を判断・計算
- 結果に応じて出力を制御
- 1に戻って繰り返し
この繰り返しが、1秒間に何万回も行われています。
クロック周波数と処理速度
マイコンの性能を表す重要な指標です。
クロック周波数とは
CPUが1秒間に何回動作するかを示す値で、Hz(ヘルツ)という単位で表します。
- 16MHz = 1秒間に1600万回動作
- 48MHz = 1秒間に4800万回動作
- 100MHz = 1秒間に1億回動作
高いほど良い?
必ずしもそうではありません。
高速なマイコン
- 複雑な処理ができる
- リアルタイム性が求められる用途に向く
- 消費電力が大きい
- 価格が高い
低速なマイコン
- シンプルな制御に十分
- 省電力で電池駆動に最適
- 価格が安い
用途に応じて選ぶことが大切ですよ。
マイコンの用途と応用例

家電製品での利用
身近な家電製品のほとんどにマイコンが使われています。
エアコン
- 室温センサーで温度を監視
- 設定温度との差を計算
- コンプレッサーやファンを制御
電子レンジ
- ボタン入力を受け付け
- タイマーをカウント
- マグネトロンの出力制御
洗濯機
- 水位センサーの監視
- 洗濯コースに応じた制御
- モーターの回転制御
炊飯器
- 温度センサーで加熱状態を監視
- 炊飯プロセスの自動制御
- タイマー機能
テレビ・エアコンのリモコン
- ボタン入力の検出
- 赤外線信号の送信
マイコンがなければ、現代の便利な家電は成り立ちませんね。
自動車での利用
現代の自動車には、数十個から100個以上のマイコンが搭載されています。
エンジン制御(ECU)
- 燃料噴射量の制御
- 点火タイミングの調整
- 排気ガスの浄化制御
安全装置
- ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)
- エアバッグの展開制御
- 衝突回避システム
快適装置
- パワーウィンドウ
- 自動ドアロック
- カーナビゲーション
- オーディオシステム
先進運転支援システム(ADAS)
- 自動ブレーキ
- 車線維持支援
- アダプティブクルーズコントロール
自動車の安全性と快適性は、マイコン技術の進化によって支えられています。
IoTデバイスとスマート家電
最近話題のIoT(Internet of Things)でも、マイコンが中心的な役割を果たしています。
スマートスピーカー
- 音声認識
- 家電の制御
- インターネット接続
スマート照明
- スマホから明るさ・色を調整
- タイマー設定
- 音声コントロール
ウェアラブルデバイス
- スマートウォッチ
- フィットネストラッカー
- 健康モニタリング
スマート家電
- 外出先からエアコンをON
- 冷蔵庫の中身をスマホで確認
- ロボット掃除機の遠隔操作
IoT時代の到来で、マイコンの需要はますます高まっていますよ。
産業機器とロボット
産業の現場でも、マイコンは欠かせません。
工場の自動化
- 産業用ロボットの制御
- コンベアラインの管理
- 品質検査装置
医療機器
- 血圧計、体温計
- 人工呼吸器
- MRI、CTスキャナー
計測器
- オシロスコープ
- デジタルマルチメーター
- 温度データロガー
農業IoT
- 自動水やりシステム
- 温室の環境制御
- ドローンによる農薬散布
あらゆる産業分野で、マイコンが活躍しているんですね。
代表的なマイコンの種類
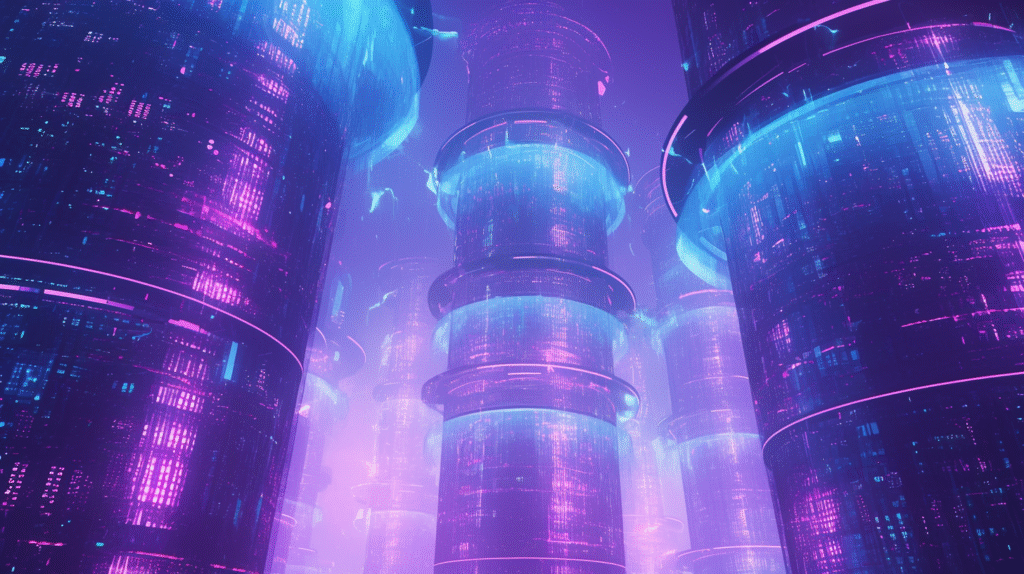
Arduino(アルドゥイーノ)
初心者に最も人気のあるマイコンボードです。
特徴
- 初心者でも扱いやすい
- 開発環境が無料で使いやすい
- 豊富なライブラリとサンプルコード
- 世界中にユーザーコミュニティがある
- 拡張ボード(シールド)が豊富
代表的なモデル
- Arduino Uno
- 最も標準的なモデル
- 価格:約3,000円
- メモリ:32KB ROM、2KB RAM
- Arduino Nano
- 小型版
- ブレッドボードに直接挿せる
- Arduino Mega
- より多くのピンとメモリ
- 大規模なプロジェクト向け
向いている用途
- 電子工作の入門
- プロトタイプ作成
- 教育目的
PICマイコン
Microchip社製の定番マイコンです。
特徴
- 産業用途で広く使用
- 種類が豊富(数百種類)
- 低消費電力
- 価格が安い(数百円から)
- プログラミングがやや難しい
代表的なシリーズ
- PIC16F:8ビット、エントリーモデル
- PIC18F:8ビット、中級モデル
- PIC24F:16ビット、高性能モデル
- PIC32:32ビット、最高性能
向いている用途
- 製品の量産
- 組み込みシステム開発
- 産業機器
ESP32/ESP8266
Wi-Fi/Bluetooth内蔵の人気マイコンです。
特徴
- Wi-Fi、Bluetoothが標準搭載
- 低価格(500円~1,000円程度)
- Arduino IDEで開発可能
- IoTプロジェクトに最適
- 処理能力が高い
ESP8266
- Wi-Fi専用
- シンプルで低価格
- IoT入門に最適
ESP32
- Wi-Fi + Bluetooth対応
- より高性能
- センサーも豊富
向いている用途
- IoTデバイス開発
- スマート家電の自作
- ホームオートメーション
STM32
STMicroelectronics社製の高性能マイコンです。
特徴
- ARM Cortexコア採用
- 高性能・高機能
- 産業用途で信頼性が高い
- 価格は中程度
- やや上級者向け
代表的なシリーズ
- STM32F0:エントリーモデル
- STM32F1:バランス型
- STM32F4:高性能モデル
- STM32H7:最高性能
向いている用途
- 高度な制御が必要なプロジェクト
- リアルタイム処理
- プロフェッショナルな開発
Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi財団が開発したマイコンボードです。
特徴
- 独自チップ「RP2040」搭載
- 低価格(約550円)
- Python、C/C++で開発可能
- デュアルコア(2つのCPU)
- GPIO端子が豊富
Raspberry Piとの違い
- Raspberry Pi = 小型PC(Linux動作)
- Raspberry Pi Pico = マイコン(プログラム直接実行)
用途が全く異なるので注意してくださいね。
マイコンのプログラミング
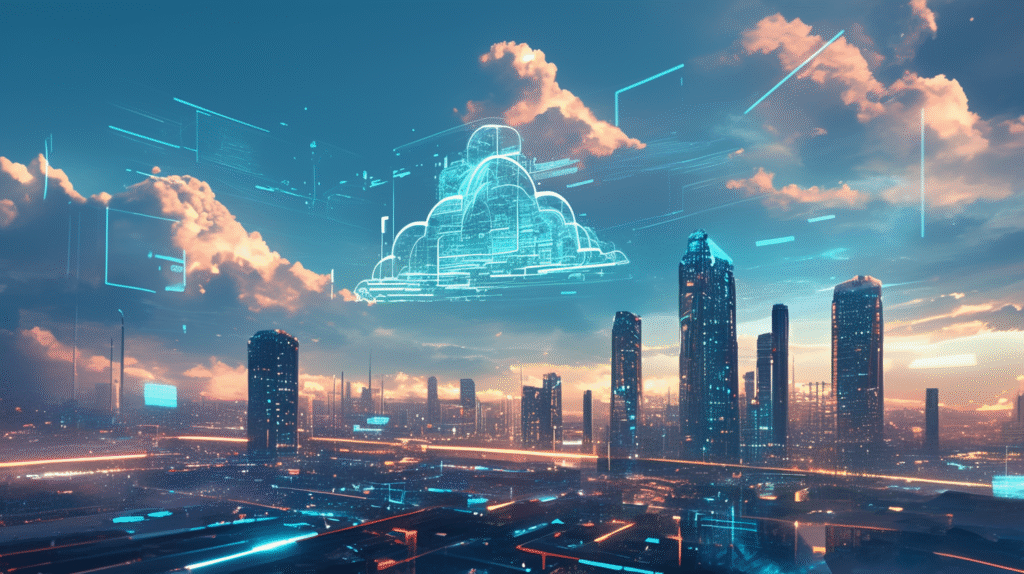
開発に必要なもの
マイコンでプログラミングを始めるために必要なものをまとめました。
ハードウェア
- マイコンボード
- Arduino Unoなど初心者向けモデル
- パソコン
- Windows、Mac、Linux対応
- USBケーブル
- マイコンとPCを接続
- ブレッドボード
- 部品をはんだ付けせずに配線できる基板
- 電子部品
- LED、抵抗、スイッチなど
ソフトウェア
- 開発環境(IDE)
- Arduino IDE(Arduino用、無料)
- PlatformIO(多機能、無料)
- STM32CubeIDE(STM32用、無料)
- ドライバ
- マイコンボードに応じてインストール
プログラミング言語
マイコンで使われる主な言語です。
C言語
- 最も一般的
- 高速で効率的
- メモリを細かく制御できる
- 学習には時間がかかる
C++言語
- Cの拡張版
- Arduinoの標準言語
- オブジェクト指向が使える
- Cより書きやすい
Python(MicroPython)
- 書きやすくて分かりやすい
- ESP32、Raspberry Pi Picoで使える
- 処理速度はC/C++より遅い
- 初心者に優しい
アセンブリ言語
- 機械語に最も近い低レベル言語
- 最速で最小メモリ
- 非常に難しい
- 特殊な用途のみ
初心者はC++(Arduino)かPython(MicroPython)から始めるのがおすすめですよ。
基本的な開発の流れ
実際にプログラムを書いて動かすまでの手順です。
ステップ1:開発環境のセットアップ
- Arduino IDEをダウンロード
- インストールして起動
- ボードとポートを設定
ステップ2:プログラムを書く
簡単なLED点滅プログラムの例:
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT); // 13番ピンを出力モードに設定
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // LEDを点灯
delay(1000); // 1秒待つ
digitalWrite(13, LOW); // LEDを消灯
delay(1000); // 1秒待つ
}プログラムの説明
setup()= 最初に1回だけ実行される初期設定loop()= 繰り返し実行されるメイン処理pinMode()= ピンの入出力を設定digitalWrite()= ピンにHIGH(5V)またはLOW(0V)を出力delay()= 指定時間(ミリ秒)だけ待つ
ステップ3:コンパイルと書き込み
- 「検証」ボタンでエラーチェック
- 「マイコンボードへ書き込む」ボタンをクリック
- 数秒でプログラムが転送される
ステップ4:動作確認
書き込みが完了すると、自動的にプログラムが実行されます。LEDが1秒ごとに点滅すれば成功です!
よく使う関数と機能
Arduinoでよく使う基本的な関数をまとめました。
デジタル入出力
pinMode(pin, mode); // ピンを入力/出力に設定
digitalWrite(pin, value); // HIGHまたはLOWを出力
int value = digitalRead(pin); // ピンの状態を読み取るアナログ入力
int value = analogRead(pin); // アナログ値(0~1023)を読むPWM出力
analogWrite(pin, value); // 0~255の値でPWM出力シリアル通信
Serial.begin(9600); // シリアル通信開始
Serial.println("Hello"); // 文字列を送信時間制御
delay(ms); // ミリ秒待つ
delayMicroseconds(us); // マイクロ秒待つ
millis(); // 起動からの経過時間(ミリ秒)これらを組み合わせて、さまざまな動作を実現できますよ。
初心者向けの始め方
まずは何から始めるべき?
マイコン初心者が最初に踏むべきステップです。
ステップ1:入門キットを購入
個別に部品を揃えるより、スターターキットがおすすめです。
Arduino入門キット(約5,000円)の内容例
- Arduino Unoボード
- ブレッドボード
- ジャンパーワイヤー
- LED(複数色)
- 抵抗、スイッチ
- センサー(温度、光など)
- サーボモーター
- チュートリアル本
ステップ2:開発環境をセットアップ
- Arduino IDEをインストール
- ドライバをインストール(必要な場合)
- ボードを接続して認識を確認
ステップ3:サンプルプログラムを試す
いきなり自分でプログラムを書くのではなく、まずはサンプルを動かしてみましょう。
Arduino IDEには、たくさんのサンプルが付属しています。
- ファイル → スケッチ例 → 01.Basics → Blink
- プログラムが開く
- 書き込んで実行
LEDが点滅すれば成功です!
ステップ4:少しずつカスタマイズ
サンプルを改造して、動きを変えてみましょう。
- 点滅の速度を変える(delay値を変更)
- 点滅パターンを変える(モールス信号など)
- 複数のLEDを制御する
遊びながら学ぶのが、上達への近道ですよ。
おすすめの学習リソース
独学でマイコンを学ぶためのリソースです。
書籍
- 「Arduinoをはじめよう」(オライリー・ジャパン)
- 「たのしくできるArduino電子工作」(東京電機大学出版局)
- 「これ1冊でできる!Arduinoではじめる電子工作 超入門」
Webサイト
- Arduino公式サイト(チュートリアル豊富)
- Instructables(世界中のプロジェクト例)
- Qiita(日本語の技術情報)
動画
- YouTube「Arduino入門」で検索
- Udemy(有料だが体系的に学べる)
コミュニティ
- Arduino Forum(公式フォーラム)
- Stack Overflow(技術Q&A)
- Twitter(#Arduino で情報交換)
分からないことがあっても、すぐに調べられる環境が整っていますよ。
よくある初心者の失敗
失敗例を知っておくと、トラブルを避けられます。
失敗1:配線ミス
- 電源(VCCとGND)を逆に接続
- 抵抗を付け忘れてLEDが壊れる
- ショートさせてマイコンが壊れる
対策
- 配線図を丁寧に確認
- 電源を入れる前に再チェック
- 抵抗値の計算を確認
失敗2:プログラムのミス
- セミコロン(;)の付け忘れ
- 括弧の対応が間違っている
- 変数名のスペルミス
対策
- IDEのエラーメッセージを読む
- サンプルコードを参考にする
- 一行ずつデバッグ
失敗3:部品の破損
- 電圧が高すぎてLEDが焼ける
- 静電気でICが壊れる
- 極性のある部品を逆接続
対策
- データシートで定格を確認
- 予備の部品を用意しておく
- ゆっくり慎重に作業
失敗は学びのチャンスです。めげずに挑戦してくださいね。
よくある質問(FAQ)
Q1:マイコンとRaspberry Piの違いは?
A:
役割が全く異なります。
マイコン(Arduino等)
- 単一の処理に特化
- リアルタイム制御が得意
- 低消費電力
- OSなしで動作
- 価格が安い(数百円~)
Raspberry Pi
- 小型のパソコン
- Linux OSが動作
- 複雑な処理が可能
- 消費電力が大きい
- 価格が高い(数千円~)
センサー制御ならマイコン、画像処理やWebサーバーならRaspberry Piが向いています。
Q2:プログラミング初心者でも大丈夫?
A:
はい、大丈夫です。
Arduinoは、プログラミング初心者でも始められるように設計されています。
おすすめの進め方
- サンプルコードを動かす
- 少しずつ数値を変えて動作を確認
- 他のサンプルと組み合わせる
- 自分のアイデアを実現
プログラミングスキルは、作りながら自然と身についていきますよ。
Q3:電子工作の知識がなくても始められる?
A:
基本的な知識があると安全ですが、学びながら進めることもできます。
最低限知っておきたいこと
- 電圧と電流の違い
- 抵抗の役割と計算方法
- LED、センサーの基本
- 配線の基本ルール
入門書や動画で学びながら、実際に手を動かすのが効率的です。
Q4:どのマイコンを選べばいい?
A:
目的によって選びましょう。
電子工作を始めたい
→ Arduino Uno(定番、情報が豊富)
IoTデバイスを作りたい
→ ESP32(Wi-Fi内蔵、低価格)
小型のプロジェクト
→ Arduino Nano、Raspberry Pi Pico
産業用途や量産
→ PICマイコン、STM32
最初はArduino Unoから始めるのが無難ですよ。
Q5:マイコンでできないことは?
A:
マイコンは万能ではありません。
苦手なこと
- 複雑な画像処理
- 大量のデータ処理
- 高度なAI処理
- Webブラウザの表示
- 動画再生
こうした処理には、Raspberry Piやパソコンのほうが適しています。マイコンは「シンプルで高速なリアルタイム制御」が得意分野です。
Q6:マイコンは何度でも書き換えられる?
A:
はい、基本的に何度でも書き換え可能です。
フラッシュメモリは、数万回~数十万回の書き換えに耐えられます。通常の使い方なら、寿命を気にする必要はありませんよ。
ただし、一部の古いマイコンには書き換え回数に制限があるものもあります。
まとめ:マイコンで広がる可能性
マイコンは、小さいながらも無限の可能性を秘めたデバイスです。
この記事のポイント
- マイコンは小型のコンピュータチップ
- 家電、自動車、IoTなど幅広い分野で活躍
- Arduinoなら初心者でも簡単に始められる
- C++やPythonでプログラミング可能
- 入門キット(約5,000円)で今すぐスタートできる
- 失敗を恐れず実践しながら学ぶのが上達の近道
マイコンを学ぶメリット
- 電子工作が楽しめる
- IoTデバイスを自作できる
- プログラミングスキルが身につく
- 就職・転職に役立つスキル
- アイデアを形にできる