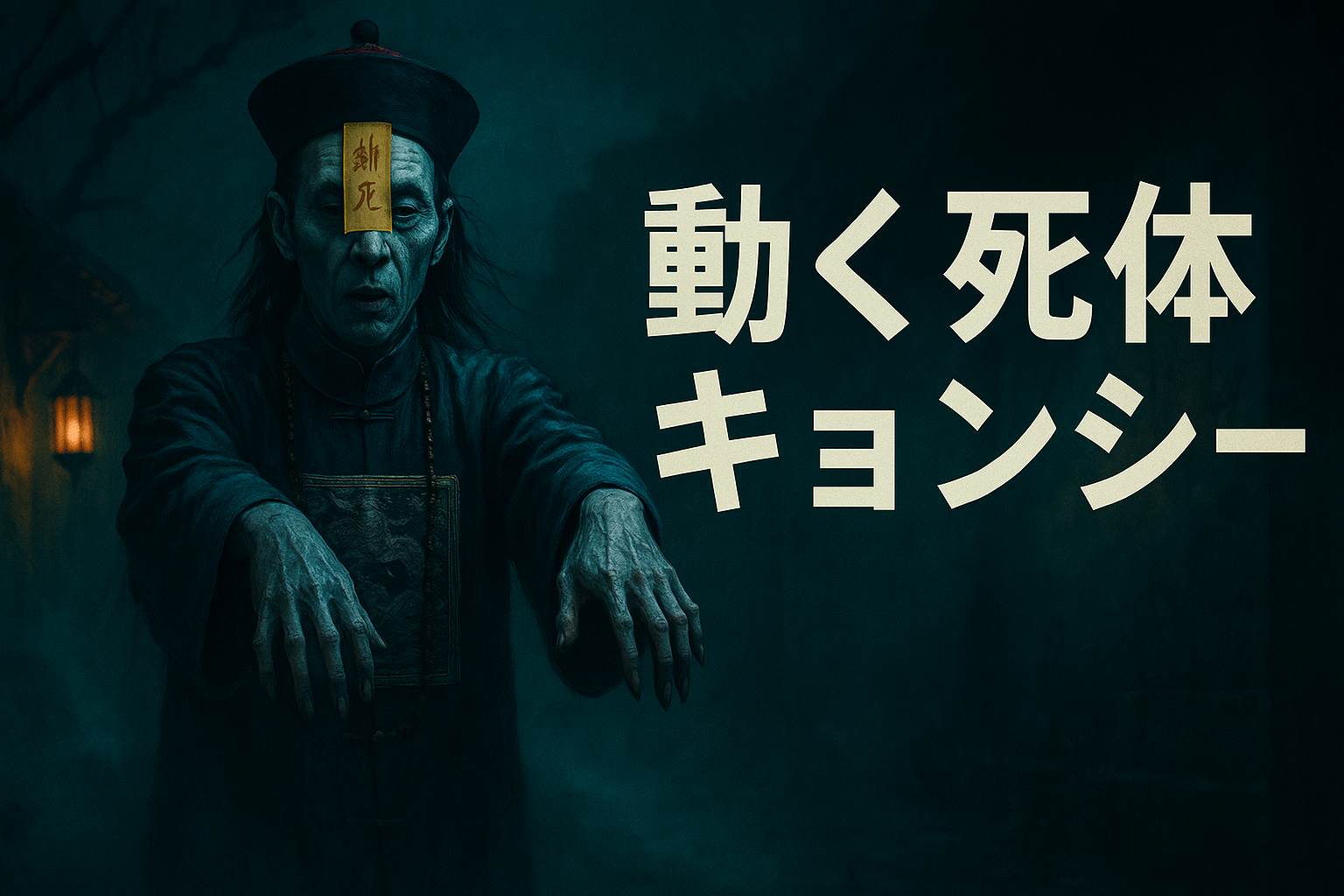夜道で、両手を前に突き出してぴょんぴょん跳ねる死体に出会ったら、どうしますか?
中国には、そんな恐ろしい動く死体の言い伝えが古くから存在していました。
その名は「キョンシー」(僵尸)。死んでもなお動き続け、人間の血を求めてさまよう不死の怪物です。でも、額にお札を貼れば動きが止まるという不思議な弱点も持っているんです。
この記事では、中国で生まれ、アジア全体で恐れられた動く死体「キョンシー」について、その独特な姿と恐ろしい伝承をご紹介します。
概要

キョンシー(僵尸/殭屍)は、中国の伝承に登場する動く死体の妖怪です。
中国語では「ジャンシー」と発音し、「僵」は「硬直した」、「尸(屍)」は「死体」を意味します。つまり、硬直したまま動き回る死体という意味なんですね。
キョンシーは普通のゾンビとは違い、死んでから長い年月が経っても腐らずに動き続けるという特徴があります。しかも、ただの死体ではなく、人間の生気(気)を吸い取ったり、血を求めて襲いかかったりする恐ろしい存在として恐れられてきました。
特に有名になったのは、1980年代の香港映画『霊幻道士』シリーズです。この映画によって、お札で動きを封じられる、ぴょんぴょん跳ねて移動するという独特のイメージが広まり、日本でも大ブームになったんです。
姿・見た目
キョンシーの姿は、とても特徴的で一度見たら忘れられません。
キョンシーの外見的特徴
- 服装:清朝時代の官服(黒い帽子と青や黒の長い衣装)
- 顔色:青白い、または緑がかった肌
- 髪:長く伸びた黒髪(時には辮髪)
- 爪:異常に長く伸びた爪
- 額のお札:呪文が書かれた黄色い紙(符)が貼られている
- 腕の位置:両手を前方に真っ直ぐ伸ばしている
キョンシーが清朝の官服を着ているのには理由があります。当時の中国では、庶民でも死後の世界での出世を願って、葬儀の際に官服を着せる習慣があったんです。
また、死後硬直で関節が曲がらないため、腕を前に突き出したままの姿勢になっています。この独特の姿勢がキョンシーの最大の特徴といえるでしょう。
時間が経つと、全身から緑色の毛が生えてきたり、より恐ろしい姿に変化することもあるといわれています。
特徴

キョンシーには、普通の妖怪とは違う独特の性質があるんです。
キョンシーの能力と性質
- 跳ねて移動:膝が曲がらないため、ぴょんぴょん跳ねて進む
- 怪力:人間よりはるかに強い力を持つ
- 不死身:普通の武器では倒せない
- 血を求める:人間の首筋に噛みついて血を吸う
- 感染能力:噛まれた人間もキョンシーになってしまう
- 夜行性:日光を浴びると燃えたり溶けたりする
キョンシーが人間を感知する方法
実は、キョンシーは目が見えていません。では、どうやって人間を見つけるのでしょうか?
答えは「息」です。キョンシーは人間が吐く息を嗅覚で感知して襲ってくるんです。だから、息を止めていれば見つからないといわれています。ただし、口が開いていると口臭で見つかってしまうので要注意!
キョンシーの弱点
- お札(符):額に貼ると動けなくなる
- もち米:生のもち米をかけると弱る
- 鏡:自分の姿を映されるのを嫌がる
- 鶏の鳴き声:朝を告げる鶏の声で逃げ出す
- 桃の木:桃の木で作った剣や杭が効果的
- 黒犬の血:黒い犬の血をかけると弱体化する
伝承
キョンシーにまつわる伝説は、中国の長い歴史の中で数多く語り継がれてきました。
キョンシーになる原因
なぜ死体がキョンシーになるのか、いくつかの理由が伝えられています。
- 風水的に正しく埋葬されなかった
- 恨みを抱いて死んだ人の怨念が残った
- 道士(道教の術師)が呪術で死体を操った
- 雷に打たれた死体が蘇った
- 黒猫が棺の上を飛び越えた
湘西の死体運び
キョンシー伝説の起源として有名なのが、中国湖南省西部の「趕屍(死体運び)」という風習です。
清朝時代、多くの労働者が故郷から遠く離れた場所で働いていました。もし亡くなった場合、遺体を故郷まで運ぶ必要がありましたが、距離が遠すぎて困難でした。
そこで、道士と呼ばれる術師が呪術を使って死体を「歩かせて」運んだという伝説が生まれたんです。実際には、竹の棒に死体を縛り付けて、二人で担いで運んでいました。竹がしなって上下に動くと、遠くから見ると死体が跳ねているように見えたのです。
道士とキョンシー
道士(どうし)は、道教の修行を積んだ術師で、キョンシーを操ることができる唯一の存在とされています。
道士は黄色い紙に呪文を書いた「符(ふ)」を使ってキョンシーを操ります。また、鈴を鳴らしながら先導することで、キョンシーを目的地まで導くこともできました。
しかし、力を持った悪い道士がキョンシーを悪用することもあり、そんな時は別の正義の道士が桃の木の剣や特別な呪文を使って退治したといいます。
文学作品での記述
清朝時代の志怪小説(不思議な話を集めた本)には、キョンシーの話が数多く残されています。
『子不語』という本には20近くのキョンシー物語があり、『聊斎志異』にも死体が動き出す話が収録されています。さらに有名な『西遊記』にも、白骨夫人というキョンシーのような妖怪が登場し、孫悟空と戦う場面があるんです。
起源
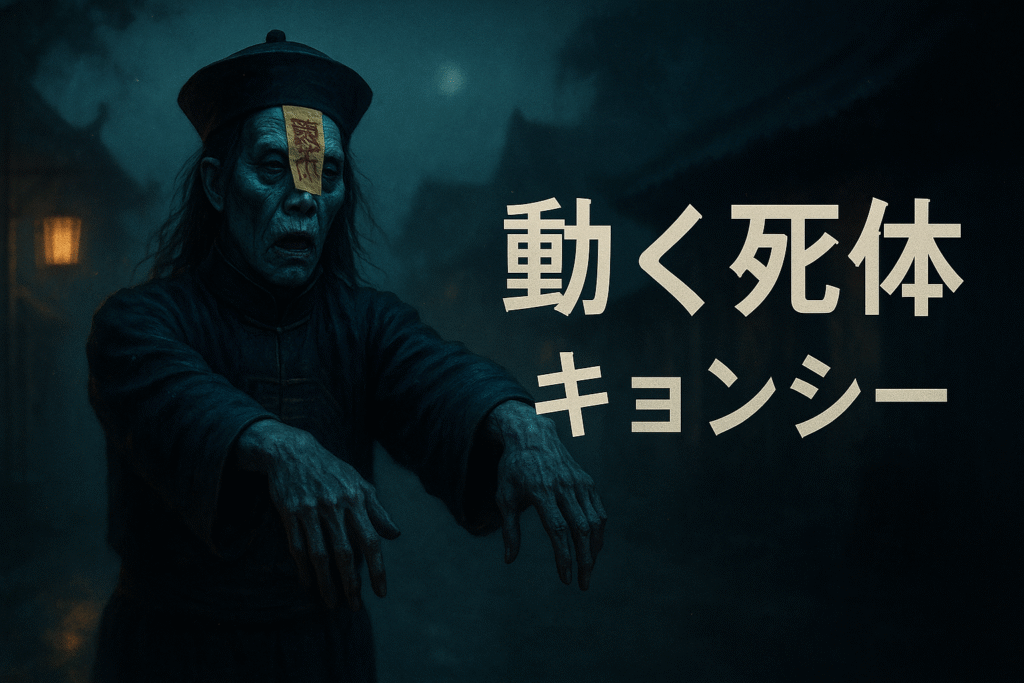
キョンシー伝説は、どのようにして生まれたのでしょうか。
自然現象からの恐怖
中国では古くから、埋葬前の死体が突然動き出すという言い伝えがありました。
これは、死後硬直や腐敗ガスによる死体の動きを見た人々が、恐怖から生み出した伝説だと考えられています。特に、乾燥した地域では死体がミイラ化して長期間保存されることがあり、これが「腐らない死体」という概念につながったようです。
道教思想の影響
道教では、人間には「三魂七魄(さんこんしちはく)」という魂があると考えられています。
魂(こん)は善良で知的な部分、魄(はく)は肉体に宿る悪い部分とされ、人が死んで魂が離れても魄が残ると、その死体がキョンシーになるという考え方が生まれました。
社会的背景
清朝時代、多くの出稼ぎ労働者が故郷から離れた場所で亡くなりました。
中国では「故郷の土に埋葬されないと魂が安らかにならない」という強い信仰があったため、遺体を運ぶ「死体運び」という職業が生まれました。夜中に死体を運ぶ不気味な光景が、キョンシー伝説を生み出す土壌となったのです。
映画による再創造
現在私たちが知っているキョンシーのイメージは、1980年代の香港映画によって作られた部分が大きいんです。
特に『霊幻道士』シリーズは、伝統的な中国の妖怪伝承にカンフーアクションとコメディを加えて、新しいキョンシー像を作り出しました。ぴょんぴょん跳ねる動き、お札で止まる設定、道士との戦いなど、映画オリジナルの要素が今では定番となっています。
まとめ
キョンシーは、死への恐怖と故郷への想いが生み出した中国独特の妖怪です。
重要なポイント
- 中国の伝承に登場する硬直した動く死体
- 清朝時代の官服を着て、腕を前に伸ばした姿
- ぴょんぴょん跳ねて移動し、息で人間を感知
- お札(符)を額に貼ると動きが止まる
- 血を吸い、噛まれた人間もキョンシーになる
- 湘西地方の死体運びの風習が起源の一つ
- 道士だけが操ったり退治したりできる
- 1980年代の映画で世界的に有名になった
キョンシーは単なる怪物ではなく、故郷に帰れずに亡くなった人々の悲しみや、死後の世界への恐れが形となった存在といえるでしょう。恐ろしくもあり、どこか哀しさも感じさせる、東洋独特の妖怪なのです。