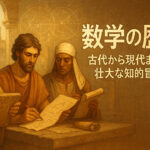泉や滝から聞こえる美しい歌声に、心を奪われたことはありますか?
ヨーロッパの伝承では、その歌声の主は「ウンディーネ」という水の精霊だと信じられてきました。
彼女たちは魂を持たない存在でしたが、人間の男性と恋に落ちることで、初めて魂を手に入れることができたといいます。
この記事では、切ない恋物語で知られる美しき水の精霊「ウンディーネ」について、詳しくご紹介します。
概要
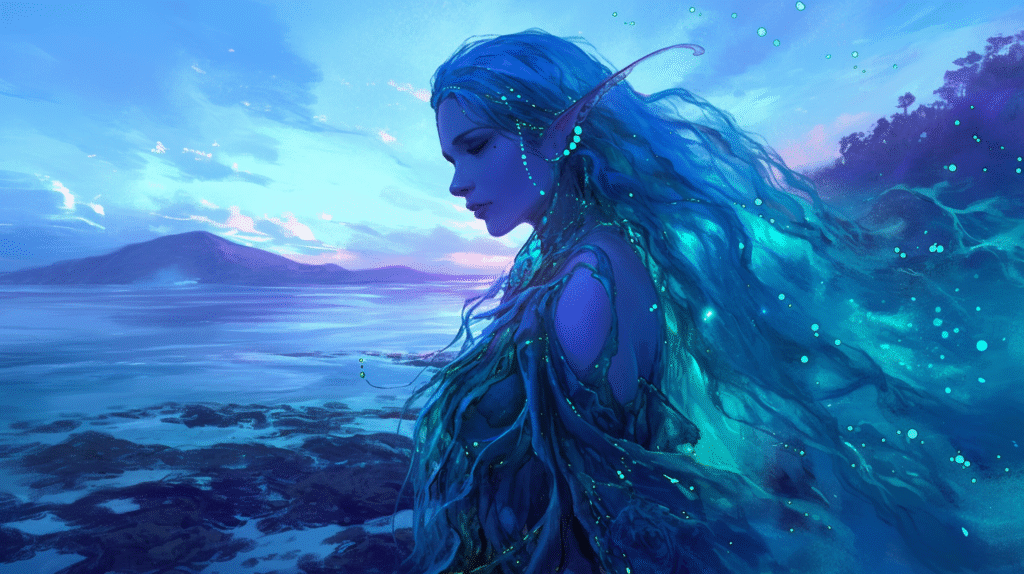
ウンディーネは、ヨーロッパの伝承に登場する水を司る精霊です。
16世紀のスイスの錬金術師・医師パラケルスス(1493-1541年)が提唱した四大精霊の一つとして知られています。
四大精霊とは、世界を構成する4つの元素(火・水・風・土)をそれぞれ司る精霊のことなんですね。
四大精霊の分類
- 火:サラマンダー(火トカゲ)
- 水:ウンディーネ(水の乙女)
- 風:シルフ(風の精)
- 土:ノーム(地の精)
「ウンディーネ」という名前は、ラテン語で「波」を意味する「ウンダ(unda)」という言葉が語源とされています。
フランス語では「オンディーヌ(Ondine)」と呼ばれることもあります。
川や泉、湖、滝などの水辺に住み、美しい歌声で知られる精霊です。
最大の特徴は、人間と結婚することで魂を得られるという点でしょう。
姿・見た目
ウンディーネは、非常に美しい女性の姿をしています。
ウンディーネの外見的特徴
- 人間の女性と同じくらいの大きさ
- 透き通るような美しい容姿
- 真珠のような白い肌
- 緑色の瞳(描写によって異なる)
- しなやかで優雅な体つき
パラケルススの説明によれば、ウンディーネは「柔らかく冷たい肌」を持っているとされました。また、基本的には人間と同じ姿ですが、時には魚やヘビの姿に変身することもあるといわれています。
興味深いのは、ウンディーネには性別がないとされながらも、ほとんどの場合、美しい女性の姿で描かれてきたこと。
これは古代ギリシャで、水は女性的な元素だと考えられていたことが影響しているんですね。
ウンディーネと似た存在として、古代ギリシャ神話に登場するニンフ(ニュンペー)という水の精霊がいます。
ニンフは山川草木の精霊の総称で、ウンディーネはこのニンフの一種とも考えられています。
特徴
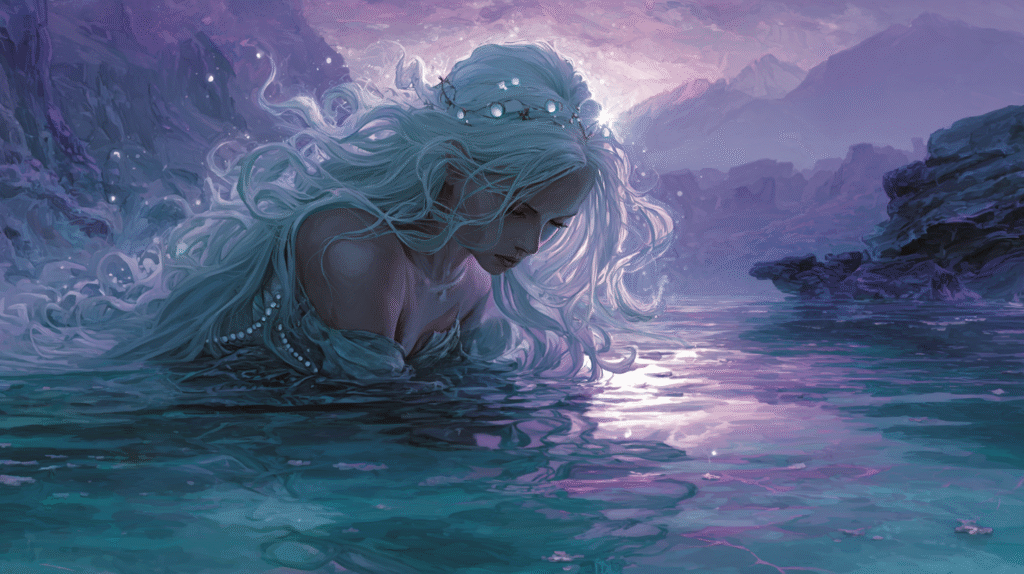
ウンディーネには、他の精霊にはない独特の特徴があります。
魂を持たない存在
ウンディーネ最大の特徴は、生まれつき魂を持っていないということです。
パラケルススの理論では、四大精霊はすべて「永遠の魂」を持ちません。
人間には死後に天国へ行く資格である「不滅の魂」が与えられていますが、精霊たちにはそれがないんです。
しかし、ウンディーネだけは特別な方法で魂を得ることができます。それが人間の男性と結婚することなんですね。
人間との結婚で魂を獲得
ウンディーネが人間の男性と結婚すると、不滅の魂の「芽」を得ることができます。
そして、二人の間に生まれた子供にも、ちゃんと人間の魂が宿ります。
このため、ウンディーネたちは人間の男性との結婚を強く望むといわれています。
四大精霊の中でも、ウンディーネは特に人間と関わりやすく、結婚できる可能性が高い存在とされました。
魂を得た後の変化
魂を手に入れたウンディーネは、人間と同じように心配事や悲しみを感じるようになるといいます。
幸せな感情だけでなく、苦しみや悲しみも知ることになる。魂を得ることは、喜びであると同時に、ある意味では不幸の始まりでもあったんですね。
水を操る能力
水の精霊として、ウンディーネには特別な能力があります。
ウンディーネの主な能力
- 水中を自由に移動できる
- 水を自在に操ることができる
- 美しい歌声を持つ
- 人間よりも長生き
水辺で暮らすウンディーネの美しい歌声は、風に乗って遠くまで響き渡ることがあるそうです。
性格の特徴
ウンディーネの性格は、文献によって様々に描かれています。
一般的には気まぐれで、移り気で、恐れを知らない明るい性格とされました。
愛情深い一方で、気分屋な面もあるといいます。
オカルト主義者エリファス・レヴィによれば、ウンディーネの性格は「のろまで信頼できない」とも評されました。
また、ウンディーネたちの王の名前は「ヒックス」と呼ばれているそうです。
結婚の掟と禁忌
ウンディーネと結婚した男性には、厳しいルールが課せられます。
絶対に守るべき掟
- 水辺でウンディーネを侮辱してはいけない
- 水辺でウンディーネを罵ってはいけない
- 浮気をしてはいけない
もしこれらの掟を破ると、ウンディーネは水の世界に帰らなければならなくなります。
さらに、夫が浮気をした場合、ウンディーネの仲間たちが近くの井戸や泉から現れて、夫を襲うこともあるとされました。
つまり、ウンディーネの夫になるのは、かなり大変なことだったんですね。
伝承

ウンディーネの物語で最も有名なのが、ドイツの作家フリードリヒ・フーケが1811年に発表した小説『ウンディーネ』です。
フーケの小説『ウンディーネ』
この作品は、ウンディーネと騎士フルトブラントの悲しい恋物語を描いています。
物語のあらすじ
ある漁村に住む老夫婦が、自分たちの子供を亡くした直後、玄関前に置き去りにされた赤ん坊を見つけます。
夫婦はその子を自分たちの娘として育てました。
赤ん坊は真珠のような肌と緑の瞳を持つ、とても美しい娘に成長しました。
娘の名前はウンディーネ。
彼女は情愛深い性格でしたが、同時に気まぐれな面もありました。
ある日、騎士フルトブラントが村を訪れ、ウンディーネを一目見るなり恋に落ちます。二人は結婚し、ウンディーネは魂を手に入れました。
キューレボルンの妨害
ウンディーネにはキューレボルンという伯父(または叔父)がいました。この名前は「冷たい泉」という意味です。
キューレボルンは、ウンディーネの結婚を快く思わず、様々な妨害や嫌がらせをしてきました。彼もまた水に関係する化け物の一種とされています。
ベルタルダとの三角関係
しかし、フルトブラントには実はベルタルダという元婚約者がいたのです。
フルトブラントは次第にベルタルダに心を移すようになり、ウンディーネの仲間たちが近くの泉や井戸から現れて、彼を襲おうとする事件が度々起こりました。
こうしたことが続いたため、ついにフルトブラントは水辺でウンディーネを罵ってしまいます。
悲劇の結末
水辺で侮辱を受けたウンディーネは、掟に従って水の世界へ帰らなければなりませんでした。彼女は深い悲しみに暮れながら、ドナウ川へと消えていきました。
去り際、ウンディーネは夫に警告します。「私たちの婚姻はまだ有効です。もしあなたが浮気をすれば、命に関わることになります」と。
しかし、フルトブラントはベルタルダと結婚式を挙げることにしました。
結婚式の前夜、フルトブラントが城の井戸のそばに行くと、そこにウンディーネが現れました。彼女はフルトブラントを抱きしめ、涙を流しながら彼に接吻して、彼の魂を水中へ持ち去りました。井戸のそばには、フルトブラントの亡骸だけが残されました。
不思議な泉
その後、フルトブラントの墓の周りを取り囲むように、自然の泉ができるようになりました。
人々は、この泉こそがウンディーネに違いないと考えたそうです。死んでもなお、彼女は愛した騎士のそばにいたかったのでしょう。
フーケの作品の影響
フーケの小説は、あの文豪ゲーテも「ドイツの真珠」と絶賛したほどの名作でした。
たちまち複数の言語に翻訳され、英語版だけでも1966年までに約100種類もの版が出版されたといわれています。この作品は、多くの派生作品を生み出しました。
ジロドゥの戯曲『オンディーヌ』
1939年、フランスの劇作家ジャン・ジロドゥは、フーケの小説を原作とした戯曲『オンディーヌ』を書きました。
あらすじ
美しい水の精オンディーヌは、騎士ハンスと恋に落ちて人間界にやってきます。しかし、オンディーヌの天真爛漫な振る舞いに嫌気がさしたハンスは、元婚約者のベルタに心を移してしまいました。
実は、オンディーヌが人間界に来る際、水界の王と契約を交わしていました。「もしハンスがオンディーヌを裏切ったら、ハンスの命を奪ってもよい」という内容です。
オンディーヌはハンスを死なせまいと様々な努力をしますが、結局失敗に終わり、ハンスは命を落としてしまいます。
オンディーヌの呪い症候群
この戯曲から、医学用語が生まれました。「オンディーヌの呪い症候群」という、睡眠中に呼吸が止まる病気です。
劇中で、オンディーヌは裏切ったハンスに「意識していなければできることが、意識しないとできなくなる」という呪いをかけました。ハンスは呼吸を意識しなければできなくなり、眠ると無呼吸で死んでしまう状態に陥ったのです。
バレエとオペラ
ウンディーネの物語は、音楽作品にも数多く取り入れられました。
主なバレエ作品
- 1843年:ジュール・ペロー振付、チェーザレ・プーニ作曲『オンディーヌ、またはナイアド』
- 1958年:フレデリック・アシュトン振付、ハンス・ヴェルナー・ヘンツェ作曲『オンディーヌ』(英国ロイヤル・バレエ団の代表作)
主なオペラ作品
- 1814年:E.T.A.ホフマン『ウンディーネ』
- 1845年:アルベルト・ロルツィング『ウンディーネ』
- 1869年:ピョートル・チャイコフスキー『ウンディーナ』
その他の文学作品への影響
フーケの『ウンディーネ』は、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの『人魚姫』(1837年)にも影響を与えたとされています。人魚姫もまた、人間と恋に落ちて魂を求める物語ですね。
また、エドガー・アラン・ポーも、ウォルター・スコットやサミュエル・テイラー・コールリッジを通じてフーケの作品に深く影響を受けたといわれています。
起源
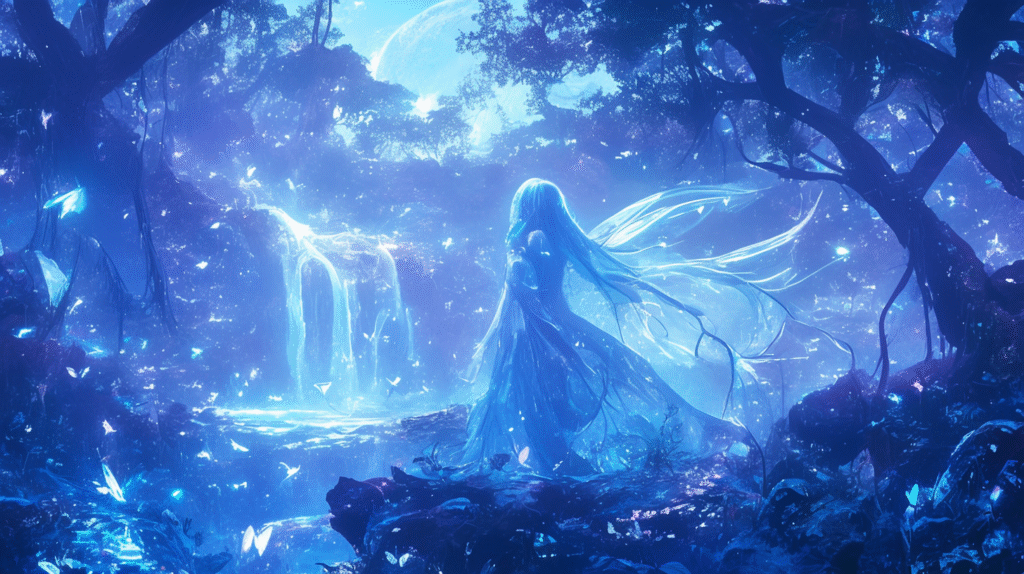
ウンディーネという概念は、どのように生まれたのでしょうか。
パラケルススと四大精霊
ウンディーネを最初に定義したのは、16世紀のスイスの錬金術師で医師でもあったパラケルスス(1493-1541年)です。
パラケルススは、著書『妖精の書(Liber de Nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus)』の中で、四大元素(火・水・風・土)にはそれぞれ対応する精霊がいると提唱しました。
この四大元素説は、古代ギリシャの哲学者エンペドクレス(紀元前490年頃-紀元前430年頃)が最初に唱えたものです。パラケルススは、この古代の思想に精霊の概念を組み合わせたんですね。
「アストラル界」の住人
パラケルススの理論では、四つの元素それぞれに「アストラル界」(パラケルスス用語では「カオス」)という目に見えない世界があり、そこに精霊たちが住んでいるとされました。
精霊たちは「目に見える自然界の、目に見えない霊的な対応物」であり、人間に似た姿をしていながら、人間の未発達な感覚では認識できない存在だと説明されました。
ニンフとの関係
パラケルススは、水の精霊をウンディーネまたはニンフ(ニュンペー)と呼びました。
ニンフは、古代ギリシャ神話に登場する自然の精霊の総称です。
もともとの意味は「花嫁」「若い娘」または「乳母」で、川や小川、泉、湖、草原、山、海などに住み、それぞれの領域を守る存在とされていました。
ニンフは時に英雄や神々の母であり、乳母でもありました。たとえば、幼少期のゼウスを育てたのもニンフだったんです。
パラケルススは、こうした古代ギリシャのニンフの伝承を取り入れ、水の精霊「ウンディーネ」として体系化したのです。
民間伝承との結びつき
パラケルススの理論が生まれる前から、ヨーロッパ各地には水の精霊に関する民間伝承がありました。
ケルト民族学者ヘンリー・ジェナーによれば、「人間によく似た種族の精霊が、人間とは別の次元に存在する」という民俗信仰が、パラケルススの四大精霊説の元になった可能性があるといいます。
ウンディーネという名前の由来
「ウンディーネ(Undine)」という言葉は、ラテン語の「ウンダ(unda)」が語源です。
これは「波」を意味する言葉で、語尾に縮小辞の「-ina」がついています。現代イタリア語に訳すと「小さな波」という意味になるそうです。
まとめ
ウンディーネは、人間との悲恋で知られる美しい水の精霊です。
重要なポイント
- 16世紀の錬金術師パラケルススが定義した四大精霊の一つ
- 美しい女性の姿をした水の精霊
- 生まれつき魂を持たず、人間と結婚することで魂を得る
- 魂を得ると人間と同じように悲しみや苦しみを感じるようになる
- 水辺で侮辱されると水の世界に帰らなければならない
- フーケの小説『ウンディーネ』で広く知られるようになった
- バレエ、オペラ、戯曲など様々な芸術作品の題材となった
- 古代ギリシャ神話のニンフが起源
ウンディーネの物語は、愛と魂、そして人間であることの意味を問いかけてくれます。
魂を得ることは幸せなのか、それとも苦しみの始まりなのか。
この切ない問いかけが、何世紀にもわたって人々の心を捉え続けているんですね。