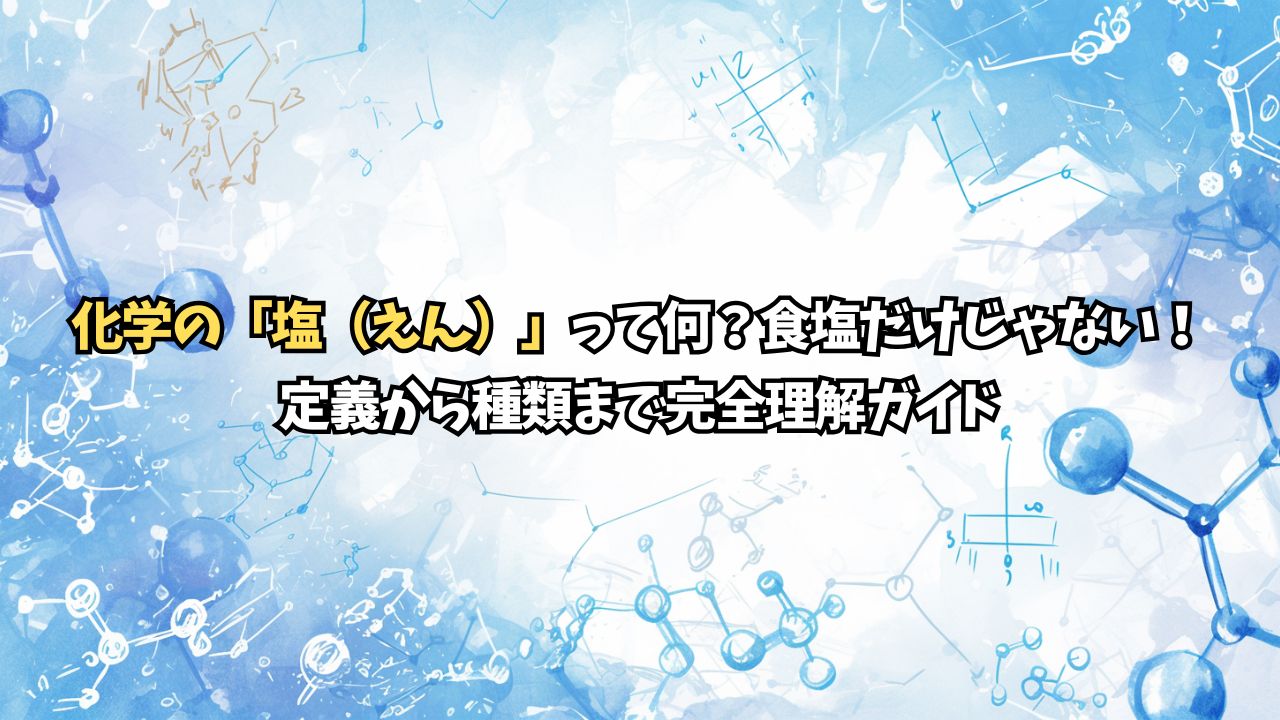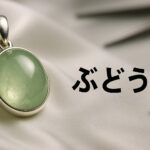「化学で塩(えん)って出てくるけど、食塩のこと?」 「酸と塩基を混ぜると塩ができるって、どういう意味?」 「正塩、酸性塩、塩基性塩の違いが分からない…」 「なぜ『しお』じゃなくて『えん』って読むの?」
こんな疑問を持ったことはありませんか?
実は、化学の「塩(えん)」は食卓塩よりもはるかに広い意味を持つんです!
この記事を読めば、化学における塩の本当の定義から身近な例まで、すべてが分かります。もう試験で迷うことはありません!
塩(えん)の正式な定義
化学における塩とは?

塩(えん)の定義:
酸と塩基が中和反応して生成する化合物
酸 + 塩基 → 塩 + 水
もっと簡単に言うと:
塩 = 陽イオン(金属イオンなど)+ 陰イオン(酸由来)
の組み合わせでできた物質
「しお」と「えん」の違い
| 読み方 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 塩(しお) | 食塩(塩化ナトリウム)のこと | 料理の調味料 |
| 塩(えん) | 化学用語、イオン化合物全般 | NaCl、CaCO₃、K₂SO₄など |
覚え方:
- 日常会話 → 「しお」
- 化学の授業 → 「えん」
塩ができる仕組み:中和反応
基本的な中和反応
最も有名な例:塩酸と水酸化ナトリウム
HCl + NaOH → NaCl + H₂O
塩酸 水酸化 塩化 水
ナトリウム ナトリウム
H⁺ + OH⁻ → H₂O(水ができる)
Na⁺ + Cl⁻ → NaCl(塩ができる)
身近な中和反応の例
胃薬(制酸剤)の働き:
胃酸(塩酸)+ 胃薬(水酸化マグネシウムなど)
↓
塩化マグネシウム + 水
(胃酸が中和される)
お菓子作り(ベーキングソーダ):
重曹(炭酸水素ナトリウム)+ 酸(レモン汁など)
↓
塩 + 水 + 二酸化炭素(泡)
(ケーキがふくらむ)
塩の3つの種類:性質で分類

1. 正塩(せいえん)- 中性の塩
定義: 酸のH⁺と塩基のOH⁻が完全に中和してできた塩
特徴:
- 水に溶けても中性(pH≒7)
- 最も基本的な塩
例:
塩化ナトリウム(NaCl)- 食塩
硫酸カルシウム(CaSO₄)- 石膏
硝酸カリウム(KNO₃)- 肥料、火薬
2. 酸性塩(さんせいえん)
定義: 酸のH⁺が残っている塩
特徴:
- 水に溶けると酸性(pH<7)
- 化学式にHが残っている
例:
硫酸水素ナトリウム(NaHSO₄)
リン酸二水素カリウム(KH₂PO₄)
炭酸水素ナトリウム(NaHCO₃)- 重曹
なぜ重曹は酸性塩なのに塩基性?
実は炭酸(H₂CO₃)が弱酸だから!
水に溶けると:
HCO₃⁻ + H₂O ⇄ H₂CO₃ + OH⁻
OH⁻が生成して塩基性を示す
3. 塩基性塩(えんきせいえん)
定義: 塩基のOH⁻が残っている塩
特徴:
- 水に溶けると塩基性(pH>7)
- 化学式にOHが残っている
例:
塩化水酸化マグネシウム(Mg(OH)Cl)
硫酸水酸化銅(Cu(OH)₂SO₄)
身の回りの塩(えん)図鑑
家庭にある塩
| 物質名 | 化学式 | 用途 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 食塩 | NaCl | 調味料 | 正塩 |
| 重曹 | NaHCO₃ | 掃除、料理 | 酸性塩 |
| みょうばん | KAl(SO₄)₂ | 漬物、消臭 | 正塩 |
| エプソムソルト | MgSO₄ | 入浴剤 | 正塩 |
| 消石灰 | Ca(OH)₂ | 土壌改良 | 塩基 |
学校の実験でよく使う塩
硫酸銅(CuSO₄)
・青い結晶
・水の検出に使用
・めっき実験
塩化アンモニウム(NH₄Cl)
・冷却パックの原料
・はんだ付けのフラックス
炭酸カルシウム(CaCO₃)
・チョーク、大理石の主成分
・制酸剤
塩の性質と特徴
共通の性質
1. イオン結晶である
陽イオンと陰イオンが規則正しく並んだ結晶
→ 硬いが割れやすい
2. 水に溶けやすいものが多い
イオンが水分子に囲まれて安定化
ただし例外もある(硫酸バリウムなど)
3. 電解質である
水溶液や融解状態で電気を通す
イオンが自由に動けるため
4. 融点が高い
イオン結合が強いため
食塩の融点:801℃
溶解度の違い
よく溶ける塩:
- ナトリウム塩(Na⁺)
- カリウム塩(K⁺)
- アンモニウム塩(NH₄⁺)
- 硝酸塩(NO₃⁻)
溶けにくい塩:
- 銀塩(AgCl など)
- 硫酸バリウム(BaSO₄)
- 炭酸カルシウム(CaCO₃)
塩の見分け方:炎色反応
金属イオンによる炎の色
リチウム(Li⁺) → 赤
ナトリウム(Na⁺) → 黄
カリウム(K⁺) → 紫
カルシウム(Ca²⁺) → 橙
ストロンチウム(Sr²⁺)→ 紅
バリウム(Ba²⁺) → 緑
銅(Cu²⁺) → 青緑
花火の色の秘密:
赤い花火 → ストロンチウム塩
緑の花火 → バリウム塩
青い花火 → 銅塩
黄色い花火 → ナトリウム塩
塩に関するよくある誤解
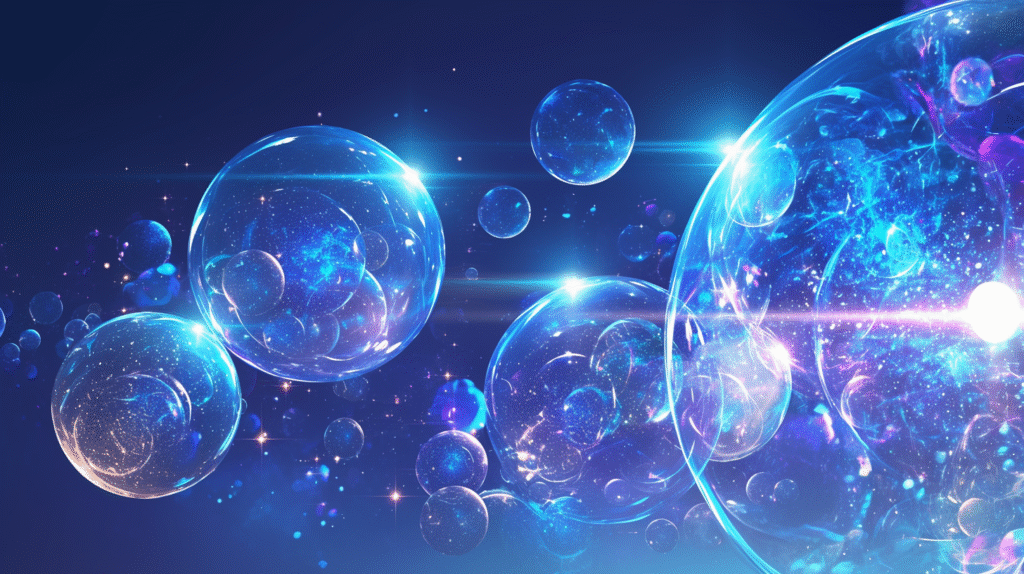
誤解1:塩はすべてしょっぱい
真実: 塩化ナトリウムだけがしょっぱい
甘い塩:酢酸鉛(有毒!)
苦い塩:硫酸マグネシウム(下剤)
無味の塩:硫酸バリウム(造影剤)
誤解2:塩は白い粉末
真実: カラフルな塩がたくさん!
青:硫酸銅(CuSO₄)
緑:塩化ニッケル(NiCl₂)
紫:過マンガン酸カリウム(KMnO₄)
橙:重クロム酸カリウム(K₂Cr₂O₇)
誤解3:酸性塩は必ず酸性を示す
真実: 重曹(NaHCO₃)のように塩基性を示すものもある
理由:もとの酸の強さによる
弱酸由来 → 塩基性を示すことも
強酸由来 → 酸性を示す
試験に出る!重要ポイント
覚えておくべき反応式
基本の中和:
HCl + NaOH → NaCl + H₂O
H₂SO₄ + 2NaOH → Na₂SO₄ + 2H₂O
HNO₃ + KOH → KNO₃ + H₂O
よく出る沈殿反応:
AgNO₃ + NaCl → AgCl↓ + NaNO₃(白色沈殿)
BaCl₂ + H₂SO₄ → BaSO₄↓ + 2HCl(白色沈殿)
塩の分類フローチャート
塩の化学式を見る
↓
Hが含まれる?
Yes → 酸性塩
No ↓
OHが含まれる?
Yes → 塩基性塩
No → 正塩
実験:塩を作ってみよう(家庭でできる)
安全な塩づくり実験
材料:
- 酢(酢酸)
- 重曹(炭酸水素ナトリウム)
手順:
1. 酢50mlをコップに入れる
2. 重曹を少しずつ加える
3. 泡(CO₂)が出なくなるまで混ぜる
4. 水分を蒸発させる
5. 酢酸ナトリウムの結晶ができる!
CH₃COOH + NaHCO₃ → CH₃COONa + H₂O + CO₂
まとめ:塩(えん)は化学の基本!
今日学んだ重要ポイント:
✅ 塩(えん)= 酸と塩基の中和でできる化合物
✅ 陽イオン + 陰イオンの組み合わせ
✅ 3種類:正塩、酸性塩、塩基性塩
✅ 食塩(NaCl)は塩の一例に過ぎない
✅ カラフルな塩、甘い塩もある
✅ イオン結晶で電解質
✅ 花火の色も塩の炎色反応
塩(えん)は化学反応の基本中の基本。
これを理解すれば、中和反応も、イオンの勉強も、ぐっと楽になります。身の回りには想像以上にたくさんの塩があふれています。
今日から、「塩」を見る目が変わるはずです!
チャレンジ問題:
- 歯磨き粉に含まれる塩を調べてみよう
- 入浴剤の成分表示を確認してみよう
- スポーツドリンクにはどんな塩が入っている?