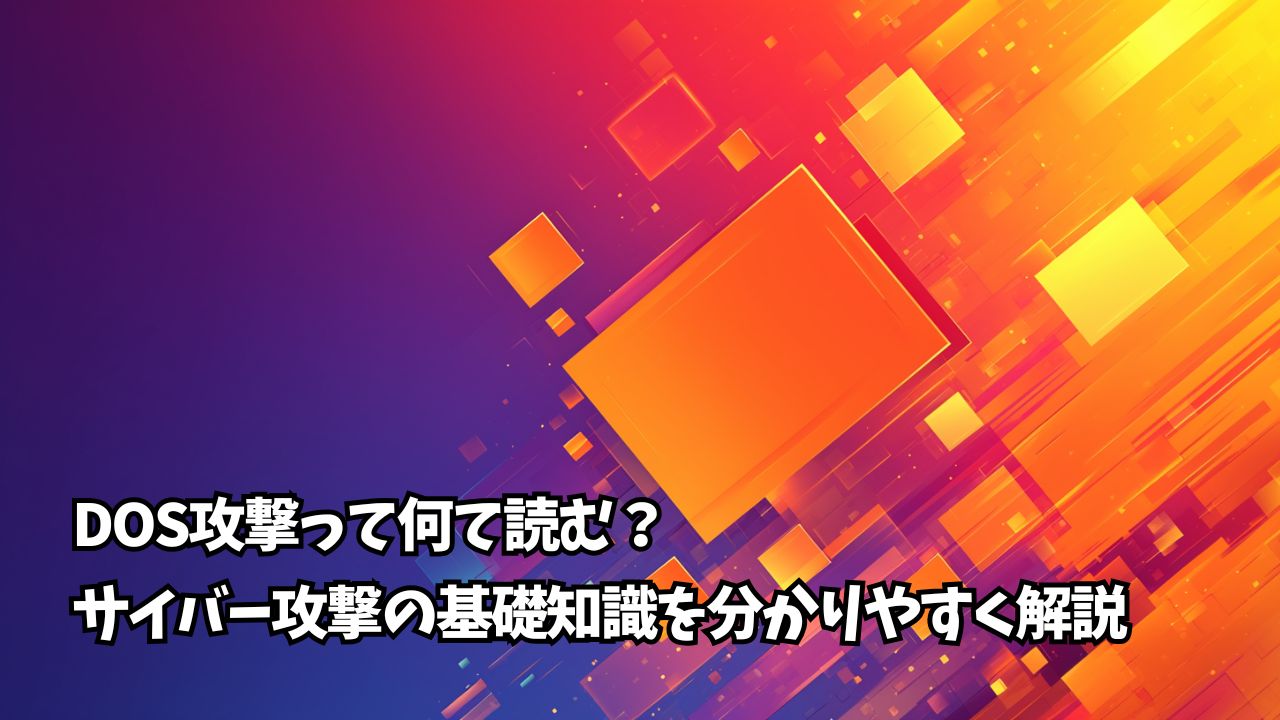インターネットのセキュリティについて調べていると、「DoS攻撃」という言葉をよく見かけますよね。
でも、これってどう読むんでしょうか?
正解は「ディーオーエス攻撃」または「ドス攻撃」です。
英語圏では「ディーオーエス」と一文字ずつ読むことが多いですが、日本では「ドス攻撃」と読む人も多くいます。どちらも正しい読み方なので、使いやすい方で大丈夫です。
ちなみに、DoSは「Denial of Service」の略で、日本語では「サービス拒否」という意味になります。
この記事では、DoS攻撃とは何か、どんな種類があるのか、そして私たちができる対策まで、順番に分かりやすく説明していきます。
DoS攻撃とDDoS攻撃の違い
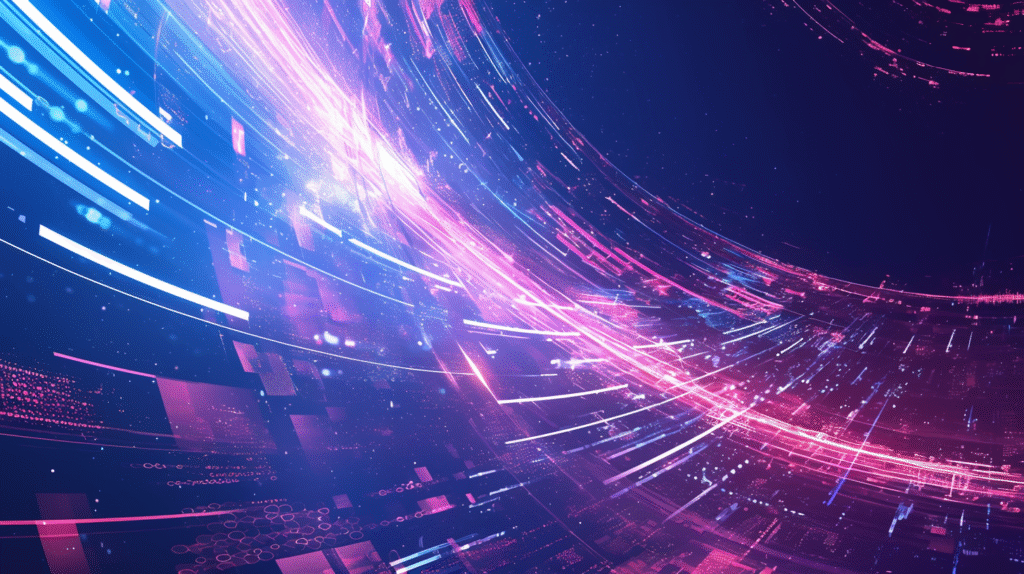
DoS攻撃とは
DoS攻撃(Denial of Service attack) は、サービス拒否攻撃とも呼ばれます。
簡単に言うと、「Webサイトやサービスを使えなくする攻撃」のことです。
レストランに例えると分かりやすいでしょう。
- 普通のお客さんが食事をしようとしているのに
- 悪意のある人が席を全部占領してしまう
- 結果、本当のお客さんが入れなくなる
これがインターネット上で起きているのがDoS攻撃です。
DDoS攻撃との違い
よく似た言葉で DDoS攻撃 があります。
DDoS(Distributed Denial of Service) は「ディーディーオーエス」または「ディードス」と読みます。
違いは攻撃元の数です:
DoS攻撃:
- 1台のコンピューターから攻撃
- 攻撃元を特定しやすい
- 防御も比較的簡単
DDoS攻撃:
- 複数(時には数万台)のコンピューターから同時攻撃
- 攻撃元の特定が困難
- 防御が難しい
- 現在の主流はこちら
最初の「D」は「Distributed(分散型)」という意味で、攻撃が分散していることを表しています。
なぜDoS攻撃は問題なのか
被害の実態
DoS攻撃を受けると、こんな被害が発生します:
1. サービスが停止する
- Webサイトが表示されない
- オンラインショップで買い物ができない
- ゲームサーバーに接続できない
2. 経済的損失
- 営業機会の損失(1時間停止で数百万円の損失も)
- 復旧にかかる費用
- 信用の低下による長期的な影響
3. 利用者への影響
- サービスが使えないストレス
- 重要な手続きができない
- 代替サービスを探す手間
攻撃の目的は何?
攻撃者の目的はさまざまです:
1. 嫌がらせ・報復
- 個人的な恨み
- 企業への不満
- 政治的な主張
2. 金銭目的
- 「攻撃を止めてほしければ金を払え」という脅迫
- 競合他社からの妨害工作
- 株価操作を狙った攻撃
3. 目くらまし
- 本命の攻撃から注意をそらす
- セキュリティチームを忙しくさせる
- その間に別の侵入を試みる
DoS攻撃の仕組みと種類
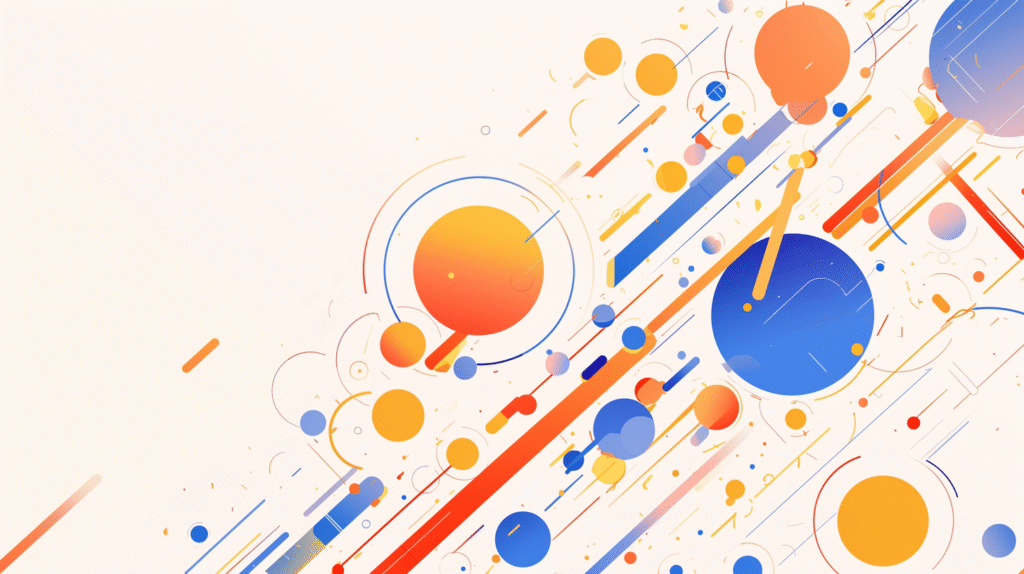
基本的な仕組み
DoS攻撃の基本は「相手のリソース(資源)を使い果たさせる」ことです。
コンピューターには限界があります:
- 処理できる通信量
- 使えるメモリの量
- 同時に対応できる接続数
これらの限界を超えさせることで、正常なサービスを提供できなくします。
主な攻撃の種類
1. フラッド攻撃(洪水攻撃)
仕組み: 大量のデータを送りつける
レストランの例:
- 電話が鳴り続けて、本当の予約が取れない状態
種類:
- SYN Flood(シンフラッド): 接続要求を大量に送る
- UDP Flood: UDPパケットを大量送信
- ICMP Flood: pingを大量に送る
2. リソース枯渇攻撃
仕組み: サーバーの処理能力を使い果たす
レストランの例:
- 超複雑な注文を大量にして、厨房をパンクさせる
種類:
- Slowloris(スローロリス): わざとゆっくり通信して接続を占有
- R.U.D.Y: フォーム送信を極端に遅くする
3. 脆弱性を突く攻撃
仕組み: プログラムのバグを利用
レストランの例:
- 裏口の鍵が壊れているのを利用して侵入
種類:
- Ping of Death: 異常に大きなpingパケットを送る
- Teardrop: 断片化されたパケットで混乱させる
最近の攻撃トレンド
IoT機器を利用した攻撃
最近は、インターネットに繋がる機器(IoT)が狙われています:
- 防犯カメラ
- スマート家電
- ルーター
これらの機器は:
- セキュリティが弱いことが多い
- 所有者が攻撃に気づきにくい
- 24時間稼働している
攻撃の大規模化
- 2016年:1Tbps(テラビット/秒)を超える攻撃が発生
- 2018年:1.7Tbpsの攻撃を記録
- 現在:2Tbpsを超える攻撃も確認
これは、一般家庭のインターネット回線の約100万倍の通信量です。
実際の被害事例
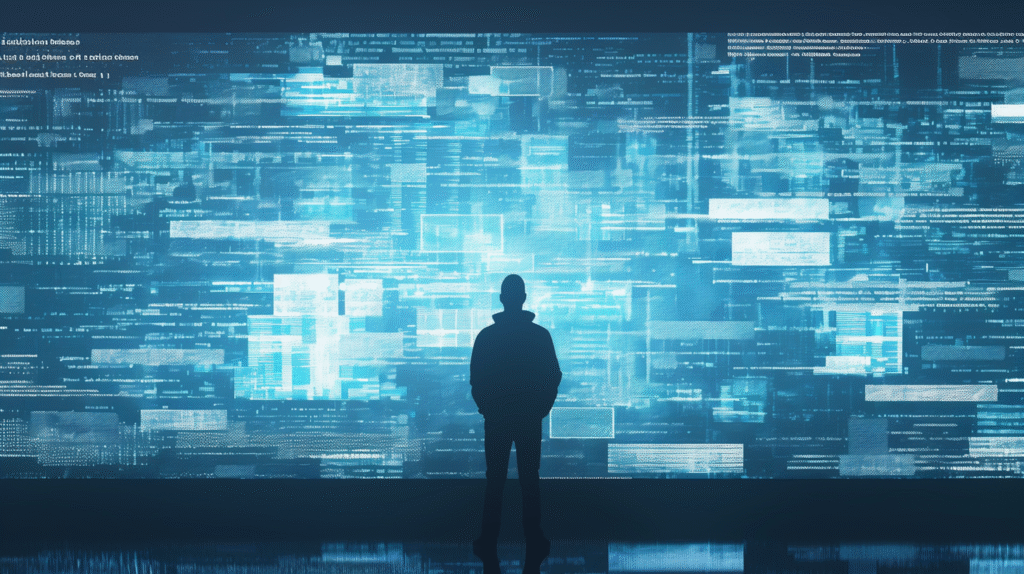
国内の事例
2020年 – ゲーム会社への攻撃
- 人気オンラインゲームのサーバーが攻撃を受ける
- 数日間、断続的にサービス停止
- プレイヤーに大きな影響
2021年 – 政府関連サイトへの攻撃
- 複数の省庁のWebサイトが一時的にアクセス不能に
- 重要な情報提供が滞る
2022年 – 大手ECサイトへの攻撃
- セール期間中に攻撃を受ける
- 数時間の売上機会損失
海外の大規模事例
2016年 Dyn攻撃
- DNS(ドメインネームシステム)サービス企業が標的
- Twitter、Netflix、CNNなど大手サービスが影響を受ける
- IoT機器を使った過去最大級の攻撃
2020年 AWS攻撃
- Amazon Web Servicesが2.3Tbpsの攻撃を受ける
- 適切な対策により、サービスへの影響は最小限
DoS攻撃から身を守る方法
個人でできる対策
1. 自分の機器を攻撃に使われないために
ルーターやIoT機器の管理:
- 初期パスワードを必ず変更する
- ファームウェアを最新に保つ
- 不要な機能は無効にする
パソコンのセキュリティ:
- ウイルス対策ソフトを導入
- OSやソフトを最新版に更新
- 怪しいメールやリンクを開かない
2. 攻撃を受けた時の対処
もし自分のサイトが攻撃を受けたら:
- まず落ち着く
- プロバイダーやホスティング会社に連絡
- アクセスログを保存(証拠として)
- 必要なら警察に相談
企業・組織の対策
基本的な対策
1. ファイアウォールの設置
- 不正な通信をブロック
- 正常な通信だけを通す
- 定期的な設定見直し
2. 帯域幅の確保
- 十分な通信容量を用意
- 攻撃に耐えられる余裕を持つ
- ただし、コストとのバランスが重要
3. 負荷分散
- 複数のサーバーで処理を分ける
- 一部が攻撃されても、他でカバー
- CDN(Content Delivery Network)の活用
高度な対策
1. DDoS対策サービスの利用
専門業者のサービスを使う:
- Cloudflare
- Akamai
- AWS Shield
メリット:
- 24時間365日の監視
- 巨大な攻撃にも対応
- 専門知識不要
2. レート制限の実装
- 同一IPからのアクセスを制限
- 1秒あたりのリクエスト数を制限
- 異常な通信パターンを検知
3. ブラックホールルーティング
- 攻撃トラフィックを無効な場所に転送
- 被害を最小限に抑える
- 緊急時の最終手段
攻撃を検知する方法
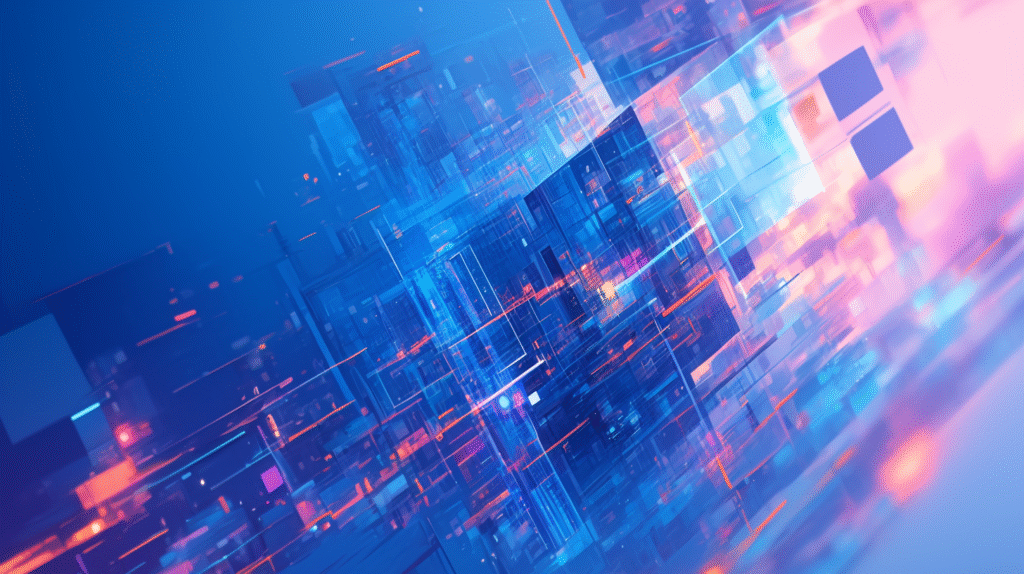
早期発見のサイン
以下の症状が出たら、攻撃の可能性があります:
1. パフォーマンスの低下
- Webサイトの表示が異常に遅い
- 断続的にアクセスできない
- エラーメッセージが頻発
2. 異常なトラフィック
- アクセス数が急激に増加
- 特定の国や地域からの大量アクセス
- 同じIPアドレスからの繰り返しアクセス
3. システムリソースの異常
- CPU使用率が常に高い
- メモリが不足している
- ネットワーク帯域が限界に近い
監視ツールの活用
無料ツール:
- Google Analytics(異常なトラフィックの検知)
- Uptime Robot(サイトの死活監視)
- Wireshark(ネットワークトラフィック分析)
有料ツール:
- Datadog
- New Relic
- Zabbix
これらのツールで、通常と異なるパターンを素早く発見できます。
法的な側面
DoS攻撃は犯罪です
日本では、DoS攻撃は明確に犯罪として扱われます。
適用される法律:
- 刑法234条の2(電子計算機損壊等業務妨害罪)
- 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
海外からの攻撃でも:
- 国際協力により捜査可能
- 実際に逮捕された事例も多数
被害に遭ったら
1. 証拠を保全
- アクセスログ
- エラーログ
- スクリーンショット
2. 被害届の提出
- 最寄りの警察署のサイバー犯罪相談窓口
- 都道府県警察のサイバー犯罪対策課
3. 被害額の算定
- サービス停止による機会損失
- 復旧にかかった費用
- 対策に要した費用
よくある誤解と真実
誤解1:小さなサイトは狙われない
真実: 規模に関係なく攻撃される可能性があります。
- 練習台として使われる
- 踏み台として利用される
- 無差別攻撃に巻き込まれる
誤解2:対策にはお金がかかる
真実: 基本的な対策は無料でできます。
- 設定の見直し
- パスワードの強化
- 定期的な更新
誤解3:一度対策すれば安心
真実: 継続的な対策が必要です。
- 攻撃手法は進化する
- 新しい脆弱性が発見される
- 定期的な見直しが重要
今後の展望
AIを使った攻撃と防御
攻撃側:
- AIが攻撃パターンを学習
- より巧妙な攻撃が可能に
- 人間には見分けにくい攻撃
防御側:
- AIによる異常検知
- リアルタイムでの対策
- 予測に基づく事前防御
5Gとその影響
5G普及により:
- より高速な通信が可能
- IoT機器がさらに増加
- 攻撃の規模も大きくなる可能性
対策も進化:
- エッジコンピューティングの活用
- より分散化された防御
- リアルタイム処理の高速化
まとめ:DoS攻撃を正しく理解して備えよう
DoS攻撃について、読み方から対策まで幅広く解説してきました。
覚えておくべきポイント:
- DoS攻撃は「ディーオーエス」または「ドス」と読む
- DDoS攻撃は複数の攻撃元から行われる、より深刻な攻撃
- 個人も企業も被害に遭う可能性がある
- 基本的な対策で多くの攻撃を防げる
- 継続的な監視と更新が重要
インターネットは便利な反面、このような脅威も存在します。
しかし、正しい知識を持ち、適切な対策を取れば、多くの攻撃から身を守ることができます。過度に恐れる必要はありませんが、油断は禁物です。
まずは、自分のルーターのパスワードを確認することから始めてみませんか?小さな一歩が、大きな安全につながります。
サイバーセキュリティは、みんなで作り上げるもの。一人ひとりの意識と行動が、より安全なインターネット環境を作っていくのです。