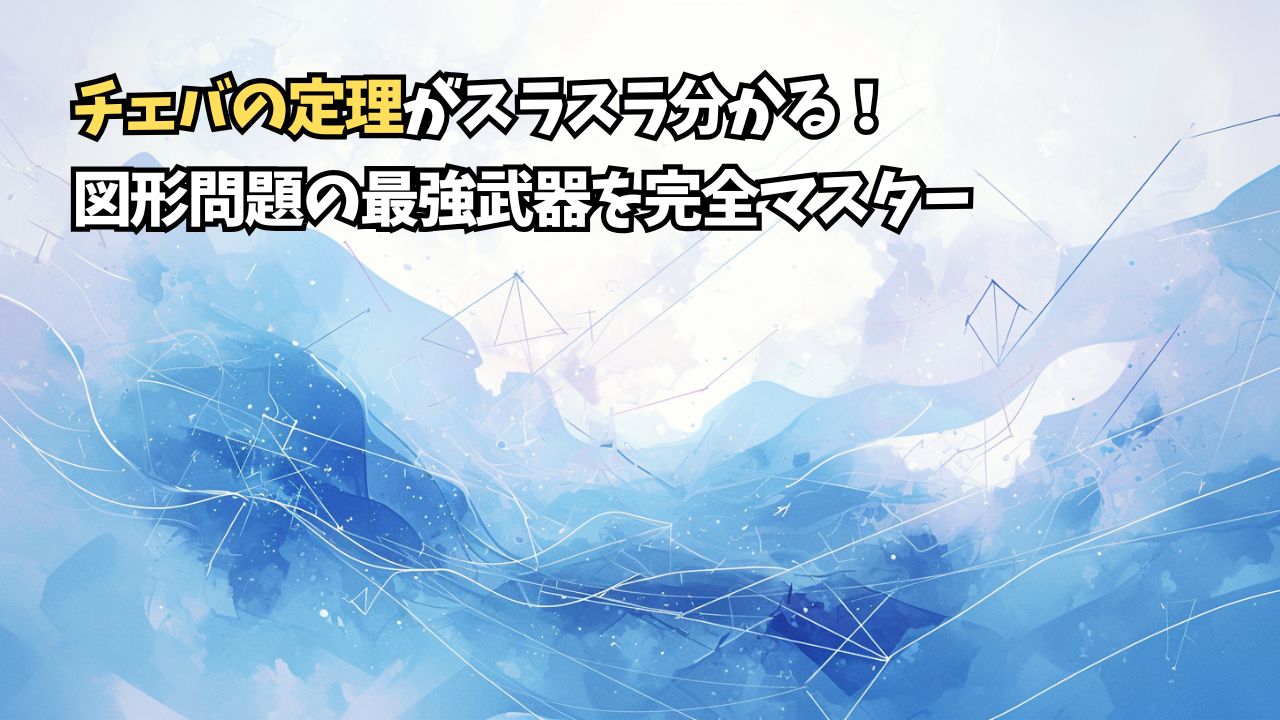「三角形の問題で、線分の比が絡むとお手上げ…」 「メネラウスの定理と何が違うの?」 「公式は覚えたけど、いつ使えばいいか分からない」
こんな悩み、ありませんか?
実は、チェバの定理をマスターすれば、三角形に関する難しそうな問題の半分以上は楽勝になっちゃうんです!しかも、覚え方にはコツがあって、一度理解すれば忘れません。
この記事では、チェバの定理を「買い物の割り勘」のような身近な例から説明して、最後には入試問題もスラスラ解けるようになる方法をお教えします。15分後には、あなたも「チェバの定理マスター」ですよ!
チェバの定理って、そもそも何?
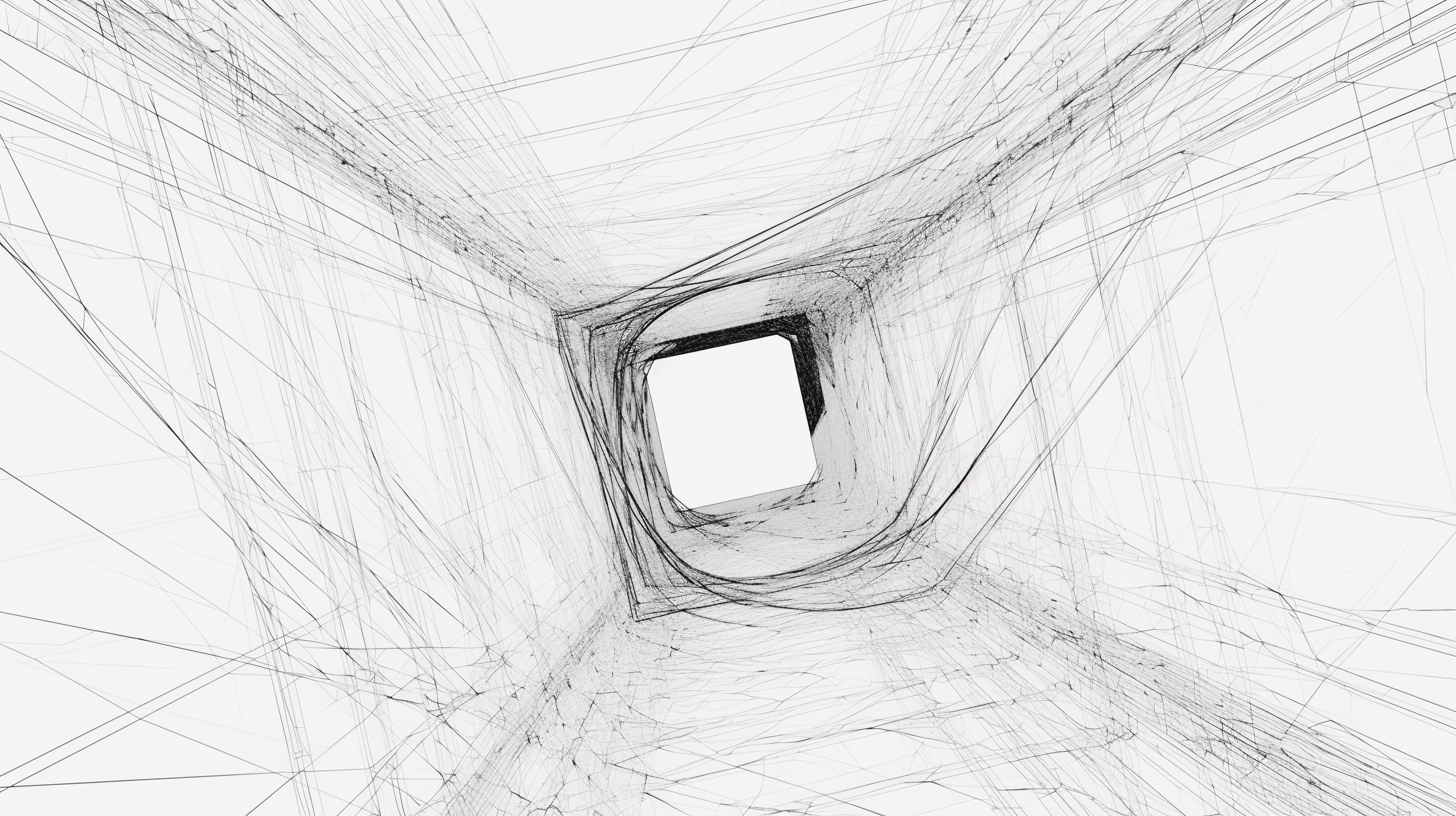
一言で言うと
三角形の中で、3本の線が1点で交わる条件を教えてくれる定理です。
もっと簡単に言うと、「この3本の線、本当に1点で交わってる?」を計算で確かめられる魔法の公式なんです。
発見者はイタリアの数学者
1678年、イタリアの数学者ジョバンニ・チェバ(Giovanni Ceva)が発見しました。今から350年も前の定理が、現代の入試でもバリバリ使われているって、すごいですよね!
チェバの定理を世界一分かりやすく解説
基本の形を見てみよう
まず、こんな図形を想像してください:
三角形ABC があります。
各頂点から向かい側の辺に線を引きます:
- Aから辺BCに線を引いて、交点をD
- Bから辺CAに線を引いて、交点をE
- Cから辺ABに線を引いて、交点をF
この3本の線(AD、BE、CF)が1点で交わるとき、ある美しい関係が成り立つんです!
チェバの定理の公式
3本の線が1点で交わる ⇔
AF BD CE
── × ── × ── = 1
FB DC EA
覚え方のコツ:「ぐるっと一周」
分子を見ると:A→F→B→D→C→E→A(頂点を一周!) 分母を見ると:F→B→D→C→E→A(逆向きに一周!)
時計回りにぐるっと回るイメージで覚えましょう。
なぜこんな式が成り立つの?(直感的な理解)
お祭りの屋台で考えてみよう
3つの屋台(A、B、C)があって、それぞれの店主が「集合場所」を決めたいとします。
- A店主:「BCの道のりをD地点で分けよう」
- B店主:「CAの道のりをE地点で分けよう」
- C店主:「ABの道のりをF地点で分けよう」
全員が納得する「フェアな集合場所」が存在する条件が、まさにチェバの定理なんです!
それぞれの分け方のバランスを掛け合わせると、ピッタリ「1」になる。これって、すごく美しい関係だと思いませんか?
チェバの定理の使い方(実践編)
パターン1:3線が1点で交わることを証明する
問題例: 「三角形の3本の中線は1点で交わることを証明せよ」
解法:
- 各辺の中点をD、E、Fとする
- 中点なので、AF/FB = BD/DC = CE/EA = 1
- 1 × 1 × 1 = 1 ✓
- チェバの定理より、3本の中線は1点で交わる!
パターン2:線分の比を求める
問題例: 「AD、BE、CFが1点で交わるとき、AF:FB = 2:3、BD:DC = 3:4 ならば、CE:EAを求めよ」
解法:
- チェバの定理より:(2/3) × (3/4) × (CE/EA) = 1
- (6/12) × (CE/EA) = 1
- CE/EA = 2
- よって、CE:EA = 2:1
めちゃくちゃシンプルでしょう?
チェバの定理とメネラウスの定理の違い
一目で分かる違い
チェバの定理:
- 3本の線が1点で交わる
- 三角形の内部で交わることが多い
- 式の値は1
メネラウスの定理:
- 1本の直線が三角形の3辺を横切る
- 三角形を貫通する直線
- 式の値は**-1**(符号に注意!)
覚え方:
- チェバ = チュウシン(中心)で交わる → 内部
- メネラウス = メッタ切り → 貫通
重要な応用:特殊な点との関係
1. 重心(3本の中線の交点)
中線は各辺を1:1に分けるので、チェバの定理で簡単に証明できます。
2. 内心(角の二等分線の交点)
角の二等分線の性質と組み合わせると、内心の存在が証明できます。
3. 垂心(3本の垂線の交点)
少し複雑ですが、チェバの定理で垂心の存在も証明可能!
これらの「五心」と呼ばれる特別な点は、すべてチェバの定理と関係があるんです。
よくある間違いと対策
間違い1:比の向きを逆にする
NG: AF/FB を FB/AF と書いてしまう
対策: 必ず「頂点から順番に」書く習慣をつける
間違い2:どの線分か分からなくなる
対策: 図に色を付ける!
- 赤:Aから出る線とその比
- 青:Bから出る線とその比
- 緑:Cから出る線とその比
間違い3:メネラウスと混同
対策:
- 交点が1個 → チェバ(値は1)
- 交点が3個 → メネラウス(値は-1)
練習問題にチャレンジ!
基本問題
問題: 三角形ABCで、AD、BE、CFが1点で交わる。 AF:FB = 3:2、BD:DC = 4:3のとき、CE:EAを求めよ。
考え方:
- チェバの定理を立てる
- 比を分数で表す
- 方程式を解く
答え: CE:EA = 8:9
できましたか?できたら、もうチェバの定理の基本はバッチリです!
応用問題
問題: 三角形ABCの内部の点Pから各辺に下ろした垂線の足をD、E、Fとする。 このとき、AD、BE、CFは1点で交わることを示せ。
ヒント: 三角形の面積比を使うと上手くいきます!
出題パターン
パターン1:証明問題
「3本の線が1点で交わることを示せ」 → チェバの定理で一発!
パターン2:比の計算
「交点での線分比を求めよ」 → チェバの定理で方程式を立てる
パターン3:座標との融合
座標平面上でチェバの定理を使う問題も増えています。
パターン4:空間図形への拡張
四面体でのチェバの定理(チェバの定理の3次元版)も存在します!
覚えるためのゴロ合わせ・記憶術

公式の覚え方
「アフブド・シーイー = 1(いち)」
AF/FB × BD/DC × CE/EA = 1
「アフブド」君と「シーイー」さんが一緒(1)になる、みたいなイメージで。
図形での覚え方
「三角形の周りを、分子が時計回り」
頂点 → 交点 → 頂点 → 交点… の順番で一周すると覚えやすいです。
チェバの定理の逆も重要!
逆の定理
実は、チェバの定理は逆も成り立ちます。
つまり:
AF BD CE
── × ── × ── = 1
FB DC EA
が成り立てば、AD、BE、CFは必ず1点で交わる!
これ、意外と使える場面が多いんです。
まとめ:チェバの定理は図形問題の最強ツール!
チェバの定理をマスターすれば、複雑に見える図形問題もシンプルに解けるようになります。
絶対に覚えるべき3つのポイント:
- 3本の線が1点で交わる ⇔ 比の積が1 これがチェバの定理の本質
- 分子は時計回り、分母は反時計回り 覚え方はこれでバッチリ
- 逆も成り立つ 比の積が1なら、必ず1点で交わる
特に、高校入試や大学入試では、チェバの定理を知っているだけで大幅に時間短縮できる問題がたくさんあります。この定理一つで、あなたの図形問題への苦手意識が消えるはずです!
次のステップ:
- メネラウスの定理も一緒にマスター
- 五心(重心・内心・外心・垂心・傍心)との関係を理解
- 実際の入試問題で練習
さあ、チェバの定理を武器に、図形問題を征服しましょう!