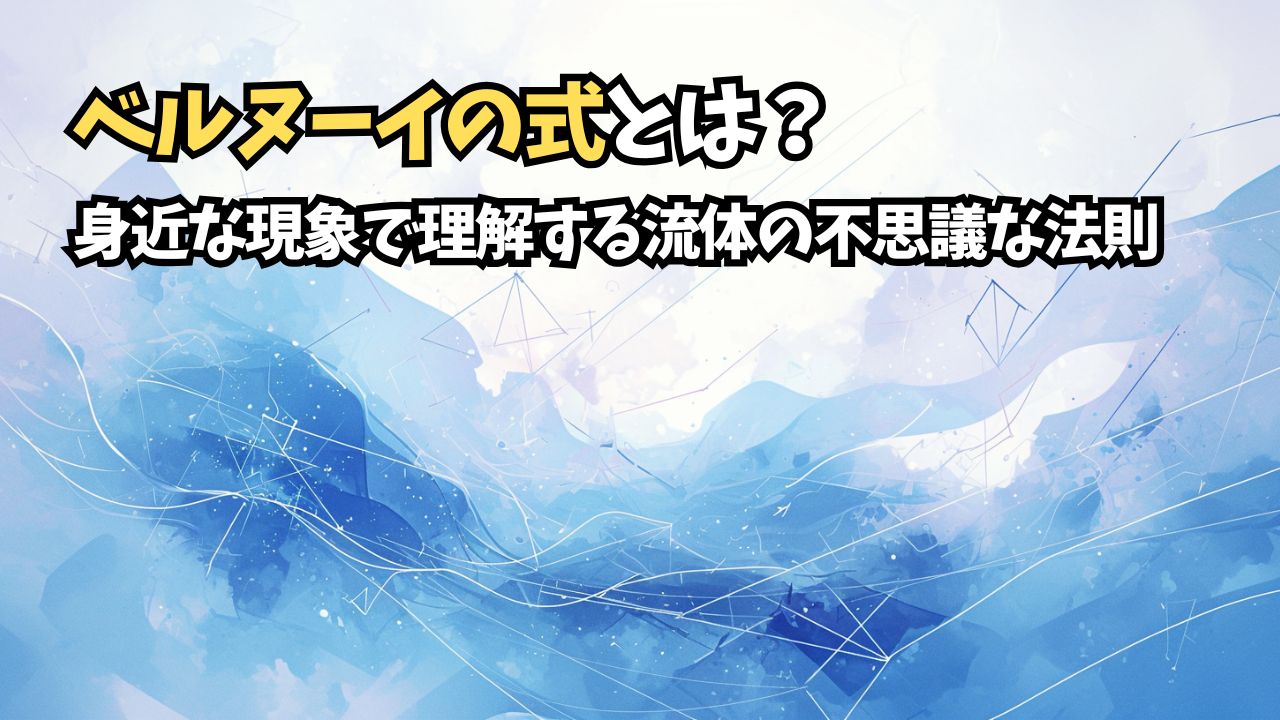「重たい飛行機がなぜ空を飛べるの?」 「電車のホームで黄色い線の内側に下がるのはなぜ?」 「霧吹きはどうして水を吸い上げるの?」
実は、これらの疑問の答えはすべて、ベルヌーイの式という一つの物理法則で説明できるんです。
18世紀にスイスの科学者ダニエル・ベルヌーイが発見したこの法則は、今でも飛行機の設計から日用品まで、私たちの生活のあらゆる場面で活用されています。
今回は、数式を最小限にして、身近な例を使いながらこの不思議な法則を解き明かしていきましょう!
ベルヌーイの式とは? – 流れる空気や水の秘密
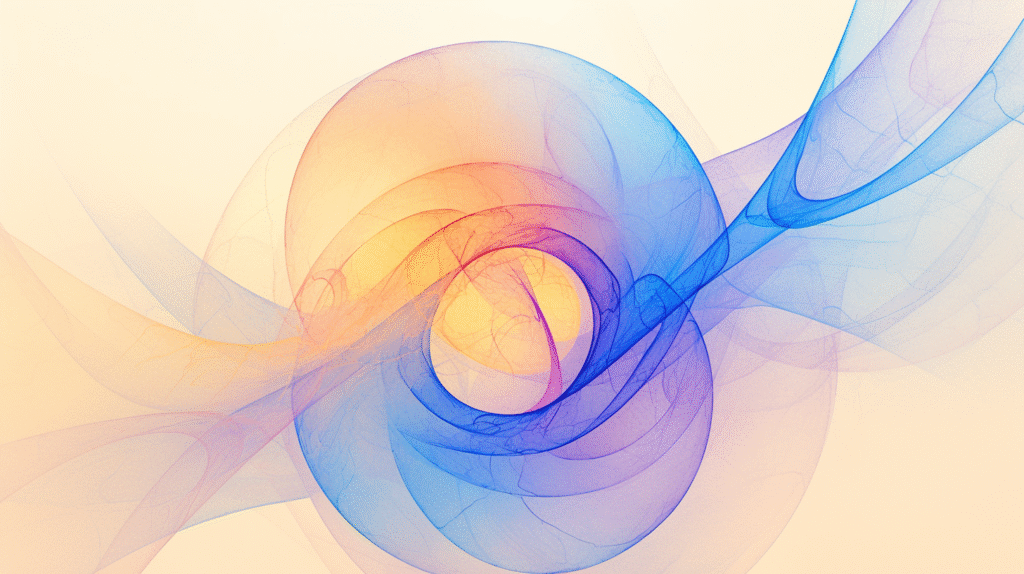
基本的な説明
ベルヌーイの式は、「流体(液体や気体)の速度と圧力の関係」を表す法則です。
簡単にいうと: 「流体の速度が速くなると、圧力が下がる」
逆に: 「流体の速度が遅くなると、圧力が上がる」
「え、速いと圧力が下がる?」と不思議に思いますよね。でも、これが自然界の面白いルールなんです。
エネルギー保存の法則との関係
ベルヌーイの式は、実は「エネルギー保存の法則」の流体版なんです。
流体が持つエネルギーは3つ:
- 運動エネルギー(速度による)
- 圧力エネルギー(押す力による)
- 位置エネルギー(高さによる)
これらの合計は常に一定。だから、速度が上がれば(運動エネルギーが増えれば)、その分だけ圧力が下がる(圧力エネルギーが減る)というわけです。
身の回りで起こるベルヌーイ現象
1. 電車とホームの危険な関係
現象の説明
駅のホームで「黄色い線より内側でお待ちください」というアナウンス、聞いたことありますよね。
これには科学的な理由があるんです:
- 電車が高速で通過すると、電車とホームの間の空気が引きずられて速く流れる
- 空気の流れが速くなると、圧力が下がる
- ホーム側の圧力の方が高くなり、人や物が電車側に引き寄せられる
実際の危険性
時速100kmで通過する電車の場合、人を引き寄せる力は相当なものになります。だから、黄色い線は命を守る大切なラインなんです。
2. 霧吹きの仕組み
現象の説明
霧吹きのレバーを押すと、なぜ下の容器から水が吸い上がるのでしょう?
- レバーを押すと、横管を空気が高速で流れる
- 横管と縦管の交差点で、空気の流れによって圧力が下がる
- 容器内の大気圧の方が高くなる
- 圧力差によって水が押し上げられる
- 吸い上げられた水が、空気の流れに乗って霧になる
香水のアトマイザーも同じ原理です。ベルヌーイの式がおしゃれに貢献しているんですね!
3. 屋根が飛ばされる理由
現象の説明
台風のニュースで「屋根が飛ばされた」という被害を聞きますが、これもベルヌーイの式で説明できます。
- 強風が屋根の上を高速で流れる
- 屋根の上の空気の圧力が下がる
- 家の中の空気の圧力の方が高くなる
- 下から上への力が発生し、屋根が持ち上げられる
対策方法
だから台風の時は、窓を少し開けて圧力差を減らすことが、時には有効な対策になるんです(ただし、状況によっては危険な場合もあるので注意が必要です)。
飛行機が飛ぶ原理 – ベルヌーイの式の最高傑作

翼の形の秘密
飛行機の翼(よく)を横から見ると、上面が膨らんでいて、下面は比較的平らです。この形を**翼型(よくがた)**といいます。
なぜこの形なのか?
- 上面の空気
- 膨らんだ部分を通るため、距離が長い
- 同じ時間で長い距離を進むため、速度が速い
- 速度が速いので、圧力が低い
- 下面の空気
- ほぼ直線的に流れるため、距離が短い
- 速度は比較的遅い
- 速度が遅いので、圧力が高い
- 結果
- 下面の圧力 > 上面の圧力
- 翼を上に押し上げる力(揚力)が発生
- 飛行機が浮き上がる!
実際の数値で考える
ジャンボジェット機(ボーイング747)の場合:
- 離陸速度:約270km/h(秒速75m)
- 最大離陸重量:約400トン
- 翼面積:約540㎡
この巨大な機体を浮かせるだけの圧力差を、ベルヌーイの原理が生み出しているんです。
日常生活で体験できる簡単な実験
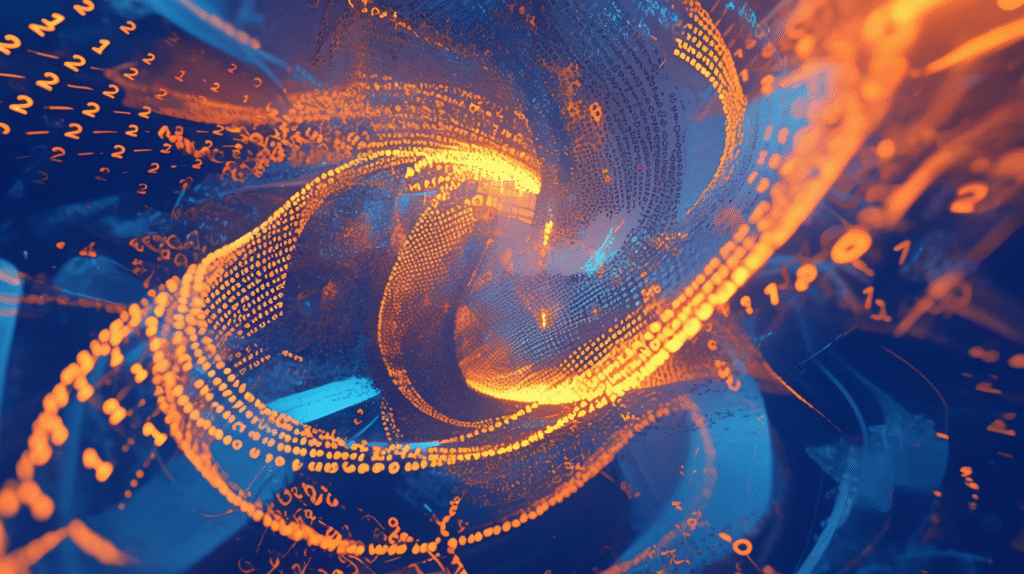
実験1:紙のトンネル
用意するもの
- A4用紙 1枚
やり方
- 紙を半分に折って、トンネル型にテーブルに置く
- トンネルの入り口から息を強く吹き込む
結果 トンネルがペシャンコにつぶれます!
なぜ?
- トンネル内を空気が高速で流れる
- 内側の圧力が下がる
- 外側の大気圧に押されてつぶれる
実験2:ピンポン球の浮遊
用意するもの
- ドライヤー 1台
- ピンポン球 1個
やり方
- ドライヤーを上向きにして風を出す
- 風の中にピンポン球を置く
結果 ピンポン球が空中で浮いたまま安定します!
なぜ?
- 風の流れの中心は速度が速く、圧力が低い
- 球が横にずれると、圧力の高い外側から押し戻される
- 結果として、中心で安定する
実験3:2枚の紙の不思議
用意するもの
- A4用紙 2枚
やり方
- 2枚の紙を5cmほど離して垂直に持つ
- 紙の間に向かって息を吹く
結果 紙が離れるどころか、くっつきます!
なぜ?
- 紙の間を空気が高速で流れる
- 間の圧力が下がる
- 外側の圧力で押されて紙が近づく
ベルヌーイの式の応用例
スポーツでの活用
野球のカーブボール
- ボールの回転により、片側の空気の流れが速くなる
- 圧力差でボールが曲がる
ゴルフボールのディンプル
- 表面の凹凸が空気の流れを変える
- より遠くまで飛ぶように設計
F1カーのウイング
- 飛行機の翼を逆さにした形
- 車体を地面に押し付ける力(ダウンフォース)を発生
工業での応用
ベンチュリ管
- 管を細くして流速を上げ、圧力差を作る
- 流量計や混合装置に利用
エアブラシ
- 霧吹きと同じ原理で塗料を噴射
- 均一な塗装が可能
キャブレター(気化器)
- エンジンに空気と燃料を混合して送る装置
- ベルヌーイの原理で燃料を吸い上げる
よくある誤解と注意点
誤解1:速度が上がると必ず浮く?
正しい理解
速度だけでなく、形状や角度(迎え角)も重要です。平らな板でも、適切な角度をつければ揚力は発生します。
誤解2:ベルヌーイの式だけで飛行機は飛ぶ?
正しい理解
実際の飛行機の揚力は:
- ベルヌーイの原理(圧力差)
- ニュートンの第3法則(作用・反作用)
- 翼の迎え角による効果
これらが組み合わさって生まれています。
誤解3:どんな流体でも同じ?
正しい理解
ベルヌーイの式が正確に成り立つのは:
- 非圧縮性流体(水など)
- 低速の空気(音速の約30%以下)
- 粘性が無視できる場合
実際の応用では、これらの条件から外れる場合の補正も必要です。
ベルヌーイの式を式で表すと
基本の式(参考程度に)
数式が苦手な方は読み飛ばしても大丈夫ですが、参考までに:
P + (1/2)ρv² + ρgh = 一定
- P:圧力
- ρ(ロー):流体の密度
- v:流速
- g:重力加速度
- h:高さ
この式は「圧力エネルギー + 運動エネルギー + 位置エネルギー = 一定」を表しています。
まとめ – 見えない力が創り出す不思議な世界
ベルヌーイの式について、身近な例を通じて理解していただけましたか?
覚えておきたいポイント
✅ 流体の速度が速い → 圧力が低い
✅ 流体の速度が遅い → 圧力が高い
✅ この原理が飛行機を飛ばし、霧吹きを動かしている
✅ エネルギー保存の法則が根底にある
普段は意識しない空気や水の流れにも、こんな法則が働いているんです。
次に飛行機に乗るとき、霧吹きを使うとき、強風の日に外を歩くとき、ベルヌーイの式を思い出してみてください。世界の見え方が少し変わるかもしれません。
物理法則は決して難しい教科書の中だけのものではなく、私たちの生活を支え、時には命を守る大切な知識なんです。この記事が、科学の面白さを感じるきっかけになれば幸いです!