三角形と直線、三角形と点…シンプルな図形の組み合わせに、実は驚くべき法則が隠されています。
それがメネラウスの定理とチェバの定理です。
「定理」と聞くと難しそうですが、実はこの2つ、**「比の掛け算が1になる」**という超シンプルな法則なんです。
建築やデザイン、さらにはゲームのグラフィックスにも使われている、実用的な定理でもあります。
今回は、この2つの定理を具体例とイラスト感覚の説明で、誰でも使いこなせるようになるまで解説します!
メネラウスの定理:直線が三角形を横切るとき
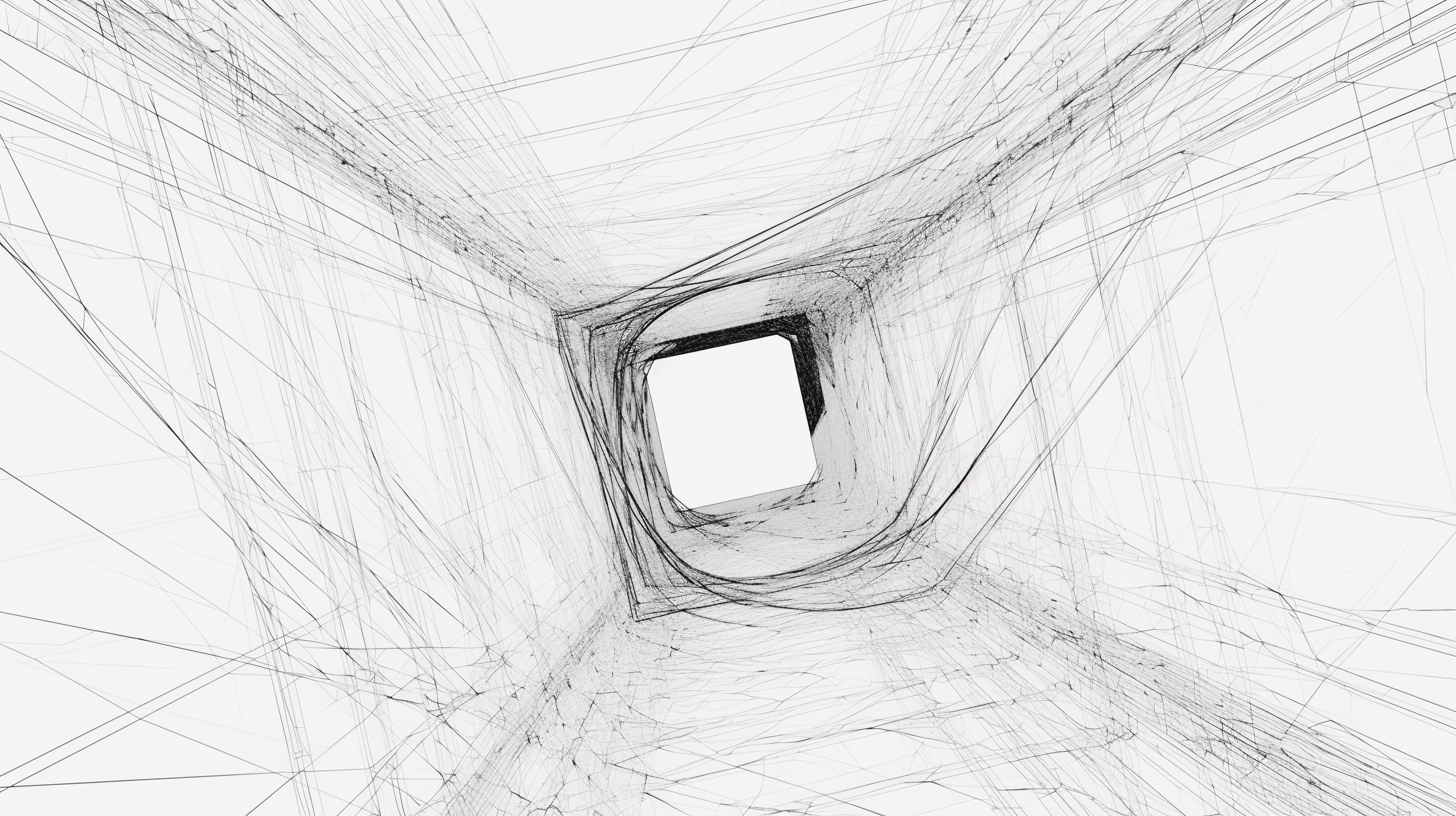
メネラウスの定理とは?
三角形を1本の直線が横切るとき、辺の比に関する美しい関係が成り立ちます。
古代ギリシャの数学者メネラウス(紀元後70-130年頃)が発見した定理です。
定理の内容
三角形ABCの辺BC、CA、ABまたはその延長線が、1つの直線と点P、Q、Rで交わるとき:
BP/PC × CQ/QA × AR/RB = 1
覚え方のコツ:「ぐるっと一周」
イメージで覚える方法
- 三角形の頂点から出発
- 交点まで進む(分子)
- 次の頂点まで進む(分母)
- これを3回繰り返して一周
- 全部掛けると1になる!
例:頂点Bからスタート
- B→P/P→C(BP/PC)
- C→Q/Q→A(CQ/QA)
- A→R/R→B(AR/RB)
ぐるっと一周して元に戻る感じです!
具体例で理解しよう
例題1:基本パターン
三角形ABCで、直線が辺を横切り:
- BP : PC = 2 : 3
- CQ : QA = 3 : 1
このとき、AR : RB は?
解法
メネラウスの定理より:
(2/3) × (3/1) × (AR/RB) = 1
2 × (AR/RB) = 1
AR/RB = 1/2
つまり、AR : RB = 1 : 2
なぜ成り立つの?:面積で考える
メネラウスの定理が成り立つ理由を、面積を使って直感的に理解してみましょう。
三角形を直線が横切ると、いくつかの小さな三角形に分かれます。
これらの面積の比が、辺の比と関係しているんです。
ポイント
- 同じ高さの三角形は、底辺の比 = 面積の比
- この関係を組み合わせると定理が導ける
チェバの定理:1点から伸びる3本の線
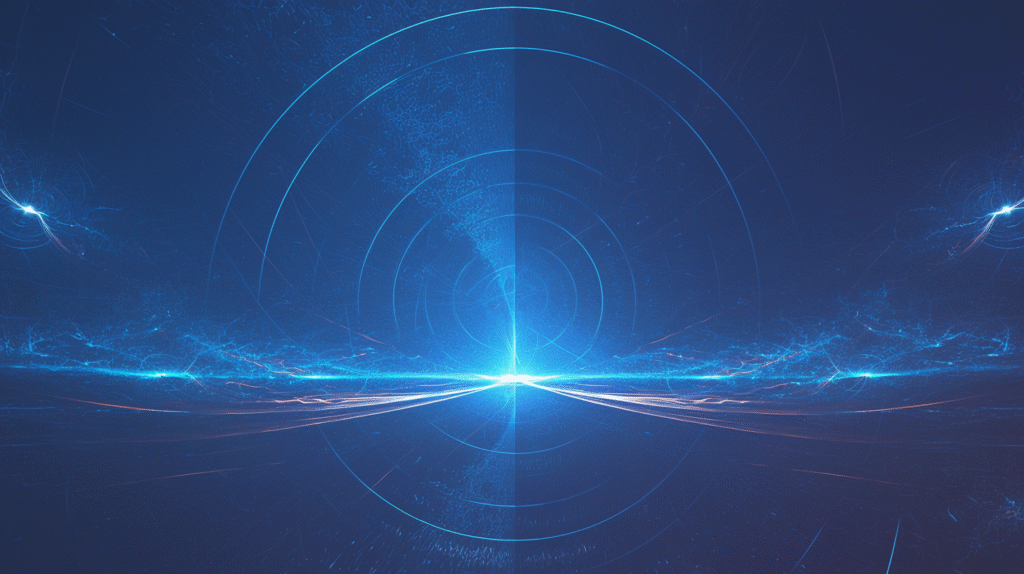
チェバの定理とは?
三角形の内部(または外部)の1点から各頂点への線を引いたときの、辺の比の関係を表す定理です。
イタリアの数学者ジョバンニ・チェバ(1647-1734)が発見しました。
定理の内容
三角形ABCの内部または外部に点Oがあり、AOの延長線がBCと点Pで、BOの延長線がCAと点Qで、COの延長線がABと点Rで交わるとき:
BP/PC × CQ/QA × AR/RB = 1
あれ?メネラウスと同じ式?
そうなんです!式の形は同じですが、図形の状況が違います。
- メネラウス:1本の直線が三角形を横切る
- チェバ:1点から3本の線が出る
この違いが重要です!
具体例で理解しよう
例題1:重心の性質
三角形の重心は、各頂点と対辺の中点を結ぶ線(中線)の交点です。
このとき、各辺は中点で分けられるので:
- BP : PC = 1 : 1
- CQ : QA = 1 : 1
- AR : RB = 1 : 1
チェバの定理で確認:
(1/1) × (1/1) × (1/1) = 1 ✓
成立しています!
例題2:内心・外心・垂心も
実は、三角形の「五心」(重心、内心、外心、垂心、傍心)はすべてチェバの定理を満たします。
チェバの定理の逆
重要な性質
辺の比が BP/PC × CQ/QA × AR/RB = 1 を満たすなら、3本の線AP、BQ、CRは1点で交わります!
これを使えば、「3本の線が1点で交わることの証明」ができるんです。
メネラウスとチェバの見分け方
図形で判断する方法
メネラウスの定理を使う場合
- 直線が三角形を「串刺し」にしている
- 交点が辺上に「一直線」に並んでいる
- 外部の直線が関係している
チェバの定理を使う場合
- 三角形の内部(または外部)に「1つの点」がある
- その点から「放射状」に線が出ている
- 3本の線が「1点で交わる」
覚え方の語呂合わせ
メネラウス 「メ(目)ネラって、一直線」 → 直線を狙う(一直線)
チェバ 「チェ(中)バ(場)に集合」 → 中心の1点に集まる
実践問題で腕試し!
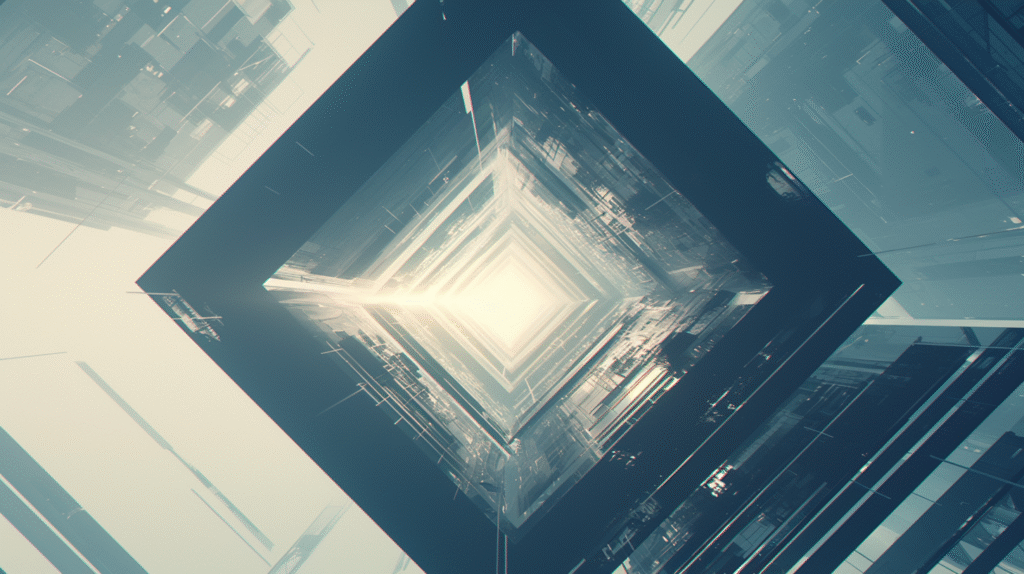
問題1:メネラウスの定理
三角形ABCで、辺BCを2:1に内分する点をP、辺CAを3:2に内分する点をQとする。 直線PQと辺ABの延長線の交点をRとするとき、AR:RBを求めよ。
解答
与えられた条件:
- BP : PC = 2 : 1
- CQ : QA = 3 : 2
メネラウスの定理より:
(BP/PC) × (CQ/QA) × (AR/RB) = 1
(2/1) × (3/2) × (AR/RB) = 1
3 × (AR/RB) = 1
AR/RB = 1/3
答え:AR : RB = 1 : 3
問題2:チェバの定理
三角形ABCの辺BC、CA、ABを、それぞれ3:2、4:1、2:3に内分する点をP、Q、Rとする。 このとき、AP、BQ、CRは1点で交わることを示せ。
解答
与えられた条件:
- BP : PC = 3 : 2
- CQ : QA = 4 : 1
- AR : RB = 2 : 3
チェバの定理の逆を確認:
(BP/PC) × (CQ/QA) × (AR/RB)
= (3/2) × (4/1) × (2/3)
= (3 × 4 × 2)/(2 × 1 × 3)
= 24/6
= 4... あれ?
※この場合は1にならないので、実は1点で交わりません!
問題3:応用問題
三角形ABCの重心をGとし、直線AGと辺BCの交点をPとする。 BP:PCを求めよ。
解答
重心の性質より、Pは辺BCの中点。
したがって、BP : PC = 1 : 1
定理の拡張と発展
符号付きの比
外分点の場合
点が辺の延長線上にある場合、比に負の符号をつけて考えます。
例:点RがABの延長線上でBの外側にある場合
- AR : RB = 5 : (-2) のように表現
この場合も定理は成立します!
空間への拡張
四面体でのメネラウス・チェバ
三角形の定理は、四面体(三角錐)にも拡張できます。
面と直線の交点、頂点から対面への線など、3次元でも美しい関係が成り立ちます。
ベクトルでの表現
位置ベクトルを使った証明
メネラウス・チェバの定理は、ベクトルを使うとエレガントに証明できます。
大学数学では、この方法がよく使われます。
実生活での応用
建築・設計での利用
トラス構造の計算
橋や建物の骨組み(トラス)の力の分配を計算する際、これらの定理が活用されます。
コンピュータグラフィックス
3Dモデリング
ポリゴンの分割や、光の反射計算などで、三角形の性質を利用します。
地図・測量
三角測量
GPS以前は、三角形の性質を使って位置を特定していました。
メネラウス・チェバの定理も、間接的に関係しています。
よくある間違いと注意点
間違い1:比の向きを間違える
正しい向き
- 必ず「点→点」の向きを統一
- 分子と分母で向きを揃える
間違い2:どちらの定理か迷う
判断基準
- 直線が見える → メネラウス
- 中心点が見える → チェバ
間違い3:外分を考慮し忘れる
注意
- 延長線上の点も含める
- 外分の場合は符号に注意
覚えておくべき特別な場合
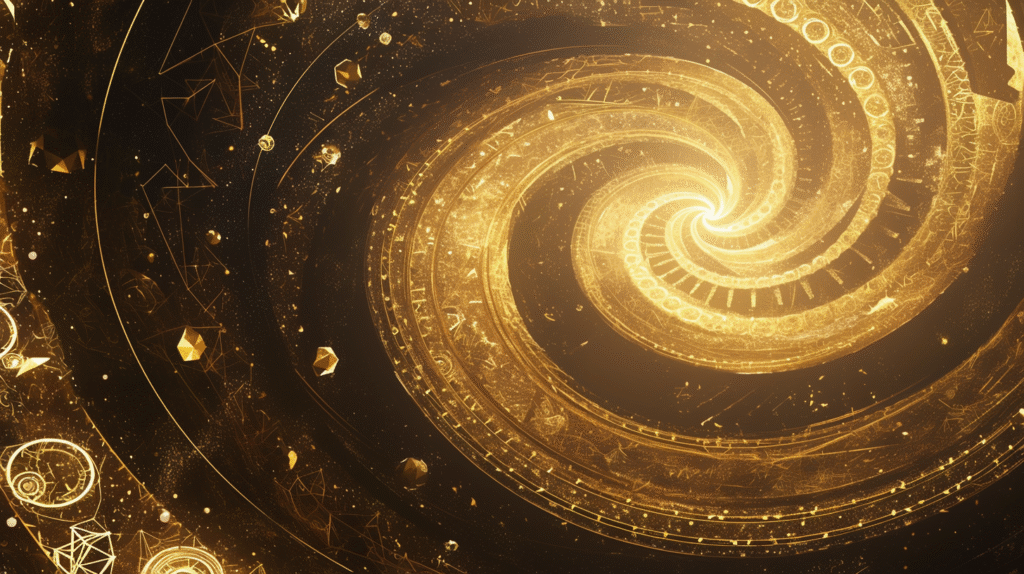
角の二等分線の定理との関係
角の二等分線が対辺を分ける比は、隣接する2辺の比に等しい。
これもチェバの定理から導けます!
中線定理との関係
三角形の3本の中線は1点(重心)で交わる。
これはチェバの定理の特別な場合です。
内心の性質
三角形の3つの角の二等分線は1点(内心)で交わる。
これもチェバの定理で証明できます。
よくある質問
Q1. どっちがメネラウスでどっちがチェバ?
A. 覚え方のコツ:
- メネラウス → ライン(線)
- チェバ → センター(中心)
Q2. なぜ積が1になるの?
A. 幾何学的には「バランス」を表しています。
物理的には、てこの原理のような釣り合いの関係です。
Q3. 証明問題でいつ使う?
A. こんな時に便利:
- 3点が一直線上にあることの証明
- 3直線が1点で交わることの証明
- 辺の比を求める問題
まとめ:2つの定理で三角形マスター!
今回はメネラウスの定理とチェバの定理について詳しく解説しました。
押さえておきたいポイント
? メネラウスの定理
- 1本の直線が三角形を横切る
- BP/PC × CQ/QA × AR/RB = 1
- 「ぐるっと一周」で覚える
? チェバの定理
- 1点から3本の線が出る
- BP/PC × CQ/QA × AR/RB = 1(式は同じ)
- 3線が1点で交わる条件
? 見分け方
- 直線が主役 → メネラウス
- 点が主役 → チェバ
? 使いどころ
- 比の計算問題
- 共点・共線の証明
- 五心の性質の証明
これらの定理は、一見複雑な図形問題を、シンプルな比の計算に変換してくれる「魔法の道具」です。
最初は図形を見て「どっちの定理?」と迷うかもしれませんが、練習すればすぐに見分けられるようになります。
三角形の美しい性質を、ぜひ楽しんでマスターしてください!

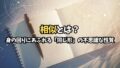

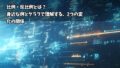




コメント