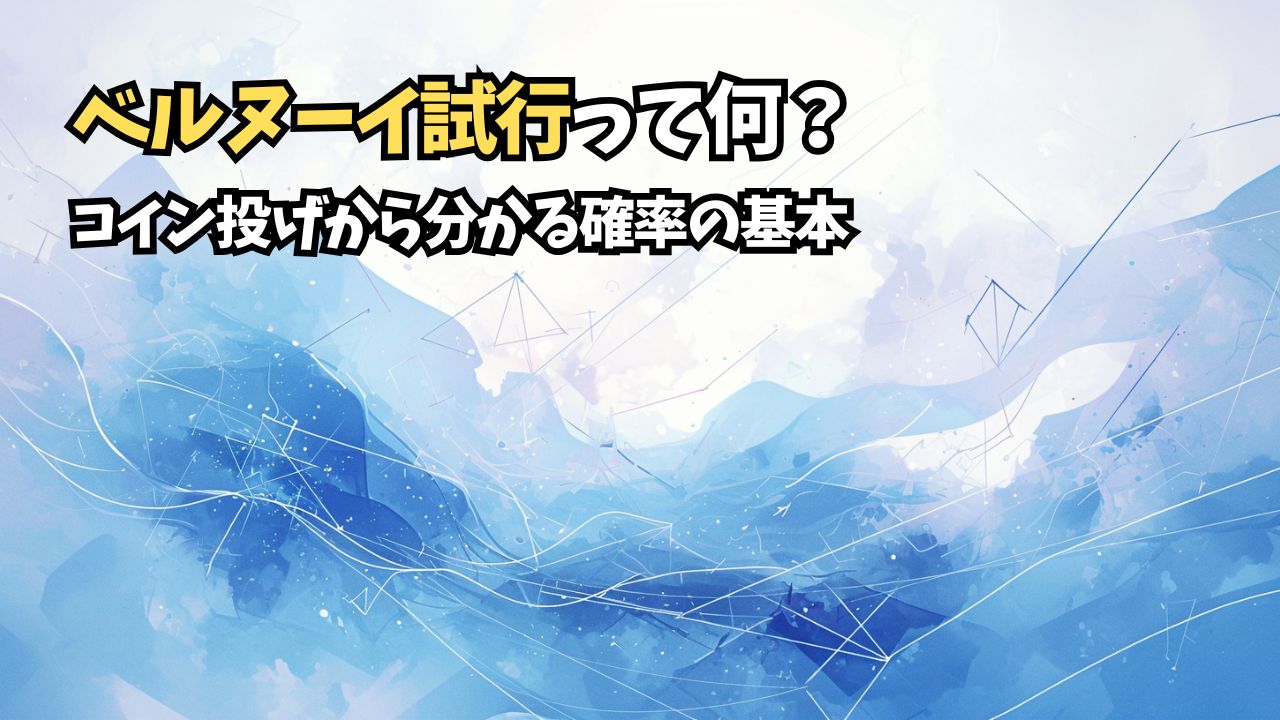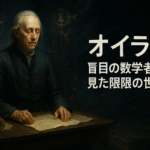「ベルヌーイ試行」って聞くと、なんだか難しそうな名前ですよね。
でも実は、あなたも毎日のようにベルヌーイ試行をしているんです。 朝起きて天気予報を見て「今日雨降るかな?降らないかな?」と考えたり、 テストで「この問題、正解できるかな?」と思ったり。
これらすべて、ベルヌーイ試行の考え方なんです。
今回は、この一見難しそうな「ベルヌーイ試行」を、コイン投げやサイコロなどの身近な例を使って、誰でも理解できるように解説していきます。
この記事を読み終わる頃には、「なんだ、こんなシンプルなことだったのか!」と思えるはずですよ。
ベルヌーイ試行の正体を明らかにしよう
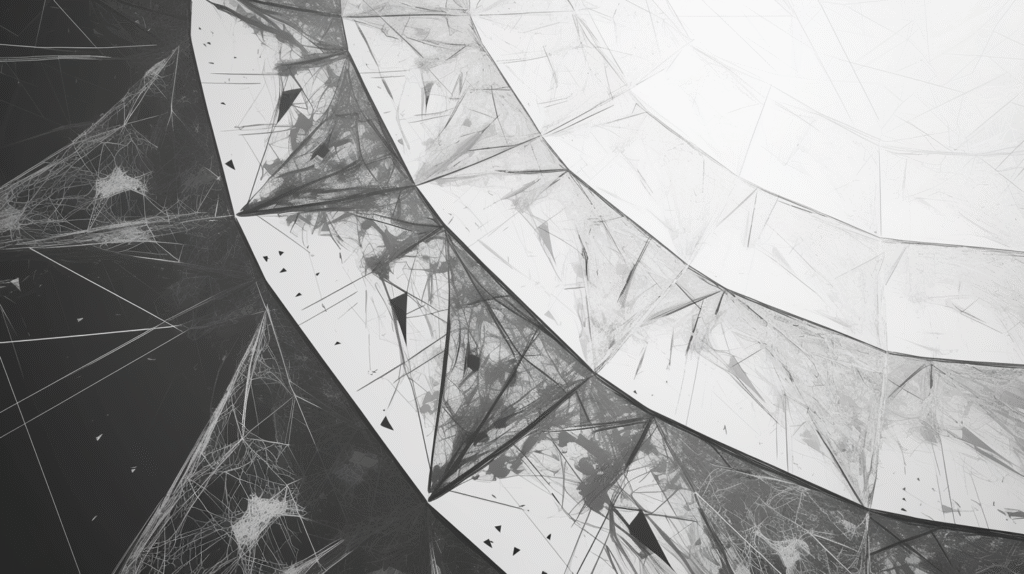
そもそもベルヌーイ試行って何?
ベルヌーイ試行とは、簡単に言うと「結果が2つしかない実験や試み」のことです。
もっと分かりやすく言うと: 成功するか、失敗するか。当たるか、外れるか。表か、裏か。 このように、結果が2種類だけの試行のことなんです。
名前の由来は、18世紀のスイスの数学者ヤコブ・ベルヌーイさんから来ています。 でも、名前なんて覚えなくても大丈夫。大切なのは中身です!
ベルヌーイ試行の3つの条件
ある試行がベルヌーイ試行と呼べるためには、3つの条件を満たす必要があります。
条件1:結果は2種類だけ
- 成功 or 失敗
- YES or NO
- 表 or 裏 中間はありません。
条件2:成功する確率は一定 何回やっても、成功する確率は変わりません。 コインなら、いつ投げても表が出る確率は1/2です。
条件3:各試行は独立している 前の結果が、次の結果に影響しません。 コインで3回連続表が出ても、次に表が出る確率は変わらず1/2です。
この3つさえ満たせば、それはベルヌーイ試行なんです!
身近な例で理解を深める
ベルヌーイ試行の例、実はたくさんあります。
完璧なベルヌーイ試行の例:
- コイン投げ(表か裏か)
- サイコロで「6が出るか、出ないか」
- くじ引きで「当たりか、はずれか」(ただし、くじを戻す場合)
- 〇×クイズの答え(正解か不正解か)
日常生活での例:
- 電車が時間通りに来るか、遅れるか
- 明日雨が降るか、降らないか
- 商品が不良品か、正常品か
- メールが迷惑メールか、普通のメールか
厳密には確率が一定じゃないものもありますが、ベルヌーイ試行として扱うことが多いんです。
コイン投げで学ぶベルヌーイ試行
最もシンプルな例:コイン投げ
コイン投げは、ベルヌーイ試行の代表選手です。
- 結果:表(成功)or 裏(失敗)
- 確率:表が出る確率 = 1/2、裏が出る確率 = 1/2
- 独立性:前の結果は次に影響しない
1回投げるごとに、これが1回のベルヌーイ試行になります。
複数回のベルヌーイ試行
コインを3回投げたらどうなるでしょう?
可能な結果のパターン:
- 表・表・表
- 表・表・裏
- 表・裏・表
- 表・裏・裏
- 裏・表・表
- 裏・表・裏
- 裏・裏・表
- 裏・裏・裏
全部で8通り(2×2×2 = 2³)あります。
このうち、「ちょうど2回表が出る」のは: 表・表・裏、表・裏・表、裏・表・表 の3通り
確率は 3/8 になります。
計算の公式を理解しよう
n回の試行で、ちょうどk回成功する確率は:
確率 = (組み合わせの数) × (成功確率)^k × (失敗確率)^(n-k)
難しそうに見えますが、実は簡単!
例:コインを3回投げて、2回表が出る確率
- 組み合わせの数:3C2 = 3通り
- 成功確率(表):1/2
- 失敗確率(裏):1/2
確率 = 3 × (1/2)² × (1/2)¹ = 3 × 1/4 × 1/2 = 3/8
さっきの答えと同じになりましたね!
サイコロで考えるベルヌーイ試行

サイコロもベルヌーイ試行になる?
「サイコロは6つの目があるから、ベルヌーイ試行じゃないのでは?」
いい質問です!でも、見方を変えればベルヌーイ試行になるんです。
例えば:「6が出るか、出ないか」で考える
- 成功(6が出る):確率 1/6
- 失敗(6以外):確率 5/6
これなら立派なベルヌーイ試行です!
実際に計算してみよう
問題:サイコロを4回振って、6がちょうど1回出る確率は?
計算:
- 試行回数 n = 4
- 成功回数 k = 1
- 成功確率 p = 1/6
- 失敗確率 q = 5/6
組み合わせ:4C1 = 4通り
確率 = 4 × (1/6)¹ × (5/6)³ = 4 × 1/6 × 125/216 = 500/1296 ≈ 0.386(約38.6%)
意外と高い確率ですね!
偶数・奇数で考える場合
サイコロで「偶数が出るか、奇数が出るか」なら:
- 偶数(2,4,6):確率 3/6 = 1/2
- 奇数(1,3,5):確率 3/6 = 1/2
これもベルヌーイ試行で、コイン投げと同じ確率構造になります。
実生活でのベルヌーイ試行
品質管理での活用
工場で製品を作るとき、不良品が出る確率を考えます。
例:ある工場の不良品率が2%の場合
- 成功(正常品):98%
- 失敗(不良品):2%
100個作ったとき、不良品が3個以下になる確率は? これもベルヌーイ試行で計算できます。
品質管理では、この確率を使って「異常かどうか」を判断するんです。
スポーツでの応用
バスケットボールのフリースローを考えてみましょう。
選手Aのフリースロー成功率が70%の場合:
- 成功:70%
- 失敗:30%
5本投げて、4本以上入る確率は?
計算すると約52.8%になります。 半分ちょっとの確率で4本以上入るということですね。
ゲームやギャンブルでの確率
ガチャゲームでレアキャラが出る確率が1%の場合:
- 成功(レアキャラ):1%
- 失敗(その他):99%
100回引いて、1回も出ない確率は? (0.99)^100 ≈ 0.366(約36.6%)
意外と高いですよね。100回引いても3人に1人は出ないんです。
ベルヌーイ試行から発展する概念

二項分布への橋渡し
ベルヌーイ試行を何回も繰り返したときの成功回数の分布を「二項分布」といいます。
例:コインを10回投げたときの表の回数
- 0回:約0.1%
- 5回:約24.6%(最も確率が高い)
- 10回:約0.1%
真ん中あたりが最も起こりやすく、両端は起こりにくい。 これが二項分布の特徴です。
期待値と分散
n回のベルヌーイ試行で、成功確率がpのとき:
期待値(平均的な成功回数)= n × p
例:サイコロを60回振って6が出る回数の期待値 = 60 × 1/6 = 10回
分散(ばらつきの大きさ)= n × p × (1-p)
この公式を使えば、結果のばらつきも予測できます。
大数の法則との関係
ベルヌーイ試行を何度も繰り返すと、成功の割合は理論的な確率に近づいていきます。
コイン投げの例:
- 10回:表が3回(30%)かもしれない
- 100回:表が45回(45%)かもしれない
- 1000回:表が490回(49%)かもしれない
- 10000回:表が4980回(49.8%)かもしれない
回数が増えるほど、50%に近づいていくんです。 これが「大数の法則」です。
よくある誤解と注意点
誤解1:連続の錯覚
「コインで5回連続表が出たから、次は裏が出やすい」
これは間違い! コインに記憶はありません。次も表が出る確率は1/2です。
これを「ギャンブラーの誤謬(ごびゅう)」といいます。
誤解2:確率の解釈
「成功確率30%なら、10回やれば3回成功する」
これも正確ではありません。 期待値は3回ですが、実際は2回かもしれないし、5回かもしれません。
確率は「長期的な傾向」を表すものです。
誤解3:独立性の勘違い
「前回当たったから、今回は当たりにくい」
くじ引きで、くじを戻さない場合はこれが正しいです。 でも、くじを戻す場合やコイン投げでは、毎回確率は同じです。
独立性があるかないか、これが重要なポイントです。
練習問題で理解を確認しよう
基本問題
問題1:コインを5回投げて、3回以上表が出る確率は?
考え方: 3回、4回、5回表が出る確率をそれぞれ計算して足す。
- 3回:10 × (1/2)⁵ = 10/32
- 4回:5 × (1/2)⁵ = 5/32
- 5回:1 × (1/2)⁵ = 1/32
合計:16/32 = 1/2
答え:50%
応用問題
問題2:ある選手のシュート成功率が40%。3本投げて少なくとも1本入る確率は?
考え方: 「少なくとも1本」は「1本も入らない」の反対。
1本も入らない確率 = (0.6)³ = 0.216 少なくとも1本入る確率 = 1 – 0.216 = 0.784
答え:約78.4%
チャレンジ問題
問題3:不良品率5%の製品を20個検査して、不良品が2個以下である確率を求めよ。
これは計算が複雑になりますが、考え方は同じです。 0個、1個、2個の場合をそれぞれ計算して足します。
実際の計算では、二項分布表や計算機を使うことが多いですね。
ベルヌーイ試行を使いこなすコツ
ステップ1:2つの結果に整理する
どんな問題でも、まず「成功」と「失敗」の2つに分けましょう。
例:テストで80点以上取る
- 成功:80点以上
- 失敗:80点未満
ステップ2:確率を確認する
成功する確率は何%か、はっきりさせます。 分からない場合は、過去のデータから推定することもあります。
ステップ3:独立性をチェック
各試行が独立しているか確認します。 前の結果が次に影響する場合は、ベルヌーイ試行として扱えません。
ステップ4:公式を適用する
条件が整ったら、公式を使って計算します。 複雑な場合は、表計算ソフトや電卓を活用しましょう。
まとめ:ベルヌーイ試行は確率の基本中の基本
ベルヌーイ試行について、基礎から応用まで解説してきました。
押さえるべきポイント:
- 結果が2種類(成功 or 失敗)
- 成功確率は一定
- 各試行は独立している
- 日常生活にたくさん応用例がある
ベルヌーイ試行は、確率論の入門として最適な概念です。 これを理解すれば、二項分布、ポアソン分布、正規分布など、より高度な確率分布も理解しやすくなります。
コイン投げから品質管理まで、幅広く使われるベルヌーイ試行。 難しそうな名前に惑わされず、「2つの結果しかない試行」という本質を理解すれば、意外とシンプルだということが分かったはずです。
今日から、日常生活の中でベルヌーイ試行を見つけてみてください。 きっと、あちこちに隠れていることに気づくはずですよ!