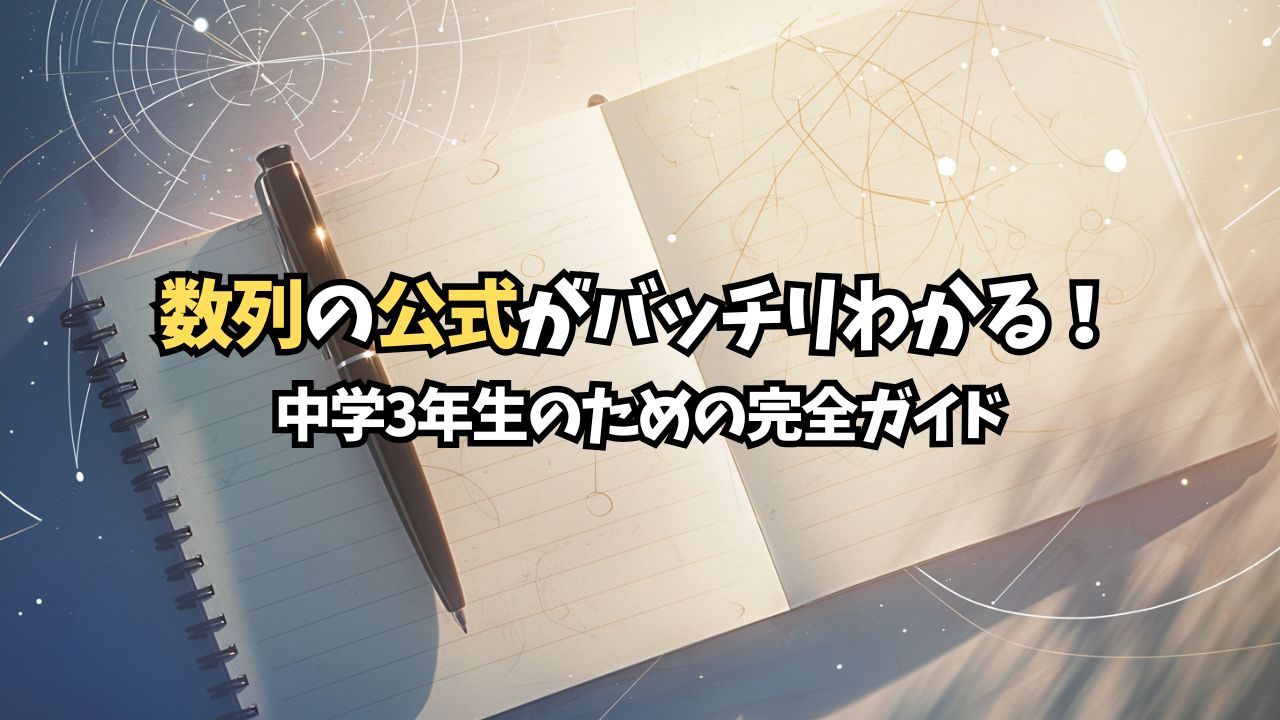「数列の公式」と聞くと、なんだか難しそう…と思いますよね。
でも実は、数列は私たちの生活の中にたくさん隠れているんです!
- 階段を登るときの段数(1段、2段、3段…)
- 毎月のお小遣いの貯金額(1000円、2000円、3000円…)
- TikTokの再生回数の増え方(100回→200回→400回…)
この記事では、等差数列と等比数列という2つの重要な数列を中心に、公式の使い方から覚え方のコツまで、じっくり解説していきます。
「なんでこの公式になるの?」「どうやって使い分けるの?」
そんな疑問にも、しっかり答えていきますよ!
1. 数列の基本をマスターしよう
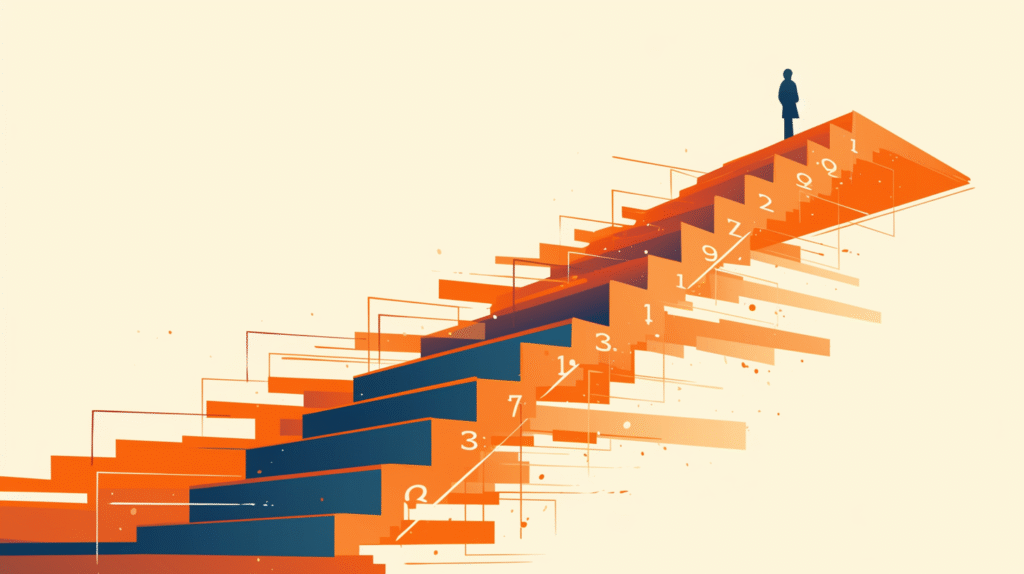
そもそも数列って何?
数列(すうれつ)とは、ある規則に従って並んだ数の列のこと。
例えばこんな感じ:
奇数の列: 1, 3, 5, 7, 9…
2倍ずつ増える列: 2, 4, 8, 16, 32…
フィボナッチ数列: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…
それぞれの数のことを**項(こう)**と呼びます。
- 初項(しょこう):最初の数
- 末項(まっこう):最後の数
- 第n項(だいエヌこう):n番目の数
数列の3大スター
① 等差数列(とうさすうれつ)
一定の数ずつ増える(または減る)数列
例:3, 6, 9, 12, 15…(3ずつ増える)
② 等比数列(とうひすうれつ)
一定の数を掛けていく数列
例:2, 6, 18, 54…(3倍ずつ増える)
③ 階差数列(かいさすうれつ)
隣り合う項の差で作る数列
例:元が 5, 11, 21, 35… なら、階差は 6, 10, 14…
2. 等差数列の公式を完璧に理解する
? 一般項の公式(n番目の項を求める)
公式:aₙ = a₁ + (n-1)d
- aₙ:第n項(n番目の数)
- a₁:初項(最初の数)
- n:何番目か
- d:公差(こうさ)- 隣り合う項の差
なぜこの公式になるの?
階段を思い浮かべてみてください。
1段目から始めて、毎回同じ高さ(d)ずつ登っていきます。n段目に到達するには、(n-1)回登る必要がありますよね(だって1段目にはすでにいるから)。
だから、n段目の高さは「最初の高さ + d×(n-1)」になるんです!
具体例で確認しよう
例題: 数列 5, 8, 11, 14, … の10番目の項は?
解き方:
- 初項 a₁ = 5
- 公差 d = 8-5 = 3
- 求めるのは n = 10
計算:a₁₀ = 5 + (10-1)×3 = 5 + 27 = 32
簡単でしょ?
? 和の公式(1番目からn番目までの合計)
末項がわかるとき:
Sₙ = n(a₁ + aₙ)/2
末項がわからないとき:
Sₙ = n{2a₁ + (n-1)d}/2
ガウスの天才的な発見
数学者ガウスが小学生のときに発見した方法がすごいんです!
1から100までの和を求めるとき:
1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100
100 + 99 + 98 + ... + 3 + 2 + 1
-----------------------------------
101 + 101 + 101 + ... + 101(100個)
答え:101×100÷2 = 5050
天才すぎる!
? 実生活での等差数列
- 階段の設計:各段の高さが一定(約18cm)
- 定期預金:毎月1万円ずつ貯金
- 映画館の座席:後ろの列ほど2席ずつ増える
- タクシー料金:410円スタート、237mごとに80円追加
3. 等比数列の公式をマスターする
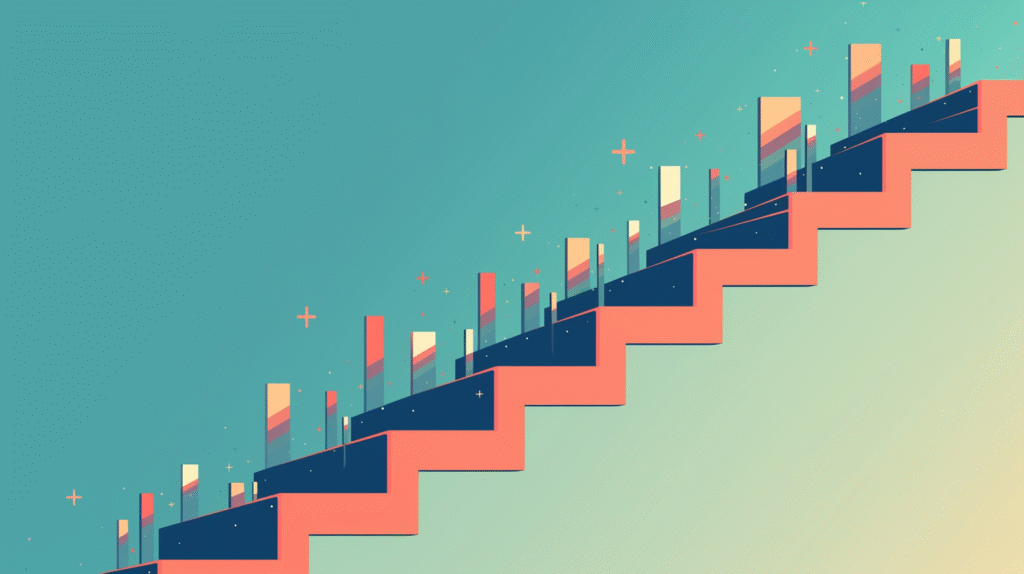
? 一般項の公式
公式:aₙ = a₁ × r^(n-1)
- r:公比(こうひ)- 隣り合う項の比
なぜ(n-1)乗なの?
これも階段で考えましょう。
1段目にいて、各段で「r倍」ジャンプします。n段目に到達するには、(n-1)回ジャンプが必要。だから r^(n-1) になるんです!
? 和の公式
r ≠ 1のとき:
Sₙ = a₁(1-r^n)/(1-r)
r = 1のとき:
Sₙ = na₁(全部同じ数だから単純にn倍)
無限等比級数(|r| < 1のとき)
公式:S∞ = a₁/(1-r)
公比が1より小さいと、どんどん小さくなって最終的に収束するんです。
具体例で理解を深める
例題(複利計算): 1000円を年利5%で預けたら、10年後はいくら?
解き方:
- 初項 a₁ = 1000円
- 公比 r = 1.05(5%増 = 1.05倍)
- 10年後は10番目の項
計算:a₁₀ = 1000 × 1.05^9 ≈ 1551円
複利ってすごい!
? 実生活での等比数列
- コロナの感染拡大:1人→2人→4人→8人…
- 紙を折る:1回折ると2倍の厚さ(42回で月に届く!)
- YouTubeのバイラル動画:シェアが倍々で増える
- 半減期:放射性物質が半分ずつ減る
4. その他の重要な数列と公式
Σ(シグマ)記号の使い方
Σは「合計」を表す便利な記号です。
書き方: Σₖ₌₁ⁿ k = 1+2+3+…+n
読み方: 「k=1からnまでのkの総和」
覚えておくべき重要な公式
1からnまでの和:
Σₖ₌₁ⁿ k = n(n+1)/2
平方の和:
Σₖ₌₁ⁿ k² = n(n+1)(2n+1)/6
立方の和:
Σₖ₌₁ⁿ k³ = {n(n+1)/2}²
面白いことに、立方の和は「和の2乗」になるんです!不思議でしょ?
? フィボナッチ数列の不思議
定義: 前の2つの項を足して次の項を作る
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…
自然界での出現:
- ひまわりの種の配列(螺旋が21個と34個)
- 松ぼっくりの鱗片(8個と13個の螺旋)
- 花びらの数(3枚、5枚、8枚が多い)
自然って数学的!
5. 公式の覚え方のコツ
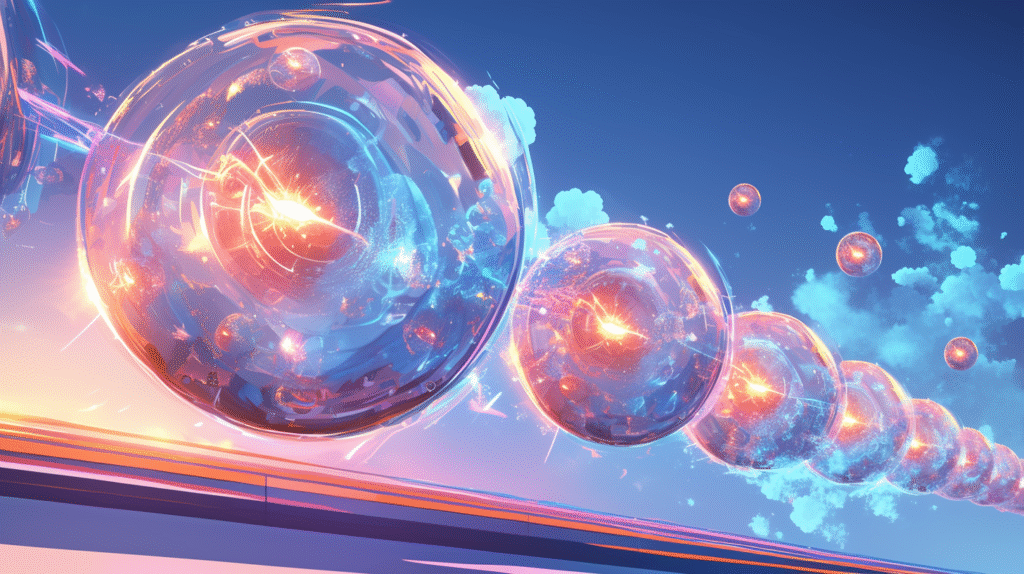
? 語呂合わせとイメージ記憶
基本の覚え方:
「等差は足し算、等比は掛け算」
色分け記憶法:
- a₁を?青
- dを?赤
- nを?緑
視覚的に公式の構造が頭に入ります!
ストーリー記憶法:
「初項くん(a₁)が、公差さん(d)と一緒に(n-1)段の階段を登る」
⚠️ よくある間違いを防ぐチェックポイント
間違い①: n と (n-1) の混同
対策→ 「自分は1段目にいる」と常に意識
間違い②: 等差と等比の公式を混同
対策→ まず差を計算、次に比を計算
間違い③: 符号のミス(特に負の公差)
対策→ 数直線を描いて確認
6. 問題を解くときの黄金ルール
? STEP法で確実に解く
Search(情報整理):何がわかっていて、何を求める?
Type(判別):等差?等比?それとも?
Equation(公式選択):適切な公式を選ぶ
Process(計算):丁寧に計算して答えを確認
判別のフローチャート
隣の項との差を計算
↓
差が一定? → YES → 等差数列!
↓ NO
隣の項との比を計算
↓
比が一定? → YES → 等比数列!
↓ NO
階差数列などを検討
7. 日常生活での応用例
? お金の計算で使う数列
単利計算(等差数列):
10万円を年利3%の単利で運用
→ 10万、10.3万、10.6万、10.9万…
複利計算(等比数列):
10万円を年利3%の複利で運用
→ 10万、10.3万、10.609万、10.927万…
20年後の差は約1.8万円!複利のパワーってすごい。
? スポーツやゲームでの数列
トーナメント戦:
16チームなら15試合必要(n-1の法則)
ポイント倍々キャンペーン:
初日10pt、毎日2倍なら…
- 1日目:10pt
- 2日目:20pt
- 3日目:40pt
- 7日目:640pt!
まとめ:数列の公式は怖くない!
数列の公式、最初は複雑に見えるかもしれません。
でも実はとてもシンプル!
等差数列 = 同じ数ずつ足す
等比数列 = 同じ数を掛ける
この基本を押さえれば、公式は自然と理解できます。
? 最重要ポイント3つ
- パターンを見つける目を養う
差?比?まず確認! - 公式の意味を理解する
なぜ(n-1)なのか常に意識 - 実例で確認する習慣
簡単な数で検算する
最後に
数列は、高校や大学でさらに発展的な内容を学びます。
でも、ここで学んだ基礎があれば大丈夫!どんな数列の問題にも自信を持って取り組めるはず。
数学の美しさと実用性を、数列を通じて感じてもらえたら嬉しいです。