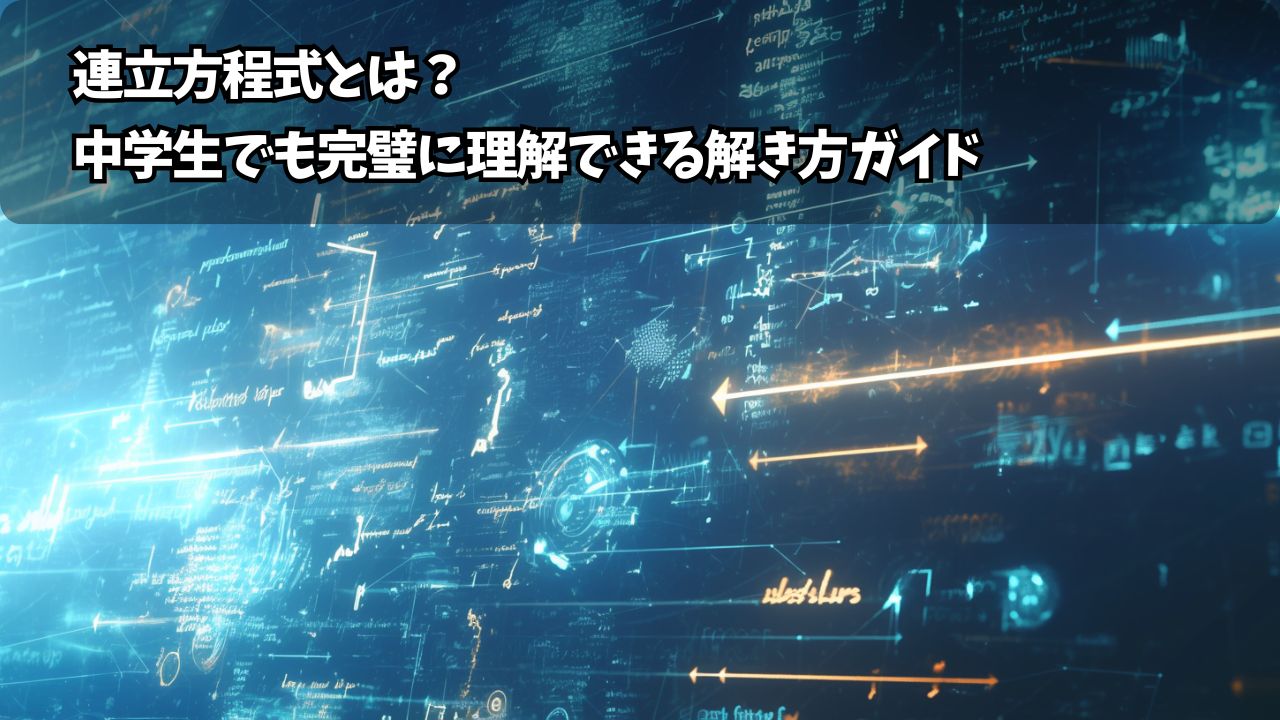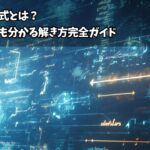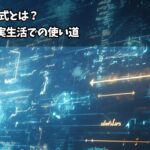「大人のハンバーガーセットが800円、子供セットが500円。
大人3人と子供2人で行ったら3400円だった。あれ?計算が合わない…」
実はこれ、ドリンクを追加注文していたんです。
大人はコーヒー、子供はジュース。それぞれいくらだったのでしょう?
これを解くには、2つの分からない数(コーヒーの値段とジュースの値段)を同時に見つける必要があります。これが「連立方程式」の出番なんです。
一次方程式が「1つの謎を解く」なら、連立方程式は「2つの謎を同時に解く」もの。
まるで名探偵が複数の手がかりから真相にたどり着くように、あなたも2つの式を使って答えを導き出せるようになります。
この記事を読み終わる頃には、「連立方程式って、パズルみたいで面白い!」と思えるはずです。
テストも怖くなくなりますし、日常の複雑な問題も解決できるようになりますよ。
第1章:連立方程式って、そもそも何?

連立方程式の正体
まず、名前を分解してみましょう:
- 連立:2つ以上が組み合わさっている
- 方程式:未知数を含む等式
つまり、「2つ以上の方程式を組み合わせて解く」ということです。
〈連立方程式の例〉
x + y = 10
x - y = 2
この2つの式を同時に満たすx、yを見つける!
なぜ2つの式が必要なの?
1つの式だけだと答えが決まらない理由:
〈1つの式の場合〉 x + y = 10
これだけだと:
- x=1、y=9 でもOK
- x=2、y=8 でもOK
- x=3、y=7 でもOK …めちゃくちゃ答えがある!
〈2つの式があると〉
x + y = 10
x - y = 2
両方を満たすのは x=6、y=4 だけ!
身近な連立方程式の例
実は日常でよく出会います:
〈買い物〉 「りんご2個とみかん3個で500円」 「りんご3個とみかん2個で550円」 → りんごとみかん、それぞれいくら?
〈部活〉 「男子と女子合わせて30人」 「男子は女子より6人多い」 → 男子と女子、それぞれ何人?
〈テスト〉 「2教科の合計が150点」 「数学は英語より20点高い」 → それぞれ何点?
グラフで見る連立方程式
視覚的に理解すると簡単:
一次方程式は直線になります。
- x + y = 10 → 右下がりの直線
- x – y = 2 → 右上がりの直線
この2つの直線が交わる点が答え!
交点の座標(6, 4)が解なんです。
連立方程式の種類
中学で学ぶのは主に2種類:
〈二元一次連立方程式〉
- 文字が2つ(x、y)
- 次数は1(x²などがない)
- 最も基本的なタイプ
〈三元一次連立方程式〉
- 文字が3つ(x、y、z)
- 式も3つ必要
- 少し応用的
今回は二元一次を中心に学びます!
この章のまとめ
連立方程式は「2つの謎を2つの手がかりで解く」もの。
1つの式では答えが決まらないけど、2つあれば特定できます。
グラフで見ると2直線の交点です。次は、実際の解き方を見ていきましょう。
第2章:連立方程式の解き方【代入法】

代入法の基本アイデア
「代入法」は、片方の式を変形してもう片方に代入する方法:
イメージ:
- 片方の式から「x = ○○」の形を作る
- それをもう一つの式のxに代入
- yだけの方程式になって解ける!
基本問題で代入法をマスター
〈例題1〉
y = x + 2 ...(1)
x + y = 8 ...(2)
解き方:
- (1)がすでに「y = ○○」の形
- (2)のyに代入 x + (x + 2) = 8
- これを解く 2x + 2 = 8 2x = 6 x = 3
- x = 3を(1)に代入 y = 3 + 2 = 5
答え:x = 3、y = 5
もう少し複雑な問題
〈例題2〉
x + 2y = 7 ...(1)
3x - y = 4 ...(2)
解き方:
- (1)を変形してxについて解く x = 7 – 2y
- これを(2)に代入 3(7 – 2y) – y = 4
- カッコを展開 21 – 6y – y = 4 21 – 7y = 4
- yを求める -7y = -17 y = 17/7
- xを求める x = 7 – 2(17/7) = 15/7
ちょっと分数になっちゃいましたね。
でも正解です!
代入法が便利な場合
こんな時は代入法が楽:
〈すでに「x = ○○」の形がある〉
x = 2y + 1
3x + y = 10
→ そのまま代入できる!
〈係数が1の文字がある〉
x + 3y = 10
2x - y = 1
→ xかyを簡単に表せる!
代入法の落とし穴と対策
よくあるミス:
〈ミス1:代入し忘れ〉 xは求めたけど、yを求め忘れる → 必ず両方求める!
〈ミス2:符号ミス〉 x = 5 – yを代入する時 × 2x = 2 × 5 – y ○ 2x = 2(5 – y) = 10 – 2y
〈ミス3:検算しない〉 必ず元の2つの式に代入して確認!
この章のまとめ
代入法は「片方の式を変形して、もう片方に代入」する方法。
すでに「x = ○○」の形があるときに特に便利です。
次は、もう一つの重要な解法「加減法」を学びましょう。
第3章:連立方程式の解き方【加減法】
加減法の基本アイデア
「加減法」は、2つの式を足したり引いたりして文字を消す方法:
イメージ:
- 片方の文字の係数を揃える
- 足すか引くかして、その文字を消す
- 1文字だけの方程式になって解ける!
基本問題で加減法をマスター
〈例題1〉係数が同じ場合
x + y = 7 ...(1)
x - y = 3 ...(2)
解き方:
- (1) + (2)を計算 (x + y) + (x – y) = 7 + 3 2x = 10 x = 5
- x = 5を(1)に代入 5 + y = 7 y = 2
答え:x = 5、y = 2
めっちゃ簡単!yが消えちゃいました。
係数を揃える必要がある場合
〈例題2〉
2x + 3y = 8 ...(1)
x + 2y = 5 ...(2)
解き方:
- xの係数を揃える((2)を2倍) 2x + 3y = 8 …(1) 2x + 4y = 10 …(2)’
- (2)’ – (1)を計算 (2x + 4y) – (2x + 3y) = 10 – 8 y = 2
- y = 2を(2)に代入 x + 4 = 5 x = 1
答え:x = 1、y = 2
最小公倍数を使うテクニック
〈例題3〉
3x + 2y = 12 ...(1)
2x + 5y = 13 ...(2)
解き方:
- xを消す場合(最小公倍数6) (1) × 2:6x + 4y = 24 (2) × 3:6x + 15y = 39
- 引き算 11y = 15 y = 15/11
または、yを消す場合(最小公倍数10)も可能!
加減法が便利な場合
こんな時は加減法が楽:
〈係数が同じか逆〉
3x + 2y = 10
3x - 5y = 1
→ そのまま引ける!
〈係数が簡単な倍数関係〉
2x + y = 5
4x + 3y = 11
→ 1つを2倍すれば揃う!
加減法と代入法、どっちを使う?
選び方のコツ:
〈代入法が良い場合〉
- すでに「x = ○○」の形
- 係数1がある
〈加減法が良い場合〉
- 係数が揃っている
- 簡単な倍数関係
〈どちらでもOK〉
- 好きな方法で!
- 慣れた方法で!
結局、答えは同じになります。
この章のまとめ
加減法は「係数を揃えて足し引きする」方法。係数が簡単な関係の時に便利です。
代入法と使い分けることで、どんな問題も効率的に解けます。次は、文章題への応用を見ていきましょう。
第4章:文章題を連立方程式で解く
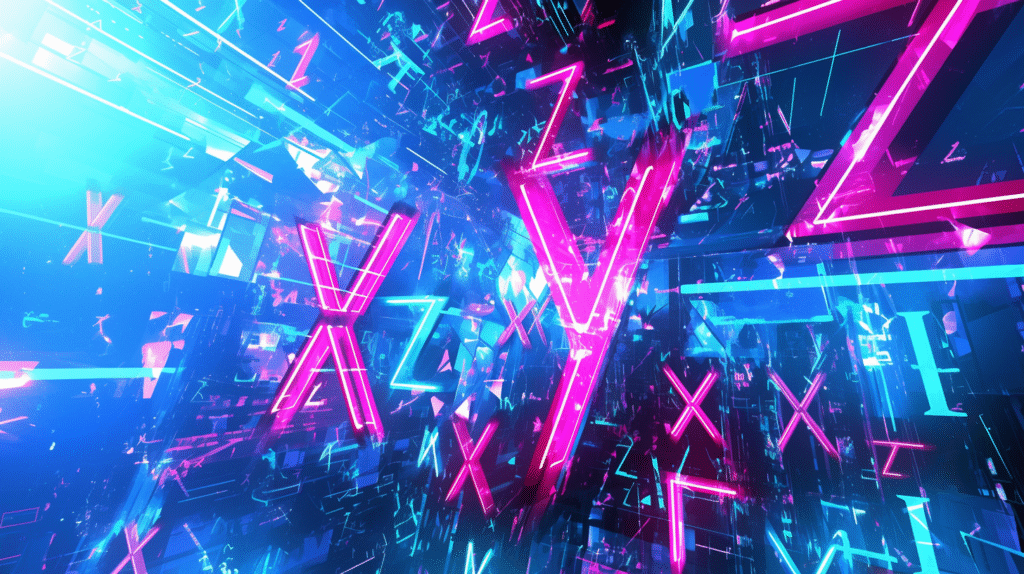
文章題を式に変換する手順
連立方程式の文章題のコツ:
〈手順〉
- 2つの未知数を決める(x、yとする)
- 文章から2つの条件を見つける
- それぞれを式にする
- 連立方程式を解く
- 答えが現実的か確認
買い物の問題
〈問題〉 「ケーキ2個とジュース3本で1100円。ケーキ3個とジュース2本で1350円。それぞれの値段は?」
解き方:
- ケーキをx円、ジュースをy円とする
- 式を作る
2x + 3y = 1100 ...(1)3x + 2y = 1350 ...(2) - 加減法で解く(両方を6倍して)
(1)×3:6x + 9y = 3300(2)×2:6x + 4y = 2700引く:5y = 600y = 120 - x を求める 2x + 360 = 1100 x = 370
答え:ケーキ370円、ジュース120円
速さの問題
〈問題〉 「AさんとBさんが10km離れた地点から向かい合って同時に出発。30分後に出会った。Aさんの速さはBさんより時速2km速い。それぞれの速さは?」
解き方:
- Aさんの速さをx km/時、Bさんをy km/時
- 条件から式を作る
- 速さの差:x – y = 2
- 30分(0.5時間)で合計10km:0.5x + 0.5y = 10
- 式を整理
x - y = 2 ...(1)x + y = 20 ...(2) - 加減法で解く (1) + (2):2x = 22、x = 11 y = 9
答え:Aさん時速11km、Bさん時速9km
割合の問題
〈問題〉 「食塩水が2種類ある。濃度8%を300gと濃度5%を200g混ぜたら、濃度6.8%になった。あれ?計算が合わない…実は量を間違えていた。正しい量は?」
解き方:
- 8%をx g、5%をy gとする
- 条件から式を作る
- 全体の量:x + y = 500
- 塩の量:0.08x + 0.05y = 0.068 × 500 = 34
- 式を整理
x + y = 5008x + 5y = 3400 - 代入法で解く x = 500 – y を第2式に代入 8(500 – y) + 5y = 3400 4000 – 8y + 5y = 3400 -3y = -600 y = 200、x = 300
答え:やっぱり最初の量で合ってた!
年齢の問題
〈問題〉 「現在、父は40歳、母は37歳。二人の年齢の和が95歳になるのは何年後?その時、父と母の年齢差は?」
解き方:
- x年後とする
- 式を作る
- x年後の父:40 + x
- x年後の母:37 + x
- 和が95:(40 + x) + (37 + x) = 95
- 解く 77 + 2x = 95 2x = 18 x = 9
答え:9年後(年齢差は変わらず3歳)
文章題のコツ
失敗しないポイント:
〈図や表を描く〉
- 線分図
- 表にまとめる
- 矢印で関係を示す
〈単位を統一〉
- 時間(分と時間)
- 長さ(mとkm)
- 割合(%と小数)
〈答えの確認〉
- 元の問題に当てはめる
- 現実的か考える
この章のまとめ
文章題は「2つの未知数、2つの条件」を見つけることが大切。
図を描いて、単位に注意して、最後は必ず確認。練習すれば必ずできるようになります。
第5章:連立方程式の実生活での活用
家計管理での活用
お小遣いや家計簿で大活躍:
〈例:お小遣いの配分〉 「月3000円のお小遣い。マンガと音楽配信に使いたい。マンガは月2冊、配信は月額制。先月は配信サービスを2つ契約して、マンガ1冊で2800円。今月は配信1つ、マンガ2冊にしたい。予算内?」
マンガ1冊x円、配信1つy円として:
x + 2y = 2800
2x + y = ?
解くと:x = 600、y = 1100 今月は 2×600 + 1100 = 2300円!余裕です。
料理での活用
レシピの調整や栄養計算:
〈例:栄養バランス〉 「鶏肉100gでタンパク質20g、カロリー200kcal。豆腐100gでタンパク質7g、カロリー70kcal。タンパク質50g、カロリー450kcalにしたい。それぞれ何g?」
鶏肉x g、豆腐y gとして:
0.2x + 0.07y = 50(タンパク質)
2x + 0.7y = 450(カロリー)
解くと:x = 200、y = 143
鶏肉200g、豆腐143gでバランス良し!
スポーツ・ゲームでの活用
戦略立案や分析:
〈例:バスケの得点分析〉 「2ポイントシュートと3ポイントシュート合計15本決めて36点。それぞれ何本?」
2ポイントx本、3ポイントy本:
x + y = 15
2x + 3y = 36
解くと:x = 9、y = 6
2ポイント9本、3ポイント6本!
仕事・ビジネスでの活用
コスト計算や生産計画:
〈例:アルバイトのシフト〉 「平日時給1000円、休日時給1200円。今月20日働いて21000円稼ぎたい。平日と休日、それぞれ何日?」
平日x日、休日y日:
x + y = 20
1000x + 1200y = 21000
解くと:x = 15、y = 5
平日15日、休日5日でピッタリ!
DIY・工作での活用
材料計算や設計:
〈例:本棚作り〉 「長い板と短い板で本棚を作る。長い板1本と短い板2本で150cm。長い板2本と短い板1本で180cm。それぞれの長さは?」
長い板x cm、短い板y cm:
x + 2y = 150
2x + y = 180
解くと:x = 70、y = 40
長い板70cm、短い板40cmで設計完了!
環境問題での活用
エコな生活の計算:
〈例:CO2削減〉 「車での通勤(1日2kg CO2)と電車通勤(1日0.5kg CO2)。月20日通勤して、CO2を25kg以内にしたい。それぞれ何日ずつ?」
車x日、電車y日:
x + y = 20
2x + 0.5y = 25
解くと:x = 10、y = 10
半分ずつで目標達成!
この章のまとめ
連立方程式は、お金の管理から環境問題まで、生活のあらゆる場面で使えます。
2つの条件がある問題は、連立方程式の出番です。
第6章:よくある質問と間違い克服法
Q1:どっちの解法を使えばいいの?
使い分けの決定版:
〈代入法を選ぶ〉
y = 2x + 3
3x + y = 10
→ すでに y = の形!
〈加減法を選ぶ〉
3x + 2y = 10
3x - 2y = 4
→ 3xが同じ!引けば消える!
〈どちらでもOKな場合〉 迷ったら、自分が得意な方で!
Q2:答えが分数になったけど大丈夫?
全然OK!でも確認は必要:
〈数学的にはOK〉 x = 5/3、y = 7/2 など
〈現実問題では要注意〉
- 人数が分数 → おかしい
- 値段が分数 → 問題文を確認
- 時間が分数 → 分に直すと自然
Q3:式が作れない
文章題の式の作り方:
ステップ1:主人公を決める 「何と何を求める?」→ それがxとy
ステップ2:日本語を式に翻訳
- 「合わせて」→ +
- 「差は」→ –
- 「〜倍」→ ×
- 「〜ずつ」→ ×個数
ステップ3:単位を確認 式の両辺の単位が同じか確認!
Q4:計算ミスが多い
ミスを減らす5つのコツ:
- 途中式を省略しない
- 番号を振る(式(1)、式(2)など)
- 消す文字を決めてから計算
- 分数は最後まで残す(途中で小数にしない)
- 必ず検算(両方の式に代入)
Q5:検算が合わない
チェックポイント:
〈計算ミス〉
- 符号(特にマイナス)
- 係数の掛け忘れ
- 移項ミス
〈式の作り方〉
- 問題文の読み違い
- 単位の間違い
- xとyの設定ミス
一つずつ確認すれば必ず見つかる!
よくある間違いパターン
〈間違い1:片方しか求めない〉 × x = 3で終わり ○ x = 3、y = 5まで求める
〈間違い2:代入する式を間違える〉 × 複雑な式に代入 ○ 簡単な式に代入
〈間違い3:係数を掛け忘れ〉 × 2x = 2 × 3 = 6 ○ 2x = 2 × 3 = 6、x = 3
この章のまとめ
間違いやすいポイントを知っていれば、ミスは防げます。迷ったら基本に戻る、検算を必ずする、これで連立方程式は怖くありません。
まとめ:連立方程式マスターへの道
長い記事を最後まで読んでくれて、本当にありがとうございます!連立方程式、もう完璧に理解できましたよね?
〈この記事で学んだこと〉
- 連立方程式は「2つの謎を2つの手がかりで解く」
- 代入法:片方を変形してもう片方に代入
- 加減法:係数を揃えて足し引き
- 文章題は2つの条件を見つけることが鍵
- 日常生活のあらゆる場面で使える
- ミスしやすいポイントと対策
〈連立方程式ができると〉
- 複雑な問題が解決できる
- 論理的思考力が身につく
- 高校数学の基礎が完成
- プログラミングの考え方も理解しやすく
- 仕事でのデータ分析にも活用