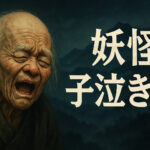大きなふきの葉の下に、小さな小さな住人がいるとしたら…そんな想像をしたことはありませんか?
北海道や東北地方には、「コロボックル」という愛らしい妖怪の話が古くから伝わっています。
この記事では、手のひらサイズの可愛い妖怪「コロボックル」について分かりやすく解説していきます。
名前の由来

「コロボックル」は、北海道地方の伝承に登場する小さな妖怪です。
名前はアイヌ語で「蕗(ふき)の葉の下の人」という意味を持ちます。
また、コロボックルは「コロポックル」とも呼ばれています。
姿・見た目
コロボックルは、とても小さな人の姿をしています。
基本的な見た目
- 身長は30~60cmほど
- 腕に刺青がある
特徴

コロボックルは、基本的には穏やかで人間に敵意を持たない妖怪です。
しかし、人間に姿を見せることはありません。
主な特徴
- 小人の妖怪
- ふきの葉の下に住んでいる(住居にもふきの葉を使う)
- アイヌ民族に友好的
- アイヌの人々と物々交換をする
- 決して姿を見せない
姿は絶対に見せたくないようで、夜にこっそり窓越しに物々交換をします。
伝承
北海道に伝わる話では、コロボックルはかつてアイヌ民族よりも前にこの土地に住んでいた存在とされています。
代表的な話
代表的なのは若者がコロボックルの姿を見てしまう話です。
- アイヌの人々はコロボックルと物々交換をしていた
- コロボックルが姿を見せたがらないので、やり取りは夜に窓越しで行っていた
- ある若者がコロボックルの姿が気になって、見てやろうと考えた
- 若者は窓越しに物を交換する際、コロボックルの腕を掴み引っ張り上げた
- コロボックルの姿を見てみると、美しい女性だった
後日、コロボックルはこの出来事に激怒して、北の海の彼方に消えていきました。
まとめ
コロボックルは、北海道や東北の自然と深くつながった、小さな優しい妖怪です。
重要なポイント
- 見た目は小人のようで愛らしい
- ふきの葉の下に住んでいる
- 人間に善意を持つが、裏切られると姿を消す
アイヌ民族ととても仲が良かったのですが、人間が裏切ってしまったためにいなくなってしまった妖怪です。