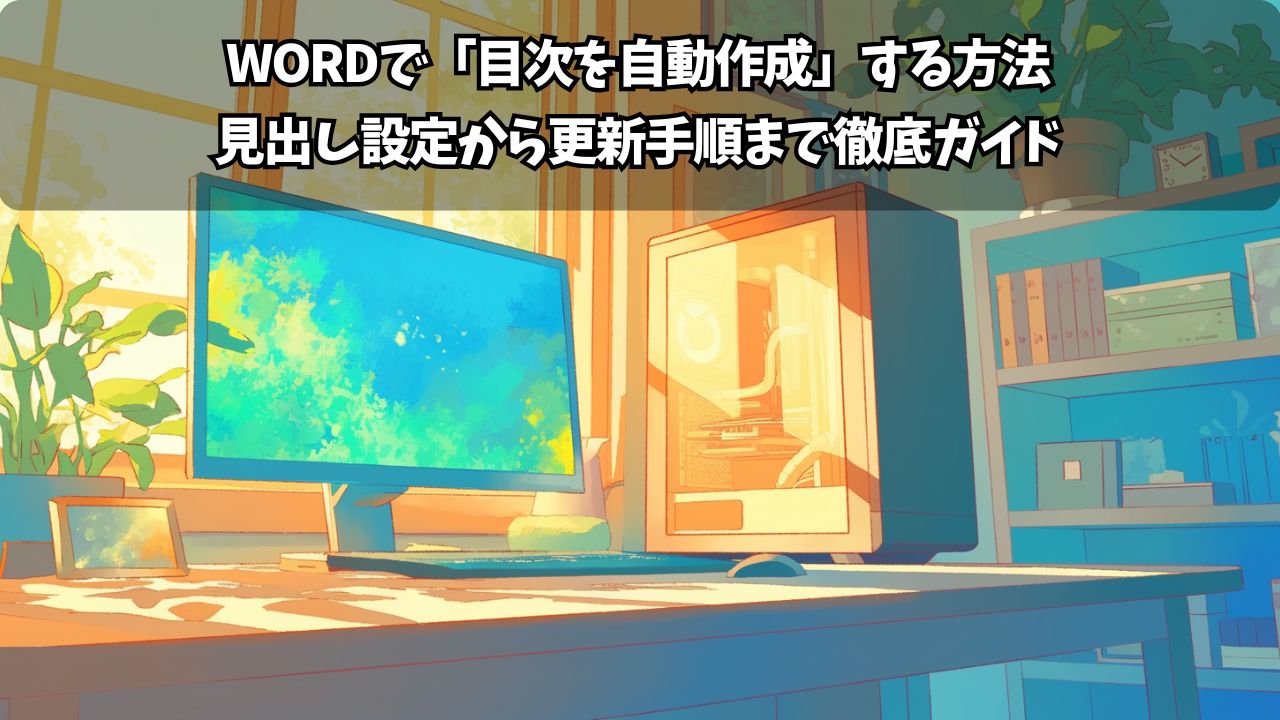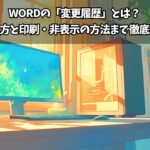「長い文書を作ったけど、手作業で目次を作るのが大変…」「章や項目が多すぎて管理できない…」そんな経験はありませんか?
そんなときに便利なのが、Microsoft Wordの**「自動目次」機能**です。正しく設定すれば、数クリックで見栄えの良い目次が完成し、変更も簡単に反映されます。
この記事では、Wordで目次を自動作成する方法を、初心者にもわかりやすく解説します。
自動目次とは何か

自動目次機能の概要
Wordの**「自動目次」**とは、「見出しスタイル」が設定された文章から自動的に目次を生成する機能です。
手入力せずとも、見出しの内容・階層・ページ番号が整った状態で表示されます。まさに「魔法のような機能」といえるでしょう。
自動目次のメリット
自動目次を使うことで、以下のようなメリットがあります。
- 時間の大幅短縮:手作業での目次作成が不要
- 正確性の向上:ページ番号の間違いがない
- 簡単な更新:文書を変更しても一瞬で目次を更新
- プロ仕様の見た目:統一されたデザインで美しい仕上がり
- ナビゲーション機能:クリックで該当ページにジャンプ
自動目次が活用できる文書
以下のような文書で特に効果を発揮します。
- 報告書・企画書:章立てが明確な文書
- 論文・研究資料:学術的な構造を持つ文書
- マニュアル・手順書:段階的な説明が必要な文書
- プレゼンテーション資料:配布用の詳細資料
自動目次作成の基本手順
全体の流れ
自動目次を作成するには、以下の3つのステップを順番に行います。
- 見出しスタイルの設定:文書の構造を決める
- 目次の挿入:自動目次を文書に追加
- 目次の更新:変更を反映させる
それぞれ詳しく解説していきます。
ステップ1:見出しスタイルを設定する
見出しスタイルの重要性
自動目次を作るには、まず**「見出し1」「見出し2」**などのスタイルを適用する必要があります。
これは単に文字を大きくしたり太字にしたりするのとは違い、Wordに「ここが見出しです」と教える作業です。
見出しスタイルの設定方法
基本的な設定手順
- 各章やセクションのタイトルを選択
目次に含めたい見出し文字を選びます - 「ホーム」タブをクリック
画面上部のリボンから「ホーム」タブを選択 - 「スタイル」グループから見出しを選択
「見出し1」「見出し2」「見出し3」などをクリック - 選択した文字が見出しスタイルになる
文字の見た目が変わり、見出しとして認識される
見出しレベルの使い分け
見出しには階層があり、適切に使い分けることが大切です。
- 見出し1:章のタイトル(第1章、第2章など)
- 見出し2:節のタイトル(1.1、1.2など)
- 見出し3:項のタイトル(1.1.1、1.1.2など)
見出しスタイルの詳細設定
スタイルのカスタマイズ
見出しの見た目を変更したい場合は、以下の方法で調整できます。
- スタイルを右クリック
- 「変更」を選択
- フォント、サイズ、色などを調整
- 「OK」をクリック
新しいスタイルの作成
特別な見出しが必要な場合は、新しいスタイルを作ることもできます。
- 「ホーム」タブ→「スタイル」グループの右下の矢印をクリック
- 「新しいスタイル」をクリック
- スタイル名と書式を設定
- 「目次に表示」にチェックを入れる
見出し設定のコツ
一貫性を保つ
- 同じレベルの見出しは同じスタイルを使用
- 階層の順序を守る(見出し1の次にいきなり見出し3は使わない)
- 見出しの内容は簡潔にまとめる
読みやすさを重視
- 見出しだけ読んでも内容がわかるようにする
- 長すぎる見出しは避ける(目安:20文字以内)
- 専門用語の多用は控える
ステップ2:目次を自動挿入する
目次挿入の基本手順
見出しの設定が済んだら、いよいよ目次を挿入します。
操作手順
- 目次を入れたい場所にカーソルを置く
通常は文書の先頭ページに設置します - 「参考資料」タブをクリック
画面上部のリボンから「参考資料」タブを選択 - 「目次」ボタンをクリック
目次の種類が一覧で表示されます - 「自動作成の目次1」または「2」を選択
好みのデザインを選んでクリック - 自動的に目次が挿入される
見出しとページ番号が自動で表示されます
目次の種類と特徴
Wordには複数の目次テンプレートが用意されています。
自動作成の目次1
- シンプルなデザイン
- ページ番号が右側に表示
- 点線でページ番号につながる
自動作成の目次2
- 少しデザイン性がある
- 章番号が強調される
- ビジネス文書におすすめ
手動目次
- 自分で内容を入力するタイプ
- 自動更新されない
- 特殊なレイアウトが必要な場合に使用
目次の配置とレイアウト
目次の配置場所
一般的には以下の場所に配置します。
- 表紙の次のページ:最も一般的
- 文書の最後:参考資料として
- 各章の始まり:長い文書の場合
ページ区切りの設定
目次を独立したページにするため、ページ区切りを設定しましょう。
- 目次の前にカーソルを置く
- 「挿入」タブ→「ページ区切り」をクリック
- 目次の後にも同様にページ区切りを挿入
ステップ3:目次を更新する方法
更新が必要なタイミング
以下のような変更を行った後は、目次の更新が必要です。
- 見出しの文言を変更した時
- 章や節を追加・削除した時
- 文書の内容を大幅に変更した時
- ページ番号がずれるような編集をした時
目次更新の基本手順
操作方法
- 目次上でクリック
目次全体が灰色の枠で囲まれます - 「目次の更新」ボタンをクリック
目次の上部に表示されるボタンをクリック - 更新方法を選択
2つの選択肢から適切なものを選びます - 「OK」をクリック
更新が完了します
更新方法の選択
ページ番号のみ更新
- 見出しの内容は変更せず、ページ番号だけを更新
- 文書の長さが変わった場合に使用
目次全体を更新
- 見出しの内容とページ番号の両方を更新
- 見出しを追加・削除・変更した場合に使用
自動更新の設定
リアルタイム更新
以下の設定で、より便利に目次を使用できます。
- 「ファイル」→「オプション」をクリック
- 「表示」を選択
- 「印刷レイアウト表示とWebレイアウト表示でフィールドコードを表示する」のチェックを外す
これにより、目次が常に最新の状態で表示されます。
目次のデザインや形式を変更する

カスタマイズの基本
目次の見た目やレベル数を調整したい場合は、詳細なカスタマイズが可能です。
ユーザー設定の目次
- **「参考資料」→「目次」→「ユーザー設定の目次」**をクリック
- 各種設定を調整
- 「OK」で反映
設定項目の詳細
表示レベル
- 最大9段階まで設定可能
- 通常は3〜4レベルが読みやすい
- 深すぎる階層は避ける
タブリーダー
目次の見出しとページ番号をつなぐ線の種類です。
- 点線(…………):最も一般的
- 線(————):シンプルなデザイン
- なし:スッキリとした見た目
ページ番号の表示
- 右揃え:一般的な配置
- 左揃え:特殊なレイアウト用
デザインのカスタマイズ
フォントの変更
- 「ユーザー設定の目次」で「変更」をクリック
- 変更したいレベルを選択
- フォント、サイズ、色などを調整
インデント(字下げ)の調整
- 目次を選択
- ルーラーでインデントを調整
- または「ホーム」タブのインデント機能を使用
高度な目次機能
ハイパーリンク機能
自動目次には、便利なナビゲーション機能が標準で含まれています。
ページジャンプ機能
- Ctrl + クリックでページ番号をクリック
- 該当ページに瞬時にジャンプ
- 長い文書のナビゲーションに便利
リンクの設定・解除
リンク機能を制御したい場合:
- 目次を右クリック
- 「フィールドコードの表示/非表示」を選択
- 必要に応じてコードを編集
複数の目次作成
図表目次の作成
文書に図や表が多い場合、別途図表目次を作成できます。
- 「参考資料」タブ→「図表番号の挿入」
- 図や表にキャプションを設定
- 「図表目次の挿入」で専用目次を作成
独自の目次作成
特定のスタイルだけを含む目次も作成可能です。
- 「ユーザー設定の目次」→「オプション」
- 特定のスタイルのみを選択
- 専用の目次を作成
目次の印刷設定
印刷時の注意点
- 目次と本文のページ番号を分ける場合は、セクション区切りを使用
- ページ番号の形式(ローマ数字、アラビア数字)を統一
- 印刷プレビューで最終確認
よくあるトラブルと解決方法
目次に反映されない見出し
原因と対策
問題:設定したはずの見出しが目次に表示されない
原因
- 見出しスタイルが正しく適用されていない
- 手動で文字を装飾しただけになっている
- 見出しレベルが目次の表示範囲外
解決方法
- 見出しスタイルを再設定
- 表示レベルを確認・調整
- 「目次全体を更新」を実行
ページ番号のずれ
原因と対策
問題:目次のページ番号が実際のページと合わない
原因
- 文書編集後に目次を更新していない
- ページ区切りやセクション区切りの影響
- ヘッダー・フッターの設定問題
解決方法
- 「目次の更新」を実行
- ページ番号の設定を確認
- セクション区切りを見直し
目次のレイアウト崩れ
原因と対策
問題:目次の見た目が崩れる
原因
- フォントや文字サイズの不統一
- インデント設定の問題
- 長すぎる見出し
解決方法
- スタイルを統一
- インデントを調整
- 見出しの長さを見直し
目次が更新されない
原因と対策
問題:更新ボタンを押しても変更が反映されない
原因
- フィールドが壊れている
- 文書が保護されている
- Wordのバグ
解決方法
- 目次を削除して再作成
- 文書の保護を解除
- Wordを再起動
目次作成のベストプラクティス
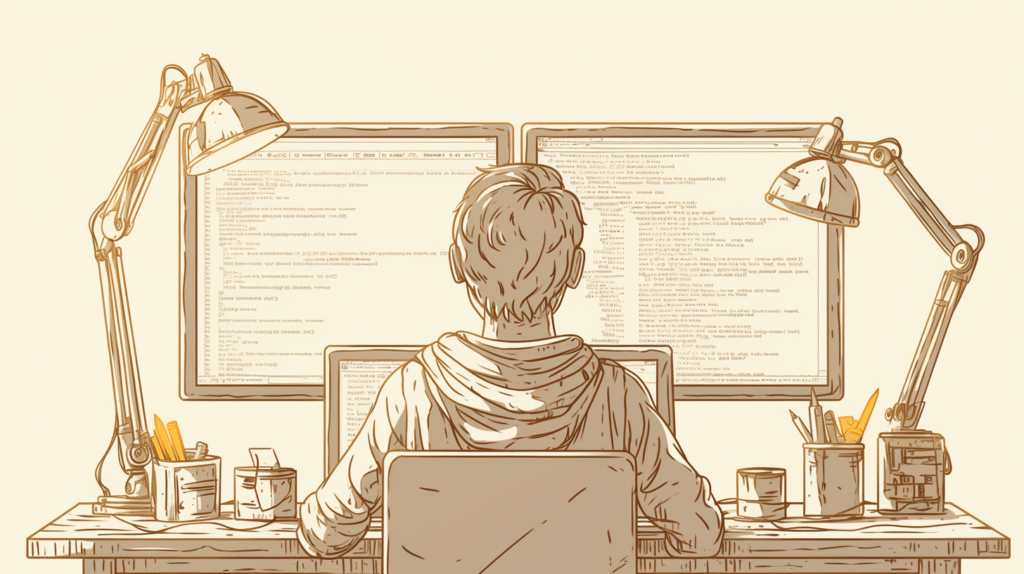
企画段階での準備
文書構造の設計
目次を作る前に、文書全体の構造を設計しましょう。
- 章・節・項の階層を明確に
- 各部分の役割を定義
- 読者の読み方を想定
見出しの統一ルール
チームで作業する場合は、見出しのルールを統一します。
- 見出しの文字数制限
- 専門用語の使用基準
- 階層の深さの上限
作業効率を上げるコツ
テンプレートの活用
よく使う文書構造は、テンプレートとして保存しましょう。
- 見出しスタイルを設定した文書を作成
- 「ファイル」→「名前を付けて保存」
- ファイルの種類で「Wordテンプレート」を選択
ショートカットキーの活用
効率的な作業のためのショートカット:
- Ctrl + Alt + 1:見出し1を適用
- Ctrl + Alt + 2:見出し2を適用
- Ctrl + Alt + 3:見出し3を適用
- F9:選択したフィールドを更新
品質管理のポイント
最終チェック項目
- すべての見出しが目次に反映されているか
- ページ番号が正確か
- 階層構造が論理的か
- 見出しの表現が統一されているか
バックアップの重要性
重要な文書は、目次作成前にバックアップを取りましょう。
まとめ
Wordで目次を自動作成するための手順をまとめると、以下の通りです。
基本的な作成手順
- 見出しスタイルを正しく設定(見出し1、見出し2など)
- 「参考資料」→「目次」で自動挿入
- 編集後は「目次の更新」で常に最新に保つ
成功のポイント
- 文書の構造設計を最初にしっかり行う
- 見出しスタイルの統一を徹底する
- 定期的な更新を忘れない
- 読者の視点で使いやすさを確認