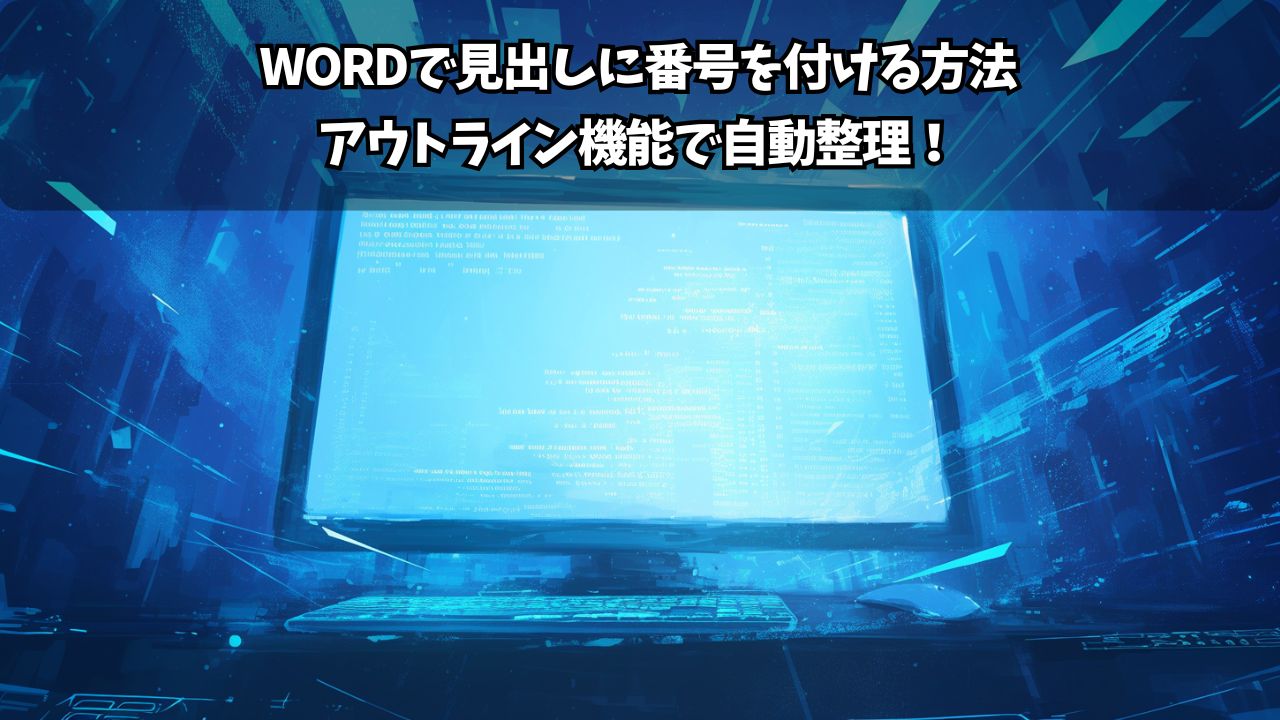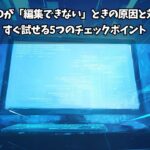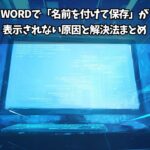「章番号を手動で入力するのが面倒」「見出しの順番を変更したら番号がぐちゃぐちゃに」このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
実は、Wordには見出しに自動で番号を付ける便利な機能があります。この機能を使えば、「1.」「1.1」「1.1.1」のような階層番号が自動で設定され、見出しを追加・削除・移動しても番号が自動調整されます。
この記事では、見出し番号の基本的な設定方法から、実務で役立つカスタマイズ方法まで詳しく解説します。報告書やマニュアル作成で困っている方は、ぜひ参考にしてください。
見出し番号機能とは?文書構造を自動管理する便利な仕組み

見出し番号とは、文書の階層構造に応じて「1.」「1.1」「1.1.1」のような番号を自動で付ける機能です。手動で番号を入力する必要がなく、見出しの順序を変更しても自動で番号が調整されます。
見出し番号のメリット
作業効率の向上 章番号を手動で管理する必要がなくなり、文書作成に集中できます。
構造の明確化 階層構造が視覚的に分かりやすくなり、読み手にとって理解しやすい文書になります。
目次との連携 見出し番号付きの見出しは、Wordの自動目次機能と連携してより便利に使えます。
ミスの防止 手動での番号付けで起こりがちな重複や欠番を防げます。
見出し番号が活躍する文書
見出し番号は様々な文書で活用できます。
ビジネス文書
- 事業計画書
- 会議議事録
- 提案書・企画書
- 業務マニュアル
- 研修資料
学術・研究文書
- 卒業論文・修士論文
- 研究レポート
- 学会発表資料
- 調査報告書
- 技術仕様書
個人利用
- 旅行計画書
- 家計管理資料
- 趣味のまとめ文書
- 備忘録・ノート
基本的な見出し番号の設定方法
ステップ1:見出しスタイルの適用
見出し番号を使うには、まず文字に「見出しスタイル」を適用する必要があります。
見出しスタイルの種類
見出し1
- 最上位の見出し(章レベル)
- 例:「1. はじめに」「2. 調査概要」
見出し2
- 第2階層の見出し(節レベル)
- 例:「1.1 目的」「1.2 背景」
見出し3
- 第3階層の見出し(項レベル)
- 例:「1.1.1 調査対象」「1.1.2 調査方法」
見出しスタイルの適用手順
- 見出しにしたい文字を選択 マウスでドラッグして、見出しにしたい文字列を選択します
- ホームタブを開く 画面上部のリボンで「ホーム」タブをクリックします
- スタイルを選択 「スタイル」グループから適切な見出しレベルを選択します
- 章レベル:見出し1
- 節レベル:見出し2
- 項レベル:見出し3
ステップ2:多段階リストの設定
見出しスタイルを適用した後、番号を自動設定します。
多段階リストの適用手順
- 文書内のどこかをクリック 番号を付けたい見出しがある文書上でクリックします
- ホームタブの段落グループを確認 「段落」グループにある多段階リストのボタンを探します
- 多段階リストをクリック 番号と文字が階層状に並んだアイコン(多段階リスト)をクリックします
- 見出しベースのリストを選択 表示されるメニューから「見出しに基づくリスト」を選択します
これで、見出し1には「1.」、見出し2には「1.1」のような番号が自動で付きます。
実際の例
設定後の見出し表示例:
1. プロジェクト概要
1.1 目的
1.2 背景
1.2.1 市場動向
1.2.2 競合分析
2. 実施計画
2.1 スケジュール
2.2 体制
見出し番号のカスタマイズ方法

基本設定だけでも十分ですが、文書の種類や会社の規定に合わせてカスタマイズできます。
番号形式の変更
利用できる番号形式
数字
- 1, 2, 3…(半角数字)
- 1, 2, 3…(全角数字)
アルファベット
- A, B, C…(大文字)
- a, b, c…(小文字)
ローマ数字
- I, II, III…(大文字)
- i, ii, iii…(小文字)
ひらがな・カタカナ
- あ, い, う…
- ア, イ, ウ…
番号形式の変更手順
- 多段階リストボタンをクリック ホームタブの多段階リストボタンをクリックします
- 新しいアウトラインの定義 メニューの一番下にある「新しいアウトラインの定義」を選択します
- レベルごとに設定 左側でレベル(1〜9)を選択し、右側で番号形式を変更します
- プレビューで確認 設定内容がプレビューエリアに表示されるので、確認してから「OK」をクリックします
インデント(字下げ)の調整
見出しの位置や番号との間隔を調整できます。
調整できる項目
番号の位置 番号が表示される左端からの距離
文字の位置 見出し文字が始まる位置
タブ位置 番号と文字の間隔
調整方法
- 「新しいアウトラインの定義」画面を開く
- 調整したいレベルを選択
- 「番号の位置」「文字の位置」「タブ位置」の数値を変更
- プレビューで確認しながら調整
区切り文字の変更
番号の後に付く文字(通常は「.」)を変更できます。
よく使われる区切り文字
- . (ピリオド)
- ) (右括弧)
- : (コロン)
- (スペースのみ)
変更手順
- 「新しいアウトラインの定義」で該当レベルを選択
- 「番号に続く文字」で希望する区切り文字を選択
- 「ユーザー設定」を選択すれば、任意の文字も設定可能
実務での活用テクニック
目次との連携
見出し番号を設定した見出しは、Wordの自動目次機能と完璧に連携します。
自動目次の作成手順
- 目次を挿入したい位置にカーソルを置く 通常は文書の先頭部分
- 参考資料タブを開く 画面上部のリボンで「参考資料」タブをクリック
- 目次を挿入 「目次」ボタンをクリックし、好みのスタイルを選択
- 自動更新 見出しを変更した場合は、目次を右クリックして「フィールドの更新」を選択
見出しのナビゲーション
長い文書では、見出しを使ったナビゲーション機能が便利です。
ナビゲーションウィンドウの使い方
- 表示タブを開く 画面上部の「表示」タブをクリック
- ナビゲーションウィンドウを表示 「ナビゲーションウィンドウ」にチェックを入れる
- 見出しで移動 左側に表示される見出しリストをクリックすると、該当箇所にジャンプ
印刷時の注意点
見出し番号は印刷にも反映されるため、以下の点に注意しましょう。
確認すべき項目
改ページ位置 見出し1の前で自動改ページする設定にすると、章ごとに新しいページから始まります。
フォントサイズ 見出しレベルに応じて、適切なフォントサイズに調整しましょう。
余白設定 インデントが深い見出しが印刷範囲に収まるか確認してください。
よくあるトラブルと解決方法
番号がずれる・正しく表示されない
原因と対処法
見出しスタイルが正しく適用されていない
- 対処法:該当箇所の見出しスタイルを再設定
手動で番号を入力している
- 対処法:手動の番号を削除し、自動番号に変更
多段階リストの設定が複数混在している
- 対処法:文書全体で統一された多段階リストを適用
番号をリセットする方法
- 問題のある見出しを選択
- 多段階リストのボタンをクリック
- 「リストの再開」または「番号の設定」を選択
- 適切な開始番号を指定
見出しスタイルのデザインを変更したい
フォントやサイズの変更
- スタイル一覧で右クリック ホームタブのスタイル一覧で「見出し1」などを右クリック
- 変更を選択 「変更」をクリックしてスタイルの変更画面を開く
- 書式を調整 フォント、サイズ、色、配置などを設定
- 変更を適用 「OK」をクリックして変更を保存
会社規定に合わせたスタイル作成
多くの会社では文書作成の規定があります。規定に合わせてスタイルをカスタマイズしましょう。
よくある規定例
- 見出し1:14pt、太字、中央揃え
- 見出し2:12pt、太字、左揃え
- 見出し3:11pt、太字、左揃え
応用的な活用方法

セクション別の番号管理
長い文書では、セクションごとに番号をリセットしたい場合があります。
セクション区切りの活用
- セクション区切りを挿入 「レイアウト」タブ→「区切り」→「次のページから開始」
- 番号をリセット 新しいセクションの最初の見出しで「番号の設定」を選択
- 開始番号を指定 「1」から開始するように設定
見出し番号を使った相互参照
文書内で「第3章で説明した通り」のような参照を自動化できます。
相互参照の挿入
- 参照したい位置にカーソルを置く 「第」や「章」という文字の間にカーソルを置く
- 参考資料タブを開く 「相互参照」ボタンをクリック
- 参照先を指定 参照する見出しを選択し、番号のみまたは見出し全体を選択
- 自動更新 見出しの順序が変わっても、参照番号が自動で更新される
テンプレート化
よく使う文書構造は、テンプレートとして保存しておくと便利です。
テンプレートの作成手順
- 見出し番号を設定した文書を作成 代表的な見出し構造を作成
- テンプレートとして保存 「ファイル」→「名前を付けて保存」→「Word テンプレート」を選択
- テンプレートの活用 新規文書作成時に作成したテンプレートを選択
まとめ
Wordの見出し番号機能を使えば、文書作成の効率が大幅に向上し、プロフェッショナルな仕上がりの文書を作成できます。
この記事のポイント
- 見出しスタイルと多段階リストの組み合わせで自動番号を実現
- 番号形式やインデントは柔軟にカスタマイズ可能
- 目次機能やナビゲーション機能との連携で使いやすさが向上
- トラブルは見出しスタイルの再適用で多くが解決
- テンプレート化で作業効率をさらに向上
効果的な使い方
- 文書作成前に見出し構造を計画
- 一貫したスタイル設定で統一感を確保
- 定期的な番号の確認とメンテナンス
- チーム内でのスタイル統一