Sublime Text(サブライムテキスト)は軽量で多機能なテキストエディタですが、VSCodeのようにデフォルトで統合デバッグ機能は備わっていません。
「じゃあSublime Textではデバッグできないの?」と思うかもしれませんが、実は工夫次第で十分デバッグに活用できます。
この記事では、以下について初心者向けにわかりやすく解説します:
- Sublime Textでデバッグ的な動作をする方法
- C言語やPythonを実行してエラーをチェックするやり方
- デバッグを助けるおすすめプラグイン
- 外部ツールとの効率的な連携方法
Sublime Textでの「デバッグ」の考え方

従来のデバッグ機能との違い
Sublime Text自体には、以下のような機能はありません:
- ブレークポイントを設置する機能
- 変数をステップ実行で追う機能
- デバッグパネルでの変数監視
Sublime Textでできるデバッグアプローチ
その代わりに、以下の方法で「軽量なデバッグ」を行うのが一般的です:
基本的なアプローチ
- ビルドシステムでエラー出力を確認
- **リンター(Linter)**や構文チェックでバグを減らす
- 外部ツールやターミナルと連携して実行・テスト
- プラグインを活用してデバッグ効率を向上
このアプローチのメリット
- エディタが軽量で起動が早い
- 自分の好きなデバッグツールを組み合わせられる
- シンプルな環境で集中できる
C言語やPythonをSublime Textから実行する方法
ビルドシステムを使った簡易デバッグ
Sublime Textの「Build System」を使えば、Ctrl + B(MacはCmd + B)でプログラムを実行し、コンソールにエラーメッセージを表示できます。
C言語の実行環境設定
手順
- 新しいビルドシステムを作成
Tools → Build System → New Build Systemを選択
- 設定ファイルを作成
{ "cmd": ["gcc", "$file", "-o", "${file_path}/${file_base_name}", "&&", "${file_path}/${file_base_name}"], "shell": true, "file_regex": "^(.+):(\\d+):(\\d+): (.*)$", "working_dir": "${file_path}", "selector": "source.c" } - ファイルを保存
- 「C_Debug.sublime-build」などの名前で保存
- ビルドシステムを選択
Tools → Build Systemで作成したものを選択
- 実行とデバッグ
Ctrl + Bで実行- エラーがあればコンソールに表示される
設定の詳細説明
$file: 現在のファイル名${file_path}: ファイルのディレクトリパス${file_base_name}: 拡張子を除いたファイル名file_regex: エラー行をクリックで飛べるようにする正規表現
Python の実行環境設定
基本的な実行
Pythonはデフォルトでビルドシステムが用意されているので:
- Pythonファイルを開く
Tools → Build System → Pythonを選択Ctrl + Bで実行
エラー行やトレースバックがコンソールに表示されます。
カスタムPythonビルドシステム
より詳細なデバッグ情報が欲しい場合:
{
"cmd": ["python", "-u", "$file"],
"file_regex": "^[ ]*File \"(...*?)\", line ([0-9]*)",
"selector": "source.python",
"env": {"PYTHONPATH": "$file_path"}
}
実行時のエラー確認方法
エラーメッセージの読み方
C言語のコンパイルエラー例
test.c:5:10: error: 'x' undeclared (first use in this function)
test.c: ファイル名5: 行番号10: 列番号- 後ろ: エラーの内容
Pythonの実行エラー例
Traceback (most recent call last):
File "test.py", line 3, in <module>
print(x)
NameError: name 'x' is not defined
エラー行への素早いジャンプ
コンソールに表示されたエラー行をクリックすると、該当する行に自動的にジャンプできます。
デバッグを補助するおすすめプラグイン

SublimeLinter(構文チェック)
リアルタイムで文法エラーや潜在的な問題を検出するプラグインです。
インストール方法
- Package Controlを開く
Ctrl + Shift + P(Mac:Cmd + Shift + P)
- SublimeLinterをインストール
Package Control: Install Package- 「SublimeLinter」を検索してインストール
- 言語別のリンターをインストール
- Python:
SublimeLinter-pylint - C/C++:
SublimeLinter-gcc - JavaScript:
SublimeLinter-eslint
- Python:
使用方法
- エラーがある行に赤い点や波線が表示される
- マウスカーソルを合わせるとエラーの詳細が表示される
- リアルタイムでチェックされるため、入力しながらミスを発見できる
GitGutter(変更箇所の表示)
コードのどこを変更したかを色で表示するプラグインです。
機能
- 追加した行: 緑色のマーク
- 変更した行: 黄色のマーク
- 削除した行: 赤色のマーク
デバッグでの活用方法
- 「バグを入れた場所の特定」に非常に役立つ
- 最近の変更箇所を一目で確認できる
- バージョン管理と連携してデバッグ効率を向上
BracketHighlighter(括弧の対応表示)
括弧の対応関係を視覚的に表示するプラグインです。
活用場面
- ネストの深いコードでの括弧ミス発見
- 関数やループの範囲確認
- 構文エラーの原因特定
Terminus(ターミナル統合)
Sublime Text内でターミナルを使用できるプラグインです。
メリット
- エディタを切り替えることなくコマンド実行
- デバッグコマンドをすぐに実行可能
- 作業効率の向上
外部デバッガとの効率的な連携
C言語でのgdb連携
本格的にブレークポイントを使いたい場合は、gdb(GNU Debugger)との連携がおすすめです。
基本的な使い方
1. デバッグ情報付きでコンパイル
gcc -g program.c -o program
2. gdbでデバッグ開始
gdb ./program
3. よく使うgdbコマンド
(gdb) break main # main関数にブレークポイント
(gdb) run # プログラム実行
(gdb) next # 次の行へ
(gdb) print variable_name # 変数の値を表示
(gdb) continue # 実行継続
(gdb) quit # gdb終了
Sublime TextとgDBの役割分担
- Sublime Text: コードの編集・閲覧
- gdb: ステップ実行・変数の監視・ブレークポイント管理
Pythonでのpdb連携
Pythonには標準でデバッガ「pdb」が付属しています。
基本的な使い方
1. コードにデバッグポイントを挿入
import pdb
def my_function(x, y):
result = x + y
pdb.set_trace() # ここでデバッグ開始
return result * 2
print(my_function(3, 4))
2. プログラム実行 実行するとデバッグモードに入り、対話的にデバッグできます。
3. よく使うpdbコマンド
(Pdb) n # 次の行へ
(Pdb) s # ステップイン
(Pdb) c # 継続実行
(Pdb) p 変数名 # 変数の値を表示
(Pdb) l # 現在の行周辺のコードを表示
(Pdb) q # デバッグ終了
より便利なipdb
ipdbを使うとより使いやすくなります:
pip install ipdb
import ipdb
ipdb.set_trace() # pdbより高機能
デバッグワークフローの例
効率的なデバッグの流れ
- Sublime Textで初期チェック
- SublimeLinterでリアルタイム構文チェック
- ビルドシステムで基本的な実行・エラー確認
- 詳細デバッグが必要な場合
- C言語: gdbでステップ実行
- Python: pdbまたはipdbで詳細確認
- 修正後の確認
- 再びSublime Textのビルドシステムで動作確認
- GitGutterで変更箇所を確認
よくある質問(Q&A)
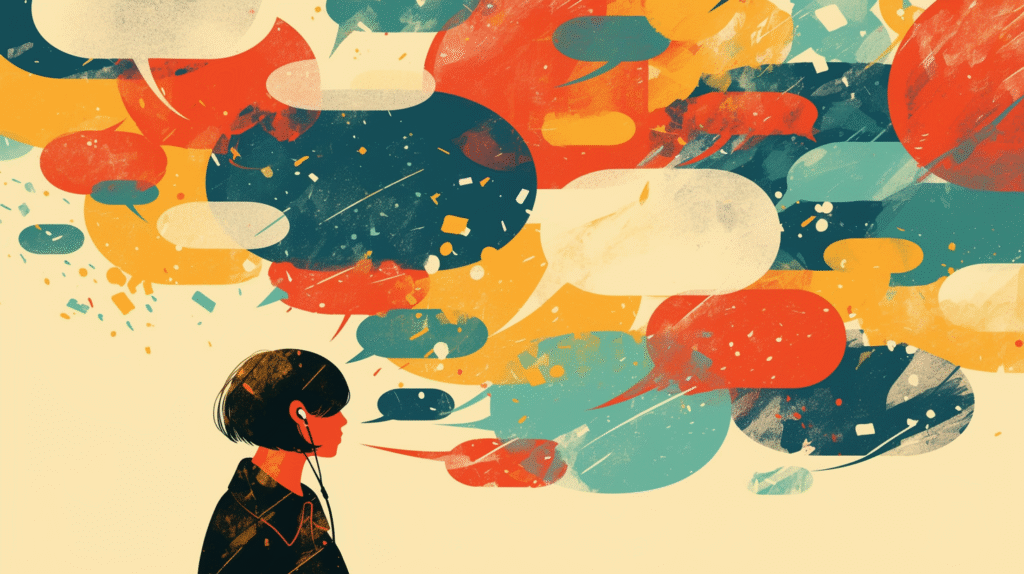
Q. VSCodeのようなデバッグパネルは使えませんか?
A. Sublime Textは軽量エディタの思想が強く、統合デバッグ機能は搭載していません。その代わり:
- 起動や動作が非常に速い
- 自分の好きなツールを組み合わせられる
- シンプルな環境で集中できる
これらのメリットがあります。
Q. 実行結果をもっと見やすくしたい場合は?
A. 以下の方法がおすすめです:
ターミナルを別窓で使用
- Windows:
cmdやPowerShellを別窓で開く - Mac/Linux:
Terminalを別窓で開く - 直接
gcc test.c && ./testなどを実行
Terminusプラグインを使用
- Sublime Text内でターミナルを統合
- エディタを切り替えることなく実行可能
Q. デバッグ情報をファイルに保存したい場合は?
A. ビルドシステムでリダイレクトを使用できます:
{
"cmd": ["python", "$file", ">", "output.txt", "2>&1"],
"shell": true
}
Q. 複数のファイルをまとめてデバッグしたい場合は?
A. Makefileを作成して、ビルドシステムから呼び出す方法がおすすめです:
{
"cmd": ["make", "debug"],
"working_dir": "${project_path}"
}
Q. リモートサーバー上のコードをデバッグしたい場合は?
A. 以下の方法があります:
- SFTP/SCPプラグインでファイル同期
- SSH接続でリモートデバッグ
- Dockerでローカル環境を再現
デバッグ効率を上げるコツ
段階的なデバッグアプローチ
1. 静的チェック(コード解析)
- SublimeLinterでリアルタイムチェック
- 構文エラーや基本的なミスを事前に発見
2. 動的チェック(実行テスト)
- ビルドシステムで基本的な動作確認
- エラーメッセージから問題箇所を特定
3. 詳細デバッグ(ステップ実行)
- 複雑な問題に対してgdbやpdbを使用
- 変数の値やプログラムの流れを詳細に確認
ログ出力の活用
プログラム内に適切なログ出力を入れることで、デバッグ効率が大幅に向上します:
C言語の例
printf("Debug: x = %d, y = %d\n", x, y);
Pythonの例
print(f"Debug: x = {x}, y = {y}")
まとめ
Sublime Textでのデバッグは、以下の組み合わせで効率的に行えます:
基本的なデバッグ環境
- ビルドシステムでエラー出力確認
- SublimeLinterでリアルタイム構文チェック
- GitGutterで変更箇所の可視化
本格的なデバッグ
- C言語: gdbとの連携でステップ実行
- Python: pdbまたはipdbで詳細確認
- 外部ツールとの適切な役割分担
ツールの使い分け
- Sublime Text: 編集・閲覧・基本確認
- 外部デバッガ: ステップ実行・変数監視
- ターミナル: コマンド実行・環境管理
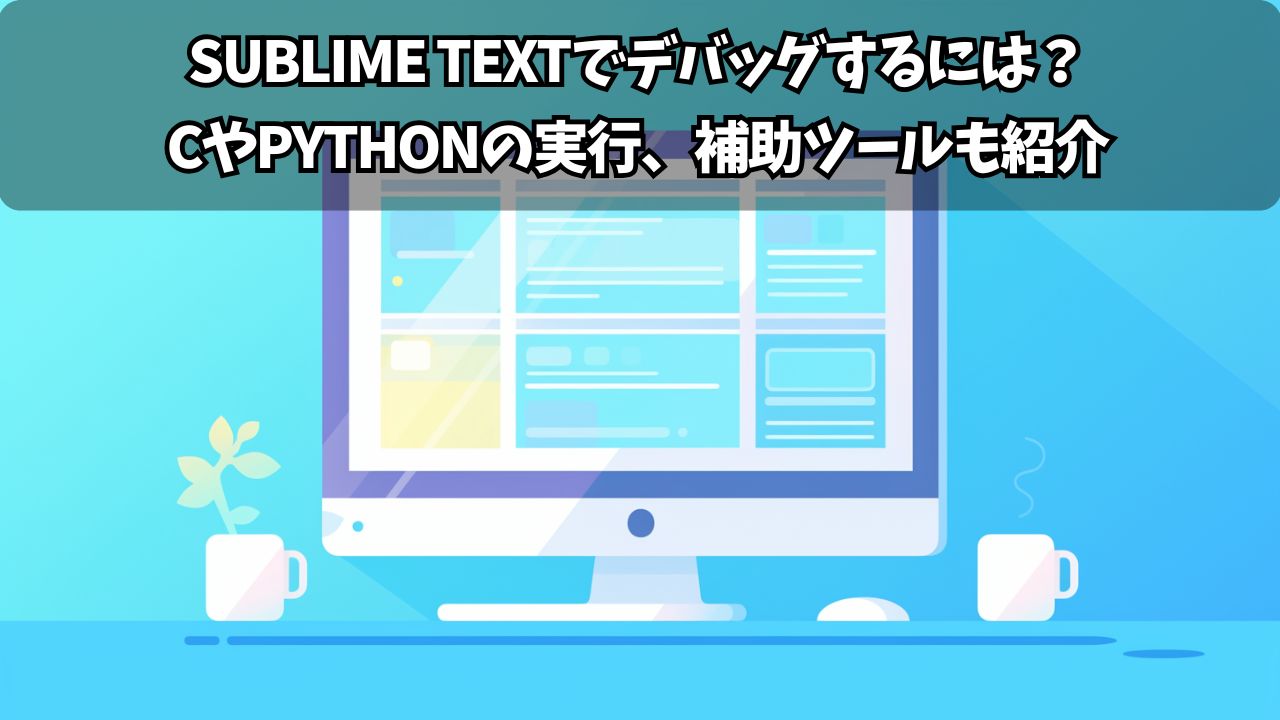







コメント